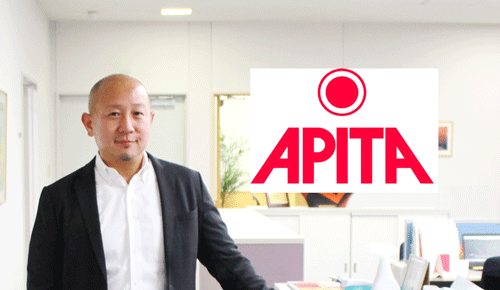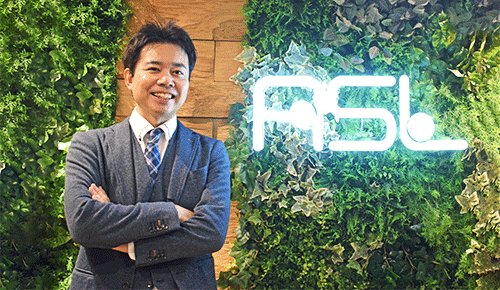大手物流企業のアルムナイ活用事例 〜即戦力採用に向けて取り組む「本音」で交流できるコミュニティづくり〜
-
タグ
-
-
社名 第一貨物株式会社 事業内容 総合物流 設立 1941年(昭和16年)3月15日 従業員数 4,424人 ※2024年3月末時点 URL https://www.daiichi-kamotsu.co.jp/ -

全国に物流ネットワークを持ち、東北~東名阪間の発着輸送に強みを持つ総合物流企業 第一貨物株式会社。従前より、輸送自体を自社の車両、施設、ドライバーを使って行う自前主義を戦略としており、今後の絶対的な労働力人口の減少を背景とした採用難が今後の命題と睨んでいました。
そんな中、同社はこれまでにも退職された方が再入社するケースがあったことから、再入社後の勤続年数を調べたところ、定着率が高いことが判明。こうした傾向から、アルムナイ採用への取り組みに注力することは、労働人口の不足を補う強力なツールとなりうると判断。
そこで、今回は、同社の常務取締役 人事部長 仁科 秀樹様、人事部次長 兼 中央研修所長 兼子 邦浩様、人事部 勤労グループ 小島 果穂様、人事部 採用グループの細川 康生様、4名の方に、アルムナイコミュニティを活かした再雇用の可能性についてお聞きしました。
以前からアルムナイ採用をしていた?上手く採用に繋げることができた理由
Qこれまでにも一度退職された方が再入社し、活躍されていた例があったそうですね?

仁科 秀樹 様(以下、仁科): はい。あまり意識をしていなかったのですが、結果として「アルムナイ採用」につながっていた事例がたくさんありました。
当社では国内でのトラック輸送を軸に、顧客の物流業務を一括して請け負う3PL事業や国際事業を展開、近年は、将来を見据えた事業ポートフォリオの再構築と業容拡大に取り組んでいます。
『物流業』を展開しているため、社員の約7割はドライバーです。取引先の99.9%は法人企業で、さまざまな製品・原材料を輸送しています。ケース物の他に、カーテンレールなどの長物・缶物・袋物など様々な荷姿の荷物があり、物量は日々10,000トンにも及びます。それを複数のドライバーがリレー形式で運んでいるんです。
一度は退職する方もいますが、大型免許や中型免許などの資格を活かし、転職後も同業他社でドライバーの仕事を続ける方も多く、しばらくして、出戻ってくる社員も多くいます。
兼子 邦浩 様(以下、兼子): 別の会社で働いてみて、改めて「働きやすい環境で、仕事が続けられる魅力」に気が付く社員が多いのだと思います。給与水準や年間休日、残業の少なさ、人間関係の良さなどを総合的に比較した結果「やっぱり第一貨物は働きやすい」と戻ってくるようです。
特に「人間関係、職場の雰囲気が良く、コミュニケーションが取りやすい」という点が、社員の働くモチベーションに大きな影響を与えていました。
仁科: 私が個別に聞いている限りでも、やはり「社風の良さ」に惹かれて戻ってくる方が多いですね。お互いの業務をカバーしあうなど、社員の面倒見の良さが特徴的です。1日の物量数は日によって変わりますから、全員が時間内に業務を終わらせようとすると、情報連携が必須になります。人間関係が良ければ、それだけ情報共有もしやすくなり、業務効率も上がっていきます。他社に転職してみて改めて、待遇・福利厚生だけではない「第一貨物の魅力」を実感したのでしょう。
Qこれまでは退職者の方々にはどのようなアプローチをしていたのですか?
仁科: 退職から3年以内の方に個別で電話をかけ「もう一度、戻ってきてほしい」と、伝えていました。
実際に電話がきっかけとなって、選考に進み、再入社に至ったドライバーはいました。しかし、自社内の仕組みだけでは限界を感じるようになってきました。
社会問題としても、よくメディアで取り上げられていますが「電話にこだわらず、あらゆる手段を用いて採用をしなければ、とても解決できないだろう」という危機意識が芽生えていました。
「最も効果的な手法は何なのか?」を考えた際に「SNSの活用」であると感じて、SNS機能を持つ外部のサービス・システムの導入を検討することになりました。
アルムナイ活用支援サービス「YELLoop」の導入と期待
Qアルムナイ活用支援サービス「YELLoop(エーループ)」導入のきっかけについて、教えてください。

以前よりお付き合いがあったマイナビに相談し、導入へ
小島 果穂 様(以下、小島): 以前から「マイナビ転職」などでお付き合いがあったため、アルムナイ採用の現状と課題についてご相談したところ「YELLoop」をご提案いただきました。
電話よりも格段に効率が上がるだけでなく、システムとして利便性が高く、操作も難なくできそうな点が評価でき、すぐに導入が決まったという次第です。現在は、アルムナイコミュニティの立ち上げに向けて、準備を進めています。
兼子: マイナビからの提案をきっかけに、アルムナイ採用者数を調べてみたんです。2022年度の時点で約100名の社員が再入社であることが分かりました。調べるまでは想像もしていなかったため、こうした傾向があったことに驚きましたね。
「YELLoop」の導入からアルムナイの方々との繋がりを創出し、ここから再入社される方が増えることを期待しています。
「YELLoop」を活用した今後の展望について
Q「YELLoop」を導入することで、どのようなメリットが得られると思いますか?
現場で「即戦力」として活躍するドライバー人材の採用に期待
仁科: やはり即戦力を採用できる可能性が広がることを期待しています。未経験スタートからドライバーを目指すには、最低1年はかかります。先輩ドライバーと同様に活躍してもらうには、2〜3年の年月が必要です。しかし一度、当社で勤務していた実績があれば、すぐにでも現場に戻って活躍できます。
YELLoopをきっかけとした採用については年間2名採用を目標に設定し、様子を見守りながら取り組んでいこうと考えているところです。多少、費用がかかったとしても「即戦力人材」を採用できる可能性があるなら、必要な投資だと思います。
ドライバーだけではなく、事務系職種の採用にもつなげたい
仁科: ドライバーに加えて、ロジスティクス事業部を支える事務系職種への採用にも活用したいですね。全社の売上構成としては2割程度の事業部ですが、今後は事業の柱として伸ばしていきたいと考えています。そうした狙いもあり、物流センターの倉庫管理担当や作業員などを、アルムナイ採用で獲得できるような仕組みづくりを進めていく予定です。
アルムナイ同士による情報から「新規事業」創出のチャンスも
兼子: 「YELLoop」の中でコミュニティができれば、そこから様々な情報共有がされると思います。そうした情報を吸い上げれば、新規事業が生まれる可能性も出てくるでしょう。例えば「A社でオフィス移転をするらしい。運搬業務のニーズがあるが、誰か手伝ってくれないか?」という書き込みに、他のメンバーが答え、ビジネスが生まれる─そんな未来が、実現できるかもしれません。
これからますます労働人口は減っていく一方ですから、「人と人との交流」を活性化させて、新たな事業展開を目指してみたいと思っています。
Q「YELLoop」の機能を活用して、取り組んでいきたいことはありますか?

最新の情報を発信し、自社の魅力を伝える
小島: コンテンツを使った自社の魅力の発信は、ぜひトライしていきたいです。最新の求人情報を優先的に載せるのはもちろん、3か月に1回発行している「社内報」も掲載し、社員の近況や会社の注目トピックを紹介しようと思っています。
特に「就業規則の変更」「働き方の変化」など、アルムナイの関心を集めそうな情報を分かりやすく伝えたいですね。
退職理由に関する「本音」を聞く
小島: また「なぜ退職したのか」「転職先と比較した時の、当社の良いところ」についても、率直に伺ってみたいです。同じ環境で働いていると、自分の置かれた状況が客観的に見えなくなるもの。一度、第一貨物を離れたからこそ分かる良さについて本音で語ってほしいです。
兼子: たしかに、本音はなかなか語ってもらえないですが、アルムナイコミュニティの中ならば言いやすいかもしれませんね。本音の中から課題の本質が見えてくれば、離職防止のヒントにも活かせるでしょう。
退職からの再入社をポジティブに捉えてほしい
細川 康生 様(以下、細川): 「退職=ネガティブな出来事」という印象を持つ方もいるかもしれませんが、当社は再入社を歓迎していますし、ポジティブに捉えています。
「また戻ったら、周囲の社員はどう思うんだろう?」と気にしている方には特に「アルムナイへ期待している想い」について、ぜひお伝えしたいです。会社からのメッセージをコンテンツに反映し、コミュニティを活性化したいと思っています。
Qアルムナイ活用のためには、教育や社内体制の整備を充実させ、「自社の魅力」として積極的に情報発信をすることも大切ですね。
仁科: そうですね。そういう意味では、当社は社員教育や社内体制に注力をしてきた実績がありますから、情報発信をしやすい土台はできています。
当社には山形県天童市内に「中央研修所」があり、学卒入社の社員はここで全員研修を受けます。
特にドライバーは、入社時から3か月の集合研修、5か月の現場実務実習を実施し、社会人としてのマナーから、運転技術、業務に必要な基礎知識までを習得します。研修所における研修カリキュラムは、対面、リモートも含めて50種類以上に及びます。
兼子:
この「中央研修所」には、第一貨物物流専門校という山形県認可の各種学校を併設しており、全国から学生を受け入れる企業内学校の機能も持っています。
昭和40年代までは、3年修学の高等学校としての認可を取得しており、中学卒業者の進学や就職を支援していた時期もありました。
そういう意味では、社会貢献度も極めて高く、腰を落ち着けて働ける風土が脈々と根付いていると言えます。「人材を育てる」という歴史の中には、もちろん社員教育も組み込まれています。
さらに「健康経営」への取り組みにも力を入れてきました。2024年には3年連続となる『健康経営優良法人2024(中小規模法人部門)』として認定されました。(2025年3月には健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)に認定。これで4年連続の認定に)そして、2025年1月には日本政策投資銀行より「DBJ健康経営(ヘルスマネジメント)格付け」を獲得。従業員の健康へ配慮しているとの評価と融資を受けました。
これは東北地方にある物流事業者として、初の取得となりました。長時間労働削減に向けた業務効率化への取り組みや、動画を活用したトップメッセージの発信などを実施してきましたが、そうした工夫を第三者に認めていただけたわけです。
こうした社内教育の充実さや従業員の健康管理を、経営の視点から取り組んでいるという強みもぜひ、アルムナイの皆さんに向けて紹介したいと思っています。
運輸業界でもアルムナイ採用は浸透していくのか?
Q「2024年問題」などが社会的にも注目されていますが、業界全体でもアルムナイへの取り組みは進むと思いますか?

仁科: 確実に進むでしょう。競合他社との会合でも、常に話題に上っています。他業界も含め、社会全体で人材獲得が難しくなっている今、アルムナイ採用はどの業界においても導入が進むのではないかと考えています。
今後はドライバーの定年問題も、考えていかなければなりません。すでに当社でも年間70〜80名が定年を迎え、そのうち半分が継続雇用となっています。しかし、残りの半分は退職していますので、会社としてもなるべく長く活躍していただけるような環境の整備を続けていく必要があるでしょう。
年齢・職種は関係ありません。まずは第一貨物の魅力を再発見していただき、また一緒に働く仲間として迎えていきたいと思っています。
こうした社会的な背景も踏まえ、アルムナイ採用は貴重な即戦力を確保できる手段であると考えています。退職時と比較しても働きやすい環境になったことなど「第一貨物の今」をしっかりと伝え、再び働きたいと思ってもらえるようにしていきたいなと。
また、一度は退職して別の環境で過ごしたからこそ、気づいた部分を本音で語っていただくことでより組織を活性化できる可能性にも期待しています。
「YELLoop」を活かし、採用に繋げるのはもちろんのこと、アルムナイの新たな活用方法を模索していきたいです。
-

-
Q 常務取締役人事部長/仁科 秀樹 様
1989年入社以降、ロジスティクス事業、輸送系事業の営業を皮切りに、事業所の運営など、現場の第一線を長く経験、宮城県、岩手県、北海道を管轄する支社の管理スタッフを経験した後、経営企画部長、天童支店長を歴任、現在は、常務取締役として、人事部門最高責任者として活躍。
『現場とともに』がモットーのプロパー役員である。
-

-
Q 人事部次長 兼 中央研修所長/兼子 邦浩 様
入社当初、経理事務の下積みを経験した後、国際・国内向け航空貨物の営業に従事、営業本部営業部次長を歴任。途中、コンサルティング会社に出向するなど、異色の経歴を持つ。現在は、人事部次長として、採用・教育を担当、中央研修所の所長を兼務する傍ら、県認可の各種学校『第一貨物物流専門校』の校長も務める。
-

-
Q 人事部 勤労グループ/小島 果穂 様
地方発で全国展開している第一貨物株式会社に魅力を感じ、2017年に入社。入社以降は人事部 勤労グループ一筋で、主に従業員の福利厚生や労務管理を担当。今回、アルムナイサービスの担当としてその構築業務を機に、新たなステージへチャレンジしたいと意気込む。
-

-
Q 人事部 採用グループ/細川 康生 様
2024年に新卒で第一貨物へ入社し、人事部・採用グループに配属。入社1年目から大卒採用をメインに、高卒採用、中途採用など、採用業務全般を担当。新人ながらインターンシップや会社説明会など、臆することなく全国を飛び回っている。
ページ上の各種情報は2025年3月時点のものです。
ご利用いただいたサービス
関連記事
お問い合わせ
-
03-6740-7228
受付時間9:15ー17:45
(土日祝・年末年始を除く)
03-6740-7228受付時間9:15ー17:45
(土日祝・年末年始を除く)
-
メールでの
お問い合わせ