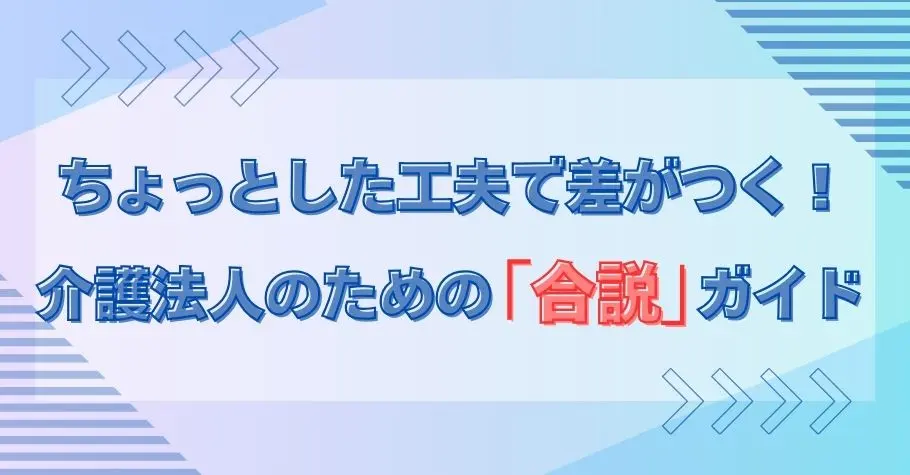ちょっとした工夫で差がつく!介護法人のための「合説」ガイド【介護職採用シリーズ_vol.14】
マイナビが2024年卒の学生を対象に実施した調査では、卒業する前年の2月までに合説に参加した学生は56.5%と、半数以上に上ります。また、2024年卒では、2023年卒に比べると、合説や大学主催のガイダンスといった対面形式のイベントへの参加率が増加しています。2月時点で参加した対面のインターンシップ・仕事体験の数も、2022年卒の1.4社、2023年卒の1.5社に比べ、2024年卒では2.7社。さらに2025年卒では、2.8社となりました。このように年々増加の傾向がみてとれます。
※出典:マイナビ「2024年卒 学生就職モニター調査 2月の活動状況」
2020年頃からコロナ禍の影響でオンラインのイベントが増加する傾向にありましたが、2024年卒以降、合説をはじめとする対面イベントの重要性は高まっていくと考えられます。
合説は、幅広い業種の企業が集まる「総合型」と、業界や対象者の属性(学部・学科など)が限定された「特化型」の2種類に大きく分けられます。また、新卒採用向けのほかに、中途採用向けの合説もあります。中途採用向けの合説は、「転職フェア」とも呼ばれます。
会場のレイアウトや説明方法は合説によってさまざまですが、新卒採用向けの合説では、企業ごとにイスを並べたブースを設置し、6人程度の求職者を集めてスライドを見せながら、自法人についてプレゼンテーションをする形式が一般的です。一度のプレゼン時間は質疑応答も含めて20~30分ほどで、1日に複数回のプレゼンを行います。
ほかに総合型の転職フェアでは、ブースを訪れた順に、一人の求職者に対して一人の職員が説明を行う形式の合説もあります。このような個別説明形式が多いようです。
若い世代の未経験者や、将来、マネジメントを担えるような総合力を備えた人材を採用したい場合は総合型、有資格者や経験者を中心に採用したい場合は福祉・介護業界特化型の合説を選ぶのが基本です。ただし、総合型の合説には人気業種の企業も多く出展しているため、競争率が高く、ブースへの着席につなげるのが難しいというデメリットもあります。まずは自法人がどんな人材を採用したいかをよく考えて、ターゲット・目的に合った合説を選びましょう。
なお、地域の社会福祉協議会が主催する福祉・介護業界特化型の転職フェアには、経験者はもちろん未経験者も多く足を運びます。即戦力となる介護職経験者と将来性のある若手人材に一度に出会えるチャンスなので、あわせて出展を検討してみてください。
介護法人が合説に出展するメリットの一つが、求職者との「偶然の出会い」を期待できることです。合説に参加する求職者には、特定の法人のブース訪問を目的にしている人もいますが、多くはさまざまな法人と出会いたいと考えています。マイナビの調査でも、2023年卒の学生が「来場型(リアルイべント)の合説に参加した目的や動機」の1位は「さまざまな企業を発見するため」(48.6%)でした。
※出典:マイナビ「2023年卒 学生就職モニター調査4月の活動状況」
とくに新卒採用の合説の場合、来場者のなかには志望業種をはっきり決めていない学生も少なくありません。知名度の低い中小規模の介護法人にとっては、介護業界や自法人に興味を持ってもらえるチャンスといえます。自法人の強みや魅力をアピールすることで、一般の学生が介護の仕事に対して漠然と抱いている「仕事がきつい」「給料が安い」といった先入観を払拭できれば、人材を獲得できる可能性は十分にあります。
加えて、転職フェアの場合は、会場の近くに住んでいる求職者や、その地域出身の求職者が多く来場する傾向があるので、応募や入職につながりやすいというメリットがあります。また、1対1の個別説明形式の転職フェアでは、じっくり話しながら、その求職者に合わせた魅力づけができるのもメリットです。
合説には、入職1~3年目の現場職員3名以上に参加、協力してもらうことをおすすめします。新卒採用の合説の場合は、来場を予定している学生の大学や専門学校のOB、OGが職場にいれば、ぜひ協力を呼びかけましょう。現場職員のうち一人はブースの入り口に立ってもらうと、若い世代の求職者が立ち寄りやすくなります。
介護法人のブースでは、中高年以上の採用担当者自身が一人で立ってプレゼンを行うケースが多いようですが、ぜひ入職1~3年目の現場職員にも、プレゼンの一部を担当してもらいましょう。求職者に近い立場・年齢の現場職員から業務内容や入職のきっかけ、経緯などを伝えてもらうことで、より求職者の共感を得やすくなります。
事情があって現場職員が会場に来られない場合は、オンライン会議ツールを介して、現場から施設案内をしてもらうのも一つの方法です。
合説のブースには、所在地やサービス形態などを記載したタペストリーや用紙、ポスターパネルなどを掲示して、一目見ただけでどこにあって何をしている法人なのかがわかるようにすることが大切です。合説の集客数は、こうしたブース装飾の有無や工夫の仕方で大きく変わってきます。
装飾・掲示物には、所在地やサービス形態のほかに、「週休3日制」「資格取得支援制度あり」といった自法人のアピールポイントを記載するのも効果的です。当日のタイムスケジュールや「説明会予約受付中!」と印字した用紙を掲示しておくのもよいでしょう。
ブースの壁や装飾・掲示物に使う色を統一させることも、求職者の目に留まりやすくする工夫の一つです。初めての出展では難しいかもしれませんが、二度目以降の出展では、ほかの法人があまり使っていない色を選ぶと、自法人のブースをより目立たせることができます。
なお、合説では、ブースで準備やプレゼンを行う職員同士の関係性や雰囲気も装飾の一部と考えて、求職者の目を意識する必要があります。たとえば、採用担当者が「少しでも多くの求職者を応募につなげなければいけない」というプレッシャーから、表情がこわばったり、若手職員に指示する口調が厳しくなったりすると、職場でもそれが常態だと思われるかもしれません。普段の職場での雰囲気や職員同士の良好な関係性が伝わるように、採用担当者自身が精神状態をリラックスさせたうえで、ほかの職員と十分にコミュニケーションをとって、チームの体制と状態を整えましょう。
合説では、法人側から求職者に声をかけて呼び込む努力が不可欠です。せっかくブースを設置しても、その場で待っているだけではなかなか十分な集客につなげることはできません。会場で次に訪ねるブースを探している求職者を見つけたら、チラシやパンフレットを渡しながら声をかけましょう。若手職員に声をかけてもらうと、より効果的です。
呼び込みでは、笑顔を絶やさず、親しみやすい雰囲気を心がけましょう。最初にかける言葉は、「目的のブースは決まっていますか?」「決まっていなかったらうちのブースに来てみませんか?」などが一般的です。会話を続けながら「うちは残業がないんですよ」「週休3日制を採用しています」などと、自法人の強みをアピールしてもよいでしょう。呼び込む職員のキャラクター、求職者の年齢や雰囲気、状況によっても適した言葉は変わってくるので、各職員が試行錯誤しながら工夫することが大切です。
プレゼンが行われている最中でも、ブースに立ち寄ってくれそうな求職者がいたら、「途中参加もOKですよ」と声をかけて呼び込みましょう。その求職者が聞けなかった前半部分については、プレゼンが終わった後に補足するか、次の回のプレゼンを聞いてもらいます。
ただし、求職者の意向を確認せずにブースに連れ込むような強引な勧誘は禁物です。また、合説ごとに開催団体によって「勧誘行為は自法人のブース前に限る」といった規約が定められているので、必ず規約を守りましょう。
- 人材採用・育成 更新日:2025/04/09
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-