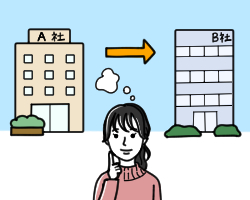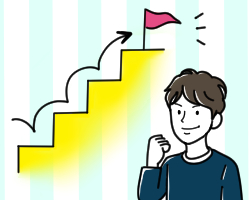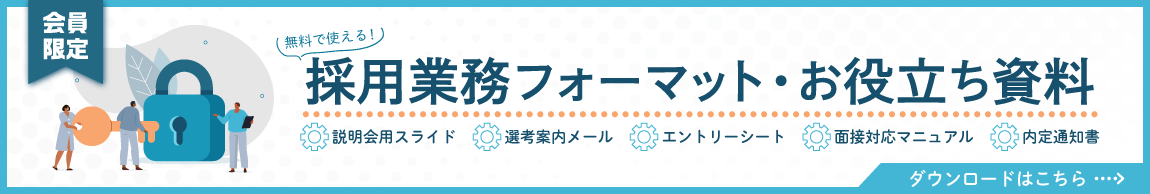文系学生の「IT就活」を知る ―キャリア発想の就活生にとって魅力的に映る企業像とは?
Mさん(以下、M): 僕は情報学部なんですが文系で、技術的なバックグラウンドはまったくありません。メディア論などが中心です。内定先は大手のSIerで、もちろんプログラミングはできませんから、上流工程でのマネジメントやコンサルティングが中心になります。
Hさん(以下、H): 私は文学部で、ばりばりの文系です。自己肯定感を育む教育について研究しています。内定先は大手のシンクタンクで、もちろん、私も技術的なバックグラウンドはありませんから将来的にはプロジェクトマネージャーになるようなイメージですね。
― ありがとうございます。お二人とも「技術的なバックグラウンドはない」とのことですが、それでもIT業界を志望したのはなぜですか?
M: 僕の場合、実は最初からIT業界を志していたわけではないんです。1年前に大手通信企業のインターンシップに参加して、現場社員の方と数日間ご一緒させていただいたのですが、結論として「一生の仕事をいま決めることは不可能」だと思いました。
であれば、将来の選択肢を増やすためにも何かスキルを身に付けておきたいと思ったんです。IT技術を使っていない企業というのも今どきありませんし、まだまだ伸びしろのある分野ですよね。なので、まずはIT業界に入って専門性を身に付けたいと思ったのがきっかけです。
H: 実は私も、最初からIT業界を目指していたわけではありません。就職活動を通じて自分自身の仕事観を見つめた結果、できるだけ多くの人に役立って社会貢献がしたいと気付きました。それで、IT業界をはじめとした無形商材を扱う企業に目が向いたという流れです。
あと、自分で思っていたほど自分自身が保守的でなく、一つのことに固執したくないと気付いたこともIT業界を目指すようになった理由ですね。Mさんと同じくキャリアの多様性があると思ったからです。
M: 僕も最初そう思っていたのですが、実はそうでもないんです。先輩方でも転職を考えている方、実際に転職した方も多く、同規模の同業他社と比較すると社員の平均年齢も低い方です。転職先も多様で、コンサルからベンチャー、商社… ここなら自分のキャリアにも広がりがあるかなと思いました。
H: 私もです。確かにイメージ的に定年まで勤め上げる会社に見えますが、そうでもないんですよね。転職を前提としてキャリアメークしている人が多いという印象です。
特に若手の社員さんが、転職を考えているということがインターンシップでわかったのが印象的でした。もちろん今いる会社も好きだけど、ということで。実際に転職された方のことを伺うと、大手のITコンサルだったりして、専門的なスキルもソフトスキルもしっかりと身に付く環境なんだなと分かって魅力的でしたね。
M: ありだったなぁ、と今なら思いますね。その可能性に気が付くのが遅かったので、すでにインターンシップや選考の募集が終わっているタイミングだったんです。早く気付いていれば、メガベンチャーやベンチャー企業への選考応募も考えたと思います。
H: 私の場合、あまり考えませんでした。先ほどもお話ししたように幅広く多くの人に役立ちたいと考えていたので、自社のサービスや製品を扱う業態にはあまり惹かれませんでしたね。
多くの人に役立ちたいとは言っても、1人でできることではありません。実際には自分の目の前にある仕事をすることになる。となると、多くの業界、多くの会社と関係を持ちながら自社の事業を展開し、幅広く社会貢献する方向性を持っていることが選考応募時の条件でした。
M: 僕の場合、社会貢献がしたいという思いはあんまりなかったですね。将来の自分のために、今どのような選択をすべきなのか、という点にフォーカスしていました。チームで動く、プロジェクトを動かす、ITの基本的なスキルを身に付けるということを前提に考えれば、ベンチャー企業は「あり」な選択肢だったのだろうと思います。
M: 先ほどの話の裏返しになりますが、自分自身の成長を考えてIT系を志望している学生には、しっかりとしたフィードバックをしてあげるといいと思います。
また、特に営業系以外を志望している場合にロールモデルが不足していて、キャリアの全体像をつかみにくいという課題があるので、インターンなどで先輩社員の話を聞く機会を多くとっていただきたいと思いました。転職が前提ということだと採用企業側は少し警戒するかもしれませんが…。
H: 私も、Mさんと同じくキャリアプランをしっかり示した方がいいと思います。そもそも文系からIT系に進んだときにどんな仕事があって、どんなキャリアプランを持てるのか、実際に先輩社員の話を聞くまでリアルにイメージできなかったのです。
あと、私はIT系の職種なら就職後にプログラミングの勉強などをすることも覚悟していたのですが、基本知識を身に付ければプロジェクトマネージャーなら仕事ができるということを知ったのも、インターンシップがきっかけでした。
文系の学生がイメージしにくいIT系職種について、丁寧に教えていただける機会があるとありがたいですね。
逆に言うと、今の内定先は私の持っているソフトスキルをしっかりと評価してくださいました。自分の強みとIT系職種の特性がどこで交わっているのか、学生側のリサーチも大事ですが、企業側からもアドバイスがあると考えやすいと思います。
- 人材採用・育成 更新日:2021/03/11
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-