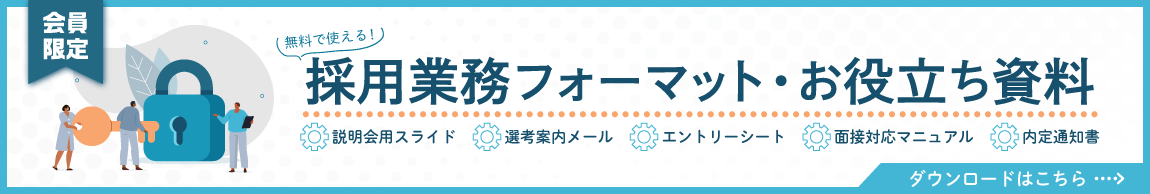「先端IT人材」どう採用すればいい? 競技プログラマを見続けてきたAtCoder 高橋直大社長に聞きました
高橋さん: はい、よろしくお願いします。AtCoderでは、プログラミングコンテストを毎週インターネット上で開催しています。学生が6割、社会人が4割くらいで、海外の方も全体の4割程度いらっしゃいます。
私たちの主催しているプログラミングコンテストは数学的な問題解決がメインで、アルゴリズム開発を中心にした内容です。
普段プログラムに触れることのない方にはなじみがないと思いますが、「アルゴリズム開発」はプログラムによって問題を解決するためのベースとなる考え方や手法を開発すること、とご理解ください。
これが非常に重要で、例えば同じ課題に挑戦して同じ解を得たとしても、アルゴリズムの出来によって解決までのスピードや、解決のために使うプログラムの安定性などが大きく変わってきます。
つまり、アルゴリズム開発の能力が高いプログラマは、現場に出たときに接する多種多様な課題に対しても迅速で的確な手法を用いてそれを解決できる可能性が高いということです。
AtCoderでは競技プログラマに対して独自のレーティングを行っているのですが、これをプログラマの能力を測る一つの指標として用いている企業も多くあります。
高橋さん: はい、おっしゃるとおりで「DXに向いている技術」というものは本質的に存在していません。非常に幅広い分野を含んだ言葉ですよね。
DXという言葉が生まれる前だって、「DX」と呼べるものはあったと思います。会計処理を手計算から電卓に、電卓から表計算ソフトに、そして専門の会計ソフトへとシフトしていった流れは、まさに「DX」ですが、そう呼ぶ人はいません。言葉がなかったからですね。
要するに、DXというのは何かをデジタル化することで顧客体験を変えていくことなのだと思います。先ほどの会計処理の話に戻せば、そろばんを弾いて処理していたものをデジタル化したことによって圧倒的に楽になり、しかも正確になったという顧客体験の変化がありました。
そして、何より大きな変化は会計にまつわるあらゆる数字を一元管理することで無駄を省き、投資すべき箇所が可視化されたことでしょう。
最近になってよくいわれている「DX」というのは、このようにデータを一元管理することによって事業変革の土台を作ることを指していると思います。
高橋さん: 社内に持つ必要があると考えます。理由は2つで、スピードと事業理解の深さです。
社外の協力会社とDXを進めようとすると、まずはRFP(提案依頼書)を作らなくてはいけませんが、繰り返しお話ししているようにDXはゴールが見えないのでまずそれが困難です。
また、仮にそれができたとしても、DXには検証と実行のサイクルを短期間でどんどん回しながら方向性を探っていくという要素がありますので、そのたびにRFPを作ったり、打ち合わせをしていたりしては時間がいくらあっても足りません。
次に事業理解ですが、いまDXを進めている企業はIT企業ではない企業が多いと思いますので、その分野のビジネスを理解したIT技術者の数自体が圧倒的に少ないんです。なので、自社で育成する必要があります。
事業を理解していないのに事業の変革ができるわけがありませんから、これは非常に重要なポイントだと思います。
高橋さん: そうです。WEB系やIT系なら、そのビジネスを知っている優秀なIT技術者は豊富に存在しています。が、土木や流通、銀行といったITから遠い業界でDXを起こそうとすると、まずはビジネス理解から始めなくてはいけないことがほとんどでしょう。
自分の技術を深めることにしか興味のないタイプも確かにいますので、センスや志向の見極めが必要な部分でもあります。自分の技術を使ってビジネスを拡大したい、変革したいと考えている人材を採用するべきです。
その点では、新卒社員の方が育成しやすいため、ビジネス理解の進んだ、自社にフィットする人材になっていく可能性が高くなると思います。また、深くビジネスを理解したIT技術者は定着率も向上しますので、その点でもメリットがありますね。
高橋さん: おっしゃるとおり、非エンジニアの採用担当者の方がDX人材の見極めをするのは難しいことです。
AtCoderが提供しているレーティングは技術力を測る客観的な指標として機能しますが、それだけでなく技術に通じた社員を面接官にすることは必要だと思います。自社の事業とマッチする技術を持っているか、またはその分野に興味があるかどうかを見極めるためには共通言語を持っている必要がありますから。
― 高橋さんの視点から見て、DXをしようという会社が採用するべき人材像はどのようなものだと思いますか?
高橋さん: 技術的な能力を別とするなら、自分ができること・できないこと、興味のあること・ないことをはっきりと言える人材は重要です。
繰り返しになりますが、DXは目指していることが本当にできるのかどうか、挑戦することから始まります。そういった環境では「何でもできます」という人よりも、自分の能力について率直に言える人の方がいいんじゃないでしょうか。
高橋さん: いわゆる「コミュニケーション力」などはそれに当たると思いますが、会社のカルチャーになじんでもらうのはもちろん、DXについては特に非常に深い事業理解が求められる分野でもあるので重要です。
ただ、仕事で求められる「コミュニケーション力」、つまり「報・連・相をちゃんとやりましょう」とか「必要な情報を的確に素早く伝えましょう」とか、そういったものがイメージできず、「面白い話をする力」とか「場を盛り上げる話術」を求められると勘違いしている学生も多くいるので、そこは丁寧に誤解を解いてあげた方がいいですね。
また、この仕事に求められる「コミュ力」は実はプログラマとしての能力にも強くリンクしているんです。論理的な展開をきちんと理解すること、そして人に正確に伝えることは、プログラマとして必ず求められる資質です。もちろん、コンピュータ相手に「やりたいこと」「やるべきこと」をインプットしていくのがプログラマの仕事ですから、その正確性ともつながっています。
- 人材採用・育成 更新日:2021/01/19
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-