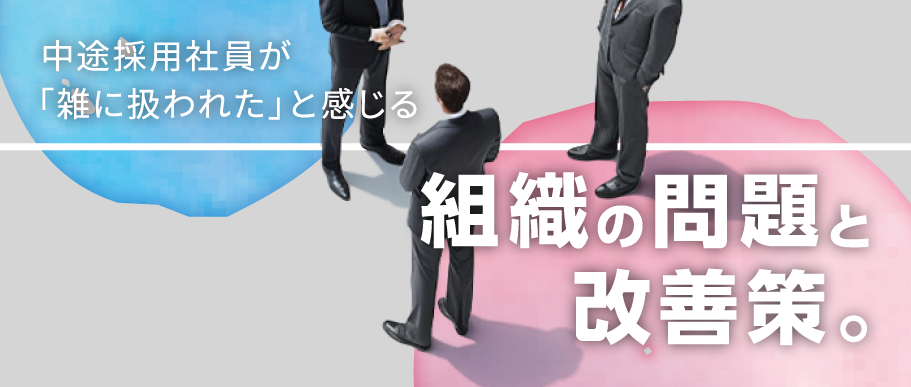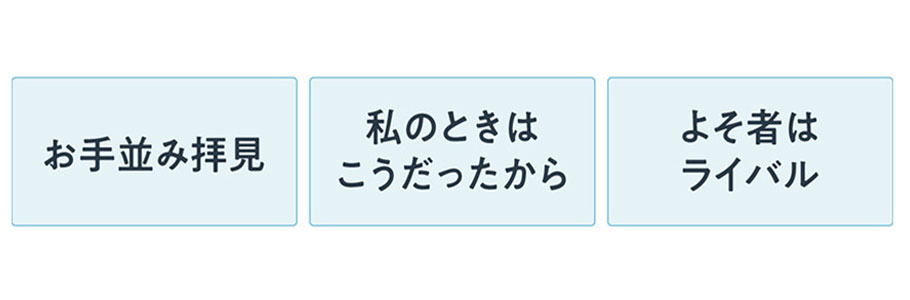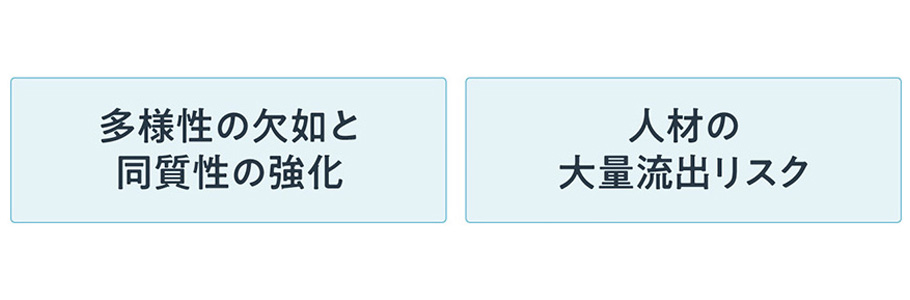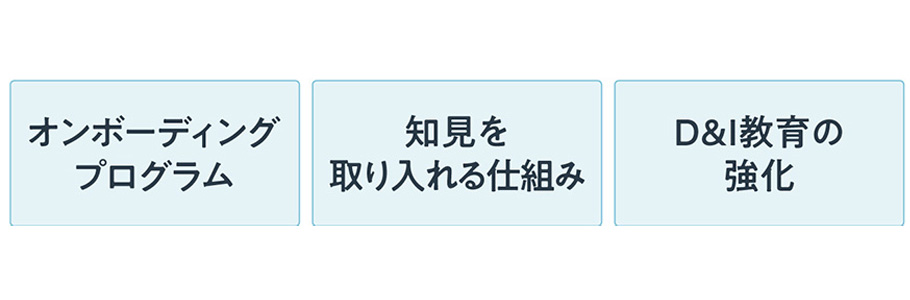中途採用社員が「雑に扱われた」と感じる組織の問題と改善策。
「せっかく転職したのに、まるで使い捨ての駒のように扱われている気がする……」。このような思いを抱いている中途採用社員が、社内にいるかもしれません。
近年、企業の人材戦略において中途採用の重要性が高まっています。 その一方で、適切な受け入れ体制が整っていない組織も少なくありません。 中途採用社員を大切にしない組織は、貴重な人材を失うリスクに直面しています。 本記事では、中途採用社員を雑に扱ってしまう心理や、そのような組織が陥る罠について解説します。
採用課題を解決!「圧倒的な工数削減をしながら成果を出す10のポイント」
<人気資料・最新版> こちらから無料でダウンロードできます
専属スタッフが採用までフォロー。初期費用0円「マイナビ転職 Booster」の資料を受け取る
中途採用社員を雑に扱ってしまう心理とは?
中途採用社員を雑に扱う組織には、現場に共通する原因があります。問題点を把握することが、解決と、健全な組織づくりへの第一歩です。ここでは、現場に見られる3つの心理を解説します。
中途採用社員に即戦力を求めることの弊害
中途採用社員に即戦力を期待することは、一見、強みを引き出し活躍を促すよいことに思えるかもしれません。しかし、実際には、それが大きな弊害をもたらすこともあります。
即戦力としての要求が過剰になると、入社したばかりの社員には過度なプレッシャーがかかります。ときには精神的な負担からモチベーションの低下やストレスが増加し、早期離職につながるリスクも高まります。 とくに、前職とは異なる文化や業務プロセスに適応するためには時間がかかることが多く、即座には期待通りの成果を出せない場合もあります。環境によっては、せっかくの才能や経験が十分に発揮されないまま、組織を去る危険が高まります。
また、適切なオンボーディングプロセスやサポート体制が不足している場合、その影響はさらに深刻です。中途採用社員の即戦力としてのポテンシャルを引き出すためには、まず適応のための支援を行うことが重要です。
これにより、組織文化や業務プロセスにスムーズに慣れ、新しい環境で最大限のパフォーマンスを発揮できるようになります。
「お手並み拝見」
1つめの心理は「お手並み拝見」の姿勢です。
中途採用社員に対して、「即戦力なら、今すぐ結果を出せるでしょう?」という無言のプレッシャーをかけてしまうことがあります。しかし、有能な人でも、新しい環境へ適応するためには一定の準備期間が必要です。
本来、この時期に必要なのは、周囲の手助けです。にもかかわらず、サポートを出し惜しみして距離を置き、力量を見定めるような雰囲気の職場があります。
中途採用社員からすれば、これはなんとも居心地が悪いもの。結果として、モチベーション低下や、組織への不信感を招くリスクがあります。
「私のときはこうだったから」
2つめの心理は「私のときはこうだったから」という考え方です。
組織の文化や慣習は、ときとして望ましくない形で継承されてしまうことがあります。
「私が入社したときは、誰も教えてくれなかった」「自分は厳しい状況から這い上がってきた」このような既存社員の自己体験が、中途採用社員への接し方に影響を及ぼすことは、珍しくありません。
これもまた、中途採用社員が本来の力を発揮することを妨げ、組織の成長を阻害する要因となります。 そしてこういった文化は、誰かが意識的に断ち切らない限り、負の連鎖となって引き継がれていくことが多いものです。
「よそ者はライバル」
3つめの心理は「よそ者はライバル」という意識です。
中途採用社員は、既存社員から “自分たちの居場所を脅かす存在” として、ライバル視されやすい立場にあります。とりわけ、競合他社から転職してきた社員や前評判が高い社員に対しては、既存社員の警戒心が顕在化しやすいものです。
中途採用社員を意思決定のプロセスから外したり、暗黙知の共有を控えたりするといった、公平性を欠く扱いが生じることがあります。このような扱いがないかどうかも、注意する必要があります。
以上、3つの心理を見てきました。
|
ここまでお読みいただき、「うちの会社には、こんな意地悪な社員はいないはず」と思うかもしれません。
しかしながら、誰もが無意識のうちに、バイアス(先入観・偏見)を抱えています。
“即戦力であるべき”、“好待遇に見合う成果を出すべき” といった思い込みにより、「本当に全力で支援できているか?」と問われれば、「YES」とは言い切れる人は多いのではないでしょうか。だからこそ、このような心理の存在を否定せず、内省する機会を持つことが大切です。
中途採用社員に冷たい会社が陥る罠
中途採用社員を軽んじる組織は、深刻な問題に直面するリスクがあります。以下の2つのポイントを見ていきましょう。
多様性の欠如と同質性の強化
中途採用社員に対する対応が不適切であれば、離職率の上昇は免れません。いくら採用活動を強化しても、バケツに穴が開いているようなものです。
結果として、似たような背景や価値観を持つ社員ばかりが残り、多様性が失われます。同質性が強化され、次第に保守的で硬直した風土に陥ります。
一方、現代は多様性が組織力の源泉となる時代です。同質的であればあるほど、組織のイノベーション力や環境変化への適応力は低下します。
人材の大量流出リスク
採用活動がうまくいき、高度人材の採用に成功するほど、その影響は既存社員にも波及します。
どういうことかといえば、
「あれほど優秀でハイスペックな人が、うちの会社を見限って辞めていった」
という事実は、残された社員の心理にも大きな動揺を与えるのです。
このリスクは、組織の存続そのものを脅かしかねません。
表面化するのは後のことかもしれませんが、「きっかけ次第で、大量離職も起こり得る」という爆弾を抱えた状態です。
組織改編や業績悪化、経営方針の転換、リーダーの交代などが、その爆弾の導火線となる危険があります。
いうまでもなく、人材の大量流出は組織の競争力を急激に低下させ、その回復には長期間を要する重大な事態をもたらします。
中途採用社員に優しい会社になるための取り組み
では、中途採用社員に優しい会社になるために、何をすべきでしょうか。ここでは、中途採用社員を尊重し、活かすための具体的な取り組みを3つ、ご紹介します。
充実したオンボーディングプログラムの構築
まずは、仕組みとしてオンボーディングプログラム(組織適応の支援制度)を整えることが急務です。
とくに中小企業の場合、入社後、必要な研修やレクチャーが十分に提供されないまま、業務に当たらざるを得ないケースが多く見られます。これが、前述の負の連鎖の根源となります。
そこで、中途採用社員の立場になり、新しい環境での不安を軽減し、思う存分に力を発揮できるプログラムを用意しましょう。
充実したオンボーディングプログラムの要素 |
|---|
|
オンボーディングに関する詳細は、以下の記事もあわせてご覧ください。
中途採用社員の知見を取り入れる仕組みづくり
中途採用社員がこれまでに培ってきた経験や知見は、組織にとって貴重な資産となります。
「お手並み拝見」「ライバル意識」といった心理を乗り越えるためには、中途採用社員が持つ知見を積極的に引き出し、協力体制を敷いてしまうことが得策です。
中途採用社員の知見を活用する仕組みの例 |
|---|
|
「教える/教えられる」という一方的な関係性ではなく、「教え合い、学び合う」という双方向性の関係性を構築しましょう。これが組織風土として根付くにつれ、中途採用社員の定着率が向上していきます。
ダイバーシティ&インクルージョン教育の強化
ダイバーシティ&インクルージョン(D&I、多様性と包摂性)の理解と実践は、中途採用社員を含む多様な人材が活躍できる環境づくりに不可欠です。
D&Iの意識が根付けば、中途採用社員に対する排他的な雰囲気は消え、スムーズに協働できるようになります。
D&I教育の取り組み例 |
|---|
|
これらの取り組みを通じて、中途採用社員を含むすべての社員が互いを活かし合える組織文化の醸成を目指しましょう。
D&Iに関する詳細は、以下の記事もあわせてご覧ください。
まとめ①:中途採用社員が早期に辞める原因とは?
中途採用社員が早期に辞める原因は多岐にわたりますが、大きく分けると4つの理由が挙げられます。
①入社後に予想と異なる業務内容や職場環境に直面した場合です。採用時の説明と実際の職務内容が大きく異なると、失望感を抱きます。
②適切なオンボーディングの欠如です。新しい環境に適応するための支援が不足していると、 孤独感やストレスが増し、結果として離職の原因にになります。
③職場の人間関係が円滑でないことです。既存社員とのコミュニケーションがうまく取れず、孤立感を覚えることが、中途採用社員の離職を引き起こします。
④過度な期待とプレッシャーです。即戦力として扱われ、本来の適応期間が与えられない中で成果を求められると、プレッシャーからくる心理的負担が離職に繋がります。
これらの原因に対処するためには、正確な職務内容と期待の共有、充実したオンボーディングプログラムの構築、職場のサポート体制の強化が不可欠です。
まとめ②:中途採用社員の定着を促進するための具体的方法
中途採用社員の定着を促進するためには、いくつかの具体的な方法が効果的です。
まず、入社初期のサポートを強化することが重要です。新しい環境での適応をスムーズにするために、メンター制度を導入し、経験豊富な社員が新入社員をサポートする体制を整えましょう。日常業務だけでなく、企業文化や社内ルールの理解を助ける役割も担います。
次に、定期的なフィードバックと評価の場を設けることです。新しい業務に取り組む中途採用社員が課題や悩みを共有できる機会を設け、上司だけでなく同僚とも意見交換ができる環境を作ることが大切です。これにより、問題の早期発見と解決が図れ、社員の安心感や信頼感が向上します。
さらに、キャリアパスの明確化も欠かせません。中途採用社員が長期的にキャリアを築いていくためには、自身の成長のビジョンを持てることが不可欠です。定期的なキャリア面談を通じてスキルアップや昇進のチャンスを提供し、目標達成に向けた具体的な支援を行いましょう。
また、柔軟な働き方の提供も効果的です。リモートワークやフレックスタイム制度を整備し、多様な働き方を認めることで、社員一人ひとりのライフスタイルに合わせた働き方を可能にします。これにより、ワークライフバランスが向上し、結果として社員の働く意欲と定着率が高まります。
お互いの理解を深めるためのチームビルディング活動も推進しましょう。社内のイベントやプロジェクトを通じて、社員同士の交流を活性化し、協力関係を築いていくことが望ましいです。これにより、中途採用社員と既存社員のコミュニケーションが円滑になり、職場の一体感が増します。
最後に、社員の意見を積極的に取り入れる企業文化を醸成するです。定期的なアンケートや意見交換会を実施し、社員の声を真摯に受け止め、改善策を取り入れる姿勢を示すことで、社員のエンゲージメントが向上します。
以上の取り組みを実践することで、中途採用社員の定着が促進され、組織全体の成長と安定を図ることができるでしょう。
さいごに
中途採用社員を「部外者」ではなく、組織に新たな価値をもたらす貴重な人材として迎え入れ、尊重することが、組織成長の鍵といえます。
やはり私たちは、尊重されたいし、リスペクトされたいし、支え合いながら結果を出したいのです。
多様なバックグラウンドを持つ人材が互いを認め合い、協働できる環境を整えることが、中途採用社員を含むすべての社員の定着率向上と、活力ある職場の創出につながります。
- 人材採用・育成 更新日:2024/11/19
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-