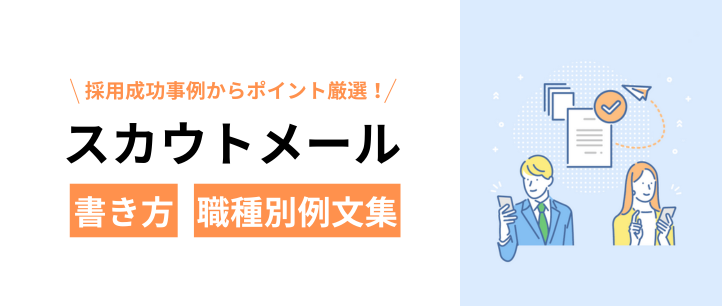現場担当者が身に付けるべき面接力とは? 採用を成功に導く「見抜く」「惹き付ける」の極意
現場担当者の「面接力」は採用活動の成否に直結する重要な要素。特に中途採用においては、採用企業と候補者とが“相互に見極め合う”ことになり、担当者には確かな面接力が求められます。
しかし、採用担当者として多忙であるがゆえ、面接を「現場任せ」にしてしまっている方も多いのではないでしょうか?
自社の印象を大きく左右する「面接」の場では、日常業務の中での「仕事力」とは異なる「面接力」が求められます。
そこで、面接力とは何か。そして、現場担当者の面接力を向上するためのポイントはどこにあるのか。企業の採用コンサルティングや面接官向けの研修などを数多く行う人材採用のスペシャリスト、株式会社HRディレクション・パートナーズ代表取締役の平尾英治さんにお聞きしました。
-

-
平尾 英治 さん 株式会社HRディレクション・パートナーズ代表取締役
1991年大学卒業後、株式会社リクルートに入社。同社HR事業部門に所属。求人広告を通じて、多くのクライアント(顧客)とカスタマー(求職者)のマッチングを実現。人材の採用広報活動や、採用戦略立案、採用基準策定、選考プロセス設計など採用支援業務に幅広く従事した後、採用コンサルタントや研修講師の実務経験を経て、2014年株式会社HRディレクション・パートナーズ設立。採用コンサルティング業務や各種研修コンテンツの設計・講師業務に携わる。主に面接官、リクルーター、採用担当者に対して年間約150本の研修、講演、セミナーに登壇し、企業の採用を成功に導くための講師業務に従事している。
面接担当者に必要な2つのスキルとは
— 初めに、面接の担当者にはどのようなスキルが必要ですか?
平尾さん: 主に2つあり、「候補者を見抜くスキル」と「候補者を惹き付けるスキル」が求められます。
面接担当者は、候補者から情報をヒアリングすることによって自社で活躍できる人材かどうかを見抜き、その上で候補者に対しては自社で働くことの価値についてしっかりと伝えることで興味を惹き付けるという両面を担う必要があるのです。
— 人材を見抜くという視点は面接官の役割として一般的だと思いますが、惹き付けるという観点は現場担当者の場合、意外と抜け落ちがちかもしれませんね。
平尾さん: そうですね。面接では候補者を評価するだけでなく、候補者に興味や関心を抱かせ、志望度を向上させることも非常に重要です。
候補者に対して一方的に質問をしたり、企業が伝えたい内容だけを伝えたりしても、惹き付けにはつながりません。候補者のニーズをある程度想定しながら、候補者が求める情報を提供していくことが大切です。
面接力の向上の注意点や魅力づけのポイントについてはこちらの記事でも紹介しています。
関連記事:【後編】面接力向上のポイントと注意点とは?|人財を入社につなげる魅力づけの方法
候補者を「見抜く」3つの視点
— 候補者を見抜くポイントはありますか?
平尾さん:主に、次の3つがあげられます。
- 対人印象
- 戦力性
- 定着性
それぞれ解説します。
「対人印象」によるネガティブチェック
平尾さん:1つ目は、候補者の態度やマナーといった「対人印象」です。
ミスマッチ人材の入社を未然に防ぐべく、第一関門としてネガティブチェックを行うことをお勧めします。
対人印象は、主に「見た目」「話し方」「話す内容」の3つで構成されます。これらのポイントを確認し、例えば「終始うつむき加減で目線が合わない」「声が小さくて話が聞き取れない」「会話のキャッチボールができない」など、候補者に対して極めて強い違和感を感じた場合、ネガティブチェックの対象にしておいた方が無難でしょう。
「戦力性」で現在のスキルを、「定着性」で将来性を評価
平尾さん:続いて、「戦力性」「定着性」という2つのポイントで候補者を見抜いていきます。
「戦力性」は、候補者の知識やスキル、専門性などです。例えばコミュニケーションスキルやリーダーシップ、マネジメントスキルなど、自社が求める戦力要件と、候補者が現在既に有しているスキルとのマッチング度合いを見極めます。
「定着性」は、転職理由や志望理由、今後のビジョンなどです。それらを聞き出すことで、早期離職のリスクがないか、定着する人材かどうか、候補者の将来性を見抜くことができます。
— 「対人印象」で候補者をふるいに掛けた上で「戦力性」と「定着性」の両面が重要になるのですね。
平尾さん:面接の担当者は、「候補者ができること・自社が求めていること 」と「候補者がやりたいこと ・自社でできること」という双方のマッチングレベルを意識して面接を進めることが大切です。
候補者を「惹き付ける」3つのポイント
— 次に候補者を惹き付けるためのポイントを教えてください。
平尾さん:大前提として、面接官となる現場担当者には、現在の採用市場について、求職者よりも求人数の方が多い「売り手市場」であることを正しく理解していただく必要があります。良い人材がいても、会社の顔である面接官が候補者に選ばれないと、採用成果につながらないということです。
それを踏まえ、以下のポイントを意識して候補者を惹き付けていきます。
- 配慮
- 態度
- 情報
それぞれ解説します。
候補者の心を開く細やかな「配慮」
平尾さん:まずは候補者に対する細やかな「配慮」が欠かせません。その一例が、面接の冒頭で行うアイスブレイクです。
特にキャリア採用では、1〜2分程度の短い時間でも、本題に入る前に雑談などを交えて候補者の緊張を和らげることで、心理的な壁を取り払い、リラックスした雰囲気をつくり出すことができます。
また、面接中に自社の情報を伝える際の言葉選びにも配慮が必要です。現場担当者にとっては日頃から使っている言葉が、候補者にとってはなじみのない業界用語や専門用語かもしれません。そうした用語は使わずに誰もが理解できる平易な言葉を選び、時には丁寧にかみ砕いて説明することで、候補者に安心感を与えながら、情報を正確に届けることができます。
候補者にとって面接官の「態度」が企業の印象に直結する
平尾さん:面接担当者の「態度」は、候補者がその企業に対して抱く印象を決定付けると言っても過言ではありません。
特にキャリア採用の場合、候補者と面接官は共に社会経験を持つビジネスパーソンとして対等な関係です。したがって、信頼関係を築く上での最低限の土台として、丁寧な言葉遣いや真摯(しんし)な傾聴姿勢といった基本的なビジネスマナーを改めて意識する必要があります。
一方で、無意識のうちに候補者に不快感を与え、企業の評価を下げてしまうNGな態度も存在します。例えば、椅子の背もたれに寄りかかって腕や足を組むといった横柄に見える姿勢や、逆になれなれし過ぎたり、不必要にフランクすぎたりする話し方は、相手から「敬意を欠いている」と受け取られかねません。
表情についても同様で、無表情で仏頂面だったり、抑揚のないドライな口調で淡々と話したりすることも、候補者を不安にさせてしまう原因となります。
面接を行う担当者は、常に相手に敬意を払い、穏やかで丁寧なコミュニケーションを心掛けるべきです。ゆっくり、少し大きめの声で、表情豊かに話すことを意識するだけでも、印象は大きく変わるでしょう。
さらに、質問の内容にも注意が必要です。採用選考とは直接関係のない、面接官自身の興味本位に基づく脈絡のない質問をすることは、候補者に「何のために聞かれているのだろう」という不信感を抱かせます。
— アイスブレイクが重要である一方、面接と直接関係のない話をする際は話題選びにも配慮が必要ということですね。
平尾さん:最も注意すべきなのが、不適切な質問をしてしまうケースです。家族構成や本籍・出身地 、思想など、本人の適性や能力とは関係のないプライベートな領域に関する質問は、就職差別につながる可能性があり、法的にも「違法行為」とされています。
特に面接に慣れていない現場担当者の場合、悪意なく過去の慣習からこうした質問をしてしまう可能性は多分にあるでしょう。しかし、現在の社会規範や法令では不適切です。面接官は、これらの質問が候補者の人権を侵害し、企業の信用を損なうリスクがあることを認識し、避ける必要があります。
候補者が知りたい「情報」を提供する
平尾さん:候補者の入社意欲を高めるためには、候補者が本当に知りたいと思っている情報を提供することが重要です。一方的な説明ではなく、候補者の疑問や不安に応える形で情報を伝えることで、企業への理解と共感を促します。
例えば、「仕事内容やミッション」 については、単に業務内容を羅列するだけでなく、具体的な業務プロセスや、その仕事を通じて生かせる知識・経験、入社後に新たに習得できるスキルや資格などを明確に伝えましょう。また、困ったときに誰に相談できるのかといったサポート体制や、業務マニュアルの有無といった情報も、候補者の不安を解消し、安心感を与えるポイントです。
多岐にわたる情報を事前に準備し、面接の場で候補者の関心に合わせて的確に提供していくことが、候補者を惹き付けるための鍵となるでしょう。
評価バイアス対策と候補者のアピールを見抜く質問術
— 他に面接担当者が注意すべきポイントはありますか?
平尾さん:以下、重要なポイントが2つあります。
- 評価バイアスの排除
- 候補者の言葉を掘り下げる
それぞれ解説します。
面接担当者のバイアスを排除し、客観的に評価しよう
平尾さん:面接では担当者の「好み」や「思い込み」といった主観で評価が左右されてしまう、いわゆる「評価バイアス」が課題になることがあります。
例として、まず「ハロー効果」が挙げられます。これは、候補者の目立った特徴に引きずられて、他の部分の評価までゆがんでしまう現象。例えば、「語学が堪能」「大手・有名企業 出身」「高学歴でリーダー経験がある」といったポジティブな特徴があると、それだけで他の能力も高いように感じてしまい、評価が上振れしやすくなるのです。
また、「第一印象」も強力なバイアス要因です。「爽やかな雰囲気」「ハキハキと元気よくあいさつができる」など、最初の印象が良いと、それだけで高く評価してしまいがちです。しかし、その爽やかさやコミュニケーション力が、実は表面的なものに過ぎない可能性もあります。話のテンポが良い、キャッチボールがスムーズといった点も、一見ポジティブですが、評価をゆがめるバイアスになり得るのです。
— 面接担当者のバイアスを取り除くためには、具体的にどのような方法がありますか?
こうしたバイアスを排除するためには、面接担当者が自分自身のバイアス(面接官の好み)を認識しなければなりません。
その方法として、私が行っている面接官研修では、参加者に「あなたの評価が上振れしやすい候補者はどんな人ですか?」といった問い掛けをするワークを実施しています。すると、「元気がいい人が好きです」「指示しなくても動ける人がいいです」など、さまざまな答えが出てきますが、それらの多くが実はバイアスの表れなのです。
一見すると「コミュニケーション能力」や「自律性」といったスキル項目に見えるかもしれませんが、実際には“個人的な好み”による印象評価に過ぎないことも多く、それを自社の採用基準と混同してしまう危険性があります。
逆に「評価が下振れしやすい候補者」についても同様で、無意識のうちに主観的な評価が入り込んでしまいます。
自分がどのような候補者に対して、無意識に高評価し、逆に、どのようなタイプを低評価する傾向があるのかを自覚することで、バイアスに惑わされず、候補者の本質的な能力や経験を客観的に評価できるようになります。
採用選考で注意すべきバイアスについてはこちらの記事でも紹介しています。
関連記事:確証バイアスとは、採用選考や人材評価のエラーを防ぐポイントと注意すべきバイアスを紹介
候補者の「成果」や「美辞麗句」に惑わされない評価のコツ
平尾さん:もう1つのポイントは、候補者の言葉をうのみにせず、掘り下げて質問し、評価するということです。面接では、候補者から過去の経歴について「これだけの成果を上げた」「達成率は〇〇%だった」など、輝かしい実績をアピールされるでしょう。
候補者の方も面接対策をしっかりされていますから、ご自身の成果(リザルト)をアピールしてくるのは当然の流れです。ビジネスパーソンとして結果を出すのは重要であり、過去に成果を残していれば再現性も期待できるため、評価材料の一つと考えることは問題ありません。
しかし、「成果=優秀」と安易に結び付けてしまうのは要注意。大切なのは、その成果が「どのような行動(アクション)によるものなのか」をセットで捉えることです。
行動やプロセスに対する候補者の意識レベルを判断するために、成果だけでなく「反省点」や「課題」を候補者自身がどれだけ深く言語化できているかを確認してみましょう。
— 聞こえの良い成果だけで満足するのではなく、具体的な行動を深掘りして質問することが重要なのですね。
平尾さん:そのとおりです。そしてもう一つ、非常に注意が必要なのが、候補者が使いがちな抽象的な「アクションワード」です。
例えば、「関係者を巻き込みました」「主体的に働き掛けました」「関係各所と調整を図りました」「プロジェクトメンバーの意見を取りまとめました」といった言葉。これらは聞こえの良い表現ですが、よく考えると具体的に何をしたのかが全く分からないですよね。実態は単なる報連相レベルのコミュニケーションだった、という可能性も十分にあります。
こうした抽象度の高いアクションワードが出てきた場合はうのみにせず、「具体的に、どのように巻き込んだのですか?」「どのような手順で調整を進めたのですか?」といったように行動事実を確認していきましょう。
「現場が求める人」と「人事が求める人」のズレを防ぐには?
— 面接を行う際、多くの場合、現場部門から「こんなスキルを持った人が欲しい」という要望を吸い上げて人物像を設定すると思います。しかし、特に採用経験の少ない企業などでは、現場の要望と、人事や面接担当者が考える要件との間に認識のズレが生じやすいのではないでしょうか?
平尾さん: まさにおっしゃるとおりで、現場と人事との間で求める人物像のすり合わせを行うことはとても大切です。現場は、どうしても日々の業務に必要な専門知識や技術、つまり「テクニカルスキル」を過度に重視しがち。「このツールが使える人」「この業界の経験が豊富な人」といった専門的なスキル要件ばかりを具体的に挙げてくることが多いものです。
一方で、チームで成果を出すために不可欠なコミュニケーション能力や問題解決能力、チームワーク、リーダーシップ といった「コンピテンシー(行動特性)」については、現場の認識が薄い、あるいは言語化できていないケースが少なくありません。
— 現場は即戦力となるスキルを求めがちだということですね。では、面接担当者としてはどのように対応すべきでしょうか?
平尾さん: 現場から上がってきたテクニカルスキルに関わる要件をうのみにせず、「それは本当に“必須(Must要件 )”なのか、それとも“あればなお可(Want要件 )”なのか」を冷静に仕分ける必要があります。
同時に、人事担当側からは「チームワーク」や「リーダーシップ 」など、どの 部署でも共通して求められるコンピテンシー要件を明確に定義し、それを現場にも理解してもらうことが重要です。「こういう行動特性を持つ人材でないと、いくらテクニカルスキルがあっても活躍は難しい」とはっきり伝えましょう。
このように、テクニカルスキルとコンピテンシーの両面から評価基準を定め、現場と人事がしっかりと共通認識を持つこと。これが、入社後の「期待外れ」を防ぎ、本当に活躍できる人材を採用するために重要になるのです。
現場担当者の面接力向上が、自社の新しい未来を創る
平尾さんのお話で、採用活動における現場担当者の「面接力」の重要性が分かりました。
「仕事力 = 面接力」ではありません。 人事担当者の方は現場の各部署から面接官をアサインする際、個人に丸投げするのではなく、企業としての採用方針や判断基準とともに、今回解説したようなポイントも伝えることが大切です。
採用競争が激しくなる今こそ、面接力を高め、自社にマッチする人材を確保することこそが、企業の新しい未来を創る力になるでしょう。
- 人材採用・育成 更新日:2025/05/20
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-