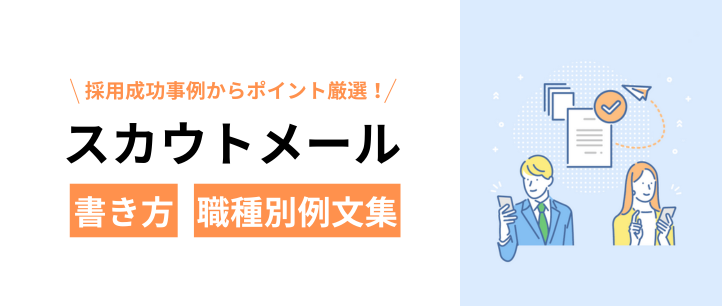「就活ハラスメント」とは? 専門家が語る企業のリスクと5つの対策
就活ハラスメントとは、就職活動中やインターンシップの学生らに対するセクシュアルハラスメントやパワーハラスメントのことを指し、具体的には以下が該当します。※
- 面接時の性的な質問や、高圧的な圧迫・人格否定の言葉
- 採用を見返りとして、特別な関係を迫る/断ると不採用とする
- インターンシップ時に、食事やデートにしつこく誘う
- インターンシップ中の学生に、人格否定の暴言を吐く
- 内定を出した就活性に対して、他社の選考辞退を促し、自社への入社を強要する
就活ハラスメントは、被害を受けた学生にとって大きな心理的ダメージとなるだけでなく、企業にとってもイメージの低下と、それに伴う応募数の減少・既存社員の退職リスクなどが生じる重大な問題です。労働施策総合推進法および男女雇用機会均等法に基づく指針においては、就活ハラスメントを防止することが望ましいと明記されており、企業側の対応も求められています。
今回は、ハラスメント対策の専門家として企業研修なども行っている相場 聖さんに、企業として行うべき対策についてお話を伺いました。
最善のハラスメント予防は「正しい信頼関係」の構築
— 今日はよろしくお願いします。近年「ハラスメント」に関する話題は増える一方ですが、その捉え方や種類はどのように変化しているのでしょうか?

相場さん: はい。私の感覚では、1年に1つは新しいハラスメントが生まれているような状況ですね。種類としては非常に多くなっていると思います。
その背景には、ハラスメントそのものの捉え方が多様化してきているという事情もあるでしょう。
従来は年齢や性別、役職などを軸に力関係の強い方がその立場を利用して行う嫌がらせのことを「ハラスメント」と定義することが一般的でしたが、そのような軸も失われつつあるということです。 「ハラハラ(ハラスメントを指摘するハラスメント)」という言葉まで生まれていることが、それを象徴しています。
— そのような環境ですと、ハラスメントを防止するということも難しくなってきているのではないでしょうか。
相場さん: そのように感じる方が多いでしょう。私も企業研修に伺うと、「何がハラスメントで、何がハラスメントではないのか、とにかく全てにおいての明確な線引きを教えてほしい」とよく言われます。しかし、完全に明確な線引きを国としても定め切れていないからこそ、難しさがあります。
とはいっても、これは「線引きが失われていった」ということではありません。
例えば「相手の肩を触る」という状況があったとして、それがハラスメントになるかならないかは状況によって左右されます。
家族や恋人同士であれば普通はハラスメントになりませんし、友人同士でもハラスメントにはなりにくいはずです。これは時代によって左右されません。
では、どのような場面で「ハラスメント」として受け取られてしまうか。その分かれ目にあるのは「信頼関係」なんです。
— 信頼関係ですか。ぜひ詳しく聞かせてください。
相場さん: はい。家族や恋人同士、友人同士の間には基本的に信頼関係が存在していると思います。それがあるからこそ、ハラスメントにはなりにくい。
ただ、職場や採用活動の現場で、家族や友人同士の間にある、長年をかけて蓄積してきた信頼関係を構築するのは不可能です。
その時に重要になってくるのが、「お互いを尊重する」ということですね。単に仲が良いとか、付き合いが長いとか、そういうことではなく、互いを尊重し合うことで生まれる「正しい信頼関係」が重要だと考えています。

「就活ハラスメント」が起こる原因と企業の損害
— 相手への尊重がベースとなった信頼関係が重要であることは理解できました。それがないから「就活ハラスメント」が起こってしまうということですね。
相場さん: はい。例えば就活ハラスメントの代表的な例として「圧迫面接」がありますが、相手を尊重していればそのような行動には出ないはずです。
他にも、採用をちらつかせて個人的な関係を迫ることや、インターンシップに参加した学生に限度を超えた厳しい言葉を投げ掛けること、内々定の条件として他社の選考を断ることを迫る「オワハラ」をすること、いずれも相手への尊重がないからこそ発生してしまう現象です。
— なるほど。しかし、面接やインターンシップでの厳しい態度は「学生のため」と考えている人もいるのではないでしょうか。
相場さん: 学生のために「あえてそうしている」という例ですね。しかし、当人がそう思っていても、相手がそう思えないのであれば、それはハラスメントです。だから「正しい信頼関係」を持つこと、つまり、相手からも信頼を得ている必要があるのです。
そのためには、相手と自分との関係性の違いを客観的に認識し、バランスを調整する能力が求められます。
いま、採用市場は売り手優位(学生優位)と言われますが、それでも面接官と就活生とでは明らかな立場の傾斜があり、面接官の方が強い立場にいることは否めません。そもそも学生と社会人という立場の違いがある上で、審査をする会社側の人間であるということ、年齢が上であるということもその理由となります。
その関係性において「正しい信頼関係」を築くためには、「自分が相手にとって強い圧を感じる存在である」ことを認識した上で、相手を尊重する態度を取らなくてはならないのです。リクルーターになることが多い若手社員であっても、これは同様です。
つまり「同僚や部下と接するのと同じ態度」では、まだ学生との間にある立場の違いは乗り越えられない可能性があります。
そのくらい慎重に自分を客観視する必要があるということですね。

— 仮に就活ハラスメントが発生してしまった場合、企業はどのような損害を受けるのでしょうか。
相場さん: まず大きいのが、「レピュテーションリスク(評判失墜)」です。今の就活は情報戦ですから、学生同士で企業のインターンシップや面接の内容、評価について口コミで情報が広がっていきます。
そのとき「あのインターンシップで暴言を吐かれた」とか、「あの企業のリクルーターから個人的に食事に誘われた」とか、そんな評判が出回れば採用市場における競争力が大きく損なわれるのはもちろん、事案の内容によっては口コミにとどまらずニュースとして全国に広がり、売り上げや株価にも影響を与えるほどの大きな損害が出かねません。
また、仮にレピュテーションリスクにつながらなかったとしても、採用の精度には大きく影響するでしょう。
— 採用の精度に影響するとは、具体的にどのようなことでしょうか?
相場さん: 圧迫面接や人格否定のような、圧が強い採用活動をしていると、その場では適応しているように見えても、学生は萎縮して「自分の意見を言えない」「質問ができない」という状態に追い込まれてしまいます。
結果として正しい見極めや企業理解の機会を失うこととなり、採用側にとっては大きなデメリットです。
企業全体としての損害を避けるためだけでなく、人材不足の時代に自社が求める学生を正しく見極め、就社意識を育ててもらうためにも、就活ハラスメントは避けるべきです。
企業が行うべき5つの「就活ハラスメント防止策」
— では具体的に、企業としてどのような対策を取るべきでしょうか。
相場さん: 理想では「学生との立場の違いを認識して、相手を尊重し、信頼関係を築き上げながら採用活動をすべき」という理念を採用に関わる全ての人に理解してもらうことが最善です。

しかし、採用活動には経営陣や人事だけでなく、リクルーターや面接官として一般社員も多く関わることから、理念の浸透が難しい場合も多いでしょう。
なので、次の5項目を軸に対策を行うことをお勧めしています。
- 企業としての方針の明確化と周知
- 採用プロセスの見直しと採用活動のルール策定
- 行動規範やガイドライン・マニュアルなどの作成・整備
- 教育研修の実施
- 相談窓口の設置
1つずつ解説します。
1.企業としての方針の明確化と周知
経営層や人事責任者から「就活ハラスメントを容認しない」ことをトップメッセージとして打ち出し、自社が採用活動を通じて大切にしたい価値観(お互いに尊重し合う、心理的安全性を担保する)などを社内に示していきます。
これをステートメントとして社外にも発表することで採用ブランディングに役立てている例もありますので、ぜひ参考にしてください。
ポイントは、禁止事項を形式的に定めるのではなく、「なぜ対策が必要なのか」「どんな企業文化を目指すのか」を明文化していくことです。禁止事項を定めて線引きを始めると、事案が発生するごとに線が狭まっていき、結果的に採用活動に支障を来す可能性があります。
採用に関わる人全員が行動基準として振り返ることのできる内容にしましょう。
2.採用プロセスの見直しと採用活動のルール策定
インターンシップから内定までの各ステージで、どのような社員が学生と接点を持つのかを可視化し、ハラスメントリスクを洗い出します。
特に、リクルーター面談やOB・OG訪問、面接など密室性の高いステップと、内々定出しなど採用活動においてキーとなるステップに注意が必要です。
リクルーター選定の基準を見直したり、学生とのメールでのやりとりや人事も確認できるプラットフォーム上に限ったり、面接でのやり取りを記録したり、「オワハラ」を防止するために学生の意思を最大限尊重することを明文化して求めたり、といった具体的な対策が考えられます。
3.行動規範やガイドライン・マニュアルなどの作成・整備
相手への尊重をベースに接するとはいっても、「尊重の仕方」を判断するためのベースにある考え方が年代などで異なるため、「何がハラスメントに当たるのか」を具体的につかむために、ガイドラインを作成するといいでしょう。
例えば「圧迫面接はしない」「個人的にデートや食事に誘わない」「プライベートには立ち入らない」など当たり前のことから、「面接で尊敬する人物を聞かない」といったことまで盛り込むことができます。
参考:面接官が注意したいNG質問・NG行動とは?対策・対処法も紹介
作成のポイントは、それが「リスク回避のための縛り」としてではなく、「相手を不快にさせず、良好なコミュニケーションを取るためのサポートツール」として機能するように意識することです。
作成したら年に一度は見直し、時代の変化に合わせて更新していくようにしていくと良いでしょう。

4.教育研修の実施
ガイドライン・マニュアルにとどまらず、採用担当者、面接官、リクルーターに向けて就活ハラスメントに関する基礎知識をインプットする研修も有効な対策です。
ここでは、ケーススタディやロールプレイを交え、学生の立場に立ってリアルに考えることができるよう工夫すると、さらに効果が上がります。
5.相談窓口の設置
最後に、プライバシーを守り、匿名性を確保しながら学生の相談を受け付けることのできる窓口を設け、採用サイトや説明会などを通じて周知することも重要です。
被害申告があったら速やかに対応できるよう、対応フローも併せて確立しておきましょう。
「相談がない」ことをもって、「就活ハラスメントは起こっていない」と断定することのないよう、徹底的な周知活動をするよう心掛けてください。
学生から「就活ハラスメント」の相談を受けたら……? すぐに行うべき5つのステップ
— 最後にあった「相談窓口の設置」についてもう少し教えてください。学生から相談があった際、企業としてどのように対応すべきでしょうか?
相場さん: 代表的な例をご紹介しますと、大きく分けて6つのステップで対応します。
- 相談の受付
- 事実関係の調査
- 被害者の救済・ケア
- 社内措置の検討・実施
- 再発防止策の策定・実施
- 必要に応じて事案を公表
こちらも、1つずつ順を追って解説します。

1.相談の受付
先ほど解説したとおり、相談を受け付けたら学生のプライバシーと匿名性を最優先として、学生の指名はもちろん、事案の内容もいったん、外部に漏れないよう厳重に管理します。匿名での通報ができる仕組みを導入するのも良いでしょう。
その上で、社内では窓口担当者を明確に決めておき、空白ができないよう、できれば複数人で対応すると良いですね。
2.事実関係の調査
次に、事実関係を調査します。
まずは学生に「いつ・どこで・どんな内容のハラスメントを受けたのか」「誰が加害者か」といったことを聞き出し、その後の調査で学生の名前を出しても良いかを確認します。
その上で、加害者であると申告を受けた社員への聞き取り、証人となり得る第三者(グループディスカッションやインターンシップの他の参加者、同席した面接官など)へのヒアリング、面接の記録やメール・通話記録など客観的な証拠も収集して調査を行ってください。
しかし、実際には密室性が高かったり、意見の食い違いがあったりして調査は難航することが多いです。必要であれば法務部門や外部の弁護士、コンサルタントなどによる第三者委員会の設置も検討すべきでしょう。
3.被害者の救済・ケア
調査の結果が出るのを待たず、被害者(学生)が2次被害や報復を受けないよう、保護する必要があります。
具体的には、加害者とされた社員を採用活動から外す、自社から被害者への連絡手段を一本化するなどの方法です。
その上で、必要に応じてカウンセリングの機会を提供するなどメンタル面のケアを行い、さらに必要であれば継続的なケアのために担当者が定期的に連絡を取れる仕組みをつくってください。
そして、調査の結果、自社に明らかな落ち度があったと分かれば、速やかに謝罪し、補償など具体的な救済措置の検討へと移ります。
4.社内措置の検討・実施
次に、加害者となった社員を就業規則や社内規定に基づき適切な処分を行います。
就活ハラスメントを抑止するためには社内に処分内容を広く周知することも有効ですが、ここではまず被害者(学生)の意向を確認しましょう。
本人が望まないのであれば、採用担当者やリクルーターなど採用に関わるメンバーに限って、今後の再発防止を考えるための事例として匿名で共有します。
5.再発防止策の策定・実施
事案が発生した背景を振り返り、なぜ就活ハラスメントが起こってしまったのか、どの段階で防ぐことができたのかを検討し、その結果を具体的な施策につなげていきます。
例えばリクルーター研修、面接官研修、マニュアルの見直し、相談窓口の周知徹底などです。
6.必要に応じて事案を公表
もしも、発生した事案がニュースになるなどして社会的に大きな注目を集めた場合には、レピュテーションリスクを最小限に抑えるため、報道対応やプレスリリースなどによって外部への説明が必要になる場合があります。
その際も被害者や関係者のプライバシーには十分に配慮し、発表の方法、内容、タイミングは慎重に検討しましょう。
— 具体的な内容で大変参考になります。ありがとうございました。

「相談がない」も要注意!就活ハラスメントを防いで良い採用活動を
取材の中で、就活ハラスメントに注意すべき企業の特徴として、「社内のハラスメント相談窓口への相談件数がない、または非常に少ない」というものが挙げられていました。それは「ハラスメントがない安全な環境」ではなく、「ハラスメントの相談がしにくい環境」である可能性があるからなのだそうです。
記事の中でもハラスメントによって学生に不要な圧力がかかり、結果として正確な見極めも就社意欲の育成もできなくなるという内容をお伝えしましたとおり、採用活動にとって「就活ハラスメント」には一切の利がありません。
まずは経営陣、人事から意識を変え、それを採用に関わる社員に広く周知できるよう準備していきましょう。
【参考資料】
就活ハラスメント 対策リーフレット(厚生労働省)
- 人材採用・育成 更新日:2025/04/09
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-