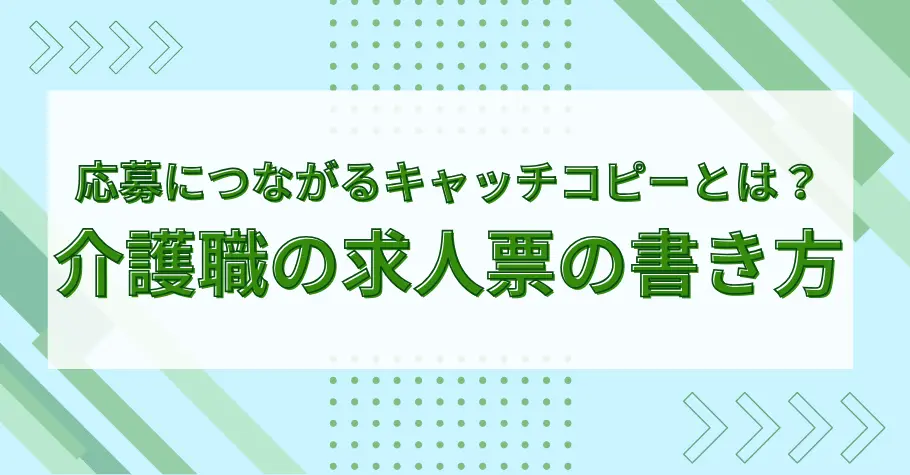応募につながるキャッチコピーとは? 介護職の求人票の書き方(キャッチコピー編)【介護職採用シリーズ_vol.12】
就職・転職情報サイトでは、求職者が職種や希望勤務地などのキーワードで求人を検索すると、検索条件に一致する求人票(求人情報)が一覧で表示されます。このとき、求職者の目にとまるのが、求人票ごとに太字で表示されるキャッチコピー(上の図の赤色で囲んだ部分)です。
求人キャッチコピーには、主に、下記の3つの役割があります。
■求人への興味づけ
■ブランディング
■応募数増加
1つ目は、自法人の魅力や理念、ビジョンをターゲットとなる求職者に伝え、興味を引く役割です。求職者は一覧のキャッチコピーを見て、直感的に気になった求人票をクリックして詳細を確認します。応募につなげるためには、まずは詳細を見てもらわなければなりません。そのためには、求職者の興味を引くキャッチコピーの打ち出し方を考える必要があります。
2つ目の役割は、自法人のブランディングです。自法人に他法人にはない特徴がある場合、それを一目で伝えるキャッチコピーを作成すれば、求職者にインパクトを強く残すことができます。
3つ目が、応募数を増やすことです。キャッチコピーで求人に興味を持った求職者が詳細画面を閲覧すると、さらにその法人や仕事内容への興味を深め、応募というその後のアクションにつながりやすくなります。
1.基本ターゲットを決める
まずは、求人情報を届けたい基本ターゲットを決めます。そういわれても、人手不足の介護法人では「応募してくれる方を幅広く歓迎する」が採用担当者の本音かもしれません。しかし、ターゲットの幅が広すぎると、誰に向けているのかわからないキャッチコピーになり、興味づけや応募数のアップにはつながりにくくなります。
少しでも応募を増やすには、たとえば「30代~40代の女性」「飲食・ホテル業界で働く男性」「20代の第二新卒者」などと、ある程度ターゲットを絞り込む必要があります。多くの場合、求人では、性別や年齢で制限をかけることはできません。年齢については制限理由を記載することで制限をかけることができる場合もあります。しかし、基本ターゲットを決める段階ではペルソナを設定するためにあえて具体的に性別や年齢もイメージしておくことが大切です。そうすることで、求職者に「自分のことかも」と思ってもらえる可能性が高まるからです。
ターゲットの絞り込み方がわからないときは、定着している自法人の職員を思い浮かべてみましょう。すると、「30代以上で家庭を持つ女性が多い」「サービス業から転職した人が多い」「人数の比率は女性が多いが、勤続年数が多い職員には男性が多い」といった傾向が見えてきます。ここからターゲットを決めていくとよいでしょう。
- 人材採用・育成 更新日:2025/02/05
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-