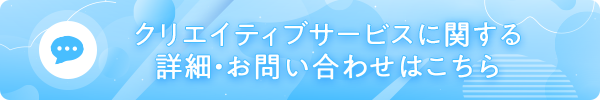【2021年最新版】新卒採用担当者必見!「採用広報ツール」の使い分けポイント ―【特集】企業として出すべき採用広報とは? 第2回
池内智美
株式会社マイナビ 就職情報事業本部 総合企画運営統括部 戦略企画運営部
2007年に株式会社マイナビ入社。現企画運営統括部に配属。大阪支社にて、関西の大手メーカー、インフラの企業の採用広報支援に携わり、その後東京本社に異動。総合電機メーカー、総合商社、金融機関などを中心に採用の広報戦略策定、企画、運用を担う。直近は、戦略企画運営部を立ち上げ、次世代の採用広報ツールの開発、市場開拓に従事。
福元健朗
株式会社マイナビ 就職情報事業本部 総合企画戦略運営部 戦略運営課
2014年に株式会社マイナビに入社。就職情報事業本部にて営業職として都内の企業を担当。16年に総合企画戦略運営部に配属となり、大手クライアントを中心に、企業の採用課題をツール制作やコミュニケーション設計を通して解決するソリューション業務に従事している。
就職活動を始めた学生の多くがまず訪れるのは、マイナビをはじめとした「ナビサイト」です。希望の条件を入力し、検索結果に挙がった企業の情報を調べるところから、就職活動は始まります。
今回のテーマである各社が自前で持つ「採用広報ツール」は、その後企業と学生が直接的な接点を持ったときに効果を発揮します。では、その前提で「採用広報ツール」はどのように使うべきなのでしょうか?
答えは条件検索だけでは浮かび上がってこない企業の風土や歴史、社員の人柄、これからの成長戦略などを学生に伝え、最良のマッチングをかなえるために使うべき、ということです。
新卒採用において、採用予定人数に対する充足率は非常に重要な指標ですが、企業が成長するためには単に「条件」が合う学生を必要な人数採用するだけではなく、自社にマッチした企業の成長を促す人材が必要です。
そのためには、企業が学生を知ることはもちろん、学生側も企業をよく知って、条件だけでなく社風や理念まで理解し納得した「相互理解」の上で内定を受諾してもらう必要があります。
今回のテーマである各社が自前で持つ「採用広報ツール」は、その後企業と学生が直接的な接点を持ったときに効果を発揮します。では、その前提で「採用広報ツール」はどのように使うべきなのでしょうか?
答えは条件検索だけでは浮かび上がってこない企業の風土や歴史、社員の人柄、これからの成長戦略などを学生に伝え、最良のマッチングをかなえるために使うべき、ということです。
新卒採用において、採用予定人数に対する充足率は非常に重要な指標ですが、企業が成長するためには単に「条件」が合う学生を必要な人数採用するだけではなく、自社にマッチした企業の成長を促す人材が必要です。
そのためには、企業が学生を知ることはもちろん、学生側も企業をよく知って、条件だけでなく社風や理念まで理解し納得した「相互理解」の上で内定を受諾してもらう必要があります。
| 採用サイトのメリット | 採用サイトのデメリット |
|---|---|
|
|
| コメント | |
| ナビサイトはもちろん、合同会社説明会などのイベントやSNSなどを通じて企業を知った学生は、ほぼ間違いなくその次に採用サイトに訪れますし、エントリーする企業を迷っているときや選考過程で疑問が浮かんだときなども、まずは採用サイトに戻って情報を調べ直しています。
採用サイトは網羅的に情報を提供し、初期の企業研究からエントリーシート提出時の情報提供、内定承諾のタイミングでのクロージングまで、全ての採用フローで活用される可能性があるツールです。 一方で、過去にサポネットで行った学生座談会でも「採用サイトのデザインが古くさく感じると、企業へのイメージも下がる」という声が聞かれたとおり、維持にコストがかかることも事実。5年もリニューアルせずに置いておくと、かなり古く感じられてしまうでしょう。 よく「エントランスにその会社の姿勢が表れる」といいますが、学生にとってはそれが採用サイトです。 維持コストはかかりますが、「採用サイトを持たない」という選択はお勧めできません。 |
|
| 映像のメリット | 映像のデメリット |
|---|---|
|
|
| コメント | |
|
採用において「カルチャーフィット」は非常に重要な指標ですが、企業側のカルチャーを最も効率よく伝えられる手段が「映像」です。実際に話し、動く社員の映像は、学生に非常に強い印象を残すでしょう。 特に社風や社員の人柄などに強みのある企業にとっては、ぜひ使っていただきたいツールです。 また、学生を会場に集めた説明会やセミナーの実施が難しい今、それらを映像として配信できることも大きなメリットとなります。 |
|
| パンフレットのメリット | パンフレットのデメリット |
|---|---|
|
|
| コメント | |
| コロナ禍によって学生と直接接触する機会が減っているため、パンフレットを制作する企業は減っています。自宅に届き、手に取ることのできるパンフレット自体が大きな差別化ポイントになっています。
また、難関校の学生ほど「読み込んで、自分で情報を整理して理解する」という方法を好むため、送付する学生を絞ってもいいかもしれません。 さらに、コロナ禍によって友人や学校の先生らと会えないため、就職活動に関する相談相手として「両親」の重要性が急速に高まっています。今の就活生の親御さん世代であれば紙のツールは相性がよく、一定のブランド感も感じてもらいやすいため、エントリーや内定受諾のタイミングで迷った就活生の背中を押してくれるかもしれません。 |
|
| イベントのメリット | イベントのデメリット |
|---|---|
|
|
| コメント | |
| 今の採用活動は、プレ広報期間を含めると1年以上と長期化しています。その中で、採用広報ツールの多くが学生からのアクセスを待つ必要のある「待ち」のツールである一方、イベントは企業側が積極的に学生との接触を図れる貴重な機会です。
また、社員に直接質問することのできるイベントは、学生にとっても貴重な機会となっています。調べれば誰でもアクセスできる情報ではなく、「自分が知りたい、自分だけの情報」を得られる唯一の場でもあるのです。 イベントの合間や修了後に、学生が社員にこそっと聞くような質問の仕方はオンラインだと実現が難しいところですが、マイナビではその課題を解決するアバタータイプのオンラインイベントツールを提供しています。ぜひご相談ください。 |
|
最後はSNSです。学生のみならず、読者の皆さんの生活にも深く入り込んでいるであろうSNSは、発信をするハードルが他のツールと比べてはるかに低いため、カジュアルかつスピーディーなコミュニケーションを取ることができます。
一方、不自然に学生の好みに「すり寄る」ような運用は学生にも見抜かれてしまうもの。また、更新が滞っていると、それはそれで悪印象にもつながりかねません。
一方、不自然に学生の好みに「すり寄る」ような運用は学生にも見抜かれてしまうもの。また、更新が滞っていると、それはそれで悪印象にもつながりかねません。
| SNSのメリット | SNSのデメリット |
|---|---|
|
|
| コメント | |
| オフな雰囲気や、イベントの裏側など学生が普通には見ることのできない情報をカジュアルに発信することのできるツールです。 また、LINEなどメッセージング機能が強いツールであれば、学生との連絡手段としても活用しやすいでしょう。 さらに、リプライやコメントで学生の質問に答えることができるため、育てていくことで採用サイト並みのプラットフォームとして機能させることも可能です。 ただし、一度始めると更新や検証、運用改善でマンパワーがかかります。覚悟を持って運用に臨む必要があることはぜひ覚えておいていただきたいと思います。 |
|
5つの採用広報ツールについて、そのメリット・デメリットと活用法をお伝えしました。
冒頭にも書いたとおり、採用広報ツールを使って情報を発信するのは、企業側が情報を積極的に発信することで「相互理解」を促し、採用の「質」を向上させることが目的です。
その情報をより効果的に伝えるために、ツール選びは非常に重要な選択の一つです。学生の就職活動の情報収集のあり方が変化した現在、限られた予算や人的リソースをどのツールに投資していくべきか、いま一度考えてみてはいかがでしょうか。
今日ご紹介した採用広報ツールは全て、マイナビでご提供可能です。長年の経験とノウハウから適切な情報発信をお手伝いできますので、ぜひお気軽にご相談ください!
冒頭にも書いたとおり、採用広報ツールを使って情報を発信するのは、企業側が情報を積極的に発信することで「相互理解」を促し、採用の「質」を向上させることが目的です。
その情報をより効果的に伝えるために、ツール選びは非常に重要な選択の一つです。学生の就職活動の情報収集のあり方が変化した現在、限られた予算や人的リソースをどのツールに投資していくべきか、いま一度考えてみてはいかがでしょうか。
今日ご紹介した採用広報ツールは全て、マイナビでご提供可能です。長年の経験とノウハウから適切な情報発信をお手伝いできますので、ぜひお気軽にご相談ください!
- 人材採用・育成 更新日:2021/10/15
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-