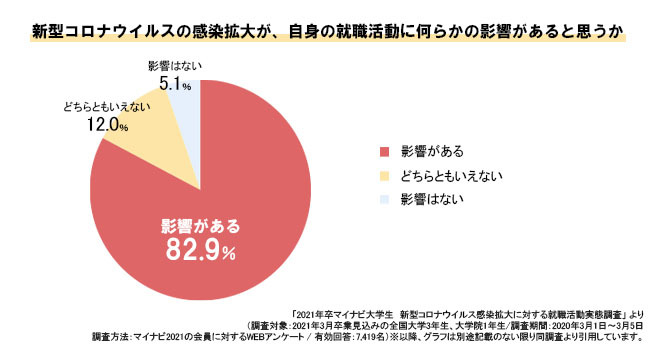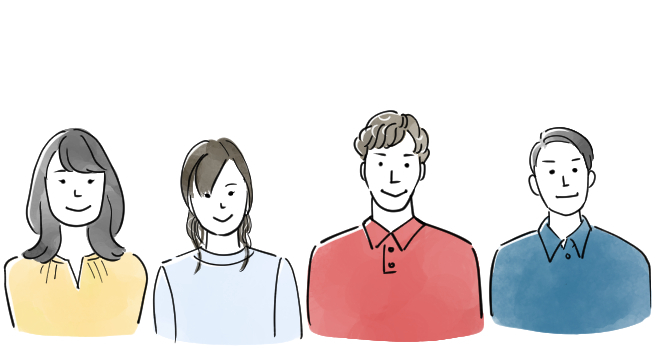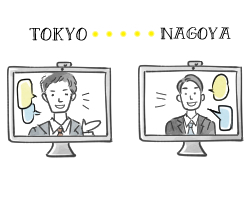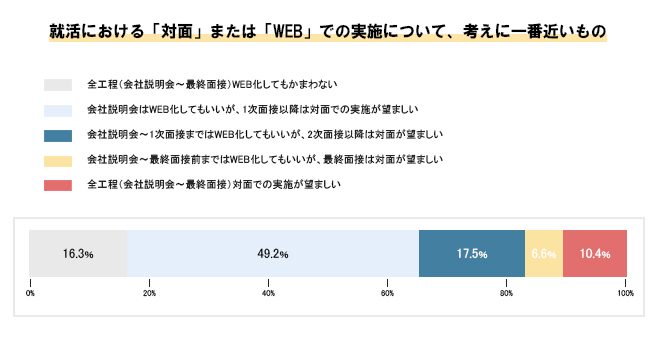オンライン採用に必要な工夫とは?2021年卒 学生のオンライン就活事情のリアルに迫る
一同: はい!
Aさん: 授業の移動時間がないので、以前よりも自分の専門以外の分野の授業を受けたりすることも増えてすごく楽しいです。また、僕は個人的に対面での質問が苦手ということもあり、チャットの方が活発に質問ができます(笑)。
ただ、実習系の授業を受けている友達の話を聞くと苦戦しているようでした。
Nさん: 私も実習系の授業を受けているのですが、思うように進まないことが多いですね。また、授業やゼミの人数が増えるとシステム障害が発生したり、そもそも授業を配信するためのツールを選ぶのが難しかったり、と先生たちもいろいろ悩まれているな、と感じています。
Hさん: 私の場合、専攻の関係で語学の授業が多いのですが、オンラインだと細かいニュアンスを理解するのが難しいな、と感じています。一方で、授業をオンラインで受けると一対一で受けているような感覚で、集中力も高まり、課題に対してもより向き合ってできるようになりました。
Tさん: 授業の出席率がすごく高くなったと感じます。僕の専攻では出席を取らない授業も多く、出席率が2割程度の授業もあったのですが、今ではほとんどの授業で出席率が8割くらいあるんじゃないかな?
Tさん: 僕は本格的にオンラインに切り替わる前の3月末には就職活動が終わっていました。ただ、メガベンチャーをメインに受けていて、企業側がオンラインでのやりとりに慣れていたこともあり、その後の面談などもスムーズに進行されていた印象があります。
Nさん: 私は航空業界を目指していたのですが、今回の新型コロナウイルスで一番影響を受けた業界ということもあり、 選考が進む中で採用計画が二転三転したりして結構振り回されました。進路を考え直さなきゃ、という時に各社がオンラインでの採用イベントを行っていたので、いろいろな業界のイベントに参加できたこともあり、もともと自分の専攻だった福祉系のベンチャーに切り替えて選考を受けました。
Nさん: やっぱり時間と交通費が節約できた、というのが大きいと思います。地方にいるとどうしても時間やお金の制約によって出席できるイベントが限られてしまうので。
1日で複数のイベントをハシゴしたこともありました。
Tさん: 僕も名古屋とはいえ、市内で受けられる選考は決して多くはなくて。だからこそ地の利や時間の条件が全国一律で同じだったのはすごくありがたかったなと感じています。
一方で、僕はオフラインのイベントにもすごく魅力を感じています。休憩時間やイベント後に社員さんに話を聞きにいって一歩リードするタイプなので(笑)。オンライン説明会だとみんな一律で決まった説明を聞くだけになってしまうので、ちょっともったいなかったと思います。
Hさん: 私が受けた企業では、社員さんがきちんとイベントをこなしていて、こういう緊急事態でも問題なく働ける会社なんだ、と実感して好印象でした。初めは直接話さない分、雰囲気がわかりにくいのかな?と不安でしたが、社員さんも自宅からイベントに参加していたこともあり、その人の雰囲気も伝わってきました。
Hさん: ある企業を受けた時、もともとグループディスカッションを予定していたのが、コロナの影響で一人ひとりが企画提案する、という内容に変更になったことがありました。グループディスカッションの場合だと、ファシリテーターや書記などその人の特性に合わせてアピールできると思うんですけれど、全員が企画提案する、だとどうしても一元的な評価になってしまうんじゃないかな、と感じました。
Aさん: 僕はオンラインでグループディスカッションに参加しましたが、学生側にも採用側にもツールについての知識や経験が求められているな、と感じました。採用の新たな軸としてツール利用法の熟達が求められているとも思います。
Nさん: 私はオンラインでの就活に切り替わったことでイベントの際の質問内容が変わったな、と感じています。ビデオ通話だと首から上しか見えないので、どんな服装で出勤しているんだろう、とか。あとは実際に会社に行けないのでオフィスの雰囲気などについては詳しく聞いていました。
好印象だったイベントについて
Nさん: ある企業のオンライン説明会では、登壇する社員さんのプロフィールなど事前に情報が共有された上で、業種ごとに異なる内容で作り込まれていて、すごく感動しました。また、リモートだからこそ普段は忙しくてイベントに参加できない役員クラスの社員さんがサプライズで登壇してくれて特別感もあり、理解度もすごく深まって好印象でした。
Hさん: 印象に残っているのはオンラインでオフィスツアーを開催してくれた企業です。オンラインということでその場には社員さんしかいないこともあり、みんなすごくリラックスしていてリアルな執務室の様子を知られてすごく良かったと思います。
Tさん: オンライン説明会では結構チャットが重要だと思っています。そこで、説明会の最初の方で「チャットツールで質問してください」みたいなアナウンスがあるときっかけができて最初から盛り上がるな、と感じます。 ある企業ではオンライン説明会で登壇する社員さんとは別にチャット専門の社員さんを配置していたのですが、会話も拾ってくれて、すごくオープンな雰囲気を感じて好印象でした。
- 人材採用・育成 更新日:2020/08/25
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-