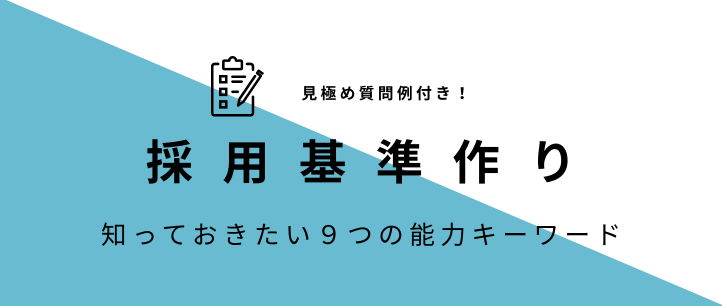離職率の高さを防ぐには?特徴・原因別の改善策とKPI
「社員がなかなか定着しない」「せっかく育てた人材がすぐ辞めてしまう」などの原因による高い離職率は、多くの企業が抱える深刻な課題の1つです。離職率が高い状態が続くと、採用や教育にかけたコストが無駄になるだけでなく、ノウハウの蓄積不足や既存社員の負担増加といった悪循環を招きます。
当記事では、人事担当者や経営層の方に向けて、離職率が高いとされる基準やその原因、離職率の高さがもたらす問題点、そして改善のための実践的な対策を解説します。
1. 離職率とは?(定義/使いどころ)
離職率とは、一定期間内に職場を離れた人の割合を示す指標で、人材の定着状況を把握するために用いられます。厚生労働省は離職率を「常用労働者に対する離職者数の割合」と定義しています。採用・定着の課題把握、改善策の優先順位付け、目標管理(OKR/MBO)に活用できます。
常用労働者とは、「期間を定めずに雇用されている者」「1ヶ月以上の期間を定めて雇用されている者」を指し、役員などは含まれません。臨時雇用や短期契約のスタッフは対象外となるのが一般的です。離職率を把握することで、企業は職場環境や人材育成の課題を明確化し、採用や定着施策の改善に活かせます。
(出典:厚生労働省「主な用語の定義」)
1-1. 離職率15.4%が基準|業界別データで自社の危険度を判定
離職率は、離職者数を年初の常用労働者数で割り、100を掛けて算出します。
離職率(%)=離職者数÷年初の常用労働者数×100
厚生労働省の「令和5年雇用動向調査」によると、全産業の平均離職率は15.4%でした。性別では男性13.8%、女性17.3%となっています。自社の離職率がこの全国平均や、自社が属する業界の平均を上回っている場合、離職率が高いと判断できます。特に業界平均との差が大きい場合は、待遇や職場環境、育成制度の見直しが必要です。産業ごとの離職率は下表を参考にしてください。
産業区分 |
離職率(%) |
|---|---|
産業計 |
15.4 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 9.2 |
| 建設業 | 10.1 |
| 製造業 | 9.7 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 10.4 |
| 情報通信業 | 12.8 |
| 運輸業,郵便業 | 10.3 |
| 卸売業,小売業 | 14.1 |
| 金融業,保険業 | 10.5 |
| 不動産業,物品賃貸業 | 16.3 |
| 学術研究,専門・技術サービス業 | 11.5 |
| 宿泊業,飲食サービス業 | 26.6 |
| 生活関連サービス業,娯楽業 | 28.1 |
| 教育,学習支援業 | 14.8 |
| 医療,福祉 | 14.6 |
| 複合サービス事業 | 7.8 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 23.1 |
2. 離職率を押し上げる5大要因|改善策とKPI設定
離職率が高い背景には、給与や待遇の不満、人間関係のストレス、柔軟性のない働き方、長時間労働、将来のキャリア不透明さなど、複数の要因が絡み合っています。ここからは、それぞれの原因と最小工数で着手できる対策とKPI目安を提示します。
2-1. 給与・待遇への不満
給与や賞与、福利厚生などの待遇面に不満があると、離職意向が高まりやすくなります。特に「仕事内容に見合った給与が支払われていない」「同業種と比べて水準が低い」といった状況は、従業員のモチベーションを大きく低下させます。
また、努力や成果が適切に評価されず、昇給や賞与に反映されない場合も不満の原因となります。待遇は生活の安定や将来設計に直結するため、期待との乖離が続けば転職を検討する動きが加速します。優秀な人材の流出を防ぐには、業務内容や成果に見合った報酬体系の整備や、評価制度の透明性向上が必要です。自社でも、給与や待遇に対する不満が多くないか、定期的なアンケートや面談で確認しましょう。
まずは次の3点から着手しましょう。
- 職種×地域の賃金ベンチマークの中央値を確認し、できる限り近づける
- 賞与・手当・昇給の条件を明文化し、求人票と社内に開示
- 残業代の算定方法を周知し、未払いゼロを監査
KPI目安:オファー受諾率+〇pt、内定辞退理由に占める「報酬」の比率−〇0%(四半期で確認)
2-2. 人間関係のストレス(上司・同僚・顧客)
職場での上司や同僚、顧客との関係に問題があると、心理的負担が蓄積し離職の要因となります。特に上司との関係悪化は評価や待遇にも影響しやすく、「相談しづらい」「意見を言えない」といった状況が長く続けばモチベーションが低下します。
また、パワハラやセクハラ、顧客からのカスタマーハラスメントなどの被害は、心身への影響も深刻です。人間関係のストレスを減らすには、組織やチームで孤立を防ぐ仕組みづくりや、風通しの良いコミュニケーション環境の整備が欠かせません。定期的な面談や社内SNSの活用など、意見や悩みを共有しやすい場を設けることが大切です。人間関係に起因する不満やトラブルがないか、相談窓口の利用状況や社内アンケートの声を確認することをおすすめします。
対策の最初の3手(例):
- 月1の1on1(30分)を全員実施し、議事メモを本人共有
- ハラスメント相談ルートを2系統(人事と外部)で運用
- 「否定しない・割り込まない」等のチーム規約を文書化
KPI目安:人間関係起因の離職面談比率−〇0%、相談件数の可視化(月次)
2-3. 柔軟な働き方の不足(リモート・フレックス・時短)
働き方の選択肢が限られている職場は、従業員の定着率が下がりやすくなります。育児や介護など家庭の事情を抱える方にとって、固定的な勤務時間や出社必須の環境は大きな負担です。
近年は働き方改革や人材不足を背景に、フレックスタイム制や時短勤務、リモートワークなど柔軟な制度を導入する企業が増えています。しかし、制度がない、または形骸化している職場では不満が募ることもあるでしょう。企業はワークライフバランスを尊重し、制度面と運用面の両方で柔軟な働き方を実現することが、優秀な人材の確保と定着につながります。自社でも、柔軟な働き方の制度が整っているか、実際に運用されているかを従業員に確認しましょう。
対策の最初の3手(例):
- 在宅/時差/短時間の適用条件を明文化(職種要件・頻度・申請手順)
- まず2職種で3ヶ月試行し、利用率と満足度を測定
- 会議の時間短縮(30→25分)とノー残業デーの設定
KPI目安:柔軟勤務の利用率〇0%、満足度+〇0pt、会議時間−〇%
2-4. 長時間労働の常態化
労働時間の長さは離職率に直結する大きな要因です。定時をすぎた過度な残業や休日出勤が常態化すると、心身への負担が増大し、働き続ける意欲を削ぐことにつながります。特に長時間労働は、家族との時間や趣味の時間など私生活を犠牲にしやすく、ワークライフバランスの崩壊を招きます。
また、慢性的な疲労や睡眠不足は健康リスクを高め、メンタル面への悪影響も大きくなります。こうした状況が続くことで、従業員はより健全な勤務環境を求めて転職を検討しやすくなり、結果として離職率が上昇します。自社でも平均残業時間や休日取得率を定期的に把握し、長時間労働が常態化していないかチェックしましょう。
対策の最初の3手(例):
- 業務棚卸(頻度×所要×付加価値)で上位20%を自動化/廃止候補化
- 月〇hの残業上限を可視化、超過時は業務削減会議を〇時間以内に実施
- 有給(年5日必達)の四半期進捗管理
KPI目安:平均残業−〇%、有給取得率+〇pt
2-5. キャリアパスの不透明さ
将来のキャリアパスが描けないことは、離職率を高める要因の1つです。昇進や昇給の見通しが不透明で、自己成長につながる経験や役割を得られない状況が続くと、従業員は自分の成長機会が限られていると感じます。また、担当業務の幅が広がらない、スキルを発揮できる場がないといった要因も、将来への不安を増大させます。
会社の経営方針や事業計画に一貫性がなく、急な方針転換や事業縮小が起こると、組織自体の将来性に疑問を抱く従業員も少なくありません。こうした状況では、従業員はより明確なキャリア形成が可能な職場を求めて転職を検討しやすくなります。自社でも、キャリアパスや成長機会が明示されているか、従業員が将来像を描けているかを面談などで尋ねましょう。
対策の最初の3手(例):
- 職種別スキルマップと昇給条件を社内公開
- 半期のキャリア面談(30分)を標準化し、合意メモを保存
- 社内公募を年2回実施(応募要件と選考フローを明文化)
KPI目安:キャリア納得度+〇%、社内公募応募率↑、希望異動の充足率↑
3. 要注意!離職率が高い企業の共通点|12項目チェックリスト
離職率が高い企業には、共通して見られる傾向があります。長時間労働や低い給与水準、育成制度や評価制度の不備など、従業員のモチベーションを損なう要素が複数重なっている場合が多いです。以下のチェックリストに当てはまる項目が多いほど、離職リスクは高まる可能性があります。
【離職率が高い企業の特徴チェックリスト】
- □労働時間が長い/休みが取りにくい
- □給与が市場水準より低い
- □人材育成計画とOJT標準が整っていない
- □評価制度が不透明・周知不足
- □上司の1on1/フィードバックが不足
- □柔軟勤務の適用条件が曖昧
- □相談ルートが1系統のみ
- □ナレッジ(手順/FAQ)の整備不足
診断目安:4項目以上に該当→要対策。6項目以上→優先度高(3ヶ月~で是正計画)
ここからは、離職率が高い企業の共通点を一つひとつ解説します。
3-1. 長時間労働の常態化
離職率が高い企業には、長時間労働が当たり前となっている組織風土があります。業務量や人員配置の見直しがされず、慢性的な人手不足が放置されているケースが多く見られます。成果より「長く働くこと」を評価する社内文化や、上司が率先して残業する慣習があると、従業員も帰りづらくなり、終業時間が後ろ倒しになります。こうした環境は、制度上は残業規制や休暇制度が整っていても、実際には機能せず、長時間労働が固定化される要因です。
また、休日出勤や夜間対応が常態化し、従業員は将来的にも改善が見込めないと感じて転職を検討しやすくなると、企業全体の離職率を押し上げる要因となります。こうした状況を是正するには、まず次の取り組みから着手すると現実的です。
取り組み例:
- 業務棚卸を実施し(頻度×所要×付加価値で評価)、上位の業務を自動化・廃止候補に
- 人員配置と業務の優先順位を見直し、残業の上限を可視化
- 休日出勤は所属長の事前承認制に改め、翌週に業務削減会議を開催
- KPI:平均残業−〇%、休日出勤件数−〇%。
3-2. 低い給与水準と不十分な待遇
労働量や責任に対して給与水準が低く、待遇が十分に見合っていないのも、離職率が高い企業の特徴の1つです。これは単なる業績不振だけでなく、長年にわたり給与体系や評価制度が見直されない企業体質にも起因します。成果を上げても昇給や賞与に反映されない状況が続くと、従業員の意欲や仕事への満足度は大きく低下します。
また、同業他社と比較して報酬が低い場合、従業員は将来の生活設計に不安を抱きやすくなります。報酬面の不満は日々の業務意欲を削ぐだけでなく、より条件の良い職場を探す動機にもなり、早期離職を招く原因となります。低賃金のまま人材流出が続くことで、残った従業員の負担が増え、悪循環に陥るリスクも高まるでしょう。改善に向けては、次の点を優先して見直します。
- 3年以上改定がない賃金表は要注意。職種×地域の市場中央値を基準に改定
- 昇給・賞与・各種手当のルールを1枚資料に整理し、社内および求人票で開示
- オファー額と評価結果の連動方針を明文化
- KPI:退職理由の「報酬」比率−〇%。
給与や待遇の問題は企業にとって根深い課題ですが、離職の背景にはこれだけでは説明できない要素も潜んでいます。
<離職の根本原因を解決する科学的アプローチ>
離職原因を学んだ今、「なぜ従業員のモチベーションが下がるのか」の本質的なメカニズムを理解することが重要です。組織心理学の研究と500社超の実践経験から導き出された、エンゲージメント向上の正しい施策をご紹介します。
3-3. 不十分な人材育成・オンボーディング
教育体制が不十分な企業では、従業員が必要なスキルを計画的に習得できず、成長の見込みを感じられなくなります。入社後の研修が形式的であったり、OJT任せで指導方針が定まっていなかったりすると、業務の習熟に時間がかかり成果を出す前に自信を失うこともあります。
上司や先輩によって教え方がばらつく環境ではスキルの定着が難しく、キャリア形成の展望を描けなくなるでしょう。教育体制が不十分で、従業員が計画的・効率的に成長できない状況が続けば、成長機会を求めて他社へ移る人が増え、離職率の上昇を招きます。人材育成は単なる研修の実施ではなく、長期的な視点で能力開発を支援する体制づくりが重要です。まずは、入社初期の立ち上がりを確実に支えるOJTの仕組みから整えましょう。
3-4. 公正に機能しない評価制度
評価制度が形だけ存在しても、成果や能力が正当に反映されなければ従業員の不満は蓄積します。評価基準が曖昧で非公開、あるいは上司の主観に左右される場合、公平性が損なわれやすくなります。こうした不透明な評価環境では「努力しても報われない」という意識が広がり、モチベーションの低下を招きかねません。
評価結果が給与や昇進にどのように結びつくかが明示されていないと、将来への展望も持ちにくくなります。企業文化として公正さや説明責任が欠けていると、従業員はより納得感の高い評価制度を求めて転職を検討しやすくなります。まずは、評価の見える化と運用の精度を高める取り組みに着手しましょう。
3-5. ハラスメントの放置
職場でパワハラやセクハラ、モラハラといったハラスメントが放置されている企業では、社員が安心して働けず、離職率が高まりやすい傾向にあります。ハラスメントは被害者の心身を大きく傷つけるだけでなく、周囲の従業員にも「自分も同じ目に遭うかもしれない」という不安を与え、職場全体の雰囲気や士気を著しく低下させます。
相談しても改善が期待できない環境や、声を上げづらい風土が根付いている場合、問題が潜在化しやすく、組織全体の信頼性にも悪影響を及ぼしかねません。その結果、従業員は将来性のない職場と判断し、より安全で健全な環境を求めて離職することになります。内部・外部の2系統窓口、匿名通報、研修(年1)を標準化するなど、未然防止と迅速対応の両輪で、次の体制を標準化しましょう。
離職率が高い企業の特徴をチェックした結果、職場環境の改善が必要と感じた方も多いのではないでしょうか。従業員が「この会社で長く働きたい」と思える環境づくりの核心は「心理的安全性」の確立です。
4. 高い離職率によって生じる問題
離職率が高い状態を放置すると、企業はさまざまな問題が起こりやすくなります。採用形態や手法によって異なりますが、採用・教育コストは「採用費+面接・教育工数×人件費+OJTによる生産性低下分」で概算でき、一般的に早期離職1人あたり50万〜150万円規模になることが多い(業種により変動)と言われています。この視点を持つことで、改善施策への投資判断がしやすくなるでしょう。
以下では、それぞれの問題について詳しく解説します。
4-1. 採用や教育のコストが無駄になる
離職率が高い企業では、新たな人材を採用しても早期に退職されてしまうため、採用活動や教育に投じたコストが回収できずに終わってしまいます。採用活動には求人原稿の作成や面接対応など多くの工数が必要であり、教育には研修やOJTなどの時間と労力が伴います。
短期間で離職されるとかけた労力がすべて無駄になり、再び採用活動を行わざるを得なくなります。結果として、人事部門の負担が増加するだけでなく、組織全体としても効率が低下しやすい状況に陥ってしまいます。
4-2. ノウハウが社内に蓄積されにくくなる
離職率が高い企業では、従業員が長く定着しないため、日々の業務で得られる知識やスキルが社内に蓄積されにくくなります。担当者が頻繁に入れ替わると引き継ぎが不十分になり、業務の質や効率が下がる原因となります。新しく入社した社員は、整備されたマニュアルやOJT体制がない状態で一から仕事を覚えなければならず、そのたびに教育に時間や労力がかかってしまいます。その結果、社内に知識が定着せず、同じミスや非効率なやり方が繰り返されやすくなります。
また、離職した社員が持っていたノウハウが社外に流出するリスクもあり、企業の成長スピードや競争力を低下させる大きな要因となります。
4-3. 優秀な人材を確保しにくくなる
離職率が高いと採用市場において「働き続けにくい職場」というイメージを持たれやすく、優秀な人材から敬遠されがちです。応募者が企業を選ぶ際には給与や待遇だけでなく「働きやすさ」や「定着率」も重要な判断基準となるため、離職率の高さは採用活動そのものに悪影響を及ぼします。
離職が多い職場では業務に追われ、教育や育成の余裕がなくなり、人材が育ちにくくなります。その結果、経験豊富な社員がいないために、人材不足が一層深刻化します。離職率の高さは「人材が定着しない」だけでなく「新しい人材も確保できない」という二重の問題を招き、企業の競争力を大きく損なう要因となります。
4-4. 既存社員の負担が増えて職場環境が悪化する
離職者が出ると残された社員が業務を引き継ぐ必要があり、1人あたりの負担が増加します。通常業務に加えて離職者の業務を担うことで残業が増え、ストレスや疲労感も強まるでしょう。ストレスや疲労が続く環境が続けば「自分も続けられない」と感じ、さらなる離職を招く悪循環に陥りやすくなります。
また、人員不足で業務が滞ったり質が低下したりすると、社内全体の雰囲気が悪化します。不満が広がり心理的安全性が損なわれれば、社員同士の関係もぎくしゃくするでしょう。職場環境の悪化は外部にも伝わり、「働きにくい会社」という印象を与え、採用活動にも不利に働く恐れがあります。
5. 高い離職率を改善するための対策
離職者が多い環境を改善する際には、まず自社の離職率や原因を正確に把握し、課題に優先順位をつけて改善策に取り組むことが重要です。職場環境の整備や評価制度の見直しなど具体的な対策を段階的に進めることで、離職率の低下につながります。
取り組みの進め方としては、最初の90日で「測る→整える→回す」を実行しましょう。
<90日間の取り組み例>
- 測る:離職率/平均残業/有給取得率/評価納得度を現状把握
- 整える:原因上位3つに対し、各3つの打ち手を適用
- 回す:月次レビューでKPIの推移を確認し、次の是正を決定
また、中途採用を進めているものの、早期の退職者が多いなど採用活動に悩みを抱えている場合は、工数を削減しながら成果を出すポイントを紹介した以下の資料も併せてご覧ください。
5-1. 職場環境を改善する
職場環境を整えることは、離職率を下げるための基本的かつ重要な対策です。労働条件の見直しに加え、社員が安心して働ける雰囲気づくりも欠かせません。たとえば、休憩スペースや社内イベントを設けてコミュニケーションを活性化させることで、相談や意見交換がしやすい風通しの良い職場を実現できます。
また、残業や休日の過多が不満につながるケースも多いため、業務配分の調整や適切な人員配置によって負担を軽減する工夫が必要です。在宅勤務や短時間勤務など柔軟な働き方の導入も有効で、従業員のワークライフバランスを支えます。働きやすさが向上すれば、社員の定着率とモチベーションの向上にもつながるでしょう。まずは次の取り組みから始めると効果的です。
取り組み例:
- 残業上限(月〇時間)と会議短縮(30分程度)を即日適用
- 休憩・集中スペースなどの業務環境を小改修(目安数週間)
- 柔軟勤務の適用条件を文書化し、2職種で試行(数ヶ月)
- KPI目安:平均残業−〇%、有給取得率+〇pt、制度満足度+〇pt
5-2. 公平な評価制度の早期構築
従業員が安心して働き続けるためには、納得感のある評価制度も必要です。評価基準が不明確であったり、上司の主観に偏った評価が行われていたりすると、不満や不信感が募り離職につながります。透明性のある基準を設け、成果や行動を客観的に測れる仕組みを導入しましょう。
また、評価者への研修を実施し、制度が適正に機能するよう整備することも必要です。360度評価や社内表彰制度などを組み合わせることで、社員一人ひとりの努力や成長を正当に評価しやすくなります。公平で明確な評価制度があれば、社員のモチベーションが高まり、定着率の改善にも直結するでしょう。具体的には、次の点を優先して整備します。
- 評価項目を3つに集約し、配点・定義・サンプル回答を公開(目安数週間)
- 評価者校正会(30分×2回)でばらつきを補正
- フィードバックは評価確定後2週間以内に実施(「事実→解釈→次回行動」で記録)
5-3. キャリアパスの明示とキャリア形成の支援
離職率を下げるためには、従業員が自社で長期的に成長できると実感できる環境を整えることが大切です。そのためには、まずキャリアパスを明確に示し、昇進やジョブチェンジのステップを可視化しましょう。加えて、社内公募制度や研修プログラムを充実させることで、社員が新たな役割やスキルに挑戦できる機会を増やせます。
定期的なキャリア面談を通じて社員の希望や課題を把握し、個々に合った成長の方向性をサポートすることも効果的です。こうした仕組みを整えることで、従業員は将来を見越して安心して働け、結果として離職防止につながります。
まずは次の3点から着手しましょう。
- スキルマップと昇給条件を社内公開
- 学習補助(年2万円/人)と社内公募(年2回)を導入
- 半期に1回のキャリア面談(30分)を標準化
5-4. 面談を定期的に実施する
定期的な面談は、従業員の不満や悩みを早期に把握し、離職を未然に防ぐための重要な仕組みです。特に1on1ミーティング・メンター制の導入は、上司と部下が直接対話することで、仕事の課題やキャリアの方向性を共有でき、信頼関係の構築にもつながります。
直属の上司には話しにくい悩みも相談できるよう、メンター制度やブラザー・シスター制度を導入することも効果的です。こうした仕組みを通じて従業員が安心して意見を伝えられる環境を整えることで、モチベーションの維持やエンゲージメントの向上につながり、結果として離職率の低下に寄与します。
運用の初期設定として、次を標準にしましょう。
- 月1回の1on1(30分)を全員実施し、議事メモを本人に共有
- メンター制度を導入(入社数ヶ月までを対象)
- 面談テンプレを統一(課題/支援/次回アクション)
5-5. 入社前ミスマッチの防止|早期離職を削減する選考設計
早期離職を防ぐには、採用段階でのミスマッチをなくすことも大切です。仕事内容や待遇、働き方などを誇張して伝えると、「思っていた職場と違う」と感じて短期間で辞めてしまうリスクが高まります。一方で、選考時に自社の特徴や業務内容を正確に提示すれば、入社後のギャップを小さくし、定着率の向上につながります。
特に、企業理念や社風と応募者の価値観をすり合わせることがミスマッチを防ぐ際のポイントです。事前に双方が納得した上で入社できれば、入社後のギャップを小さくし、安定した雇用関係を築きやすくなります。
具体的には、次の取り組みを標準化しましょう。
- 求人に「簡易JD(業務割合/期待成果/NG事項)」を添付
- カジュアル面談→業務体験・課題試験の流れを標準化
まとめ
離職率とは一定期間内に職場を離れた人の割合を示す指標で、全産業平均は15.4%です。離職率が高い企業では採用・教育コストの無駄やノウハウの蓄積困難など、多くの問題が生じる可能性が高まります。労働条件や評価制度の見直し、面談の実施による不安や悩みの早期解決など、従業員が安心して働ける環境を整えましょう。
<離職率を改善するための実践お役立ち資料>
この記事でご紹介した「離職率改善の対策」を実際の職場で実行するには、従業員のエンゲージメント向上から具体的な定着施策まで体系的なアプローチが必要です。多くの企業様が抱える「優秀な人材がすぐ辞めてしまう」「離職の本当の原因が分からない」といった課題を解決するため、お役立ち資料をご用意いたしました。
【基礎】職場環境を改善し定着率を上げたい方向け
人事部長が知っておきたい「心理的安全性」のポイント~定着率アップ・採用率アップに不可欠~
※人間関係のストレスを解消し、従業員が安心して働ける職場づくりの具体的手法
【ダウンロードはこちら】
【応用】従業員のモチベーション向上を図りたい方向け
従業員エンゲージメントを向上させる「正しい施策」とは?~組織心理学の研究者×500社超のコンサル経験を持つプロが対談~
※離職率を根本から改善する、科学的根拠に基づいたエンゲージメント向上の実践手法
【ダウンロードはこちら】
「なんとなく人が辞める」という状況から、「従業員が長く働きたいと思える組織」を科学的に構築できます。優秀な人材の定着と組織の持続的成長を実現するためにも、ぜひ体系的な離職率改善にお取り組みください。
※当記事は2025年8月時点の情報をもとに作成しています
- 人材採用・育成 更新日:2025/10/10
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-