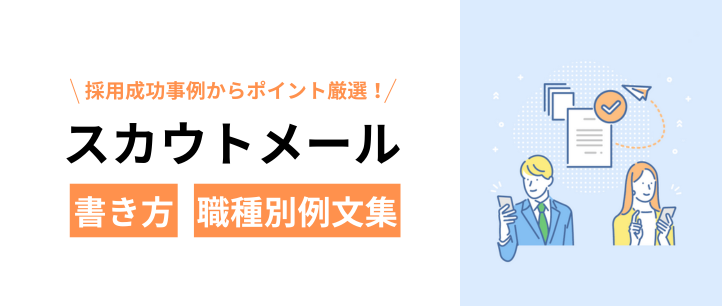採用のときに企業が抱える課題9つ|調査方法や解決策を解説
「求人を出しても応募が来ない」「面接の調整をしても辞退が続く」「せっかく採用しても早期に離職してしまう」など、採用活動に関する悩みを抱える企業は少なくありません。
採用がうまく進まなければ、慢性的な人手不足が続くだけでなく、組織全体のパフォーマンスや今後の事業計画にも影響がおよぶ恐れがあります。
採用の課題には、募集・面接・内定・定着といった各フェーズごとに異なる要因が関係しているため、効果的に改善するには、それぞれの段階に応じた対応が必要です。
この記事では、採用活動の各フェーズで発生しやすい課題の背景を整理し、よりよい採用につなげるための具体的な解決策を紹介します。
1. 新卒・中途採用における採用課題とは
採用課題とは、企業の人材採用活動における成功率や効率の低下を招く要因や問題のことです。放置すると、採用活動にかかるコストが膨らむばかりか、組織全体の生産性や事業成長にも悪影響を及ぼす可能性があります。
例えば、応募数が伸びない、欲しい人材からの応募が得られない、選考で辞退が多発する、採用後の定着率が低いなどが採用課題に該当します。
採用課題は、大きく以下の3段階に分類できます。
母集団形成段階 |
ターゲットとなる求職者層に求人情報が届かない、応募が集まらないなどの課題 |
|---|---|
選考段階 |
面接辞退や選考通過率のばらつき、候補者の見極め精度に関する課題 |
内定・入社段階 |
内定辞退、早期離職、入社後のパフォーマンスの低迷など、定着や戦力化に関する課題 |
採用課題は採用活動全体の工程に関わるものであり、表面化する時期もその段階によって異なります。
1-1. 自社の採用課題の調査方法
採用課題を的確に把握するためには、採用活動の各工程におけるデータを収集・分析することが不可欠です。
最初に確認すべきは、選考プロセスごとの通過率を示す歩留まり率や、採用活動全体にかかる採用コストを示す採用単価などの定量データです。これらの数値は、採用活動のどの段階に問題が潜んでいるかを可視化する手がかりとなります。
歩留まり率は、以下の式で算出できます。
歩留まり率(%)=通過者数 ÷ 対象者数 × 100
例えば、書類選考の段階で100人中20人が通過した場合、歩留まり率は20%です。同様のやり方で、応募から内定までの各段階をチェックすれば、特に歩留まりが低い工程を特定できます。
通過率が低い箇所は、何らかの問題がある可能性が高く、早期の見直しが必要です。
採用単価は複数の採用媒体を採用しているときは特に重要です。チャネルごとの費用対効果を比較し、採用単価が高騰しているチャネルがあれば、別の手法への切り替えを検討するタイミングと言えます。
関連記事:採用コストの削減方法。分析から施策までわかりやすく解説
1-2. 新卒・中途採用の採用トレンドと課題解決のヒント
採用活動の設計には、時期や求職者の属性に応じたトレンドの把握が欠かせません。特に新卒と中途では、求職者の行動傾向や重視する要素が異なるため、それぞれに応じた採用戦略の最適化が求められます。
●新卒採用のトレンド
新卒採用では、採用活動の早期化が加速している点が大きな変化です。2026年卒では、46.0%の企業が採用スケジュールを前年より前倒ししており、就職情報サイトへの登録や夏インターンシップへの参加がピークを迎える時期も早期化しています。
また、学生の長期インターンシップ志向が強まっており、5日以上の就業体験を希望する傾向が前年より高まりました。業務理解や企業理解を重視する傾向が強いため、インターンシップの内容設計がこれまで以上に重要です。
一方で、受け入れ枠の制限などの影響で、全体のインターンシップ参加率はやや減少傾向にあります。そのため、対策として短期でより柔軟に実施できる「オープン・カンパニー」を導入する企業が増えると予測されています。
採用活動の早期化が進む中で、内定辞退や早期離職のリスクも顕在化している状況です。内定者の多くは複数社からの内定を得ており、企業は選ばれる立場として、内定後のフォロー施策(座談会や職場見学、交流促進など)を強化する必要があります。
出典:サポネット「【2027年卒最新版】新卒採用スケジュールとトレンドまとめ」
●中途採用のトレンド
マイナビが従業員数3名以上の企業に向けて行った中途採用に関する調査では、2024年の1社あたりの採用人数は、平均20.8人と2020年と比べて7人以上増加しました。2025年も9割以上の企業が積極採用を予定しており、特に未経験者の採用を進める傾向が顕著です。
また、若年層(20~30代)や専門職(DX人材、ITエンジニアなど)へのニーズが高く、正社員人材の確保に苦慮する状況が続いています。一方で、ミドル・シニア層についても、定年延長や労働力不足を背景に採用の幅が広がっています。
中途採用における大きな課題として挙げられるのが、「やっぱり離職」問題です。選考時点で離職リスクを懸念しつつも採用した人材が、やはり早期に退職してしまうケースが約4割の企業で報告されています。
主な離職理由には、仕事内容や社風とのミスマッチ、上司との相性不一致などが挙げられており、採用前後のすり合わせ不足が要因と考えられます。企業には、選考段階での認識共有や、入社前の職場体験・社員交流などを通じたミスマッチ防止策の強化が求められるでしょう。
採用費用が年々増加する中で、採用後の定着率を高める取り組みが採用戦略全体の費用対効果を左右する重要な鍵となります。
出典:マイナビキャリアリサーチラボ「中途採用状況調査2025年版(2024年実績)」
2. 母集団形成段階で起こりやすい課題と解決策
採用活動においては、適切な母集団を形成できるかどうかが成功の第一歩となります。しかしながら、「応募が集まらない」「求める人材が応募してこない」「応募が多すぎて処理しきれない」といった課題は起こりやすく、採用担当者の悩みの種です。
以下では、母集団形成における代表的な課題とその解決策を紹介します。
2-1. 求人を出しても応募が集まらない
求人媒体や人材紹介会社を利用しても、そもそも応募者数が集まらず成果が出ない場合は、次のような原因が考えられます。
母集団の人数不足に対しては、露出強化と情報の最適化が必要です。
例えば求人広告においては、タイトルや冒頭文に魅力を感じられなければ、閲覧や応募に結びつきません。プロの広告業者などに原稿作成をアウトソーシングするのも効果的です。また、ダイレクトリクルーティングを行っている場合は、定型文の一斉送信ではなく、ターゲットごとに内容をカスタマイズしたスカウト文面が必要となります。求人広告のスカウト分の書き方については、以下も参考にしてください。
関連記事:【例文付き!】スカウトメールで優秀な人材を獲得する方法~書き方ガイド・応募率UPのポイントを解説
さらに、企業説明会や業界イベント、SNSなどのチャネルを併用し、幅広い応募者との接点を増やすことも有効です。多面的なアプローチをすれば、応募数の増加が期待できます。
2-2. 求める人材が応募してこない
求職者の属性が自社のターゲットから外れている場合、選考工数ばかりが増加し、採用効率が著しく低下します。応募は集まっても、採用条件を満たす人材がいないというミスマッチが発生する背景には、以下のような原因が考えられます。
求める人材の質の課題を解決するためには、採用ペルソナに基づいた精度の高い採用活動が大切です。「自社がどのような人材を求めているのか」を明文化し、理想的な採用ペルソナを設計すれば、メッセージや媒体の選定、表現内容に一貫性を持たせられます。
加えて、若年層の採用であればSNS広告の活用や動画コンテンツの発信、社員インタビューの掲載など、求職者の目線に立った魅力的な情報発信を検討するとよいでしょう。
2-3. 応募者の数は十分だが、スキルや経験が求める基準に合わないケースが多い
母集団形成が成功しても、それに見合う選考リソースが確保できていない場合、かえって業務が逼迫することになります。特にスキル不足やマッチしない応募者の割合が多い場合、書類選考や面接対応にかかる負担が大きくなり、優秀な人材の見極めが困難になります。
応募する人材が多すぎる場合、選考条件を整理し、限られた人事リソースで適切に絞り込みができる仕組みを構築するのが大切です。
例えば、応募条件に資格や実務経験の有無などを追加すれば、条件を満たさない応募者の流入を抑制できます。また、ポートフォリオの提出や適性検査などを応募段階で行えば、ある程度ふるい分けが可能です。
ただし、要件を厳格にしすぎると応募数自体が減少するリスクもあるため、バランスが重要ですまた、採用管理システムなどを使い、採用業務を効率化するのもよいでしょう。
3. 選考段階で起こりやすい課題と解決策
採用活動における選考段階では、応募者との接点がより深くなる一方で、面接辞退や見極めの難しさといった課題も顕在化します。以下では、特に起こりやすい3つの課題と、それぞれに対する解決策を解説します。
3-1. 面接辞退が多い
面接辞退は、新卒・中途を問わず発生する代表的な選考課題の1つです。面接辞退が増える原因としては、以下が挙げられます。
面接辞退を防ぐには、応募から面接までの対応を素早く丁寧に進めることが基本です。応募者対応は24時間以内を目安に連絡を入れ、面接日程も柔軟に提示することで辞退のリスクを軽減できます。
特に中途採用では、在職中の応募者が多いため、業務終了後の時間帯や土日面接・オンライン面接の導入など、応募者に配慮したスケジュール調整が重要です。また、面接前に企業情報や社員紹介、選考フローなどを事前に案内することで、応募者の不安を払拭し、辞退を防止する効果に期待できます。
関連記事:【歩留まり改善】面接後の辞退が起こる要因と改善方法
3-2. 優秀な人材を見極められない
優秀な人材を見極めることができず、採用判断に迷いやばらつきが生じるケースも、選考段階での典型的な課題です。優秀な人材の見極めに失敗する原因は、以下の通りです。
優秀な人材を見極めるためには、採用基準を明確にし、面接官全員で共有することが不可欠です。スキルや経験だけでなく、社風との相性や価値観といった定性的な要素も含め、面接チェックリストや評価シートを用いて一貫性を保つ工夫が求められます。
さらに、適性検査やパーソナリティテストなどのツールを導入することで、短時間の採用面接では判断しづらい潜在的な能力や企業との相性を可視化することが可能です。また、新卒や第二新卒の採用では、ポテンシャル重視の判断軸も必要となるため、応募者との対話を通じて将来像やキャリア観を深掘りする姿勢も大切です。
関連記事:経験者の中途採用面接では何を確認すべき? その難しさと見極め方
3-3. 役員面接や最終面接の歩留まりが極端に悪い
一次・二次面接を通過した応募者が、最終面接や役員面接で大量に不合格となるケースもよくあります。これは、以下のような理由で人事部門と経営層で求める人物像にズレがあることが主な原因です。
このような課題に対しては、人事部門と経営層の間で、採用ターゲット像を具体的にすり合わせることが重要です。
重要なのは、人事担当者・現場責任者・役員の三者間で「採用における優先事項」と「理想の人材像」を共通言語化することです。スキル要件だけでなく、価値観やカルチャーフィット、今後の役割期待といった評価軸まで含めて書面化し、部門横断でのすり合わせを行うとよいでしょう。
また、最終面接で判断する要素を他の面接と重複させず、役員は経営視点での資質確認(理念共感、中長期での貢献可能性など)に集中できるよう、あらかじめ役割分担を明確にしておくと選考の効率と整合性が向上します。
4. 内定・入社段階で起こりやすい課題と解決策
内定を出しても、人材が定着しなければ採用は成功したとは言えません。選考においてミスマッチが起こっていると、内定辞退や早期離職といったさまざまな課題が発生します。
以下では、内定・入社段階で特に起こりやすい課題と解決策を解説します。
4-1. 内定辞退が多い
面接を通過し、内定を出したにもかかわらず辞退されてしまうケースは、企業側にとって大きな損失となります。特に一次面接から最終面接、内定通知までのフローの中で、企業の魅力を十分に伝えきれていないと、辞退率が高まる傾向があります。
内定辞退が多くなる原因は、以下の通りです。
内定辞退を防ぐには、内定者との継続的な関係構築が重要です。内定を出した後は、単なる「連絡待ち」ではなく、企業側から積極的にコミュニケーションを取りましょう。面接通過後すぐにフォローメールを送り、内定者向けの座談会や懇親会、先輩社員との面談機会を設けるといった内定者フォローが有効です。
また、圧迫的な面接態度や長すぎる選考プロセスは、それだけで内定辞退につながる要因になり得ます。応募から内定までは原則2週間以内を目安とし、候補者の負担にならない運営を心がけましょう。
さらに、ネット上の自社に関する情報を確認し、不安材料となる要素が多い場合は、面接の場で丁寧に補足説明を行うといった対策も効果的です。
4-2. 人材が早期に離職する
早期離職の発生は、採用活動や人材育成に大きな影響を及ぼす要因の1つです。マイナビによる20~50代の正社員3,000人を対象にした調査では、早期離職の経験がある人は全体の9.1%でした。特に20代の割合は11.0%と高く、入社後半年以内に退職した経験を持つ若手人材が多い傾向が見られます。
出典:マイナビキャリアリサーチラボ「早期離職に繋がる入社後のギャップとは?-年代別の理由と企業の対策を紹介」
早期離職が起きる原因は、以下の通りです。
課題に対しては、入社前後の情報ギャップを減らす施策が有効です。
例えば、リアルな職場情報を求職者に伝える「RJP(Realistic Job Preview)」の導入が効果的です。良い面・悪い面の両方を伝えることで、入社後のミスマッチを防ぎやすくなります。
また、求職者の人物像を客観的に把握する「リファレンスチェック」も有効です。前職での勤務実績や人間関係を確認すれば、配属先の環境や業務とのマッチング精度が高まり、早期離職のリスクを下げることができます。
さらに、面接時には業務内容・組織風土・指導スタイルなどを丁寧に伝えるとともに、入社後もフォロー体制を整えることが、定着率向上に繋がります。特に若手人材に対しては、理不尽と受け取られないようなコミュニケーションやOJT設計が求められます。
4-3. 採用した人材のパフォーマンスの上げ方が分からない
採用した人材のパフォーマンスが思ったより上がらず、どのように改善を目指せばよいのか分からず悩むのもよくある課題の1つです。特に中途採用者の場合、即戦力として迎えたものの、期待通りの成果が出ていないと感じる企業も少なくありません。パフォーマンスの上げ方が分からない状況に陥る原因は、以下の通りです。
解決にあたっては、採用時点での情報提供を見直し、企業風土や評価制度、仕事内容について正直に伝え、適性を確認することが基本となります。加えて、入社後のスムーズな立ち上がりを支援するために、OJTだけでなくメンター制度の導入や定期的な1on1面談を通じて、早期の課題抽出と対応を行う体制が有効です。
また、活躍の評価指標が明確でない場合は、短期・中期の業務目標をすり合わせる機会を設け、目標達成に向けた道筋を本人と共有することが重要です。
即戦力といえども、企業に慣れるまでには一定の時間を要します。配属後すぐに成果を求めすぎず、中長期的な視点でサポートする姿勢が、結果的にパフォーマンス向上につながります。
5. 採用課題の解決に成功した企業の事例
採用課題を抱えていた企業が、外部サービスの導入をきっかけとして課題を解決し、採用成功につながったケースはいくつもあります。
以下では、マイナビのサービスにより中途採用の課題解決に成功した企業事例について、紹介します。
5-1. 株式会社Study Valley様
株式会社Study Valley様は、2020年に設立されたEdTechサービス開発企業です。中途採用者の早期離職が課題となっており、採用時のミスマッチを解消するために、マイナビのオンラインリファレンスチェックサービス「TRUST POCKET」を導入しました。面接だけでは見極めが難しい人柄や職務適性を、前職の上司や同僚からの情報により可視化することで、入社後の活躍をより具体的に想定できるようになったといいます。
導入前は、選考辞退の増加やスピード低下を懸念していましたが、実際には候補者の協力も得られ、選考フローへの影響は最小限に抑えられました。また、リファレンス情報は採用可否の判断材料だけでなく、入社後の育成方針の策定やオンボーディング支援にも活用されています。こうした取り組みにより、社員の定着率が向上し、人的資本の可視化と組織全体の最適化にもつながっています。
関連記事:前職の上司・同僚によるリファレンスサービスを活用。客観的なデータにより採用時のミスマッチが減少
5-2. 株式会社沼尻電気工事様
株式会社沼尻電気工事様は、埼玉県深谷市に本社を構える電気設備工事業者であり、地域密着型の企業として従業員満足度の向上に力を入れています。中途採用では知名度不足や人材確保の難しさが課題となっていましたが、マイナビ転職を活用したことにより、約2年間で20名の採用に成功しました。特に未経験者を対象に広く募集を行い、資格支援制度と社内教育を整備したことで、若手社員の定着と成長を実現しています。
社屋の移転やオフィス環境の改善、作業服の刷新、就業規則の見直しといった社内改革も並行して進め、働きやすい環境づくりに取り組んできました。また、マイナビからはPR動画やホームページリニューアルの提案も受け、企業の魅力発信を強化することができました。こうした取り組みにより、応募者の質が高まり、現場にも良い効果がもたらされています。今後も「社員100名体制」の実現に向け、中途採用と新卒採用の両輪で人材確保を進めていく予定です。
関連記事:専門業種「電気設備エンジニア」候補20名の採用に成功。「選ばれる企業」になるための、未来を見据えた取り組みとは
まとめ
採用活動における課題は、応募・選考・内定・入社後といった各段階で異なる形で表面化します。応募が集まらない、ターゲットとする人材が応募してこない、面接辞退が多い、内定辞退や早期離職が続くといった状況は、多くの企業が直面しやすい問題です。
こうした課題に対処するには、各工程における数値データをもとに現状を分析し、課題の本質を特定することが不可欠です。さらに、応募要件の見直しやフォロー体制の強化、配属後のサポート設計などを通じて、採用から定着・活躍までの全体最適を図る必要があります。
マイナビ転職 Boosterは、求人サイトの集客力と専属スタッフによる対応力を兼ね備えたサービスです。候補者が集まらないお悩みがあっても、日本トップクラスの会員登録数を誇る「マイナビ転職」を活用し、母集団形成が可能です。また、応募者との選考前対応や合否連絡、面接の日程調整などをマイナビに任せられ、ミスマッチを防げます。
さらに、成果報酬型のサービスのため、初期費用はかかりません。万が一採用した方が早期退職してしまった際には、請求後でも報酬の一部を返金します。
採用課題を抱えられている企業様は、ぜひマイナビ転職Boosterをご利用ください。
※当記事は2025年6月時点の情報をもとに作成しています
- 人材採用・育成 更新日:2025/07/25
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-