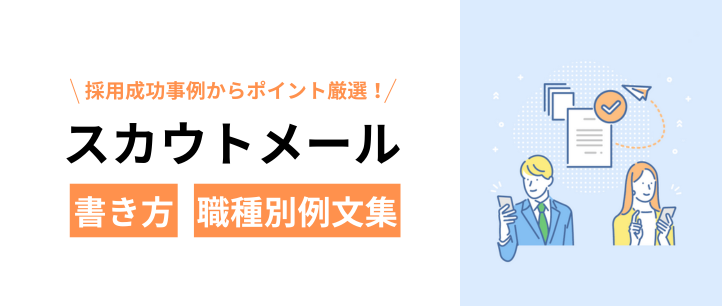従業員エンゲージメントとは?高める施策や高い企業の事例を解説
従業員エンゲージメントとは、従業員が企業の理念や目標に共感し、自発的に貢献しようとする意欲を指す言葉です。日本では離職率の増加や労働生産性の低さといった問題が指摘されており、エンゲージメント向上の必要性が高まっています。しかし現状、成果に対する不公平感、働き方の柔軟性不足、チャレンジ精神が抑圧される環境など、日本企業特有の問題があり、なかなかエンゲージメントの低さが改善されていない現状があります。
この記事では、経営者や人事担当者、従業員のエンゲージメント向上に関心のある方々を対象に、従業員エンゲージメントの定義と重要性、日本企業における課題、具体的な施策やエンゲージメントを高めるのに成功した企業の事例を解説します。
1. 従業員エンゲージメントとは
従業員エンゲージメント(社員エンゲージメント)とは、従業員が会社の理念や方向性に共感し、自分から「会社に貢献したい」と思う意欲のことです。
「エンゲージメント」には「約束」「絆」といった意味があり、従業員エンゲージメントが高い場合、愛社精神や企業への信頼度が高いと言えるでしょう。
なお、従業員エンゲージメントの定義について、専門家の解説を読みたい方は、ぜひこちらの資料も参考にしてください。
1-1. 従業員エンゲージメントの3要素
従業員エンゲージメントは、「理解度」「帰属意識」「行動意欲」の3つの要素で構成されます。
【従業員エンゲージメントの3要素】
理解度 |
企業が目指す方向性や理念、ビジョンなどを理解した上で、従業員が会社の考えを支持している状態を指します。従業員エンゲージメントを向上させるための最初のステップとして非常に重要です。 |
|---|---|
帰属意識 |
従業員自身が企業の一員であるという自覚をもち、企業や一緒に働く仲間に対して共感や誇り、忠誠心を抱いている状態です。企業への理解度が高まるにつれて従業員の帰属意識が育ち、従業員エンゲージメントが向上すると言われています。 |
行動意欲 |
企業の成功のために、従業員自身が自発的・積極的に仕事に取り組む姿勢を指します。企業への理解度や従業員の帰属意識が高まることで、従業員の行動意欲が増すと言われています。 |
従業員エンゲージメントを維持・向上させるためには、上記の3つの要素を意識することが大切です。従業員の企業への理解度を高めながら帰属意識を育てることで、行動意欲が向上し、従業員エンゲージメントが形成されることを押さえておきましょう。
1-2. 従業員エンゲージメントと従業員満足度の違い
従業員満足度とは、従業員が自身の所属組織に対して「業務内容」「給与」「職場環境」「福利厚生」「人間関係」などの事項にどの程度満足しているか定量化したものです。従業員満足度が高い職場は従業員が働きやすいという魅力があるだけでなく、生産性向上や優秀な人材の定着など企業側にも多くのメリットがあります。
このように、従業員満足度は従業員から会社への評価を表す指標であると言えます。一方で、従業員エンゲージメントは従業員の会社への貢献意欲の高さや所属意識の強さを示すものです。従業員の考え方や行動、熱意を重視して会社と従業員とのつながりの強さを計測するという点で、従業員満足度とは異なると言えるでしょう。
1-3. 従業員エンゲージメントとワーク・エンゲージメントの違い
ワーク・エンゲージメントとは、従業員が自分の仕事に対して誇りや熱意を持ち、業務に没頭して高いパフォーマンスを発揮できる心理状態を意味する言葉です。ワーク・エンゲージメントが高い従業員は仕事に対して前向きで充実感を得ているため、仕事への満足度が高く会社への帰属意識も強い傾向があると言われています。
このように、ワーク・エンゲージメントは「自分の仕事」に対する愛着から生まれるものです。一方で、従業員エンゲージメントは「所属する組織」への愛着から発生するという違いがあります。どちらもエンゲージメントが向上すれば従業員が仕事に積極的に取り組む状態になるという共通点がありますが、行動の動機が異なることに留意しましょう。
2. 従業員エンゲージメントが重視される理由
従業員エンゲージメントは1990年代にアメリカで提唱された概念ですが、最近は日本の社会・企業においても重視されるようになってきました。ここでは、日本において従業員エンゲージメントが注目されるようになった主な理由・背景を解説します。
2-1. 従業員の離職率が上がっている
近年では終身雇用という概念が薄れている上に価値観が多様化しており、若い世代を中心に1~2回の転職は一般的と捉える方が増えてきました。特に新卒就職者の離職率は高く、厚生労働省によると2021年3月に卒業した新卒就職者の就職後3年以内離職率は高卒で38.4%、大卒で34.9%となっています。
(出典:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します」)
また、マイナビの調査では、働きがいを感じていない新入社員の約3割は1年以内の退職を検討しているという結果も得られています。少子高齢化に伴う人材不足を防ぐためにも、従業員エンゲージメントを向上させ、従業員離職率を抑えることがポイントとなるでしょう。
(出典:株式会社マイナビ「マイナビ転職、「新入社員の意識調査(2022年)」を発表」)
2-2. 非対面コミュニケーションが増加している
近年では働き方改革やコロナ禍の影響などにより、テレワーク(リモートワーク)やビデオチャットでのオンライン会議が可能な環境づくりを行った企業も多いでしょう。しかし、非対面コミュニケーションが浸透した一方で、従来の対面コミュニケーションを行う機会が減少し、従業員エンゲージメントが低下した企業も少なくありません。
特に、対面コミュニケーションで自然に行われていた働きぶりに対するフィードバックや周囲からの支援が、非対面コミュニケーションへの移行によりなくなってしまうケースは多くあります。
マイナビBizの調査によると、社内コミュニケーションの頻度が低いと職場への愛着や仕事へのやりがいを従業員が感じにくい傾向があるとされています。
(出典:株式会社マイナビ「マイナビBiz「新入社員のエンゲージメントと職場環境に関する調査 (2021年)」)
非対面コミュニケーションでもエンゲージメントが低下しないよう、意識して企業側はエンゲージメント向上に取り組む必要があるでしょう。
2-3. 労働生産性の向上が急務となっている
日本では長時間労働が課題となっている業界・職種も多くありますが、国際的にみると日本の労働生産性は高いとは言えません。OECD加盟38か国中、日本の時間当たり労働生産性は29位、1人当たり労働生産性は32位であり、改善の余地がある状態と言えるでしょう。
(出典:日本生産性本部 生産性総合研究センター「労働生産性の国際比較2024 概要」)
従業員エンゲージメントを高めることは、従業員自身が組織のために主体的に行動できる従業員を増やすことにもつながります。業務の効率化や新しいアイデアの創出にもつながり、生産性の向上にも期待できるでしょう。
3. 日本企業の従業員エンゲージメントが低い原因
ギャラップ社の2024年の調査によると、日本の従業員エンゲージメントは約6%でした。この数値は世界平均の23%と比べて大幅に低く、日本は世界で最も従業員エンゲージメントが低い国の1つとされています。
ここでは、日本企業の従業員エンゲージメントが低くなる主な5つの原因について、それぞれ解説します。
(出典:ギャラップ「State of the Global Workplace 2024 REPORT」)
(出典:ギャラップ「日本の雇用主が直面する人材確保の課題」)
3-1. 成果が適正に評価されない人事評価制度がある
日本企業の従業員エンゲージメントが低くなる理由の1つとして、人事評価制度に不満があることが挙げられます。最近では年功序列の評価制度から成果主義へと移行する企業も増えていますが、評価制度や評価基準が適正かどうか検討しないまま運用しているケースも多いでしょう。
仕事の頑張りや成果に対して正当な評価が受けられない状態では、従業員側も仕事に対するモチベーションを保てません。会社に対して不信感を抱くようになれば、従業員エンゲージメントも低下するでしょう。
3-2. 勤務時間制度の弊害が起きている
多くの企業で勤務時間制度が採用されていることも、日本における従業員エンゲージメントが低い理由の1つと考えられます。勤務時間制度がある場合、業務効率化によって早く仕事を終えても勤務終了時刻まで退社できず、業務量をこなしても給与はそれほど増えません。
一方で、仕事の進みが遅い従業員が残業をすれば、残業代により収入が増えることになります。このような環境では、業務を効率化して多くの仕事に取り組む意欲が低くなるため、従業員エンゲージメントも低下してしまうでしょう。
3-3. 厳しすぎる規制によりチャレンジするのが難しい
日本の企業が過剰に法令・ルールを守る傾向があることも、従業員エンゲージメントを低下させる原因の1つと言われています。
社内で規制を設けることはリスクマネジメントとして必要な側面もありますが、過剰なルールは従業員の新しいチャレンジの妨げになる恐れがあります。新しいことに挑戦しにくい職場では、成功の喜びや仕事へのやりがいも感じにくくなるでしょう。結果として、従業員モチベーションや従業員エンゲージメントの低下につながります。
3-4. 個々人の強みや専門性を業務に生かしにくい
「年功序列」「終身雇用」に基づく職能型人事制度が多くの日本企業に根付いていることも、日本の従業員エンゲージメントが低い理由の1つとされています。職能型人事制度では、多様な仕事に対応できるオールラウンド型の人材が評価されやすく、個人の強みや専門性を業務に生かすことはそれほど重視されません。
一方で、従業員エンゲージメントは自分の役割や使命が明確化された環境で向上しやすいと言われています。それぞれの強みや専門性を生かしにくい現在の状況では、従業員エンゲージメントを高めることは難しいでしょう。
3-5. 仕事が細分化しすぎている
組織が複雑化し、仕事が細分化されすぎていることも、従業員エンゲージメントが低くなる理由の1つとして挙げられます。
組織が大きくなり縦割り化すると、他の部署・チームが行う業務が見えにくい状態になり、仕事が細分化されることで仕事の目的が分かりにくくなります。「誰のために」「何のために」仕事をしているか分からない状態では、仕事に対するモチベーションが低下してしまうでしょう。結果として従業員エンゲージメントの低下にもつながります。
しかし、これらの従業員エンゲージメントの低下の原因となる要素があったとしても、人事部や会社の上層部が気付けず、結果として離職を招くケースがあります。エンゲージメントの低下に気付き、不満を見逃さずに現場を変える意識を持つことが大切です。
従業員エンゲージメントが低下していることに気付くきっかけについて知りたい方は、ぜひこちらの資料を参考にしてください。
4. 従業員エンゲージメントを高めるメリット
従業員エンゲージメントを高めることは、企業組織にとって多くのメリットがあります。ここでは、企業が従業員エンゲージメントを向上させる3つのメリットについてそれぞれ解説します。
4-1. 従業員が定着しやすくなる
従業員エンゲージメントを高めるメリットの1つとして、従業員の定着率が高まることが挙げられます。
従業員エンゲージメントを意識した施策を行うことで、会社に対する愛着や貢献意欲が高まれば、自社で働くことに価値ややりがいを感じられるようになります。優秀な人材が転職や退職を考えることも少なくなるため、人材流出を防ぐこともできるでしょう。
4-2. 生産性が向上する
生産性の向上につながることも、従業員エンゲージメントを向上させるメリットの1つです。
従業員エンゲージメントを高めることは、従業員のモチベーション向上にもつながります。従業員一人ひとりが仕事に熱心に取り組み、組織の業務改善などを主体的に進めることで生産性アップにつなげられるでしょう。顧客満足度の向上や業績アップにつながることも期待できます。
4-3. 従業員が健康に働きやすくなる
従業員エンゲージメントを高めることで、従業員が職場に対し安心感や安定感を抱くようになるため、健康に働きやすくなるというメリットもあります。
従業員エンゲージメントが高い企業では、従業員自身の行動や意思決定が成果につながる経験を積みやすく「自分はできる」という感覚が育ちやすいと言われています。仕事に対するネガティブな感情やストレスが発生しにくくなるため、心身ともに安定した状態で仕事に取り組んでもらえるようになるでしょう。
5. 従業員エンゲージメントを高める施策
従業員エンゲージメントを高めるために必要な施策として、厚生労働省は「働きがいの現状を確認する」をはじめとする6つの取り組みを紹介しています。ここでは、厚生労働省の情報を中心として、6つの従業員エンゲージメント向上施策について詳しく解説します。
5-1. 働きがいの現状を確認する
従業員エンゲージメントを高めるためには、まず、従業員が会社や仕事に対してどの程度の働きがいを感じているか現状を確認することが大切です。定期的に従業員エンゲージメント調査(エンゲージメントサーベイ)を行い、分析した上で対策を考えましょう。
エンゲージメントサーベイには、1年に1回程度行う「センサスサーベイ」や、1~4週間に1回ほどの頻度で行う「パルスサーベイ」など複数の種類があります。それぞれの手法の目的やメリット・デメリットを考慮した上で、自社の課題に適した調査方法を選択するとよいでしょう。
5-2. 柔軟・多様・快適な労働環境を整備する
従業員エンゲージメントの向上を図るには、柔軟かつ多様で快適な労働環境を整備することも重要です。例えば、テレワークの導入やワークライフバランスを重視した休暇制度、就業形態、総合的なハラスメント対策の推進といった施策が挙げられるでしょう。
また、株式会社マイナビの調査によると、従業員エンゲージメントを高める目的で副業・兼業を認める制度を導入している企業も増えています。
(出典:株式会社マイナビ「「中途採用実態調査(2024年)」を発表」)
結果、「自ら目的を設定し、確実に業務を進めるようになった」、「業務に対し、進んで取り組むようになった」といった思いを、副業・兼業を導入した企業の社員のうち7割近くが感じています。
(出典:株式会社マイナビ「「中途採用実態調査(2024年)」を発表」)
多様な人材が活躍できる環境を整えることで、従業員エンゲージメントも高まるでしょう。
5-3. 仕事の意味や面白さを見出せるよう働きかける
仕事や所属する組織に対する誇りを高め、仕事の意味や面白さを見出せるよう会社側が働きかけることも大切なポイントです。
業務の目的や意義、目標などを上司から部下に伝えたり、従業員が自分で工夫したことを認めて褒めたりするなど、仕事に対するモチベーションを高めましょう。従業員が仕事そのものに意欲を持てるようになれば、仕事に対する楽しみや組織への愛着心も芽生えます。
5-4. 従業員と組織の方向性を一致させる
従業員エンゲージメントが低下する原因の1つとして、会社の理念やビジョン、経営層の考えなどが従業員と共有されていないことが挙げられます。
従業員エンゲージメントを高めるためには、企業理念や経営理念、経営方針を明確化して従業員に浸透させ、従業員と組織の方向性を一致させることが大切です。社長メッセージを定期的に発信したり、会社が目指す姿について職場で話し合いをしたりするなど、会社側の考えを伝える機会を積極的に作るようにしましょう。
5-5. 納得感のある評価や処遇で報いる
仕事への意欲や能力のある従業員に対し、納得感のある評価や処遇で報いることも、従業員エンゲージメントの向上に欠かせない観点の1つです。人事評価制度の改訂を検討する際には、「企業理念や経営ビジョンと評価が関連づいているか」「年齢や性別など属性の違いで不利益を被ることがないか」などをチェックしましょう。
良い評価に対する処遇としては、昇給などの金銭的報酬のほか、社長表彰などの感情報酬の活用も考えられます。評価をもとに人材配置を適切に行うとともに、能力や貢献意欲の高い人材を重要なポストに抜擢するといったことも検討しましょう。
5-6. 能力・キャリア開発を充実させる
従業員エンゲージメントを高めるためには、従業員が新しいことに積極的にチャレンジできる環境を整えることも大切です。従業員自身の「できること」「やりたいこと」が広がれば、仕事への意欲が高まり、成功の喜びや仕事へのやりがいを実感できるようになるでしょう。結果として、所属意識や行動意欲の高まりにつながります。
従業員の能力や意欲を高めるには、日常的な業務指導(OJT)や定期的な研修を通して、従業員のスキルアップ・成長を支援することが大切です。従業員の自律的なキャリア形成(キャリア自律)に向けた相談機会を積極的に設けることも重要になるでしょう。
従業員エンゲージメントを向上させるために、具体的にどのような施策を取ればよいのか知りたい方は、以下のホワイトペーパーをぜひご一読ください。
6. 従業員エンゲージメントが高い企業の事例
従業員エンゲージメント向上を図るためには、企業における実際の取り組み内容から学ぶことも大切です。ここでは、従業員エンゲージメントが高い企業の事例を2つ紹介します。
株式会社福井 |
|---|
株式会社福井では「離職者が多い」という課題を解決するために、エンゲージメント調査を実施しました。調査の結果に経営層がしっかりと対応することで従業員との信頼関係が構築され始めたことから、対話不足が離職につながると考え、従業員と管理職の定期面談を導入しています。 これらの結果、従業員と管理職の間で相互理解が深まり、人材定着や連帯感の醸成、従業員の自主性の向上といった効果が現れました。採用活動においてもエンゲージメントの高さがアピールポイントとなっており、多様な従業員の採用につながっています。 |
株式会社サイバーエージェント |
|---|
株式会社サイバーエージェントでは、従業員一人ひとりを大切にして中長期的な視点で人材育成を行う方針へと転換したところ、離職率の大幅な改善が実現しました。 現在も同社では毎月3問ほどの短い従業員アンケートを実施し、人事部門がすべての意見に対応することで従業員との信頼関係を構築する努力を続けています。また、能力の発揮が期待できる従業員には責任のある立場を任せ、成果を出した従業員には盛大に表彰するなど、従業員のやる気を引き出す評価制度も整備しています。 |
まとめ
従業員エンゲージメントを高めることで、離職率が改善し、生産性の向上や従業員の健康維持など、企業に多くのメリットをもたらします。エンゲージメントの向上には、評価制度の見直しや柔軟な働き方の導入、キャリア開発支援などが効果的です。
また、会社の方針や理念を社員に浸透させ、社員自身が仕事にやりがいや意義を感じられるよう働きかけることも重要になります。企業の取り組み事例でも、定期的な従業員アンケートや管理職との対話、評価の明確化といったアクションによって、従業員エンゲージメントが改善される成果が現れています。
従業員エンゲージメントを調査した後、どのようなアクションをすればよいのかは以下のホワイトペーパーで専門家が解説しております。ぜひご一読ください。
- 経営・組織づくり 更新日:2025/05/23
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-