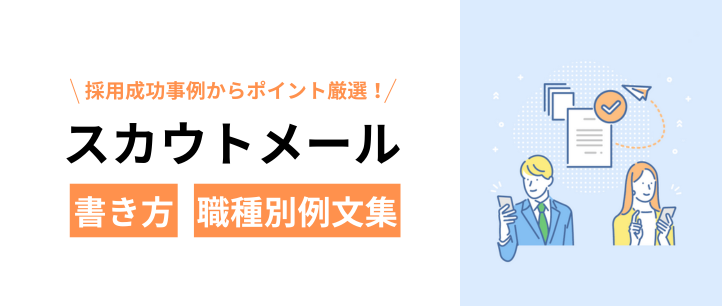行動心理学者に聞く! 学生のホンネを引き出し、志望度を上げる雰囲気づくりのコツ
売り手市場(学生有利)の採用環境が続き、年々母集団形成が厳しくなっていく中で、これまでのように「1対多数」のコミュニケーションではなく、面接やカジュアル面談、インターンシップでのフィードバックなど、「1対1」のコミュニケーションの重要度が増しています。
「1対1」の場は、学生が抱いている不安や疑問を解消し、自社理解と志望度向上を促す絶好の機会です。ここで話しやすい雰囲気づくりに成功し、本音を引き出すことができると、学生からの印象がアップし、志望度向上につながることが分かっています。
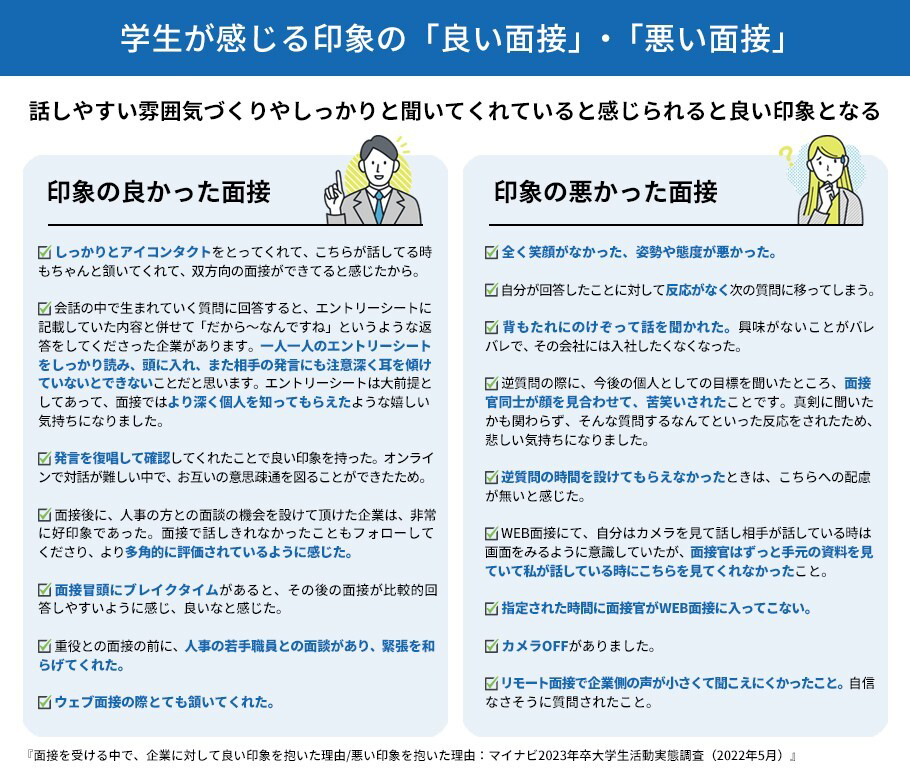
そこで今回は、行動心理学にまつわる著書を多数上梓されている、明治大学の堀田秀吾先生にインタビュー。「学生のホンネを引き出す雰囲気づくりのポイント」について、心理学の観点から教えていただきました。
今の学生は「諦めることに慣れていて」「人懐っこい」
— 堀田先生、今日はよろしくお願いいたします。まずは、先生が専門にされている「行動心理学」について教えてください。
堀田先生: 行動心理学とは、人がある行動を取る根底にある、心理的な理由について探る学問です。「どうして人はそのような行動を取るのか」を解明すれば、逆にその人に取ってほしい行動へと導く方法も明確になるというわけです。
— 人の行動と心理を専門とし、着目されている先生からご覧になって、現代の学生ならではと感じる特徴はありますか?
やはり、コロナ禍を経験していることが影響していると思われる学生は多いですね。
まず、私の目には「諦めることに慣れている」と映ることがあります。「やりたいことができなかった」というコロナ禍の経験から、自分が実現したいことに情熱を燃やして「なんとしてでも実現するんだ!」という熱い感じを受けることは少なくなったかもしれません。「できないなら、できないでしょうがないね」と、どこか冷めたようなところがありますね。
ただ、もう一方で、コロナ禍でごく身近な人々としかコミュニケーションを取れなかった経験が影響しているのか、人懐っこいような面も見受けられます。
— そういった傾向を踏まえて、企業の担当者が学生とコミュニケーションを取る際に気を付けるべきことは何かありますか?
堀田先生:
先ほど「人懐っこい面がある」と言いましたが、その点を生かして少しフランクな口調を混ぜていくのはいいかもしれませんね。
きっちりと説明しなくてはいけない「事実」は敬語で、自分の感情を表すようなときにはフランクに、と使い分けてみてください。
例えば「私は就職活動のときに苦労してね……」というように、フランクな自己開示をしていくと、学生側も心を開きやすいと思います。
しかし、距離感を縮めようとし過ぎるのは禁物です。まず基本として、「学生は社会人と対面することに緊張している」ことをしっかりと意識してください。その上で、信頼を得られるように振る舞う必要があります。
最も本質的なのは、「相手を尊重する」ことです。 「どうせ学生だ」と見下したり、軽く見たりすることなく、一人の大人としてきちんと敬意を持って対応をしてください。
「発話量」と「座り位置」がポイント
— 学生を一人の大人として扱うというのは、理解しているつもりでも、相手の目にはそう映らないこともありますね。
堀田先生: そうかもしれません。難しいようなら、まずは「発話量」に気を付けてみるといいでしょう。
私は裁判員制度で活発な議論を生むための仕組みの研究をしているのですが、その中で分かってきたことがあります。それは、人は「発話量が多い方が立場が上である」と捉え、上下関係を内面化・強化してしまう傾向がある、ということです。
法律のプロである裁判官と、一般市民である裁判員の間には知識量に差があります。また、相手が裁判官というだけで市民は萎縮してしまいます。そういった関係の中でも活発に議論してもらうためには、裁判官側の発話量を抑えることが有効であると分かっているのです。
つまり、面接などの場で社会人の側があまりに多く発話すると、それによって立場の違いが明確化されてしまい、学生を萎縮させてしまう恐れがあるということです。
それから、同じく裁判員制度の研究から分かったことがもう一つあります。それは、「座る位置」です。学生との面談のような場だと、多くの企業が長机を挟んで向かい合うようなスタイルをとると思いますが、実はこれが相手の緊張感を高めてしまうのです。
できれば円卓に並んで、ないなら四角い机の角を挟んで隣り合うように座ってみてください。これだけで相手の緊張をほぐし、対等な立場で話せる雰囲気になります。
シチュエーション別 学生の心をつかむテクニック

— いろいろと具体的なテクニックを教えていただいて参考になります。では、具体的なシチュエーション別の対応例を教えてください。
シチュエーション1:大手志望のAさんが、スタートアップである自社の説明会に。なんとか興味を持って選考まで進んでほしいが……
堀田先生: なるほど。スタートアップである自社と、Aさんが志望している大手を比較して、自社にも興味を持ってもらいたいというシチュエーションですね。
そういう場合、「大手志望」とはいっても、具体的な個社を志望しているのではなく、抽象的なイメージしか持っていない場合も多いと思います。
なので、まずはしっかりと、冷静に比較できるように紙やホワイトボードなんかを使って離職率や福利厚生、キャリアパスなどの比較可能な項目について書き出し、整理していくことが有効でしょう。
その上で、実際に自社(スタートアップ)で働いている社員の声を届けてあげると、比較した上で具体的な就業のイメージをつかむことができ、志望度が上がっていくかもしれません。
あとは、スタートアップならではのフットワークの軽さを生かして、こまめにコミュニケーションを取るようしましょう。
単純接触効果といって、人間はコミュニケーションを取る回数が多いほど好感を持つ傾向があります。
シチュエーション2:社員座談会に参加してくれたAさん。話を聞いてみると、他業界にも興味を持ち始めたらしい。自社への志望度を高めるには?
堀田先生: まずは、Aさんがどのようなキャリアを望んでいるのかをよく聞いてみることですね。自社と他業界のどちらにも興味があるということは、Aさんの目線からは何か共通するポイントがあるはずです。
よく聞いて、共感を示して、その上で自社のメリットをしっかり語ってあげることで好感を持ってもらうことはできると思います。
その際、絶対避けてほしいのは、他社のネガティブな情報を言うことです。それをしたところで、あなた自身の心証が悪くなるだけのことが多いですね。
シチュエーション3:無事、Aさんに内定を出すことができたが、やはり他社と迷っている様子。内定受諾のためにはどうしたらいい?
堀田先生:
正念場ですね。しかし、こういうときほど焦りは禁物です。
まずは学生の「自分軸」、つまりキャリアの中で何を実現したいのか、どのように社会人人生を生きていきたいのかということを改めてしっかりと聞いて、共感を示しましょう。
その上で、Aさんが考える「自分軸」を自社ならどのように実現できるのか、しっかりと話してください。
また、Aさん個人のどんな能力をどう評価しているかを、言葉にして伝えることも重要です。それが具体的であればあるほど、承認欲求が満たされる上、その能力を自社で生かすイメージを具体的に描いてもらえますので、入社の意思を高めることができるでしょう。
— 非常に具体的なテクニックを教えていただき、ありがとうございました!
本音を引き出す学生とのコミュニケーションポイントまとめ

本記事で紹介された、心理学に基づく学生とのコミュニケーションに使えるポイントをまとめました。
●発話量を控える
→心理的な上下関係がフラットになり、相手の発言が増える
●できれば円卓に並んで、ないなら四角い机の角を挟んで隣り合うように座る
→対等な立場で話せる雰囲気に
●なるべく頻繁にコミュニケーションをとる
→単純接触効果により、好意を抱きやすい
●悩んでいたら、書き出して整理
→頭の中だけで考えていると混乱しやすい。書き出すと情報が整理されて判断しやすくなる
●なるべく具体的に評価する
→相手の承認欲求が満たされ、活躍イメージが明確になる
こうしたメソッドの効果を最大限発揮するには、まずは学生に敬意を払いつつ、共感を示しながらよく話を聞くことを意識することが重要です。ぜひ、ご自身の学生とのコミュニケーションを振り返った上で、これらのメソッドを活用してみてはいかがでしょうか。
- 人材採用・育成 更新日:2025/03/10
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-