2025年卒座談会 あえて「文系就職」する理系学生の動き方・考え方とは?
採用市場で「人手不足」という言葉がよく聞かれるようになってはや数年。企業の採用意欲の高まりの影響もあり、人手不足が加速することはあっても、すぐに改善する見込みは今のところありません。
中でも以前から採用ハードルが高く、今後も採用が困難であろうと思われるのが「理系人材」です。ITの発展、AIの隆盛などさまざまな要因から、多くの企業は理系学生の採用を積極的に行っていますが、その絶対数が文系学生よりも少ないため、厳しい市場感となっています。
そんな中、今回の学生座談会では「理系の学部にいながら、文系就活をしている」という3名の方に来ていただきました。
理系の学部・学科に所属しながら、文系職での就職を希望する学生たちは、いったいどう動き、どう考えているのでしょうか。
<座談会参加者>
中でも以前から採用ハードルが高く、今後も採用が困難であろうと思われるのが「理系人材」です。ITの発展、AIの隆盛などさまざまな要因から、多くの企業は理系学生の採用を積極的に行っていますが、その絶対数が文系学生よりも少ないため、厳しい市場感となっています。
そんな中、今回の学生座談会では「理系の学部にいながら、文系就活をしている」という3名の方に来ていただきました。
理系の学部・学科に所属しながら、文系職での就職を希望する学生たちは、いったいどう動き、どう考えているのでしょうか。
<座談会参加者>
「文系就職」を決めた理由
— 今日はお集まりいただき、ありがとうございます。皆さん、理系学部・学科で学びながら、就活は「文系就職」を希望していらっしゃいますが、まずはその理由をお聞かせください。
Aさん: はい。在籍している学科では9割以上が院進(大学院に進学)するのですが、僕自身は1年生の早いうちに院進しないことを決めていました。
もちろん化学は好きですし、学業として続けるのは楽しいのですが、仕事にするとなると、自分には向いていないのではないかと思ったからです。
この分野で研究職に就くのは非常に難しく、また僕よりもずっと優秀で、ずっと化学が好きな人というのがたくさんいることを実感したのが大きな理由ですね。
Kさん: 私の学科も多くが院進するのですが、入学からの3年間で私の好きなこと、仕事にしたいことが「これではない」と思ってしまったのが理由です。
もっと人と関わる仕事、人のことを考える仕事がしたいと思い、人材系企業への就職を希望して就活を続けています。
Sさん:
私の学科は文系寄りの理系で、企業や社会が抱える課題を解決する方法を学んだり、考えたりしています。コンサルティングに近い内容です。
院進率も半分程度で、私も院進して授業料を払いながらコンサルティングを学ぶよりも、就職して実務の中で給与をもらいながらコンサルティングを実践した方がいいと思い、就職を希望しました。
早めから動いて余裕をつくる それぞれの就活スタイル
— ありがとうございます。それぞれご事情がありますね。文系就職をするとはいえ、やはり理系だと卒業のために研究や授業などがお忙しいのでは?
Sさん: 私の場合はお話ししたように「文系寄り」なので、一般的な理系学科ほどは学業と就活の両立に苦労はしないと思います。実際、学科の先輩方を見ていても、あまり苦労されている様子はありません。
ただ、インターンシップで出会った先輩方はかなり早めから就活を始めていて、その姿を見て少し焦りを感じ、私自身は2年生の3月から就活を始めました。
早めに動いたことで、結果として多くの企業を見ることができ、最初は大手コンサルティング会社を志望していましたが、今はベンチャー企業に興味を持って選考に入っています。
Kさん: 院進をしないと決めれば、ある程度は学問と就活の両立は可能かなと思いました。それでも定期テストなどはクリアしていく必要があるので、私の場合は週に1日は「勉強しかしない日」をつくって、あとは就活に励むようにしています。
今は第1希望と第2希望の最終面接対策を行っているところです。
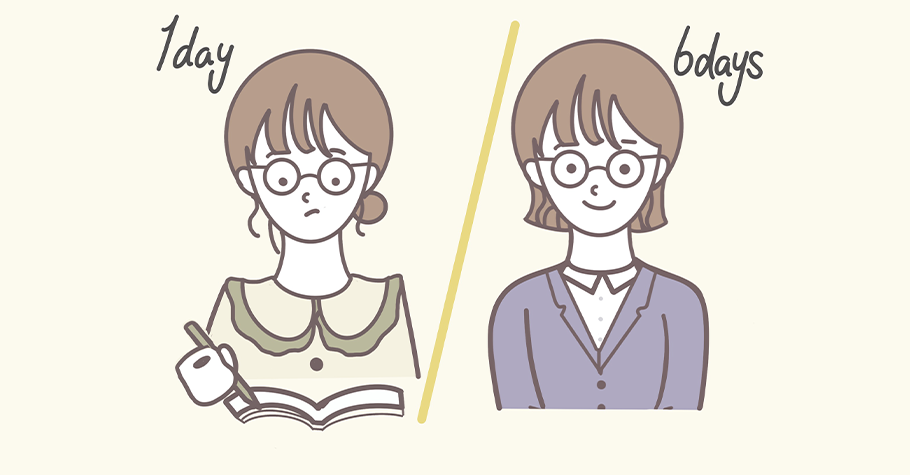
これから卒業に向けて本格的に忙しくなる時期を前に、心の余裕が生まれます。
— 夏期休暇中の就活というと、インターンシップでしょうか?
Aさん: そうです。僕は最終的に人事の仕事がしたいというのが目標なので、「人と直接関わる仕事」を条件にインターンシップを探して参加していました。
インターンシップの内容は企業によってまちまちですが、社員の方から直接お話を聞く機会を得られ、社風や社員の方々の雰囲気をじかで感じられたのが意義深かったですね。
求めるのは「成長環境」 どこでそれを感じた?
—
いま、社風の話がありました。事前アンケートを拝見すると、志望する企業の条件として、全員が「成長環境」を挙げています。
そして実際に、皆さんは志望先企業をある程度絞って選考を受けていますね。どこで「成長環境」があることを知り、志望するに至ったのでしょうか?
Sさん: 私は、大手企業とベンチャーの両方でインターンシップを体験したことが大きなきっかけだったと思います。
どちらも職業体験型のインターンシップで、大手企業では堅実にマニュアルどおりの仕事をすることが求められる一方、ベンチャー企業では自身の思考力やアイデアを活かす機会が多いことが身をもって実感できました。
また、インターンシップ後の社員との面談も、企業の成長環境や社員の成長を具体的に知る機会になったと思います。
社員の方々がどのようにキャリアアップしていったのか、どんな目標を持って仕事をしているのかを聞くことができ、私も成長できる企業で働きたいという思いが強まりました。
Kさん: 私も、企業の風土や成長環境を実感したきっかけは、複数の企業でのインターンシップやリクルーター面談でしたね。
特に、社員の方との面談では具体的なキャリアパスや事業内容を詳しく聞くことができ、入社後の自分を想像しやすくて良かったですね。
また、そういった経験を通じて、自身の将来を実現できる環境であり、成長機会がある企業を選びたいという思いが強くなりました。
Aさん: 僕も、インターンシップ後の社員との面談は、非常にいい情報収集の場になりましたね。
説明会やインターンシッププログラムの中では聞けない、社員の方個人の体験談を聞くと、お二人がおっしゃるようにリアルな情報を得られたと感じられ、自分の志向に合っていれば、ぐっと志望度が高まります。
— 企業はSNSを通じた公式な情報発信や説明会などにもコストをかけていますが、それらよりも社員個人との会話の方が皆さんの志望度に影響があったんですね。
Kさん: そうだと思います。私が人材業界を志望することになった直接のきっかけも、社員の方との面談でした。
Sさん: 私の場合は、ロールモデルとなる社員の方とお話しできたのがとても良かったと思います。
私もこうなっていきたい、と感じられて志望度がぐっと上がりましたね。
Aさん: 公式の発信はもちろん見ますが、やっぱり少し「着飾っている」感は否めないので…… できるだけ社員の方とじかにお話しできる機会をつくり、大切にしていました。
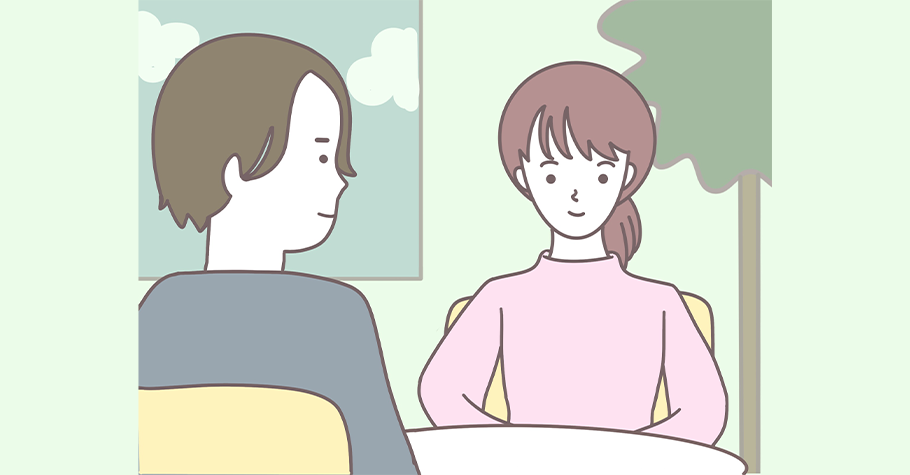
「良いインターンシップ」は一通りではない
— 社員との面談はインターンシップ後に行われたことが多いようですが、そもそも、どういうきっかけでインターンシップ先を探し、参加されているのでしょうか?
Aさん: 僕の場合は、先輩からの口コミが中心でした。あのインターンシップは面白いよ、成長できるよ、といったものです。
Sさん: 私は口コミのほかに、就活支援団体からの紹介で参加したインターンシップもありましたね。
— そうしてさまざまなインターンシップに参加したと思いますが、良いインターンシップ、悪いインターンシップの違いはどのようなものだと思いますか?
Kさん: 私の場合、まずはいろいろな業界を見ていきたいと思っていたので、早期選考の要素があるインターンシップはあまり響きませんでした。
選考要素があることそのものというよりは、そういったインターンシップが職業体験型でないことが多いからです。
こちらは情報収集のつもりなのに、企業側は選考のつもり、という齟齬(そご)があるのが原因かなと思います。
逆に良かったインターンシップは、実際に社内で使っているフレームワークを利用したワークができた企業です。具体的な働き方を想像できたので。
Aさん: そうやって実際の仕事をリアルに想像できるものは、僕も印象が良かったですね。あとは、フィードバックがしっかりしていたインターンシップも好印象でした。
ワークの解に対するフィードバック、チームに対するフィードバック、そして個人に対するフィードバックと3段階あると思うのですが、個人に対するフィードバックがあると志望度が上がると思いました。
自分を見てくれている、という実感につながりますし、何より自身の成長につながりますから。

逆に、印象の悪かったインターンシップは、周りの学生のやる気がないものです。特にグループで取り組むインターンシップで一緒になった学生のやる気がないと、成長にもつながらないばかりか、一人で苦労ばかりを抱えるような印象も受けました……。
Aさん:
同意見です。参加学生の態度ややる気に関する評判は周りでも耳にしますね。せっかくいいプログラムでも、そんなところで評判を落とすのはもったいないと思いました。
なので、僕は選考の厳しいインターンシップに優先して参加していました。
企業は学生と出合う「きっかけ」をどうつくる?
—
皆さん、多くの企業からアプローチがあったと思います。
インターンシップなども参加しながら実際に社員の話を聞いて志望度を上げていったということですが、特に好印象だったアプローチはありましたか?
Sさん: 複数企業に一括でエントリーシートを提出できる就活支援サービスを通じたアプローチで、私自身のことをしっかり見てくれていると感じると好印象でした。
定型文ではなく、エントリーシートの内容をきちんと読んでからメッセージをくださっているんだな、と思えるようなものです。
Kさん: すごく分かります。逆スカウト系の就活サービスで、「Kさんのこんなところが弊社に合っていると思うので」など、私のことを理解した上でアプローチしてくださっていることが分かると好印象ですね。
Aさん: 僕自身は企業からのアプローチで特に印象的なものはありませんでしたが、同じ学生からの口コミによってそれまで知らなかった企業に目が向いたという経験はあります。
先輩や同級生などが実際にインターンシップや選考に参加して得た体験談とセットで話が聞けるので、すごく説得力があるんですよね。もちろん、逆に志望度が落ちるということもありますが…。
— 今日はありがとうございました!
「文系就活」は特別ではない
理系学部・学科に在籍しながら文系就職をする理系就活生の活動実態について、話を聞くことのできる貴重な機会でした。そして、今回の座談会に参加してくれた3名の学生から聞けた話では、動き方や志望度の変化の仕方に「特別」な何かがあるわけではなく、インターンシップを通じた接触から始まり、しっかりとしたフィードバックや社員との交流を通じて徐々に志望度を上げていくという、いわゆる「王道」が有効な採用施策となるようです。
しかし、それぞれ事情があって文系就活をしているという事情も鑑みるべきでしょう。文系職で採用して、その後に理系職へと配属替えをするということを考えているのであれば、採用前にそのことを話し、合意を得ておく必要は当然あると思います。
それぞれ具体的なエピソードを交えてお話しいただいたので、皆さまの採用活動にお役立ていただけると幸いです!
- 人材採用・育成 更新日:2024/01/15
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-














