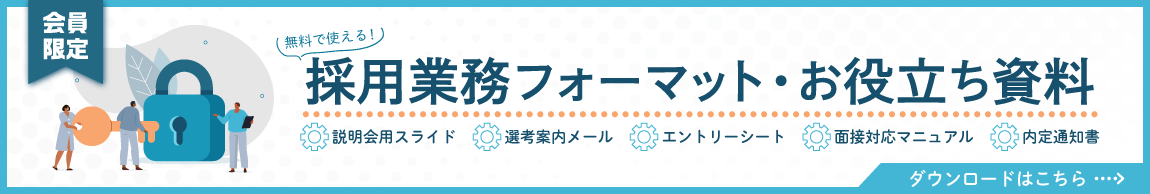人材要件のお悩み、まずはここから!人材要件Q&A
会社の未来を支える人材を採用することは、会社の未来をつくることに他なりません。なので「会社の経営がどのような方向に向かっていくのか」ということを人材要件を策定する前に熟知しておく必要があります。そのためにも、経営トップ層との会話は重要です。
ただし、経営層が持っている具体的な「欲しい人材像」がそのまま人材要件にするべき人材像であるとは限らないことには注意しましょう。
きちんと現場を見た上で「どの部署に、どんなパフォーパンスができる人が、何人必要なのか」と、人事の目で具体的なイメージをつくり上げることが大切です。
また、現実問題として受け入れ部署の状況や社内の教育体制も冷静に見る必要があるでしょう。
「経営の方向性」「それをかなえる人材戦略」そして「社内の実情」をよく理解することが大切です。
「創造的思考」や「状況適応力」「問題解決思考」など、多くの企業が人材要件に共通して盛り込む項目が少なからずあります。もちろん競争が激しくなりますし、結果として人材要件に定めた学生を採用できなければ意味がありません。
まずは優先順位をよく考えましょう。全てを並列にして「全部の資質を持った学生が欲しい!」と考えても、それはなかなかかないません。
創造的思考と自主性なら、どちらが重要ですか? 問題解決思考と比べると?
一つひとつを比べて、絶対に欠かせない「MUST要件」と、できれば欲しい「WANT要件」に分けて見るところから始めましょう。
優先順位さえしっかりしていれば、必ずしも、オンリーワンの人材要件でなくてもいいんです。
御社の人材要件には、もしかすると「コミュニケーション能力が高いこと」と書いてありませんか?
コミュニケーション能力と一言で言っても、「聞く力」「伝える力」「関係性をつくる力」などに分解することができます。この中で、御社が本当に必要としているのはどの能力でしょうか?
「聞く力」が高い人材でクライアントからのヒアリング精度を上げたい、「伝える力」が高い人材で広報の戦力を向上させたい、「関係性をつくる力」で社内のコミュニケーションを活性化させたい… など、実際に求めている能力は「コミュニケーション能力」という言葉だけでは表現できていないはずです。
このように、一つの言葉に多くの意味を込めすぎると、人材要件の抽象度はどんどん上がってしまいます。
その言葉を人材要件に入れることになった経緯や理由をよく確認しながら、本当に求めるべき能力を表現できる言葉に置き換えていきましょう。
人材要件を作る理由は、採用した人材が早期に退職してしまったり、能力が発揮できずにくすぶってしまっていたり、またはカルチャーになじめなかったり…といったミスマッチを起こさないための予防策という側面があります。
もし、今までに採用した学生の質やその後の成長に問題がなく、特に課題を抱えていないのであれば、無理して人材要件を作る必要はないでしょう。
ただし、なぜ今まで満足する採用ができていたのかは、明確にしておく必要があります。
もしその理由が、経験を積んだ面接官だったり、社長面接で適性のない学生を見逃さずに不採用にできていたからだとすれば、社内の人事異動や社長交代などによって採用がうまくいかなくなる可能性が高いですよね。
そうなったときに慌てなくて済むように、自社にとって必要な人材像を明文化しておくと安心です。
https://hrd.mynavi.jp/products/saiyouryoku/
「人材要件」は採用においてとても重要なものですが、一方で言葉が独り歩きしていて、具体的になにをしていいのか分かりにくいですよね。
この記事が皆さんの手助けになれば、幸いです。
- 人材採用・育成 更新日:2021/01/14
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-