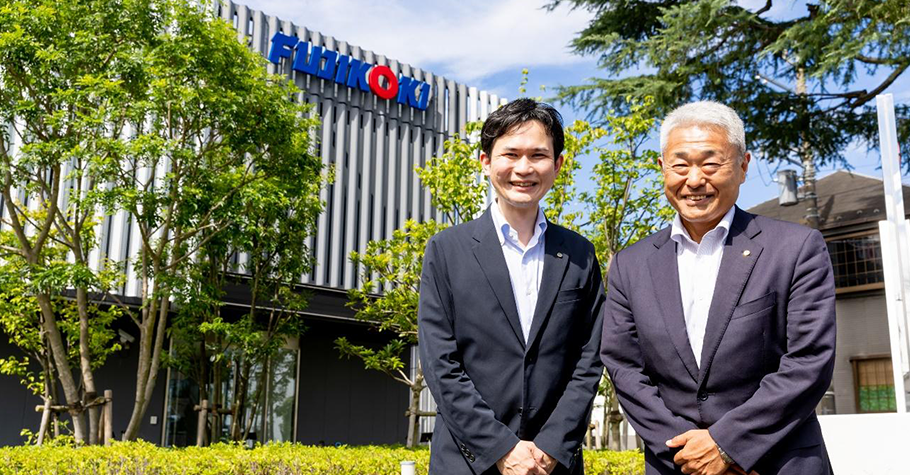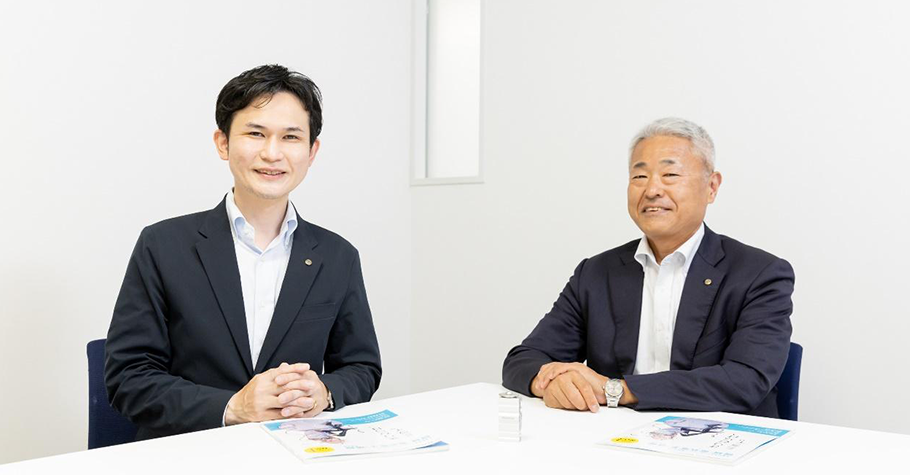1
/news/news_file/file/thumbnail_s-column-116.png
2
草薙さん: 不二工機はグローバル連結で約4,700名の社員を抱えるBtoBの専業メーカーで、冷凍・空調機器の心臓部である膨張弁などの自動制御機器に関して圧倒的なシェアを持っています。ただ、残念なことに「BtoBの専業メーカー」という性質上、一般の学生への認知度は決して高くはなく、採用活動に当たっては母集団形成が課題となっていました。
そこで、ここ数年は全社的に採用体制の強化に取り組んでおり、2年前にはリクルーター制度を導入し、一部の社員にはリクルーターとして母校の研究室などにアプローチをかけてもらいました。しかし、それだけではまだまだ十分な母集団形成が難しいということで、より多くの学生にリーチできるこの情報誌に着目したのです。
草薙さん: 以前からWEBメディアによる採用活動は展開していたのですが、それだけだと先ほど述べたように首都圏や関西圏の学生ばかりが集まってしまう傾向にありました。その点、この情報誌であれば全国の大学のほか、マイナビに登録している理系学生の自宅にも配布されますので、地方の学生に不二工機のことを知ってもらうにはうってつけだと考えたのです。
福井さん: この情報誌には不二工機だけでなく、日本を代表する多くの企業の社員たちが掲載されています。しかも、紙の情報誌には保管性や再読性が高いといった特色があるので、多くの学生が手元に置き、時折、眺めては気になった会社のホームページをチェックしたりするはずです。ひとりでも多くの学生がそういった行動の中から不二工機に関心を持ち、次のステップに進んでくれればと思います。
草薙さん: 将来を見据えると、電気自動車などの新型カーエアコンに対応できる人材、今以上にグローバルな視点に立ったマーケティングやファイナンスに対応できる人材が不可欠になります。そのため、採用体制を強化し、新しいタイプの人材を募ることにしたのです。
福井さん: コロナ禍やウクライナ危機によって一時的な資材の不足などの問題はありましたが、グローバルな規模で引き合いは増加しており、業績も順調に推移しています。そもそも、壁掛け形の業務エアコンというのは日本オリジナルのもので膨大なノウハウが詰まっており、海外メーカーではほとんど取り扱っていません。それだけに世界的なシェアも高く、電気自動車のカーエアコン同様、まだまだ伸びしろがある分野なのです。こうした将来性もしっかりと伝えていくことで、理系人材の心をしっかりとつかんでいきたいですね。
福井さん: 取材に協力してくれた現場や、採用に携わる面接官などとの協力体制を構築できたことがメリットとして挙げられます。さらなる母集団形成の強化や、内定辞退率の低下を目指していくには、全社的に「当社も人材獲得競争にさらされている」という危機感を共有しつつ、会社の魅力をどう伝えていくかといったことを真剣に考え、実践しなければなりません。情報誌を初めて導入したことは社内的にもインパクトがありましたし、現場からの協力を得るきっかけにもなりましたので、この変化を引き続き推進していきたいと思います。
草薙さん: 若手社員が、情報誌に掲載されること自体は大きなメリットだと捉えています。実際、若手社員にとっても、他社の素晴らしい人材と肩を並べて紹介されることは大きな励みになるはずです。
また、社内での認知も着実に広がってきていることもあり、来年度以降は新たな社員にも登場してもらい、少しずつ自社の優れた人材に光を当てていく機会にしていきたいと考えています。そうすることで、人事部としても社内の優秀な人材の発掘にもつながりますし、社員たちがどのような思いで、どんな仕事に携わっているのかをあらためて知る機会になるからです。これは後々の人事戦略を描く上でも大きな財産になるはずです。
福井さん: 誌面に登場いただいた社員やその上司、人事部などにPDFデータで配布しました。反応も上々でしたし、人事戦略を策定し、推進していく上で絶好の種まきになったと実感しています。他部門などにも幅広く配布することで、いずれはそれぞれの部門から掲載候補者が推薦されてくるような流れになっていくことを期待しています。
学生・大学に直接リーチできる情報誌のメリットを活用し、認知向上と母集団形成強化を実現!
BtoBの専業メーカーにとって、地方を含めた幅広い母集団形成は課題として挙げられることが少なからずあります。
東京都世田谷区に本社を置く不二工機は、グローバル企業としてグループ連結で約4,700名の社員を抱え、近年のマーケットや需要の拡大を実感する一方で、次世代を担う人材の獲得を課題に感じられていました。
そこで同社は、理系人材の獲得に向けた認知向上と母集団形成への注力のスタートとして、昨年度から理系の学部生・大学院生に配布される情報誌『企業研究&インターンシップ完全ガイド 機械・電気電子・情報系学生版』(発行:マイナビ)への掲載を実施。
結果、認知向上と母集団形成を推進できただけでなく、社内の採用体制の強化にも効果があったそうです。
その具体的な背景や導入時の取り組みなどについて、不二工機のご担当者に伺ってみました。
東京都世田谷区に本社を置く不二工機は、グローバル企業としてグループ連結で約4,700名の社員を抱え、近年のマーケットや需要の拡大を実感する一方で、次世代を担う人材の獲得を課題に感じられていました。
そこで同社は、理系人材の獲得に向けた認知向上と母集団形成への注力のスタートとして、昨年度から理系の学部生・大学院生に配布される情報誌『企業研究&インターンシップ完全ガイド 機械・電気電子・情報系学生版』(発行:マイナビ)への掲載を実施。
結果、認知向上と母集団形成を推進できただけでなく、社内の採用体制の強化にも効果があったそうです。
その具体的な背景や導入時の取り組みなどについて、不二工機のご担当者に伺ってみました。
― まずは情報誌『企業研究&インターンシップ完全ガイド 機械・電気電子・情報系学生版』を導入された経緯や背景からご紹介いただきたいと思います。
草薙さん: 不二工機はグローバル連結で約4,700名の社員を抱えるBtoBの専業メーカーで、冷凍・空調機器の心臓部である膨張弁などの自動制御機器に関して圧倒的なシェアを持っています。ただ、残念なことに「BtoBの専業メーカー」という性質上、一般の学生への認知度は決して高くはなく、採用活動に当たっては母集団形成が課題となっていました。
そこで、ここ数年は全社的に採用体制の強化に取り組んでおり、2年前にはリクルーター制度を導入し、一部の社員にはリクルーターとして母校の研究室などにアプローチをかけてもらいました。しかし、それだけではまだまだ十分な母集団形成が難しいということで、より多くの学生にリーチできるこの情報誌に着目したのです。
― WEBメディアではなく、あくまでも紙の情報誌を活用しようと考えた理由があればお聞かせください。
草薙さん: 以前からWEBメディアによる採用活動は展開していたのですが、それだけだと先ほど述べたように首都圏や関西圏の学生ばかりが集まってしまう傾向にありました。その点、この情報誌であれば全国の大学のほか、マイナビに登録している理系学生の自宅にも配布されますので、地方の学生に不二工機のことを知ってもらうにはうってつけだと考えたのです。
― 実際に情報誌を手に取ってみて感じたことがあれば教えてください。
福井さん: この情報誌には不二工機だけでなく、日本を代表する多くの企業の社員たちが掲載されています。しかも、紙の情報誌には保管性や再読性が高いといった特色があるので、多くの学生が手元に置き、時折、眺めては気になった会社のホームページをチェックしたりするはずです。ひとりでも多くの学生がそういった行動の中から不二工機に関心を持ち、次のステップに進んでくれればと思います。
― 全社的に採用活動に力を入れ始めた背景にはどのようなことがあったのでしょうか。
草薙さん: 将来を見据えると、電気自動車などの新型カーエアコンに対応できる人材、今以上にグローバルな視点に立ったマーケティングやファイナンスに対応できる人材が不可欠になります。そのため、採用体制を強化し、新しいタイプの人材を募ることにしたのです。
― 採用活動を前向きに進めているということは、業績は好調なのでしょうか。
福井さん: コロナ禍やウクライナ危機によって一時的な資材の不足などの問題はありましたが、グローバルな規模で引き合いは増加しており、業績も順調に推移しています。そもそも、壁掛け形の業務エアコンというのは日本オリジナルのもので膨大なノウハウが詰まっており、海外メーカーではほとんど取り扱っていません。それだけに世界的なシェアも高く、電気自動車のカーエアコン同様、まだまだ伸びしろがある分野なのです。こうした将来性もしっかりと伝えていくことで、理系人材の心をしっかりとつかんでいきたいですね。
― 情報誌を活用して感じたメリットや活用後の変化などについて教えてください。
福井さん: 取材に協力してくれた現場や、採用に携わる面接官などとの協力体制を構築できたことがメリットとして挙げられます。さらなる母集団形成の強化や、内定辞退率の低下を目指していくには、全社的に「当社も人材獲得競争にさらされている」という危機感を共有しつつ、会社の魅力をどう伝えていくかといったことを真剣に考え、実践しなければなりません。情報誌を初めて導入したことは社内的にもインパクトがありましたし、現場からの協力を得るきっかけにもなりましたので、この変化を引き続き推進していきたいと思います。
草薙さん: 若手社員が、情報誌に掲載されること自体は大きなメリットだと捉えています。実際、若手社員にとっても、他社の素晴らしい人材と肩を並べて紹介されることは大きな励みになるはずです。
また、社内での認知も着実に広がってきていることもあり、来年度以降は新たな社員にも登場してもらい、少しずつ自社の優れた人材に光を当てていく機会にしていきたいと考えています。そうすることで、人事部としても社内の優秀な人材の発掘にもつながりますし、社員たちがどのような思いで、どんな仕事に携わっているのかをあらためて知る機会になるからです。これは後々の人事戦略を描く上でも大きな財産になるはずです。
― 完成した誌面は社内でどのように回覧したのですか。
福井さん: 誌面に登場いただいた社員やその上司、人事部などにPDFデータで配布しました。反応も上々でしたし、人事戦略を策定し、推進していく上で絶好の種まきになったと実感しています。他部門などにも幅広く配布することで、いずれはそれぞれの部門から掲載候補者が推薦されてくるような流れになっていくことを期待しています。
草薙さん:
先生方の中には「情報通信の知見を冷凍・空調機器の自動制御機器メーカーでどう活用できるのか」とお感じになっている方も多いかと思いますので、この情報誌を通して「大学で電気工学や情報通信の基礎を学んだ人材が、不二工機でその知見に磨きをかけることで、電気自動車などの新分野において長期にわたって活躍できる人材になる」というビジョンをお伝えしていきたいと考えています。そうすれば、多くの先生方が自然と当社のポテンシャルに気付き、研究室の学生にもそのことを共有してくれるようになると思うのです。
福井さん: マイナビのネットワークのおかげで、すでに多くの大学や学生の皆さんにリーチできたかと思いますので、今回の施策には大いに満足しています。今後は自社のリクルーター制度などとの連携を強化し、より積極的な情報発信ができる体制づくりを目指していきたいと思います。
草薙さん: 欲を言えば、さらに多くの教育機関にこの情報誌を普及していただけるとありがたいですね。高等専門学校や工学系短期大学といった教育機関の卒業生の方にも、当社には本社の設計部門や工場のエンジニアとして活躍できる土壌があることから、より広くアプローチできればと思います。
― 今後、マイナビやこの情報誌に期待することがあればお聞かせください。
福井さん: マイナビのネットワークのおかげで、すでに多くの大学や学生の皆さんにリーチできたかと思いますので、今回の施策には大いに満足しています。今後は自社のリクルーター制度などとの連携を強化し、より積極的な情報発信ができる体制づくりを目指していきたいと思います。
草薙さん: 欲を言えば、さらに多くの教育機関にこの情報誌を普及していただけるとありがたいですね。高等専門学校や工学系短期大学といった教育機関の卒業生の方にも、当社には本社の設計部門や工場のエンジニアとして活躍できる土壌があることから、より広くアプローチできればと思います。