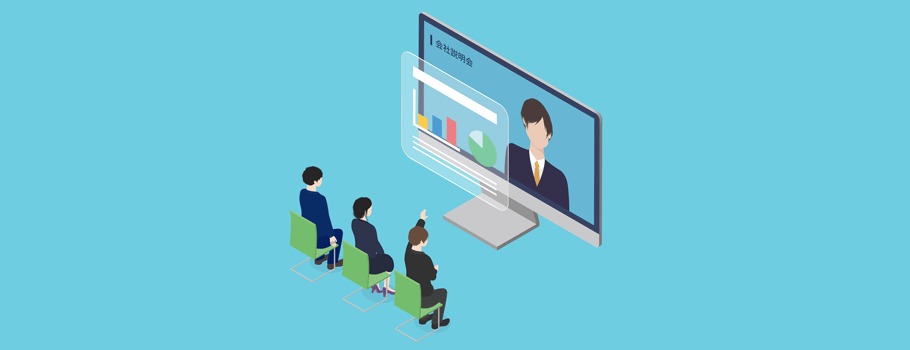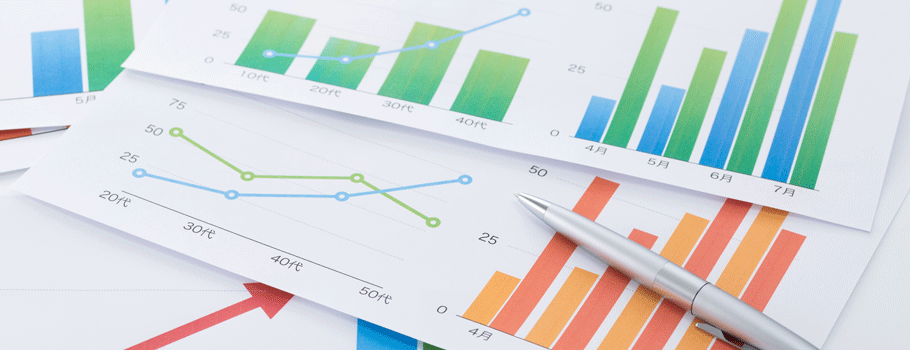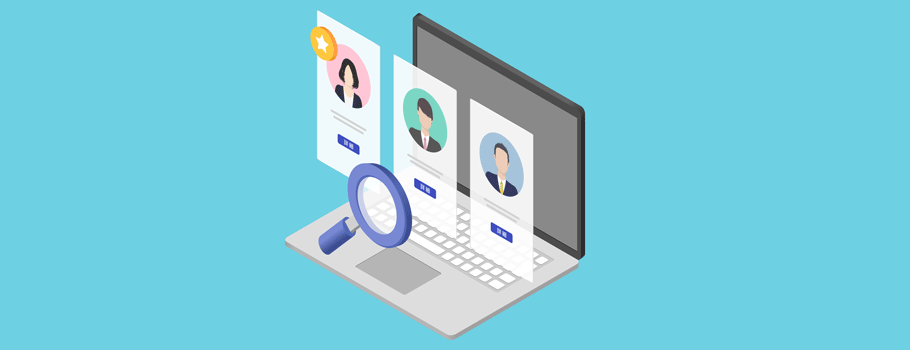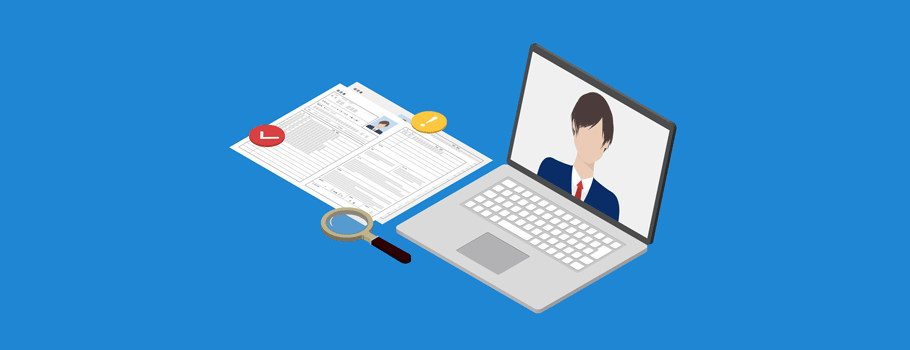母集団形成とは? 導入プロセスと運用の注意点
母集団とは
「母集団」とは、統計学で調査となる数値や属性など源泉となる全てのデータの集合体を指し、マーケティング調査や社会調査、世論調査に用いられています。つまり、「母集団形成」とは、調査対象のデータを作り上げることです。
近年では、従業員採用の現場で、この「母集団」の概念が採り入れられ、「母集団形成」に注目が集まっています。
採用での母集団形成とは
採用での母集団形成とは、自社の求人に興味や関心を持っている求職者を集めることです。集められた、母集団の中から、書類選考、面接などのプロセスを進め、最終的な採用者を決定します。
採用で母集団を形成する目的
優秀な人材を確保するため
より多くの母集団を形成し、多くの人材の中から選考することによって、自社にあった優秀な人材を採用できる可能性が高まります。
適切な採用人員を確保するため
充分な数の母集団を形成することで、計画している採用人数を確保することができます。
母集団形成が重要になっている背景
激化する人材獲得競走
大きな要因のひとつに少子高齢化による生産年齢人口(15~64歳)の減少があります。 平成29年度版厚生労働白書の「年齢3区分別人口及び人口割合の推移と予測」によると、 2016年1億2,700万人だった人口は、2065年には8,800万人台に減少し、60.3%だった生産年齢人口は、51.4%まで減少すると予測されています。
コロナ禍により、一時的に有効求人倍率は低下傾向にありますが、企業は慢性的な人材不足にあり、求職者を各社で奪い合う、売り手市場はさらに厳しくなると予測されています。
採用マーケティングの導入
激しくなる採用競走の中、企業は採用にマーケティングの発想を採り入れました。
企業が、商品やサービスを販売する際には、顧客に選んでもらう必要があります。企業は、見込み客を集め、データ管理をし、接触しながら信頼関係を築き、ロイヤリティを高めて、最終的に選んでいただき顧客とするマーケティング手法を採用しています。
同じように、売り手市場の採用では、人材に自社を選んでもらう必要があり、マーケティング的なアプローチが求められています。
自社に興味のある見込み人材を集め、データで管理し、接触しながら信頼関係を築き、ロイヤリティを高めて、最終的に選んでもらい人材を獲得する。
この採用マーケティングを実現するために、見込み人材を集める「母集団形成」は重要な役割を果たしています。
母集団形成のメリット
データ分析を元に計画立案ができる
採用には、各プロセス(書類応募、書類選考、面接など)に進んだ人数の割合を指す「採用歩留まり」があります。これらの各プロセスのデータを蓄積することで、必要な人数を採用するためには何人の母集団が必要なのか? 母集団を集めるためにどんな施策の数・種類が必要か? などのデータを基にした予測が可能になり、精度の高い採用計画が立案できます。
採用の確率を高められる
形成した母集団をデータ管理し、人材と適宜接触することで、自社に対するロイヤリティを高め、採用の確率を高めることができます。
社員の質の向上に貢献する
母集団を応募経路や学歴などの要素に分解し、分析することで、どの要素から採用した人材が、より社に貢献する傾向にあるか可視化できます。そのデータを基に、特定の要素を多く集めることができれば、採用の質を向上させることができます。
母集団形成における新卒採用と中途採用の違い
新卒採用の母集団形成
新卒一括採用では、母集団の形成が非常に重要な役割を果たします。自社に興味を持っている学生を中心に、早めに母集団を形成し、学生と長期的かつ継続的に接触することで、信頼関係を築くことが大切です。一方で、学生の本分である学業に影響を与えないように、採用スケジュールには充分配慮が必要です。
「2022年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項」として、内閣府は経済団体に以下のように要請しました。
| 広報活動開始 | 卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降 |
| 採用選考活動開始 | 卒業・修了年度の6月1日以降 |
| 正式な内定日 | 卒業・修了年度の10月1日以降 |
また、のちのデータ分析のために、形成した母集団をどのような要素で分類するのか仮説や指標を用意しておきましょう。
中途採用の母集団形成
中途採用は、スケジュールはなく、必要に応じて適宜実施することになります。目的は大きく分けて2つあり、経験の浅い第二新卒を求める場合と、専門的なスキルを持つ即戦力を求める場合です。
経験の浅い第二新卒を求める場合
新卒採用と異なり、採用スケジュールに縛りはありません。長期間接触している間に、他社に転職してしまう可能性もあるため、多くの求職者と接触できる求人媒体やセミナーを用いて、短期間で、まとまった母集団を集める採用活動を行います。
専門的なスキルを持つ即戦力を求める場合
採用ターゲットも具体的なスキルや経験を持つ人材が対象となり、人数こそ少ないですが、絞られた母集団が形成されます。求める人材が明確なため、求人媒体に加えて、人材紹介などの手段が用いられます。
母集団形成の導入プロセス
母集団形成は、採用マーケティングの最初のステップです。ここでは、母集団形成の導入プロセスを解説します。
事業計画の確認
企業には、本年度、次年度、三か年計画、五か年計画などの短期、中長期の計画が用意されています。その計画を達成するために必要な人員も定義されています。計画に即したスキルを持った人材、人数を採用するために、どのような質で、何人の母集団を形成するべきか逆算し、計画をしましょう。
スケジュールの策定
前述の通り、採用は事業計画がベースになります。事業計画を基に採用計画を立案する場合、何月に何人が必要か確認し、中途採用ならば半年以上前。新卒採用ならば、学生のスケジュールにあわせて、前もって母集団の形成を準備しましょう。
母集団形成方法の検討
母集団形成を行うのに必要な求人方法を検討しましょう。次章では、具体的な母集団の形成方法を解説します。
母集団形成の方法
求人媒体
近年はオンライン化が進み、求人媒体には、多くの求職者が登録しています。あらゆる人材にリーチし、量も確保しやすく、さらに、求職者とのコミュニケーションが管理しやすい特長もあります。
例えば、マイナビ転職では、業界最大級の登録者683万人(2021年10月現在)にアプローチできるため効果的に母集団形成ができます。
人材紹介・ヘッドハンティング
多くの人材にアプローチはできませんが、エージェントが、フィルタリングした希望に近い人材を紹介します。また、自社の社名を伏せた非公開求人も可能です。
会社説明会、就職セミナーなどのイベント
複数の企業が集まる就職セミナーや、自社が主催する会社説明会にて求職者と接触します。 大学や高校主催のセミナーも実施されており、一度に多くの求職者と接触できることが特長です。
広告と自社採用ページ
インターネットなどの広告を利用して、自社の採用ページに求職者を誘導する方法です。特にFacebook広告は、ターゲティングができるため、自社のイメージに近いユーザーに広告を出すことができます。また、自社採用ページから申込みする求職者は意欲が高く採用確率が高い傾向にあります。
リファラル採用
既に働いている社員からの紹介や、知人からの紹介など、人脈を通じて行われる縁故採用です。お互い知っている人同士の信頼関係をベースとしているため、ミスマッチが少ない傾向にあります。
ダイレクトリクルーティング
求職者が登録されているデータベースにアクセスし、企業が求職者をピンポイントでスカウトします。採用担当者が個別対応する必要があり、多くの求職者と関係を作ることが難しい場合もあります。
ソーシャルリクルーティング
TwitterやLine、Facebook、YouTubeなどのSNSを活用して行うリクルーティング手法です。 SNSを通じて、企業の魅力を配信します。自社をよく知ってもらう認知と、SNSを用いたコミュニケーションで母集団の形成を行います。
失敗しないための母集団形成の注意点
採用ターゲットの明確化
ターゲットを絞らずに集めると、多くのコストと、選考するための人的工数が発生してしまいます。また、ターゲット像がボヤけると、求職者に響かず、人数が集まらないケースもあります。事業計画にあわせて、必要な人材を現場にヒアリングして、適切なターゲット像をつくりましょう。
まめな接触で信頼関係を築く
母集団を形成する目的は、求職者との信頼関係を構築し、ロイヤリティを高め採用につなげることです。母集団を放置すると他社への入社が決まってしまうかもしれません。接点を有効活用して信頼を築きましょう。
結果の分析が重要
採用目標を達成したのちに、効果検証を行いましょう。どの経路から集めた母集団が有効だったのか? 費用対効果は? どの施策からの評価が高かったのか? などデータを分析し、以降の採用活動に役立てましょう。
少子高齢化による生産人口の減少で、企業の人材獲得競走は、ますます激しくなっていきます。売り手市場のこの時代、優秀な人材を集めるために母集団形成に注力し、採用マーケティングを活用して、求職者から選ばれる企業を目指しましょう。
- 人材採用・育成 更新日:2022/03/30
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-