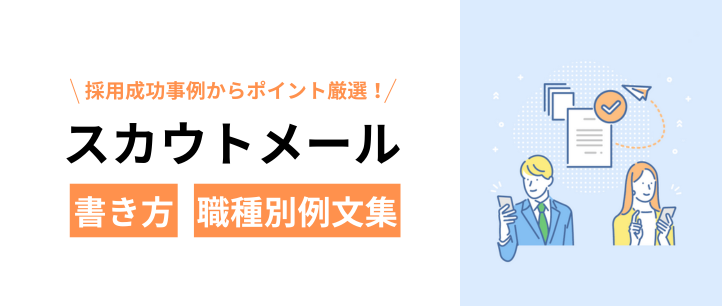採用プロセスを最適化する方法とは?各プロセスの課題と改善策も解説
「求人を出しても応募がない」「採用してもすぐに辞めてしまう」といった、採用活動がうまくいかない悩みを抱える企業が増えています。採用の難易度が高まる背景には、採用市場の構造的な変化や、従来の採用手法が通用しにくくなっている現状があります。
だからこそ、今は採用フロー全体を見直し、自社にとってどのフェーズに課題があるのかを正確に把握することが必要です。また、課題を見つけ、対策を講じることが、採用成果の向上につながります。
この記事では、採用課題を採用の各フェーズ別に整理しながら、具体的な対策や事例を紹介します。
1. 採用プロセスとは
採用プロセスとは、企業が必要とする人材を確保するために実施する一連の活動の流れを指す言葉です。一般的には採用計画の立案から入社後の定着支援までの採用にかかわるすべての工程を意味しており、採用フローとも呼ばれることもあります。
採用プロセスを決める作業は単なる工程表決定ではなく、企業の戦略や人材像を反映させる重要な業務です。採用活動の効率や選考の質は、採用プロセスの設計に大きく左右されます。
また、応募者にとっても採用は企業との最初の接点であり、進め方によって企業の印象が大きく変わります。
企業と応募者の双方に影響があるため、採用プロセスの最適化は採用の成功と企業の発展に欠かせません。
2. 採用プロセスを最適化する3つのメリット
採用プロセスの最適化は、採用活動の効率や成果に大きく影響します。最適化が不十分なままやみくもに採用活動を続ける場合、生産性が低下し、自社に対する悪い印象を与えます。採用活動の成果が上がっていないと感じた場合、自社の課題を洗い出し、最適化を進めましょう。
ここでは、採用プロセスを見直すことで得られる3つの主なメリットを解説します。
2-1. 採用活動を効率化できる
採用プロセスを明確に設計し、各工程を整理することで、採用活動全体を効率化できます。募集から入社までの流れを可視化すれば、それぞれのステップで何をすべきかが明確になり、担当者間での情報共有やタスクの分担もしやすくなります。
特に選考管理や日程調整などは、応募者が多くなるほど業務量が増えがちです。採用プロセスを標準化すれば、工数の多い工程の自動化・簡略化が進み、人事担当者の負担軽減にもつながります。
また、採用が計画どおりに進まない場合も、課題のある工程を特定しやすくなります。例えば、「応募者が集まらない」「一次面接の通過率が極端に低い」といった傾向を定量的に把握できるようになれば、それぞれの工程が抱える採用課題に合わせて最適な手を打てるでしょう。
2-2. より自社にマッチした人材採用につながる
採用プロセスを最適化すると、単に応募者数を増やすだけでなく、自社に適した人材を見極めて採用できる可能性が高まります。選考における採用基準や採用ペルソナを明確に設定することで、企業が求めるスキル・経験・人物像に合致した候補者を抽出しやすくなります。
やみくもに応募を集めて選考を進める手法では、ミスマッチが生じやすく、入社後の定着率や早期離職率にも悪影響を及ぼします。一方で、採用プロセスを通じて企業のカルチャーや価値観を明確に伝えられれば、候補者も自分に合った職場かどうかを判断しやすくなり、内定辞退や入社後のギャップも抑えられるでしょう。
2-3. 採用期間を短縮して辞退を防ぎやすくなる
採用プロセスを最適化することで、書類選考や面接、合否連絡など各段階の所要時間を短縮できます。
採用プロセスが煩雑で長期化すると、候補者の意欲が低下し、競合他社への流出を招く要因になります。特に優秀な人材ほど複数の選考を並行して進めており、判断の早い企業が選ばれやすい傾向があります。そのため、プロセスの簡素化と対応の高速化が必要です。
また、選考がスムーズに進めば、応募者も企業への信頼感や好印象を抱きやすくなり、内定承諾率の向上にもつながります。採用活動にかかる人的・金銭的コストの抑制にも効果があり、効率と成果の両立を目指す上で、採用プロセスの最適化は欠かせません。
3. 一般的な採用プロセスごとの課題と改善のポイント
採用プロセスを最適化する際には、各工程について見直す必要があります。
以下では、一般的な採用プロセスの各工程と、工程ごとに起こりやすい採用課題の解決策について解説します。
3-1. 採用計画を立てる
採用計画は、採用活動を戦略的に進める上での起点となる工程です。採用の目的やスケジュール、採用人数、雇用形態、業務分担などを具体化し、採用活動全体の土台を整える役割を果たします。計画が不明確なまま採用を進めると、必要な時期に人材を確保できなかったり、現場とのミスマッチが発生したりするリスクが高まります。
まず重要なのは、自社の事業計画に基づいた「採用の必要性と背景」を明確にすることです。部署ごとの人員配置や業務の拡大・変化に対応できるよう、「いつまでに」「どのポジションを」「何名採用する」必要があるかを定めましょう。
採用する人材はどのポジションでどのような業務を担うのか、業務の遂行にはどの程度の経験・スキルが必要かといった点を、事業や部門の現実に即して洗い出してください。
その上で、いつから募集を開始し、どの程度の期間を選考・内定・入社に割り当てるのかを決めれば、後々の採用活動もスムーズに進みます。
関連記事:採用計画の立て方を分かりやすく解説!テンプレートあり
3-2. 求人を募集する
採用計画を策定した後は、求める人材に確実に情報を届けるための求人募集工程に進みます。この工程では、採用チャネルの選定や求人情報の設計が中心となります。採用ターゲットとなる人材に見つけてもらい、応募したいと思ってもらうためには、募集方法の選定と求人内容の最適化が重要です。
まずは、どの採用チャネルを活用するか決める必要があります。例えば求人媒体と一口に言っても、Webサイト、スカウトサービス、人材紹介、ハローワーク、SNSなど多様な採用手法があり、それぞれ特性が異なります。求める人物像や雇用形態に応じて、最適なチャネルを選定することが採用成功の鍵です。
求人情報そのものの質にも注意が必要です。特に仕事内容の記載が不十分な場合、求職者に不安を与え、応募意欲を損なう要因となり得ます。仕事内容や雇用条件が不明瞭という印象を与えないように、売上目標、商談件数、残業時間の平均など、定量的な情報を盛り込むとよいでしょう。
また、会社をよく見せようとしすぎた結果、ミスマッチが発生するのはよくある失敗の1つです。自社について悪い点も伝えるようにすれば、ミスマッチを防ぎやすくなります。
関連記事:求人票の書き方・記載例を解説!チェックポイント・成功事例も紹介
3-3. 会社説明会やカジュアル面談を行う
会社説明会やカジュアル面談は、選考前に求職者と企業が相互理解を深める重要な接点です。求職者に企業への関心を高めてもらい、入社後のギャップを防ぐためには、この段階での情報提供とコミュニケーションの質が問われます。
新卒採用では、会社説明会によって企業の概要や方針、各部門の業務内容を伝える機会を設けるのが一般的です。一方、中途採用では、個別に行うカジュアル面談が主流で、選考要素はなく、求職者と社員がざっくばらんに情報交換を行う場として機能します。
しかし、これらの機会がうまく機能しないケースもあります。
会社説明会でよく見られる課題の1つが、伝わりづらいプレゼンです。全体像が分かりづらかったり、説明が抽象的すぎたりすると、参加者の理解や関心を得られず、志望度が高まりません。まずは全体像を伝えた上で、聞き手を巻き込むような質問やクイズ形式の導入、仕事内容や職場環境の具体例を交えたストーリー性ある説明をすれば、志望度を高めやすくなります。
カジュアル面談でよくある失敗としては、カジュアル面談の面接化があります。本来は選考要素がないにもかかわらず、志望動機などの面接で行うような問いかけをしてしまうと、候補者は不審に感じるでしょう。カジュアル面談はあくまで相互理解の場であるという認識を関係者間で共有し、企業側も候補者の価値観や関心に応じた情報提供を重視する姿勢が必要です。
説明会や面談後に今後の選考の流れを説明せずに終了してしまうことも、候補者の意向度を下げる要因になります。終了時には、選考に進む意思があるかどうかを確認した上で、次のステップの案内や連絡タイミングを伝えましょう。
関連記事:カジュアル面談とは?面接との違いやメリット・面談の進め方を解説!
3-4. 選考・面接を進める
選考・面接は、求職者の能力や適性、人柄が自社に合致するかを見極める工程です。書類選考、適性検査、面接などの段階を通じて、採用の是非を判断していくことになります。
面接で特に注意すべき課題は、面接は人材を評価するだけでなく、応募者からも企業が評価されるという点です。求職者にとって面接官は企業の代表であり、言動1つが企業全体の印象を左右します。面接時の言葉遣いや態度、質問内容に不適切な点があれば、たとえ条件が良くても辞退される可能性があるため、面接官の教育は必須です。
また、応募者の見極めが不十分になるのもよくある課題です。原因として、質問の設計に問題があるケースが多く見られます。例えば、「当社の印象はいかがですか?」といった曖昧な質問では、応募者の志望度や適性を正確に判断できません。このような場面では、「当社に応募した理由を具体的に教えてください」といった明確で意図が伝わる表現を用いると効果的です。
スキルの見極めについても同様に、質問が漠然としていると実力を正確に測れません。「英語を使った業務は対応可能ですか?」と尋ねるよりも、「海外の取引先との会議で、英語での交渉を担当した経験はありますか?」と具体的な状況を提示することで、実務レベルのスキルを見極めやすくなります。
関連記事:未経験者の中途採用面接では何を確認すべき? その難しさと見極め方
3-5. 内定者フォローを行う
内定者フォローは、内定辞退を防ぎ、入社意欲を維持する上で欠かせないプロセスです。特に新卒採用では内定から入社までの期間が長いため、コミュニケーションの希薄化が内定辞退につながるリスクがあります。
内定者フォローの課題の1つに、企業からの情報発信が一方通行になっているという点が挙げられます。お互いにコミュニケーションを取れるように、メンター制度を導入し、若手社員をメンターとしてつけるのがおすすめです。小さな質問や不安も気軽に相談できる環境づくりが、安心感と帰属意識の醸成につながります。
また、多くの内定者は、業務内容を早期に理解したいと考えています。業務内容に関する動画や資料を共有したり、簡単な課題に取り組んでもらいフィードバックを行ったりすることで、入社後の業務イメージを明確にできるでしょう。
ただし、内定者のスケジュールに対する配慮を忘れると、かえって内定辞退につながる恐れがあります。新卒採用の場合は卒論や卒業旅行、中途採用の場合は前職の退職に伴う引き継ぎや手続きが残っているケースも多いです。状況に応じて対面で交流する、オンラインでコミュニケーションを取るなど、相手に応じた手段を選べば、満足度も上がります。
関連記事:【歩留まり改善】内定辞退を防止するには?辞退の理由要因と改善方法
3-6. 入社後フォローを行う
入社後のフォローが不十分な場合、採用活動の成果が十分に生かされず、早期離職につながる恐れがあります。実際に、マイナビの調査では20代の正社員のうち11.0%が半年以内の早期離職を経験しており、企業活動において深刻な課題です。
出典:マイナビキャリアリサーチラボ「早期離職に繋がる入社後のギャップとは?-年代別の理由と企業の対策を紹介」
特に目立つ理由としては、「職場の雰囲気が自分に合わなかった」「想定していた仕事内容と異なっていた」といった、入社前後のギャップによるミスマッチが挙げられます。このようなギャップを減らすには、入社後の丁寧なフォローが欠かせません。
オンボーディングプログラムの実施や入社後研修により、大きなギャップを感じずに入職できる職場環境を作るのが大切です。また、評価制度を透明化し、より頑張りが評価される仕組みを作って定期的にフィードバックを行うのも、入社後フォローとして有効です。
関連記事:中途採用者に必要なフォローとは?入社後に実施すべきことを紹介
4. 採用プロセスを最適化する6つのポイント
これまでの見出しでは、採用プロセスの個々の工程を部分最適する方法について解説してきました。この見出しでは、採用プロセス全体の最適化を行い、採用活動をよりよいものにするポイントを紹介します。
4-1. 採用戦略について全社で共通認識を持つ
採用活動の成果を最大化するためには、採用戦略を人事部門だけで完結させず、全社的に共有し、共通認識を持つことが不可欠です。
採用戦略とは、企業の中長期的な目標達成に必要な人材を、いかに効率よく、かつ確実に確保するかを計画するものです。採用市場が流動化し、求職者側の情報収集力が高まる中では、場当たり的な対応では継続的な人材確保は難しくなっています。経営戦略と紐づいた採用戦略を立て、それを社内全体で共有することが求められています。
「どのような人材が必要か」「なぜその人材を採用したいのか」といった基本的な方針が現場と共有されていなければ、選考基準や入社後の評価にもブレが生じやすくなります。また、企業全体の方向性と異なる現場の判断により、入社後に早期離職が発生するケースも考えられます。
そのため、採用戦略の内容を明文化し、人事部門だけでなく各現場部門・経営陣にも共有する体制づくりが必要です。以下のような方法で、共通認識を作りましょう。
4-2. 採用ペルソナを明確にする
採用活動の精度を高め、入社後のミスマッチを防ぐためには、採用ペルソナを明確にすることが重要です。
採用ペルソナとは、企業が求める理想の人材像を具体的に描いたものです。年齢や性別、職歴といった表面的な属性だけでなく、価値観・志向性・ライフスタイルなども含めて、1人の人物としてイメージできるレベルにまで設計する必要があります。
例えば「30代前半で、前職ではIT企業の営業マネージャーを経験した。成長意欲が高く、地方での子育てと両立できる働き方を求めている」など、具体性が高いほど効果的です。
ペルソナ設計は、以下のような手順で行います。
1 |
採用目的を明確にし、必要な人材要件を整理する |
|---|---|
2 |
経営層や現場社員にヒアリングし、活躍している人材の特徴を抽出する |
3 |
仮のペルソナを社内で共有し、意見をすり合わせて精度を高める |
4 |
採用市場の実情をペルソナに反映し、採用活動に使う |
明確な採用ペルソナがあれば、求人票の作成、スカウト、面接などの場面で一貫性のある判断が可能になり、採用活動全体の質が向上します。
4-3. 採用コストを見直す
効率的な採用活動を実現するためには、採用コストの内訳とそのバランスを把握した上で、見直しを図ることが重要です。
採用コストとは、採用活動にかかるすべての費用の合計を指す言葉で、大きく分けて「内部コスト」と「外部コスト」の2種類があります。
内部コストには、採用担当者の人件費や候補者とのやりとりにかかる通信費、面接時の交通費などが含まれます。一方、外部コストには、求人サイト掲載料、人材紹介会社への手数料、説明会の会場費などがあり、特に外部コストは高額になる傾向があります。
費用の全体像を把握した上で、「1人あたりの採用単価」を算出することが、採用活動の費用対効果を最適化するために重要です。
例えば、採用活動にかかった内部コストと外部コストの合計が500万円で、10名の採用に成功した場合、次のように計算されます。
500万円 ÷ 10名=1名あたりの採用コストは50万円
採用単価を明確にすることで、予算超過の有無やコスト配分の妥当性を検討できます。
採用活動の中でも、特に中途採用は採用予算を超過するケースが多く、2024年のマイナビの調査では中途採用にかかる費用の実績が平均650.6万円と、予算平均(565.3万円)を約85万円上回りました。
出典:マイナビキャリアリサーチラボ「中途採用状況調査 2025年版(2024年実績)」
特に従業員数が多い企業ほど予算を超過する傾向が見られるため、コスト構造を定期的に見直し、どの費用が成果に結びついているかを分析することが大切です。
関連記事:採用コストを削減する8つの方法|内訳や計算方法も紹介
4-4. 採用プロセスごとの歩留まりを把握する
採用活動の効率を高めるには、各選考フェーズにおける「歩留まり」を把握・改善することが重要です。
採用における歩留まりとは、応募から内定承諾までの各工程で、次の段階に進んだ候補者の割合を示す指標です。例えば、面接を受けた50人のうち20人が次の面接に進んだ場合、「20 ÷ 50 × 100」で歩留まり率は40%となります。このように、歩留まり率が高いほど、選考途中での辞退や不合格が少ない=採用プロセスがうまく機能していると評価できます。
代表的な歩留まり指標としては、以下のようなものがあります。
ただし、途中辞退率や内定辞退率は、他の指標とは異なり「低いほうが望ましい」点に注意が必要です。
2024年のマイナビの調査では、中途採用における平均的な歩留まり率は以下の通りです。
書類通過率:55.2%
内定率:28.8%
内定承諾率:90.8%
出典:マイナビキャリアリサーチラボ「中途採用状況調査 2025年版(2024年実績)」
各フェーズの歩留まり率を可視化し、特に数値の低い工程については原因を分析すれば、辞退や不合格の要因に応じた改善策を講じられます。
4-5. 採用管理システムを導入する
採用活動を効率的かつ戦略的に進めるには、採用管理システム(ATS)の導入が有効です。
ATS(Applicant Tracking System)は、求人の掲載から応募受付、応募者対応、選考状況や応募者情報の管理、結果の分析までを一括で行えるシステムです。
応募者ごとの進捗状況や面接スケジュール、選考の通過率などのデータを一元化し、採用の歩留まり率や辞退率なども可視化できます。ボトルネックとなる工程の特定や改善策の立案にも役立つでしょう。
特に「大人数の採用を行う」「複数の媒体で求人を出している」「継続的に採用活動を行っている」企業にとっては、ATSは採用業務効率化と精度向上の両面でメリットが大きいツールです。
4-6. 外部サービスへのアウトソーシングも考える
採用活動における業務負担が大きく、十分なリソースを確保できない場合は、採用代行などの外部サービスを活用するのも効果的です。
採用代行サービスを専門に扱う企業では、採用計画の立案や選考フローの設計といった上流工程を支援する「コンサルティング型」や、書類選考・日程調整・面接アレンジなどを代行する「業務サポート型」など、ニーズに応じた多様な支援が用意されています。部分的な委託も可能であり、自社の課題や優先順位に応じて柔軟に対応範囲を調整できる点がメリットです。
採用業務を外部に委託することで、社内の担当者はコア業務に集中でき、限られたリソースでも安定した採用活動の継続が可能になります。
また、採用代行会社は豊富なノウハウを有しており、効果的な求人原稿の作成や母集団形成の手法、歩留まりの改善点など、実践的なアドバイスが得られるのも大きなメリットです。社内の採用体制やスキルに不安がある場合や、採用活動をスピーディに立ち上げたい場合には、外部サービスの導入を前向きに検討してみるとよいでしょう。
5. 採用プロセスの最適化に成功した企業事例
採用プロセスの最適化に成功すれば、安定した人材確保が可能になり、今後の事業成長にもつながります。以下では、マイナビのサービスを導入することで、採用プロセスの最適化に成功した企業の事例を紹介します。
5-1. 株式会社Carecon様
エンジニアの育成とシステム開発を軸に事業を拡大している株式会社Carecon様は、計画的な採用が難しかったリファラル中心の手法を見直し、採用プロセスの最適化に取り組みました。従来はリファラルや協業先からの紹介が中心でしたが、母集団の形成が難しく、計画的な採用を進めにくい状況でした。
そこで、応募者の母集団を拡大するためにマイナビ転職を導入し、営業・制作担当と連携しながらターゲットに合わせた求人広告を制作しました。これにより応募数が大幅に増加し、女性応募者の割合を増やすことに成功します。
さらに、選考前にカジュアル面談を設け、企業の価値観や働き方を丁寧に伝えた上で、候補者のキャリア観や目的を深掘りする対話を重視することで、入社後のミスマッチを防ぐ工夫を行いました。また、採用業務を営業部門から専任チームに引き継ぎ、選考フローを体系的に整えた結果、地方拠点での採用や女性比率の改善にもつながり、組織全体の成長を生み出す好循環を生み出しています。
関連記事:マイナビ転職の利用で母集団形成に成功し、毎月安定した人数を採用できるように。独自のカジュアル面談で本音を聞き出し、ミスマッチを防止
5-2. 株式会社ミホミ様
株式会社ミホミ様は、コロナ禍を機に組織の年齢構成に偏りが生じたことから、マイナビ転職フェアを活用した採用プロセスの最適化に踏み切りました。
従来の新卒採用に依存した体制から脱却し、中途採用を中心としたより柔軟でスピーディな採用プロセスを構築しました。初回から専務や部長など裁量のあるメンバーが参加し、求職者とその場で対話した上で次の選考へ案内する体制を整えた結果、選考期間の大幅な短縮に成功します。
さらに、求職者が自ら興味を持って訪れたブースでの対話を重視し、カルチャーフィットを見極めた上で即時対応を行う仕組みを確立しました。加えて、採用活動ごとに社内で方針を明確にし、振り返りを通じて判断基準や行動をブラッシュアップすることで、PDCAサイクルを自然に機能させ、採用数とマッチ度の両立を実現しています。
関連記事:転職フェア内で「求めている人材かどうか」を直ちに見極め、選考期間を短縮。3回の出展で合計8名の内定獲得に成功!
まとめ
採用プロセスの最適化は、単なる業務改善ではなく、企業の成長戦略に直結する重要な取り組みです。採用計画の立案から入社後フォローまで、各工程で起こりやすい課題に対応しながら、全体を通じた歩留まりの把握や採用コストの見直しを行うことが求められます。
採用プロセスを見直すことで、効率的かつ戦略的な人材確保が可能となり、早期離職の防止やミスマッチの削減にもつながります。
さらに、成功事例に見られるように、社内連携や柔軟な採用施策によって、より良い採用成果を上げることも可能です。
採用に関する課題を感じている企業は、自社の採用プロセスを可視化し、改善に向けた取り組みを進めてみましょう。
※当記事は2025年6月時点の情報をもとに作成しています
- 人材採用・育成 更新日:2025/07/25
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-