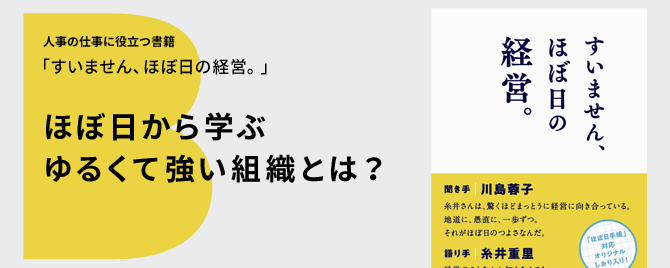「すいません、ほぼ日の経営。」 ほぼ日から学ぶゆるくて強い組織とは?
コピーライターとして知られる糸井重里氏が経営する「株式会社 ほぼ日」。2017に上場を果たした「株式会社 ほぼ日」では、ウェブサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」の運営やオリジナル商品の開発、販売を主な事業として行っています。特に「ほぼ日手帳」は、実際に使用している方も多いのではないでしょうか。
大ヒットとなったほぼ日手帳は、社員の「ほぼ日読者の生徒手帳を作ろう」という一言から始まった商品です。当初は開発担当者が他社の手帳を前にアイデアを出そうとしていたものの、糸井氏は商品研究を辞めさせ、ターゲットを設定しない、顧客調査をしない、といった形で商品開発を進めていったといいます。
そんな常識とは一線を画した商品開発の手法と、独自の経営哲学を持つ「ほぼ日」の組織は一体どんな理念で組織を作り、どう動いているのでしょうか。ほぼ日の主宰である糸井氏にジャーナリストの川島蓉子氏がインタビューをする形式の書籍『すいません、ほぼ日の経営。』をもとに、糸井氏の組織に対する考えを紹介します。
『すいません、ほぼ日の経営。』では、株式会社ほぼ日が事業を進めるうえで大切にしていることや、働き方改革への取り組み、株式上場を目指した理由が糸井氏本人の口から語られています。
「面白いかどうか」でプロジェクトが始まるほぼ日では、誰にでも発案者となれるチャンスがあります。「好き」か「嫌いか」を掘り下げていく過程から生まれたアイデアを実行し、ときに失敗したとしても「うまくいかなかった理由」を全員で考えて次に生かす……そんな事業の進め方は、企画書や会議、市場調査を必要としていません。だからこそ、他の企業が真似できない、ほぼ日ならではの強みが出た商品が作られるのです。
また、ほぼ日は「働き方改革」でも唯一無二の取り組みを見せています。一般的な企業では、「労働時間を制限し、給与を減らす」ケースが珍しくありません。しかし、ほぼ日では「労働時間を短縮するが、給与のベースを上げる」といった、真逆のことに挑戦しています。その背景には、「勤務時間が減ったとしても、魅力的なアイデアが生まれれば事業につながる」といった考えがありました。
このように、一般的な企業では思いつかないような、ほぼ日オリジナルのアイデアと、その背景にある思いを学べるのが、本書の大きな魅力です。
本書において、糸井氏はほぼ日の組織図を「人体模型図の内臓のようになっている」と称します。
これは、「それぞれの臓器がお互いに信号を出し合い、信号を受け取り合うことで全体が動いている」という人体と、「それぞれのチームがそれぞれ自律的に動いて関係し合う仕組みが、うちに合っている」という組織を重ね合わせた発想により生み出されています。
企業の組織図といえば、代表を中心に、本部、チームのリーダー、チームメンバーと、組織内で立ち位置が下の人が連なっていく、いわゆるツリー型が一般的です。しかし、ほぼ日の「内臓型組織」では、上下関係がないどころか、組織全体がすべてつながりつつ、役職を果たしている珍しい組織となっています。
そのため、社員は新たにプロジェクトを始めようとした時点で、直接糸井氏に可否を尋ねることも珍しくありません。そして糸井氏も、「もし失敗したとしても、失敗から次の何かが生まれることがある」として、積極的に挑戦させています。
こういった、「会社とは、こうあるもの」という既存の概念にとらわれない発想が、ほぼ日の今を作っているといっても過言ではないのです。
私たちの会社が社会に受け入れられるための
前提となるものです。
相互に助け合うということ、
自分や他人を「生きる」「生かす」ということです。
つよく
企画やアイデアやコンテンツを、
会社として、組織として「実現」「実行」できること、
現実に成り立たせることです。
おもしろく
新しい価値を生み出し、
コンテンツとして成り立たせるということです。
「ほぼ日刊イトイ新聞」や「TOBICHI」のように
「場」を生み出し、ひとが「場」に集まる理由です。
これが、ほぼ日の強みです。
ほぼ日は、この言葉の順番もたいせつにしています。
まず「やさしく」が、おおもとの前提にあり、
「やさしく」を実現する力が「つよく」です。
その上に、新しい価値となる「おもしろく」を
どれだけ生み出せるかが、ほぼ日の特徴です。
本書だけでなく、ほぼ日のホームページには、「やさしく、つよく、おもしろく。」という行動指針が記載されています。
当初、糸井氏は「言葉はなにかをするためにあるのであって、言葉に合わせるためになにかをするわけではない」という思いから、行動指針を言葉にする難しさを感じていたといいます。それでもあえて言葉にしたのは、東日本大震災がきっかけでした。
「復興支援を行うことは、直接の利益には結びつかない。しかし、会社として集まっている自分たちがやるべきだし、やっていいことでもある」という気づきから、「利益につながらなくても、やったほうがいいことも含まれる」という思いを、「雪かき」に重ねました。
ある店が、自分の店の隣まで雪かきをするのは、損得だけで見れば「損」かもしれません。しかし、この行動には「もうからないからやらない」のではなく、「社会的使命だと思ってやる」という考え方も存在しています。
たとえ利益にならない行動であったとしても、結果として「安心できる」、「自分たちの心が落ち着く」という点から「自分たちの得になる」ということから、「やさしく」という行動指針を定めたのです。
社員の従業員エンゲージメントを向上させ、自社に貢献する姿勢を作り出す意味でも、「行動指針」や「ビジョン」は必要不可欠です。ただ、それらには、企業そのものを縛ってしまう危険性もはらんでいます。
糸井氏が「やさしく」という行動指針に行き着いたのは、東日本大震災による社会との関わりに気がついたからこそ。今一度、目先の利益だけに目をやるのではなく、「社会」との関わりを意識することが大切なのでしょう。
一般的な企業とは異なり、総務や人事、経理といった事業部以外の社員も行動指針を実践しているほぼ日。総務といえば、企業を“縁の下で支える”立場のイメージがあるなかで、「ものすごく前にいる」というほぼ日は、珍しいように思えるかもしれません。
そもそも、ほぼ日では「やりたい人が手を挙げて、メンバーを集める」という形でプロジェクトが進んでいます。社員同士が「あなたに頼みたいんだけど……」と声を掛け合うほか、率直な意見を求め合う環境ができているからこそ、このような形での組織作りが可能となっているのです。
そしてほぼ日のオフィス内では、「部署ごとにメンバーを区切らない」、「4ヶ月に一度席替えを行う」といった取り組みが行われています。「隣の席にいる人が何をやっているのか理解できる」ことから、「お互いの仕事を尊敬する」ことにつながっているといいます。
「同じ会社で働いているけれど、あの人が何をしているのか説明できない」、「管理部と事業部の連携ができていない」という課題は、多くの企業において生じているかもしれません。その背景には、組織が「縦割り化」してしまっている状況が大きく影響していると言えるでしょう。
同じ部署ごとに座席が固定され、日常的に同じメンバーとしか関わらないのであれば、自然と各々の範囲は狭くなってしまいます。結果として「自分たちのテリトリーを守りたい」という発想につながり、縄張り意識が生じます。そこで企業全体に関わる問題があったとしても、「そっちには関係がない」、「私たちでなんとかできる」という意固地な姿勢から解決が遅くなる……という悪循環となってしまうでしょう。
そんな状況を回避するためにも、人事はほぼ日のような「席替え」や、部門にとらわれないプロジェクトを推し進めることが求められているのです。
部門ごとの上下関係もないほぼ日では、「誰がつくったか」ではなく「どんな場がつくったか」が重要視されています。実際に、糸井氏は「おもしろい場をつくって、その中からおもしろいアイデアが生まれてくる」ということを一貫して取り組んできたと述べています。
ほぼ日が「おもしろいアイデアが生まれてくる場」になっている背景には、成功体験がありました。新しいことをやるうえで、「本当にできるのだろうか」という不安はつきものです。しかし、「あなたならできる」という言葉をかけることで、「やってみよう」という意思決定をさせています。「できないかもしれない」と考える時間を、「まずはやってみる」という意思で削減することにつなげているのです。
もちろんそこにはお互いの信頼関係が必要です。しかし、社員のモチベーションを向上させるためには、このうえない一言でしょう。「社員の育成方法がわからない」、「新しいことにチャレンジさせたいが、モチベーションをどう上げたらいいのか」という課題を感じている場合は、まずはメンバー同士の信頼関係を構築すると同時に、「あなただから頼みたい」という一言をかけられるよう意識してみてはいかがでしょうか。
ほぼ日は「内臓型組織」でそれぞれの役割を果たし、お互いを尊敬し合える環境にありますが、以前から糸井氏は他の企業の組織に「これはいやだな」と思う瞬間があったといいます。
内臓として組織を見ると「この部分はなくてもいい」とは簡単に言えません。むしろ「別の臓器で補う」、「切除したが、別の臓器が鍛えられた」ということもありえます。血のめぐりがいい健康的な人体のように、組織もそれぞれの部署間で積極的なコミュニケーションが成立すれば、企業そのものも確固たる絆が芽生えるのかもしれません。
- 労務・制度 更新日:2019/07/02
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-