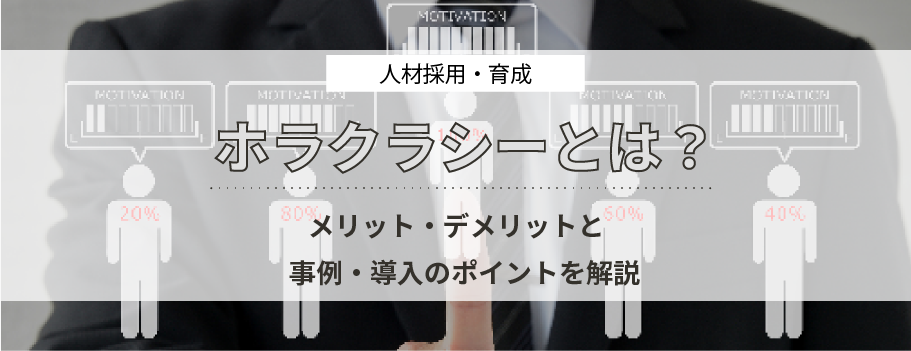ホラクラシーとは?メリット・デメリットと事例・導入のポイントを解説
大きな特徴は管理職を設けない点です。管理職が持っていた意思決定の権限を個人やチームに与え、フラットで民主的な組織をつくります。
変化が激しい現代の経営環境では、柔軟に組織や業務のあり方を変化させ、社員一人ひとりの自主性とエンゲージメントを高めることで、現場での創意工夫やイノベーションを絶え間なく生み出していかなければなりません。
ホラクラシーは、変化に強く迅速な意思決定ができる組織をつくるために、発案された概念です。
また、ホラクラシー組織をつくるための「ホラクラシー憲法」をフレームワークとして定義していることも特徴のひとつです。
フレームワークとは、問題解決・意思決定を行う際の、規則や概念、構造の集合を指します。
ホラクラシー組織とティール組織の違い
ホラクラシー組織と似た概念で「ティール組織」という考え方があります。
「ティール組織」は、一致した目標に対して、現場のメンバーが必要に応じて意思決定を行う組織です。現場に決定権を移譲したフラットな組織を構築する概念はホラクラシーと同じです。
ホラクラシーとの大きな違いは、ホラクラシーは「ホラクラシー憲法」というフレームワークが用意されており、このフレームワークをベースに組織の運営が行われます。一方で、ティール組織は、細かなフレームワークは定義されていません。
ティール型組織を実現する方法論のひとつにホラクラシーがあると考えることもできます。
ホラクラシー組織の起源や改変の歴史
「ホラクラシー」という概念は、2007年、アメリカ・ペンシルベニア州のソフトウェア企業、ターナリー・ソフトウェアの創業者ブライアン・ロバートソンが、従来型の会社組織とは全く異なる民主的でフラットな組織のあり方を模索する中で構想しました。
ホロクラシーの着想は、物理学や哲学の概念である「ホロン」に由来します。
ホロンとは、個のひとつ一つが「部分」であり「全体」であるという概念を指します。
このホロンを会社組織に見立て、個々人が役割を果たすことで、柔軟に活動できる組織を構想し「ホラクラシー憲法」というフレームワークをつくりあげました。
「ホラクラシー憲法」は2009年にv1.0が誕生し、自社の経験やクライアント企業との経験をフィードバックし、以降数年で、v2.0、v2.1、v3.0、v4.0、v5.0と短い期間でのアッデートを行い、オープンソースとしてGitHubを通じて全世界に向けて公開されています。
「ホラクラシー憲法」はアップデートを重ね、今も進化し続けています。
ホラクラシーが注目されている理由と導入メリットは?
ホラクラシーが注目される背景
企業の経営環境が急速に変化する中「経営層からの指示を待つ」「現場からの提案を経営層が決断を下すまで待つ」旧来型の組織では、他社に遅れを取ってしまいます
また、労働人口が減少し、人材獲得競争が激しくなるなかで現場の裁量権が少ない職場では「やりがい」を感じられず、優秀な人材は転職してしまう可能性もあります。
企業がイノベーションを起こし、持続的に成長していくための手段として、ホラクラシーを活用した優秀な人材が活躍できる魅力的な組織つくりが注目を集めています。
メリット1:意思決定の速度があがる
現場に裁量権を与えることで、上層部の決定を待つことなくスピーディーに意思決定が行われます。その結果、変化に対応できる柔軟な組織運営が可能です。
メリット2:社員の成長を促せる
現場に裁量権を与えることで、個々の社員が役割と責任を自覚できます。上からの指示を待つだけでなく、自ら責任を持って意思決定を行う自律的な社員が育てられます。
メリット3:社員のモチベーションが向上する
現場に裁量権を与えることで、社員は自分の能力を活かしたいと考え、やりがいを感じながら仕事に取り組むようになります。モチベーションの向上は生産性を高め、また、活躍できる仕組みを作ることで、優秀な人材の採用や、離職率の低下などの効果が期待できます。
ホラクラシー導入のデメリットは?
ホラクラシー組織には、従来のヒエラルキー型組織にはない大きなメリットがある反面、デメリットもあります。
したがって、導入にあたってはメリットだけでなくリスクやデメリットを考慮して、導入時の想定シミュレーションをしっかり行う必要があります。
デメリット1:統率の難しさ
ホラクラシーは、指示や管理をする管理職を置かない組織です。そのため、個々の社員は、目標・役割・責任を正しく理解し、自分をコントロールして業務を遂行する能力が求められます。
目標・役割・責任が組織として浸透できなかった場合は、個々のバラバラな意思決定に振り回されて組織があらぬ方向に進んでしまう可能性があります。
デメリット2:リスク管理の難しさ
現場が意思決定を行うには、情報がなければできません。ホラクラシーの組織運営には、全員が同じレベルの情報にアクセスできる必要があります。
これは、社内の機密情報をより多くの社員がアクセスできる状態を意味し、セキュリティリスクが高まります。
また、意思決定には高いコンプライアンス意識が求められます。意思決定者が増え、コンプライアンス意識にバラつきが生まれるリスクも想定されます。
人事責任者必見・ホラクラシー組織導入の基礎知識
では、ホラクラシー型の組織を作り上げるにはどうすればよいのでしょうか?ここでは「ホラクラシー憲法」に定められた「ホラクラシー組織」の核となる考え方や、人事労務が特に対応すべき事項に絞って解説します。
ホラクラシー組織の仕組みについて
ホラクラシー組織では、管理職は存在しない代わりに業務は「ロール」と呼ばれる役割単位で分割されます。
ロールには、各企業が運営する中で発生する様々な役割に割り当てられます。「採用活動」「給与管理」から「文房具発注」や「社内イベント企画」といったものまで様々なロールが考えらます。
これらのロールを社員の能力に応じて、社員同士が相談しながら割り当てていきます。
このとき、必ずしも割り当てられるのは1つだけではなく、2つ、3つと複数のロールが割り当てられることが一般的です。
そして、各社員には自分のロールの定義範囲内における業務であれば、従来型組織では上位職の承認を必要とするような戦略的判断を要する課題であっても、自ら意思決定を行える権限が付与されます。
一方、全体の組織運営は、ロールの集合体である「サークル」というチーム単位によって行われます。近いロールを持つ従業員同士がミーティングを重ね、情報共有を図ることで、より重要な意志決定や業務実績の確認、会社全体のミッションや目的との整合性を図っていきます。
このときサークルには「リーダー」が割り当てられますが、いわゆる従来型組織における「部長」「課長」といった固定的なポジションではなく、その「ロール」においての取りまとめ役・調整役といった位置づけとなります。
また、企業を取り巻く経営環境の変化によって、既存の「ロール」では対応しきれない領域の課題や問題が発生し、業務にあたる当事者があいまいになる状況が発生します。
ホラクラシーではこれを「ひずみ」と呼び、ひずみを解消するために新たな「ロール」が生み出され、近接する「ロール」に従事する従業員の中から、柔軟に割り当てられることになります。
ホラクラシー組織での給与決定プロセスとは?
従来のヒエラルキー型組織と違い、ホラクラシー組織においては、評価を行う上司がいません。給与は「人」につくのではなく「ロール」に紐付けられて決定され、社員全員に共有されます。
つまり、インセンティブや勤続年数・年功序列による特別給や能力給は一切付与せず、昇進・昇格もないため昇給制度も存在しません。その人に割り当てられたロールが変われば給与額もロールの重要性に応じてその都度変更されることになります。
ホラクラシー組織を実現する人材像とは?
権限は責任とセットです。ホラクラシー組織では、徹底して権限が分散されるため個々の社員にも権限に応じた責任が生まれます。
主体的にものごとを考え、決断し、その責任を負う覚悟で行動できる自律的な人材が適しています。
いわゆる指示待ち型や、責任を回避する傾向の人材は不適といえるでしょう。
ホラクラシー組織の導入と注意点
最後に、ホラクラシー組織の導入を推進するために抑えておきたいポイントを解説します。
1.まずは数人のチームに導入してみる
既存の会社経営に対する考え方と全く異質の概念となるので、いきなり全社全体で従来のピラミッド型組織を捨ててホラクラシー経営への全面移行は、リスクが高い行為です。
あまりにも劇的な変化が一度にもたらされると、拒否反応もまた大きなものとなり、社内が大混乱に陥る可能性があります。
実際、優良ベンチャー企業として世界的に有名なザッポス社でさえ、ホラクラシーを社内に一斉導入したときに、新たな組織形態を嫌った約20%弱の社員が同社を自主的に去ることになったほどです。したがって、まずは、数人のチームや小さな部署単位で始め、最適化しながら広げていく方法が良いでしょう。
2.情報共有の仕組みをつくる
ホラクラシーを実践する専門家や経営者が口を揃えて強調するのは、ホラクラシー経営が成立する最大の前提条件は「情報共有」です。
意思決定を行うには、管理職のみアクセスできた高位な情報に、メンバーが全員アクセスできる体制をつくる必要があります。
また、既存の上司が情報をまとめて、チームを最適化する「上下」の仕組みがなくなるため、メンバー間の「横」方向の情報共有の仕組みも必要になります。
各メンバーの進捗状況が可視化できるツールや、チャットツールなどを用いて、メンバー間の連携を強化しましょう。
人材を育てる覚悟が必要
上述した通り、ホラクラシー組織では、社員一人ひとりにより大きな権限を委譲し、社員はそれに比例した責任を果たす必要があります。
したがって、社員には、組織の目標を正しく理解し、高いコンプライアンス意識を持ち、自己管理能力が高め、自律的・能動的に物事を対処できる資質が求められます。
見合った外部人材の採用と合わせて、社内での「コンプライアンス研修」や「自立型人材育成研修」「ホラクラシーの概念を学ぶ研修」を通じて、ホラクラシー組織の運営に適した人材を育てていく覚悟が必要です。
ホラクラシー導入が向いている組織と向いていない組織
ホラクラシーは、いままでの組織を0からひっくり返す概念です。ホラクラシーを全社導入する場合は、既にヒエラルキー組織ができあがっている会社や、社員数の多い会社では、大きなコストとリスクが発生します。
つまり、対象の組織の人数が少ないほど導入しやすく、組織の人数が多いほど導入が困難になります。
また、社員の資質も要因になります。権限や責任を負うことを望まない社員が多い組織では、ホラクラシーは機能しないでしょう。
さらに、業務内容によっても向き不向きがあります。例えば、工場の現場など、正確にミスのない作業が求められ、意思決定のシーンが少ない現場では、効果を発揮しにくい傾向にあります。一方で、新規事業開発など、個人の裁量権が大きい業務では効果が期待できます。
ホラクラシー組織導入の事例
実際に、ホラクラシー組織、ホラクラシー経営を導入し、課題解決に取り組む企業を紹介します。
意思決定のスピードを向上させる
法人・個人向けの宅食サービスなどを提供する「株式会社OKAN」の経営層は、会社の成長にともない「部門間の分断」や「意思決定のスピ―ド」に課題を感じていました。
そこで、2018年に、ピラミッド型の組織から、階級のないフラットなホラクラシー組織へと改変を実行。CEOの下にチームを配置して、特定部署以外のリーダーを廃止し、現場の社員が意思決定をしていく仕組みを導入しました。
社員のモチベーション向上に
求人メディア「Green」などを手掛ける株式会社アトラエでは「意欲ある人がいきいきと働ける組織」を目指し、ストレスの一因になる「出世や役職」をとりはったフラットな組織作りを手掛けています。
定期的にコミュニケーションを強化するグループワークを行い、組織課題の共有や行動指針、企業文化の浸透をはかり、自走できる社員を育成しています。
「ホラクラシー」の導入にはビジョンが必要
- 経営・組織づくり 更新日:2023/10/24
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-