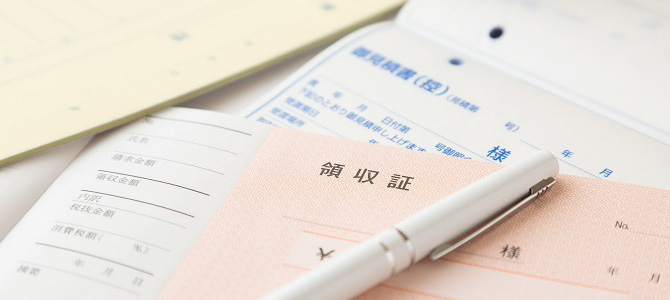「仕事は人間関係が9割」の著者が教える!5つのケースから学ぶ職種別・メンタルケアのコツ
みなさん、こんにちは。宮本 実果(みやもと みか)です。わたしは、産業カウンセラーとして2007年に開業し、10年間で6,000件以上のビジネスパーソンのパーソナルセッションと企業における社員研修の講師を実施してきました。
その中で痛感しているのは、企業による「社員のストレス対策」の重要性です。終身雇用制度や年功序列制度がなくなり、仕事の成果やキャリア形成を自分の力で切り拓かなければいけない現代人は、数多くのストレスと戦い続けています。
そのため、社員に高い満足度で働いてもらい、生産性を高め、定着率を上げるには、働きやすい環境や制度を企業側が整備する必要があるのです。
とはいえ、「ストレス対策といっても、何から始めたらいいかわからない」という方も多いかもしれません。そこで今回は、職種や役職ごとのストレス原因や、心を病んでいる兆候を見抜く方法、解決策までを徹底解説します。
CASE1. 営業職の場合
営業職のビジネスパーソンがストレスを感じる原因の多くは、期待されているほど成果を出せていない場合の「自責の念」と「上司からの叱咤(しった)」です。例を挙げましょう。20代の頃に飲食業界で全店舗№1の売り上げを記録し続け、スタッフやお客さまからの信頼も厚かったAさんという方がいました。前向きでチャレンジ精神旺盛なAさんは、30代に向けたキャリアアップで、畑違いの金融業界の営業職へ飛び込んだのです。
でも、その転職はあまりうまくいきませんでした。がむしゃらに頑張ってはみたものの、金融の専門知識のなさにつまずいてしまったのです。飲食店の店長時代に武器にしていた“元気と笑顔”だけではお客様からの信頼ももらえず、なかなか成果につながりませんでした。
このような日々が続く中で「自分のスキルが通用しないのは、周りが頑張りを認めてくれないからなのか?」と問題の本質から目を背けて自分を追い込んでしまいました。これが「自責の念」です。さらに、結果が出ないことによって日に日に「上司からの叱咤」が多くなり、ストレスに押しつぶされそうになってしまいました。
なぜこんなことが起きてしまったのでしょうか。その理由は、営業職に就いている方が「経験を活かしたキャリアアップ転職やヘッドハンティングによって、次々と報酬や労働条件が良いところへ移れること」にあります。
だからこそ、「自分は過去にも結果を出してきたし、コミュニケーションスキルも高いから信頼関係も築ける。次の職場でもきっと上手くいくはずだ」と信じこんでしまい、何かトラブルが起こっても“本質的な問題点”をみつめることができなくなってしまうのです。
また、営業職は個人それぞれに明確な数値目標がある場合がほとんどです。そのため、日常の業務態度よりも目標達成の度合いを評価軸にされることが多く、チームワークのスキルが少し低い面があります。そのため、課やチーム内での「成果の奪い合い」や「目標未達成者への叱責」が起こりやすいのです。
営業職の方へのアドバイス
営業職の方が他社や畑違いの業界に転職する場合、失敗する原因の多くが「準備不足・調査不足」です。より具体的に言えば、転職先の企業研究、業界研究が足りていないケースが多いのです。
営業職の方は「自分のコミュニケーションスキルさえあれば、転職先でもうまくやっていける」という考え方をしてしまう傾向にあります。ですが、仕事における信頼関係や成果は「専門的知識」と「コミュニケーションスキル」がセットになるからこそ実現できるものです。
まずは、「その職場で仕事をするにあたり必要な知識を持てているか」をもう1度チェックしてみてください。そのためには、社員を交えた営業のロープレなどが有効です。そして、足りていない知識があれば、身につけるための具体的な行動を考えてみましょう。
そうすれば、自責の念に押しつぶされることは少なくなり、結果的に上司の叱責も減ってくるはずです。
CASE2. 事務職の場合
事務職には営業職のように数値目標がなく「コミュニケーションスキル」「仕事に対するモチベーション」「業務改善」などが評価の基準となることが多いです。そのため、「評価に影響しないように、なるべく無難に過ごしたい」と考える方の割合が高いという特徴があります。人間関係のトラブルが起こったり、悪目立ちしたりすることを恐れる人も多いです。それゆえに、間違った判断で仕事をして失敗し、上司から責められた際に、恥ずかしさと悔しさで大きなストレスを抱えてしまいます。
ここで厄介なのが、「本人は業務改善のためにやったことでも、上司が理解してくれないケースがある」ことです。その場合には、上司の個人的な価値観で判断されることに理不尽さを感じ、ストレスがより大きくなってしまいます。つまり、事務職の大きなストレス原因は「成果軸が曖昧でわかりにくいこと」にあります。
成果軸が曖昧だと、こんなことも起こります。大手メーカー企業に勤める事務職のBさん(30代女性)は、正社員登用試験を控えた契約社員でした。自社に正社員登用制度ができたことを境に、今まで以上に積極的に仕事に取り組むようになりました。
「言われたことだけをやる」スタイルから、「業務改善を提案し、自ら積極的に他の社員の手助けをする」スタイルへ。仕事に対するモチベーションが各段に上がったのです。ですが、Bさんには課長に対して1つ不満がありました。
それは、自分だけ評価面談が実施されない事です。他の社員は年に2回程度の課長面談があり、頑張りを口頭で認めてもらったり、課題を伝えてもらえたりしました。だからこそ、どのようにキャリア形成をすればいいのかが明確になり、モチベーション維持にもつながっていたのです。
一方でBさんは、課長との面談の機会はなく、日常の会話でなんとなく話す程度。社員になるにはどんなことを準備すべきで、自分の積極的な姿勢がどう評価されているのか。全くわかりません。結局、不安な気持ちからストレスが溜まり、仕事へのモチベーションも低下してしまいました。
課長の立場からすると、「評価軸が不明瞭なため、面談をしてもBさんの業務を評価しづらい」と面談を軽視していたのかもしれません。ですが事務職は、評価面談の機会を失ってしまうと、目的意識が薄れてストレスが大きくなり、モチベーションが一気に下降する可能性も否めないのです。
事務職の方へのアドバイス
事務職の方は「自分のキャリアのゴールをどういったところに置くか?」を一度考えてみてください。いま勤めている会社で長く働くことでしょうか? それとも、どんどんキャリアアップしていくことでしょうか?
前者であれば、まずは焦らずに普段の業務をしっかりやってほしいです。先ほど述べたように事務職には数値目標がないため、自分のやるべき仕事をやり、社内のメンバーときちんとコミュニケーションを取っていれば、極端に評価が下がることはないからです。
後者であれば、自分がやっている努力がなかなか自社で評価されないのだとしたら、それは「将来のための投資」だと思ってください。言い換えれば「どの会社に移ってもやっていけるスキル」を身につけるための修業期間だと考えればいいのです。そして十分なスキルが身につけば、より良い会社に転職すればいい。
革新的なことに挑戦する事務職をなかなか評価してくれない会社も、なかにはあります。でも、ビジネス変化の激しい現代では、そういう会社はだんだんと淘汰されていくはずです。
だから、モチベーションの高い方は目線をもっと先に向けましょう。「自社の中で評価される事務職」ではなく「どこに行っても評価される事務職」を目指すのです。そうすれば、日常生活で感じるストレスはかなり軽減されると思います。
CASE3. エンジニアの場合
エンジニア職は一般的に「長時間労働が常態化している」と言われます。しかし、近年の傾向としては社内やプロジェクトでの労働時間やコスト管理が徹底されており、多忙な時期を除けば、休日や代休もほぼ予定通り取得できている方が多いように感じます。では、何がストレスの原因になっているのでしょうか。実は、エンジニアに多いのが職場内における人間関係・コミュニケーションの悩みです。
具体的にどのようなことが起こるのか、例を見てみます。あるIT企業で働くCさん(30代女性)は、女性が自立して長く働くためにと考え、新卒から3年間働いた会社を退職し、異業種転職でエンジニアの道を選びました。
気がつけば35歳。すでに10年のキャリアになっており、そろそろマネジメントの領域にも挑戦してみたいと考えていました。CさんのOJTスキルは部内でも評判が良く、丁寧でわかりやすい説明が若手社員からの圧倒的な信頼を得ていたのです。
でもあるとき、キャリア転職で同じプロジェクトに配属された男性が、自分を通り越してプロジェクトリーダーに抜擢されました。Cさんにとっては上司になります。一生懸命コミュニケーションをとり、仕事を円滑に進める努力をしました。
しかし、その男性上司はエンジニアとしてのスキルは高い一方でコミュニケーションスキルが低く、社内外ともにトラブルが目立つようになりました。また、それが原因でチームメンバーの残業が増え、プロジェクトの予算を圧迫する可能性が濃厚になってしまったのです。
そこで、Cさんはそのことを男性上司に伝え、自らが出来る事を実行しようとしたときに、なんと強く叱責されてしまいました。ただでさえ社歴が長くOJTの評価も高かった自分を置いて、その男性がプロジェクトリーダーになったわけですから、ストレスはピークに達し職場で泣いてしまったそうです。Cさんは会社からの評価に大きな不満を抱き、転職も考えたといいます。
エンジニアはプロジェクト単位で仕事をすることが多いため、常に多様なメンバーと適切なコミュニケーションをとる必要があります。相手に情報や意図を正しく伝えることや、トラブルを回避するためのホウ・レン・ソウがうまくできないと、あっという間にストレスフルな職場になってしまいます。
また他の職種に比べると、専門的な技術や知識を持った転職経験者も多いのも特徴。そのため、キャリア転職した側はそれなりのポジションで入社しますが、もともとその企業で働いていた社歴が長い社員にとっては、納得のいかないケースも多々あるのです。
エンジニアの方へのアドバイス
認識や価値観の相違が原因のトラブルを回避する有効な方法があります。「プロジェクトのゴールをメンバー全員が理解すること」です。
本来、プロジェクトメンバー同士のコミュニケーションというのは何かを達成するための“手段”です。そこには必ず“目的”があります。うまく連携が取れなくなっている組織は、誰かの言葉や行動をあげつらったり感情的に批判してしまったりと、本来の目的を見失っている状態なのです。
それを防ぐため、なるべくプロジェクト序盤の段階で「認識合わせ」に時間を割きましょう。そして、メンバー同士で達成すべきゴールを理解し、その目的から外れた議論をしないと約束します。
エンジニアは他の職種と比べると、口下手な方が多いです。それゆえに、コミュニケーションの齟齬がトラブル原因となってしまうのかもしれません。でも、目的を達成するために、必要な議論のみにフォーカスする「ビジネスコミュニケーション」を意識すれば、トラブルが起きることも少なくなるはずです。
CASE4. 人事・総務の場合
人事・総務職は、なにかと人間関係の板挟みになってストレスを抱えやすい職種です。たとえば、現場からは社員研修制度や評価制度への見直しを求められる一方、経営陣とも意見が対立してしまい、折り合いをつける方法に頭を悩ませるなんてことも数多くあります。また、人事労務の管理のみならず、採用や育成、人員配置なども重要な仕事。ですが、変化がめまぐるしく労働人口も減少している現代のビジネス環境では、優秀な人材の確保もますます難しくなっています。「自社の採用・育成スタイルで、本当に大丈夫なのだろうか?」と話す人事担当者にお会いする機会も、数多くあります。
たとえば、上場企業の人事担当者(50代男性)Dさん。彼は新たな人材獲得や人材育成の方法を模索するため、今までに行ったことのない異業種交流会やセミナーに参加する機会が増えたそうです。けれど、その背景にはDさんの“不安”が大きく影響していました。
なぜかというと、これまで企業の第一線で人事の仕事をしてきたにも関わらず「自分には他社で通用するスキルがなく、キャリアを活かせる仕事もない」と感じてしまったそう。それが原因で、夜もなかなか眠れない日が続き、体調を大きく崩してしまったのだといいます。
最近は、ミドルハイ世代でも自身のキャリア形成に悩んでいる方が多くなってきています。人事・総務職は人の市場価値について客観的な視点を持ち、さまざまな情報が入ってくるからこそ、不安になる気持ちも強いのかもしれません。
人事・総務の方へのアドバイス
「人」と関わる機会がとにかく多いのが人事・総務の仕事。だからこそ、さまざまな人のキャリアを客観視するうちに「自分はこのままキャリアを積んで大丈夫だろうか」と不安になってしまうケースは少なくありません。
でも、逆に考えてください。他の人を客観視できるということは、自分のことも客観視して「何のスキルを身につければいいか」を検討できるはずです。そうすれば、今持っている強みは何か、次に身につけるべきスキルは何かなど、やるべきことが見えてきます。そして行動に移せれば、将来についての漠然とした不安はかなり軽減されるはずです。
もしも本稿の読者が若手の人事・総務の方であれば、「自分はそれほど多くの人たちと会った経験や客観視した経験がないから、自分を客観視して分析することは難しい」と思ってしまうかもしれません。その場合は、ベテランの人事・総務の方と会う機会を設けることをおすすめします。
その方々の経験と知識に基づいたアドバイスを聞くことで、自分のキャリア形成について具体的なイメージを持ちやすくなるはずです。
CASE5. マネージャーの場合
マネージャー職には大きく分けて、自身もプレーヤーとして現場で活躍するプレイングマネージャー、マネジメントを専門とするマネージャーの2つがあります。そして、特に前者は強いストレスを受けやすいのです。プレイングマネージャーが大変なのは、自分もまだまだ発展途上にもかかわらず、成果を出しながら部下も育成し、バランスを取りながら仕事をする必要があるためです。専門的なスキルを持ち、仕事への意欲も高いマネージャーほど、強いストレスを感じやすいという傾向もあります。
たとえば、コンサルティング業界で働くEさん(40代男性)は、優秀な成果を出し続け、クライアント企業の担当者からも信頼されていました。あるとき、新たに契約が成立したクライアント企業へ、コミュニケーションスキルが高いと社内で評判の部下のコンサルタントを派遣させることになりました。
しかし、2か月のプロジェクト期間を終えようとしたとき、突如クライアント企業から呼び出されたのです。先方の担当者はかなり激怒しており、契約通りの金額を支払うことに躊躇しはじめました。
話を聞いてみると、どうも部下がビジネスシーンに不向きなコミュニケーションを取っていたようです。部下本人は、クライアント企業の担当者と仲良く楽しく仕事をしようと、良かれと思って数々の行動をしていました。けれど、それは先方の求めていたことではなかったのです。
一方で、専門知識は求められるレベルに達しており、プロジェクトを遂行する上では問題がなかったことも確認できました。本来であれば、専門のコンサルタントとしての業務は問題なく達成できたのですから、クライアントを説得し、契約内容は交渉すべきです。
しかしEさんは、怒鳴られたことで冷静さを失ってしまい、その場で平謝りし、契約金を下げることを約束してしまいました。また、普段は感情的にならない性格にもかかわらず、部下に対して怒鳴ってしまったそうです。マネージャーとしての立場で冷静に考えることができず、自らを強いストレスにさらしてしまいました。
なぜこのような事態になってしまったかというと、Eさんが大変優秀なコンサルタントだったことが背景にあります。優秀なプレーヤーは、つい「相手も、自分と同じレベルの仕事が当たり前のようにできる」と考えてしまうことがあるのです。ある意味、優秀“だからこそ”のジレンマかもしれません。
マネージャーの方へのアドバイス
ここでは、特にプレイングマネージャーの方を対象として解説します。同職についた方は、「自分が担っている『プレイヤー』と『マネージャー』という2種類の仕事は、“切り離して考えるべきもの”」という意識を持ってください。
プレイヤー(=成果を出すポジション)の頭で考えると、部下に高い期待をかけすぎてしまい、ミスを許せなくなります。「自分と同じことができるはず」という目線で見てしまうからです。そうではなく、マネジメント業務をする際にはマネージャー(=人や組織を育てるポジション)の頭で考える習慣をつけましょう。
そうすれば、「部下の失敗は、育成のためには必要なものだ」と冷静に考えられるはずです。2つの視点が混ざってしまうと、仕事における判断基準が不明瞭になってしまい、自分が保てなくなってしまいます。
心を病んでいる兆候を、しぐさや行動などから見抜く方法
ここからは、社員が心を病んでいる兆候を見抜く方法を解説します。まず前提として知っておいてほしいのが、ストレスには「快ストレス」と「不快ストレス」の2種類があること。今回解説してきたものは不快ストレスにあたり、病気の原因になる可能性が高いものです。
不快ストレスを受けると、心身にさまざまな影響があります。身体症状としては、肩こり、疲労感、頭痛、動悸、めまい、下痢、食欲不振、睡眠障害などです。ここから心身症へと発展し、消化器疾患や片頭痛、過敏性腸症候群の身体的な疾患へ発展してしまうこともあります。
また、強い不安感や、緊張、抑うつ、気力低下、意欲減退などが伴うことも。これらの症状が見られるようなら、その社員は何かしら強いストレスを抱えていると考えた方がいいでしょう。
加えて、このような状況が慢性化する前には前兆があります。「いつもできることができなくなる」ということです。具体的には、仕事上でのミスや作業能率の低下、事故頻発、アルコール依存などがよく起こります。
また、カウンセリングセッションの中で私が気をつけていることの1つに「クライアントが言っている言葉だけを判断材料にしない」ことがあります。なぜなら、辛い思いや苦しい思いをしていても、クライアントが正直に口に出さない場合もあるからです。
それでは何を判断材料にすべきか。ノンバーバルな(言葉によらない)サインです。たとえば、悲しい話をしているのに笑いながら話す、不自然に手を強く握りしめて話す、涙を流しながら話すなどの行動を見逃さないようにしてください。
こういった点をチェックできるように、周囲のメンバーや上司、人事担当者も普段から気をつけて観察しておくことが重要です。前兆の時点で早めの対応ができれば、大事に至らずに解決の糸口が見つかる可能性が高くなります。
無意識に「型にはめる言葉」を使わない
気をつけなくてはいけないのは、「うちの会社は○○だから」や「この仕事は△△だから」と無意識に発言してしまう周囲のメンバーや上司、教育担当者です。その言葉は「だから、□□すべきだ(してはいけない)」という圧力になってしまいます。新卒社員の教育のためだとしたらある程度は仕方ないとしても、中途のキャリア採用者に向かってこんな発言をしたら相手はどう思うでしょう。自分の存在や価値観をないがしろにされたように感じるはずです。
新しい風を吹かせるために新しい人材を採用しているのに、自社の風土や型にはめようとしては本末転倒です。非常にもったいないことをしていると気づかなくてはいけません。相手を「自分にとって取り扱いやすい人」にしようとすれば、大きなストレスが生まれ、的確なパフォーマンスが発揮できなくなってしまいます。
人事考課の“目的”を考える
本メディアが人事担当者向けということもあり、最後は人事考課(メンバーの業務への貢献度・業績などを一定の基準で査定し、それを人事に反映させること)に関するノウハウを書いておきたいと思います。そもそも、人事考課にはどんな目的や役割があるかご存知でしょうか? 大きくわけると2つあります。①従業員が割り当てられた仕事をどのような態度でどの程度遂行したかの実績 ②潜在能力、適性についての評価
人事担当者であれば、だれもが理解している内容です。しかし問題は、この2つを“適切にできていない”方が多いことです。
人事考課の目的や役割を正しく理解せず、昔からの慣習や個人の主観でなんとなく評価したり、評価結果をどう活かすのかが不明瞭だったりすると、公平性に欠けた人事考課になってしまう可能性が高くなります。また、単なる上司との人間関係に依存した評価軸になってしまう恐れもあるでしょう。
そうなってしまうと、「頑張ってもどのみち評価されない」「上司の機嫌を取らなければ意味がない」というフラストレーションにつながってしまいます。
本来、人事考課は、社員に対してフィードバックをすることで能力開発やキャリア開発に活かしてもらい、社員の成長による組織の活性化を目指すという重要な役割があります。だからこそ、人事担当者の方には、自社の人事考課が適切なものになっているかを今一度見直してほしいのです。
そうすることで、少しずつ社員が働きやすい環境になり、スキルの高い人材が育成でき、魅力ある人材を採用できる好循環が生まれるのではないでしょうか。それが社員の満足度と幸せにつながり、組織の成長に結びつくと、私は信じています。
- 労務・制度 更新日:2017/09/22
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-