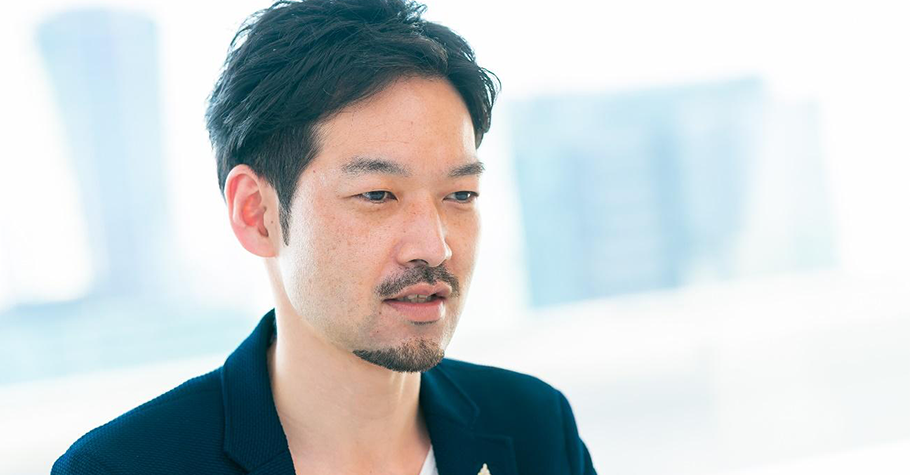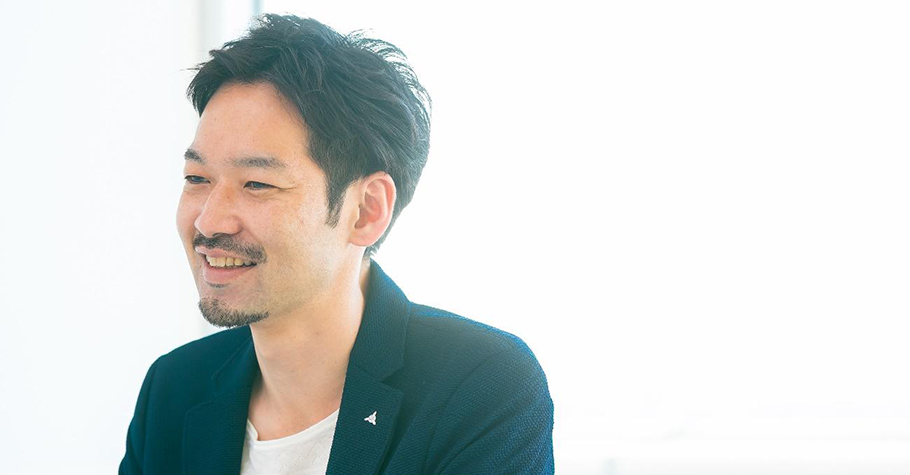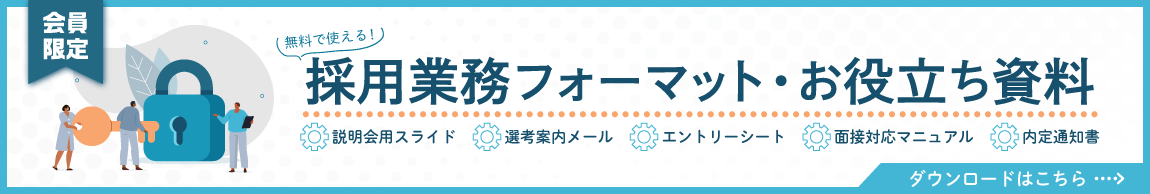採用SNSの始め方と運用のポイント【メディア別攻略BOOK付き】
SNSは今や個人のものだけではなくなり、企業にとっても重要なマーケティングツールのひとつとなっています。採用に関しても、学生からの認知を獲得したり、関係を築いたりといった目的で多くの企業が活用しています。
読者の皆さまの中にも、採用活動でのSNS活用を検討されている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、どのように始めたら良いのか、きちんと続けられるのか、リスクはないのか……気になることも多いかと思います。そこで今回の記事では、SNSを用いた採用支援に数多く携わっている、株式会社ライスカレーの山下涼介さんにお話を伺いました。
新卒採用とSNS。どう捉え、どう活用すべきなのでしょうか。
読者の皆さまの中にも、採用活動でのSNS活用を検討されている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、どのように始めたら良いのか、きちんと続けられるのか、リスクはないのか……気になることも多いかと思います。そこで今回の記事では、SNSを用いた採用支援に数多く携わっている、株式会社ライスカレーの山下涼介さんにお話を伺いました。
新卒採用とSNS。どう捉え、どう活用すべきなのでしょうか。
― とはいえ、企業はナビサイトに採用ホームページなど数多くの採用広報物を持っていますよね。これらの広報物とSNSは何が違うんでしょうか。
山下さん: どの採用広報手段も学生にとっては「企業理解を得る」という目的がありますが、「期待する情報が違う」と理解するといいと思います。
ナビ媒体は入り口として広く浅い情報を、採用ホームページではより深掘りした網羅的な企業理解を得ることができます。しかし、いずれも企業目線で公式色の強い情報として学生は受け取るはずです。
一方で、SNSはそもそもがユーザーファーストのプラットフォームです。そのため、学生も自分たちの目線に近い情報を期待しています。きれいにまとまったホームページやナビなどの情報だけでは知ることのできない、カジュアルでリアリティのある情報を伝えられる媒体だからこそ、SNSで企業理解が深まるんです。まずはこの特色の違いを理解していただくと良いと思います。
― SNSは採用広報において無視できないものということはよく分かりました。一方で、SNSを運用し始めるところから、運用中の目標設定、効果測定まで、その設計と社内への理解の浸透が難しいというお話もよく聞きます。
山下さん: そうだと思います。SNSを導入する際に最も大変なのは運用における適切な目的・目標の設定です。これは、はまってしまいがちな落とし穴なのですが、採用のためにSNSアカウントを立ち上げるとなると、まず頭に浮かぶ目標が「採用数」ではないでしょうか。しかし、これはSNSの目標設定としてはお勧めできません。
― その理由はなんでしょうか。
山下さん: まず、SNS経由での採用数を本当に計測できるのか?という問題があります。採用できた学生のほとんどは自社を志望していたわけですから、SNSを見てはいたでしょう。しかし、SNSが決め手ということはあまりないと思います。それは「ホームページを決め手に入社を決めた」や、「パンフレットが良かったので入社を決めた」という学生がいないのと同じです。
― ここからは、SNSの運用においてよくあるお悩みについて伺っていきたいと思います。まずは炎上について、学生の反応がダイレクトに返ってくるものだからこそ慎重になる企業も多いのではないでしょうか。
山下さん: 炎上が心配だというのは理解できますが、SNSを持っていなくても会社説明会や面接、各種広報ツールといったあらゆるコミュニケーションの場面には炎上のリスクが隠れています。なぜなら、学生がすでにSNSを使っているからです。失言を拡散されることもあるでしょうし、学生が「圧迫面接だ」と感じてそれをSNSに書けば炎上してしまうかもしれません。
SNSの炎上対策で最も重要なのは、事前の察知と素早い対処です。こうした炎上が起こった際に対処する窓口としても、むしろSNSは持っておいた方が安全という見方もできます。
― 関連して、発信内容に対する社内のチェックはどこまで入れるのが適切なのでしょうか。
山下さん: SNSは情報発信の頻度が高く、またそのスピードも速いので、細かい表現や誤字脱字などはある程度大味で見ておくくらいの方が良いと思いますが、自社として発言してはならない内容のチェックは丁寧にした方が良いですね。ある程度その判断ができる担当者に運用を任せたり、アドバイザーとして付いてもらうことも良いと思います。
― 冒頭に学生ファーストの媒体であることは伺いましたが、学生の視点というのはどのように拾っていくのが良いのでしょうか。
山下さん: 各コンテンツに対する反応をきちんと分析して、好まれる情報の傾向をつかんでおくということがまず大前提です。
その上で、アドバイスやネタが必要なこともあると思います。そういった場合は、学生に近い人に相談してみるのがいいですね。社内で言えば、新卒社員がそうです。
学生の目から見て、どういう情報が欲しいのか、どんなコミュニケーションが好ましく感じるのか……そんなことを聞くことから始めてみましょう。また、ユーザーにカジュアルに投げ掛けができるのもSNSのいいところです。アンケートを取ってみるのも良いでしょう。
― いまお話しいただいたようなハードルを乗り越えてSNSを運用し始めても、なかなかうまくいかない……という悩みもよく聞かれます。そういうお悩みにはどう答えていらっしゃいますか?
山下さん: まず知っていただきたいのが、SNSは最初のプランニングどおりの運用を続けて成果を上げるということの方が少ないくらい、難しい媒体です。
一方で、「トライアンドエラー」ができる媒体でもあり、さまざまな種類のコンテンツや表現を試し、最適解を探していくことができます。
いろいろと試行錯誤してもKPIに達しないのであれば、プランニングからやり直せばいいんです。せっかく始めたのであれば、「成果が上がらない」という理由でやめてしまうのはもったいない。どんどん試行錯誤して、当たるまで試せばいいと思います。
― 成功企業の事例ばかり目に付くので、すぐに成果が出ないと「もうやめよう」と判断してしまうこともありそうですね。
山下さん: そうですね。そもそも会社のイメージ自体が良かったり、有名だったりすると苦労せずにバズることがあります。そういう例を見て「自社でもああいうアカウントを作ろう」と考えても、普通は難しいですね。学生と向き合って、試行錯誤するしかないですよね。
山下さんのお話で特に印象的だったのは、「SNSはトライアンドエラーができるツールである」という言葉です。
少しうまく行かないとSNS運用に意味が見いだせなくなってしまいがちですが、本来SNSは「学生と最も近いコミュニケーションチャネル」。それは、言い換えれば学生に最も向き合えるメディアともいえるのではないでしょうか。
その意味で、細かい試行錯誤はSNSを育てる上でも重要ですが、自社の採用を強くしていく上でもきっと糧になるはずです。
ダウンロード資料では、より具体的なメディア別の特徴やアドバイスを掲載しています。こちらも併せて活用していただき、ぜひ採用SNSを通じて自社の採用力を高めていってください!
少しうまく行かないとSNS運用に意味が見いだせなくなってしまいがちですが、本来SNSは「学生と最も近いコミュニケーションチャネル」。それは、言い換えれば学生に最も向き合えるメディアともいえるのではないでしょうか。
その意味で、細かい試行錯誤はSNSを育てる上でも重要ですが、自社の採用を強くしていく上でもきっと糧になるはずです。
ダウンロード資料では、より具体的なメディア別の特徴やアドバイスを掲載しています。こちらも併せて活用していただき、ぜひ採用SNSを通じて自社の採用力を高めていってください!
- 人材採用・育成 更新日:2022/06/15
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-