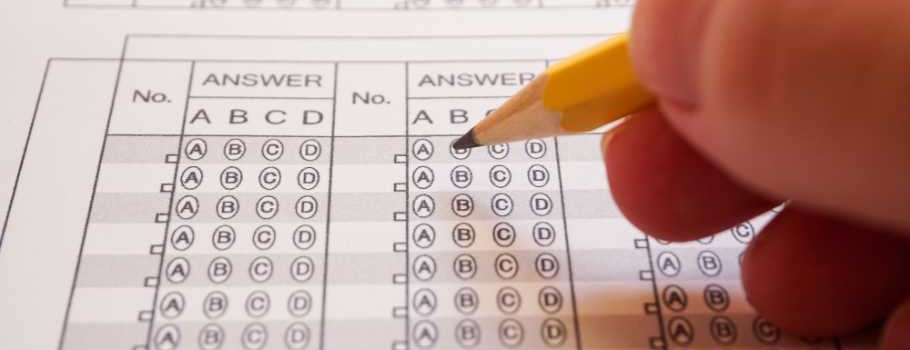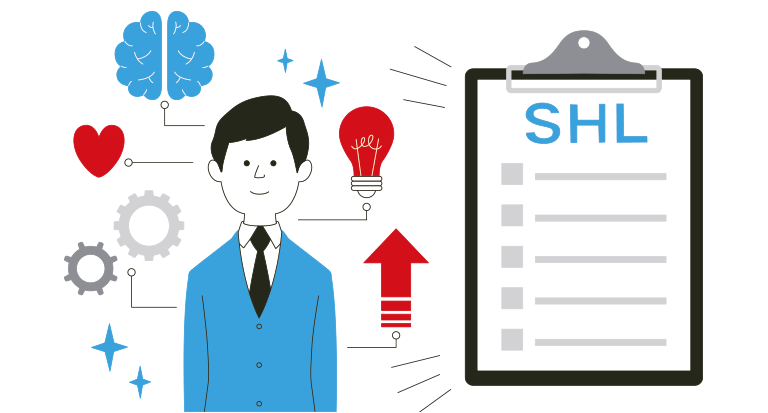採用過程に適性検査を導入するメリットと事前に押さえておきたい基礎知識
「能力テスト」「能力適性検査」とも言われるテストです。このテストでは、思考力や知識量を計測します。「言語テスト」と「非言語テスト」の設問に分けられ、基本的な学力を問う問題が出題されます。
言語テストは、国語の問題が中心となります。文章を読んで正しい意図を理解する質問や、文章の整合性を問う質問が出題されます。また、業務に英語が必須の企業では、英語の問題も出題される場合があります。非言語テストは、計算問題や、文章を読解して計算する文章題、図形を用いたパズルのような問題が出題されます。
応募者の多い企業の人事では、合否ラインの点数を設定して、基準点以下を自動的に不合格にする運用を行っているケースもあります。
「パーソナリティテスト」「性格テスト」とも言われるテストです。主に応募者の性格や人柄を見極めるテストです。パーソナリティテストには、行動を決定する特性(=コンピテンシー)をあぶりだす、コンピテンシー診断や、職場環境、人間関係における「ストレス要因」を探るストレス耐性テストなどもあります。診断結果をもとに、面接時の参考資料として活用できます。
適性検査のなかには、能力テストとパーソナリティテストを組み合わせ、単に応募者の選考基準とするだけでなく、職業適性やストレス耐性などを考えあわせて採用後の配置や育成に活かせるものもあります。
さらに、営業職向けのSAB、事務職向けのOAB、IT職向けのCABなど、専門職に特化したものや、多言語に対応しているテストもあります。
| 種類 | ペーパーテスト | WEBテスト | テストセンター | インハウスでの WEBテスト |
|---|---|---|---|---|
| 特徴 | 採用企業が用意した部屋、もしくは定められた会場で筆記試験を行う。 主に機械で採点ができるマークシート方式を採用。 |
応募者は、所定のWEBサイトにアクセスしてオンラインで適性検査に回答する。 自宅など試験を行うのに適切な場所を応募者が準備する。 応募者が用意したパソコンで適性検査を行う。 |
「テストセンター」と呼ばれる全国各地に設置された会場に応募者がおもむき検査を受ける。 マークシート形式による筆記や、WEBテスト形式などで行われる。 |
応募者は採用企業が指定した場所、例えば会議室などにおもむきWEBテストを受ける。 |
| 実施の準備 | ペーパーテストを行う会場の手配。 試験監督者の手配。 応募者に日時・会場の案内などを通知。 |
応募者にWEBテストでアクセスするURLやログイン方法、実施方法などの案内を通知。 | 応募者に日時・会場の案内などを通知。 | WEBテストを行う会場の手配。 WEBテストで用いるパソコンなどの環境の手配。 応募者に日時・会場の案内などを通知。 |
| 結果確認 方法 |
オンライン報告で行われる場合と、書面を送付する場合がある。 | 一般的にオンラインで試験後に速やかに結果を閲覧することが可能。 | 一般的にオンラインで試験後、速やかに結果を閲覧することが可能。 | 一般的にオンラインで試験後に速やかに結果を閲覧することが可能。 |
| メリット | 試験官を配置することで、不正行為を取り締ることができる。 | 場所や時間を問わずに実施するため、遠隔地に居住している応募者、海外在住の応募者も参加できる。 採用企業は、会場の手配などの工数も不要。 |
テストセンターのスタッフが、運営や管理を行うため、採用企業は会場の手配などの工数が不要。 不正行為を取り締ることができる。 |
試験官を配置することで、不正行為を取り締ることができる。 |
| デメリット | 会場の手配や試験官の手配など、採用企業に工数が発生する。 一旦、採点センターまで配送して採点するため、結果が出るまで、配送から3日程度の時間がかかる。 |
遠隔地で実施するため監視が難しく、替え玉受験や、複数人で知恵を集めて回答するような不正行為がある。 オンラインMTGの仕組みを利用して、本人確認と映像を監視しながら実施するなどの対策を行うことも可能。 |
実施には業務の委託費用が発生し、その分採用コストが上がる。 | WEBテストの遠隔地でもテストを受けられるメリットがなくなる。 会場の手配や試験官の手配など、採用企業に工数が発生する。 |
適性検査で得られるデータは、選考時の活躍できる人材の見極めや採用ミスマッチを防ぐ基準になるだけでなく、より成果を上げるための人材の配置や、人材の育成、採用活動の振り返りに有効活用できる必須のツールです。
最近では、WEBテストが普及し、遠隔地や外国にいる優秀な人材も採用候補として広がり、また、結果もすぐに分かるため、迅速かつ効率的に応募者を評価できる仕組みが整っています。
受験者数が年間100万人を超えるテストを実施している精度の高い適性検査SHLを活用すれば、
データを元にした人材評価や人材活用が実現し、人事・採用業務の効率化と企業の発展に大きく貢献するでしょう。
- 人材採用・育成 更新日:2023/08/10
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-