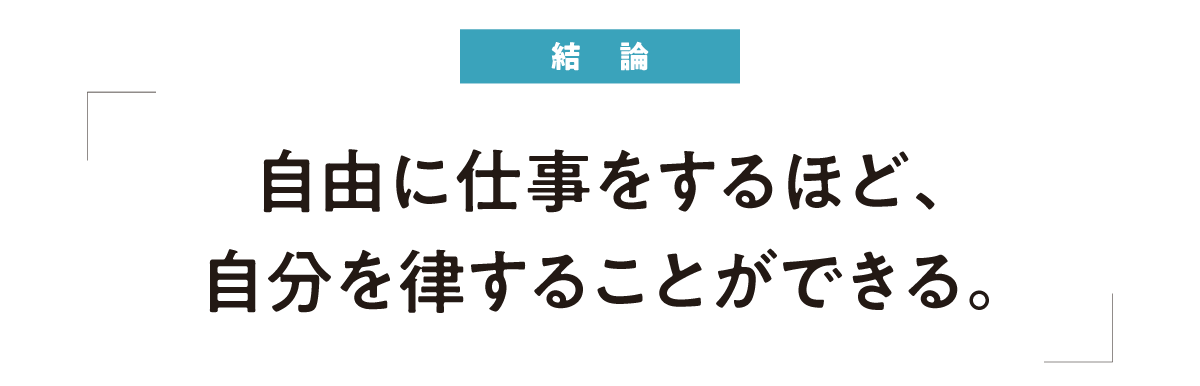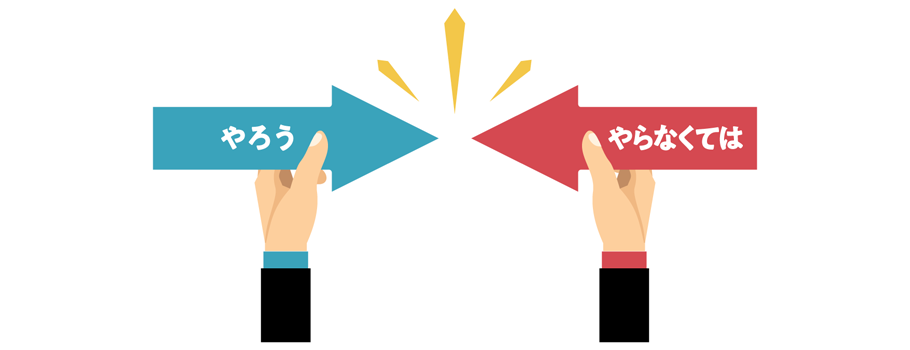自由に働くほど規律正しくなる——不思議な体験をした組織の話。
この記事では、2020年代以降の“あたらしい働き方”のヒントとして、この結論の背景や理由を、共有したいと思います。
働き方の自由度を上げて得たかったモノと得られたモノ
まず、今回の事例となる組織が、どんな課題を抱え、どう解決しようとしたのか、バックグラウンドからご紹介します。
得たかったモノ:採用力
率直にいえば、働き方の自由度を上げることにした理由は、“採用力”が欲しかったからです。
もちろん、既存従業員のモチベーションや満足度への寄与も、念頭においてはいました。
しかし、リアルな話をしてしまえば、「採用力を高める必要性」が、組織として強くありました。
その理由は、大企業に比べて、ネームバリューや安定性のアドバンテージがない、小さな会社だったからです。
当時、筆者が在籍していたのは、まだまだ駆け出しのベンチャー企業でした。小さな会社が採用力をつけるには、大企業が提供できない「価値」を創造する必要があります。
「毎日、15時30分からの出社でOKの会社を探している」
「どんな価値を創造するか?」は 、さまざまな選択肢があります。
その中で、「“自由に働ける”という価値を創造すること」を選択した背景として、特徴的なエピソードがありました。
採用面接にやってきたAさんが提示した、
「毎日、15時30分からの出社でOKの会社を探している」
という条件です。
「自由度を高めてアドバンテージをとる
Aさんは、非常に専門的かつ高度なスキルと輝かしいキャリアの持ち主でありながら、転職活動が難航していました。
その理由は、
「日本の株式市場の取引時間(9時〜15時)は、出社せずに、トレードしたい」
という希望を持っていたためです。
私たちの組織は、Aさんの条件を受け入れて、Aさんを採用しました。「働き方の自由度」によって、アドバンテージをとる戦略に出たのです。
得られたモノ:生産性
Aさんのような魅力的な人材に対する採用力を高めるために、自由な働き方を推進した結果、得られたモノは「生産性」です。
別の言い方をすると、 「採用力が強化されたのみならず、組織全体として、少ないコストで大きな売上を生み出せるようになる」 という果実を得ました。
※上記結果となった要因は、この記事の後半で詳しく考察します。
実際に行ったこと
「働き方の自由度を上げる」とは、具体的に何を行ったのかといえば、以下が挙げられます。
●勤務時間の柔軟化
もともとフレックスタイム制度を導入していたが、コアタイム(かならず勤務しなければならない時間帯)を廃止した。
●リモートワークの導入
打ち合わせや会議がないなど、出社する必然性がない日は、事前申請によって自宅勤務を可能とした。
●フリーアドレス
オフィス内に固定席を設けず、好きな場所で働けるようにした。
なお、注意点として、上記は全部署・全従業員に一括導入したものではありません。
業務上の都合により可能なチーム、および希望者からスモールスタートし、法的な整備も含めて、時間をかけて導入していきました。
自由に働くと生産性が高まるのはなぜ?3つのポイント
さて、続けて「なぜ、自由に働くと生産性が高まったのか」、その要因について、考察していきます。
実際に、部下やほかのメンバーたちと接するなかで気づいたポイントは、次の3つです。
- その1:「やらなくては」が消えると「やろう」が現れた
- その2:個人最適化が進んだ
- その3:ルールコストが削減された
その1:「やらなくては」が消えると「やろう」が現れた
1つめとして挙げたいのが、「やらなくては」が消えると「やろう」が現れる、という現象です。
自由度が低い環境で働くことは、
「○○をやらなくてはいけない」
「○○をやらされている」
「○○すべきである」
など、Must(マスト)の縛りを強く受けます。
「Mustを取っ払ってしまったら、規律が乱れて、めちゃくちゃになってしまうのではないか」という恐れは、杞憂でした。
Mustを取っ払うと、抑えつけられていた「自律性」が飛び出して、水を得た魚のように泳ぎだした印象があったのです。
その2:個人最適化が進んだ
2つめのポイントは「個人最適化」です。
全従業員に共通の一定ルールが、それぞれの従業員の最大パフォーマンスを引き出す機会を、阻害していた事実に気づきました。
たとえば、受験生の頃、勉強スタイルは人それぞれだったはずです。
- 朝型
- 夜型
- 音のない図書館
- ほど良い雑音のあるカフェ
- お気に入りの音楽
- 深夜ラジオ
- その他
同じように、多くの従業員が、
「自分にとってのベスト・スタイル」
を追求することで、個人成績を向上させていきました。
自由度を高めることは、
「自律性を持って、ベストを追求することが、許される」
と同義だったのです。
その3:ルールコストが削減された
3つめは「ルールコストが削減された」ことです。筆者個人的には、この恩恵を最も大きく受けました。
従業員をコントロールするためのルールは、じつは、非常に高コストなのです。
どんなコストがかかるのでしょうか。たとえば、以下が挙げられます。
- ルールを策定し、運用するための労力的なコスト
- ルールに合わせて部下を管理し、適切な指導をする時間的なコスト
- 公平なルール遵守やペナルティ管理のツールを導入する金銭的なコスト
- ルールを守らない同僚を見て、イライラする精神的なコスト
- ルールを守れない自分に対して、罪悪感を覚える精神的なコスト
当時、筆者のチームには、「どうしても出社時間を守れない、天才肌の部下」がいて、マネジメントに悩んでいました。 本人の個性として、努力だけではどうしようもない面があることに気づきつつ、責任者として、ルール違反を見逃すわけにはいかない重圧があったからです。
朝、彼女のいないデスクを見るたびに、憂うつな気分になっていたことを思い出します。 ルールでコントロールするのをやめて救われたのは、部下よりも筆者のほうだったかもしれません。
「自由」を組織に取り入れるヒント
「これから、自社でも、自由に働くカルチャーを創っていきたい」 というとき、どんなふうに取り入れていくとよいのでしょうか。
最後に、実践のヒントをお伝えします。
些細に見える“小さな自由”の大きなパワー
「自由に働く」と掲げると、大きな組織改革が必要なイメージがありますが、実際には“ほんの小さな自由”にも、大きなパワーが秘められています。
「1つしかなかった選択肢が、2つに増える」だけでも、大きな変化です。
たとえば、以下が挙げられます。
- 出社時間を「9時から」または「10時から」のどちらか選べる
- デスクチェアの種類を選べる
- 公平なルール遵守やペナルティ管理のツールを導入する金銭的なコスト
- 支給パソコンの機種を選べる
- フィスの席配置を選べる
すべての企業が、同じレベルで、従業員に選択肢を提供できるわけではありません。「自社にとって、可能な範囲」から、選択肢を提供する姿勢が、とても重要です。
たとえ「こんなちっぽけなこと」と感じるような、些細な自由であっても、“自分で選べること”が、従業員の自律性にポジティブな影響を与えてくれるからです。
自由な働き方も含めて自由に選択してもらう
経営陣が「自由」の企業イメージを強化したいばかりに、無理やり自由化を進めてしまう例もあります。
しかし、自由も押し売りすれば、Must(マスト)の縛りに変化してしまうでしょう。
おすすめしたいのは、自由な働き方を含めて、選択制にすることです。
自由化による組織の混乱を抑制しつつ、「今までの働き方を変えたくない」というニーズにも応えることができます。
さいごに
本記事では「自由に働く」をテーマに、筆者の体験談をお届けしました。
記事中に登場した“15時半出社希望のAさん”は、すばらしいパフォーマンスで企業成長に貢献したあと、現在では専業投資家の道を歩んでいます。 投資が大好きで、専業投資家になることが夢だったそうです。
“時間を守れない天才肌の部下”は、時間を守る必要がなくなると、思う存分、仕事に集中できるようになり、文字通り時間を忘れて、没入していきました。 結果、イノベーティブな製品を開発して、多くの顧客に幸せな価値を届けています。
私たちは、自由に働き、どこへたどり着きたいのでしょうか。その先を見据える目こそ、自分を律する原動力であると思います。
- 経営・組織づくり 更新日:2023/04/18
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-