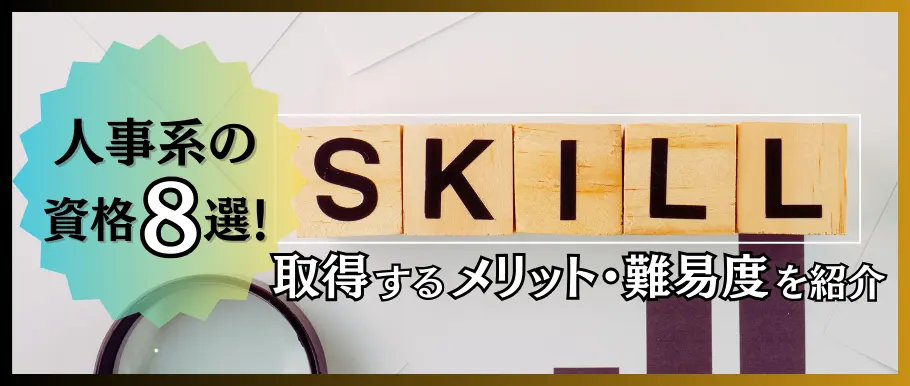人事系の資格8選!取得するメリット・難易度を紹介
人事担当者として、資格の取得は、仕事の幅を広げ、キャリアップの大きな武器となります。そして、勉強の過程で実務に役立つ広範な知識を身につけることができます。
この記事では、人事系資格を取得するメリット、人事担当者に必要なスキル、対人折衝スキル向上に役立つ資格・検定、労務知識の向上に役立つ資格・検定、人事総務系で取得しやすい資格・検定を紹介します。
採用課題を解決!「圧倒的な工数削減をしながら成果を出す10のポイント」
<人気資料・最新版> こちらから無料でダウンロードできます
専属スタッフが採用までフォロー。初期費用0円「マイナビ転職 Booster」の資料を受け取る
人事系資格を取得するメリット
人事担当者に必要なスキルを紹介します。資格や検定で得た知識は、この必要なスキルを高めることに貢献します。
対人折衝の能力
会社は、従業員にとって、自己実現の場や生活の糧を得る重要な場所です。そして、人事は、その従業員をマネジメントする重要な役割を担っています。
従業員をマネジメントするためには、観察眼や、従業員の心のケア、自主性を引き出すコーチングスキルも必要です。
従業員、一人ひとりと向き合い、適切なコミュニケーションを取っていく能力は人事担当者の必須スキルになります。
労務知識
人事担当者の実務は、行政手続きも多く、憲法や労働基準法などの各種法令と密接に関わっています。特に労働者の権利は、法律で強く守られており、理解をしていないと、知らない間に違法行為を犯してしまうリスクがあります。
対人折衝スキル向上に役立つ資格・検定
人事担当者の必須スキルである対人折衝能力。その能力を強化する資格・検定を紹介します。
キャリアコンサルタント
特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会が所管し、2016年より国家資格となった新しい資格です。
労働者の職業選択・能力開発に関する相談・助言を行う専門職です。学科と実技試験があり、5年毎に更新が必要な資格です。
人事担当者がこの知識を身につけることで、従業員にキャリアに関する適切なアドバイスを行うことができます。
合格率: 64.0%(2021年 キャリアコンサルティング協議会(CCC)受験者)
受験資格
- 厚生労働大臣が認定する講習の課程を修了した者。
- 労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力開発及び向上のいずれかに関する相談に関し3年以上の経験を有する者。
- 技能検定キャリアコンサルティング職種の学科試験又は実技試験に合格した者。
- 上記の項目と同等以上の能力を有する者
2の「3年以上の経験」とは、以下のいずれも適合するかどうかという考え方を基準に、個別に判断することになります。
- キャリアコンサルティングによる支援対象者が、「労働者」であること。なお、ここでいう労働者とは、現在就業している方のみならず、現在仕事を探している求職者(ハローワーク等の職業紹介機関に求職の申込みを行っている方、学卒就職希望者等)を含みます。
- 相談の内容・目的が職業の選択、職業生活設計又は職業能力開発及び向上に関するものであること。
- キャリアコンサルティングが一対一で行われるもの、又はこれに準ずるもの(少人数(概ね6名以内)グループワークの運営等)であること(情報提供に止まるもの、授業・訓練の運営そのもの等は含みません)。
試験の免除
技能検定キャリアコンサルティング職種の1級又は2級の学科試験、実技試験をそれぞれに合格した者については、キャリアコンサルタント試験の学科試験、実技試験のそれぞれに合格した者とみなします。
詳細な受験資格(※1)は、ホームページをご確認ください。
キャリアコンサルタントについて、詳しくは以下の記事もお読みください。
関連記事:キャリアコンサルタントとは|人事、採用担当者に向けて資格取得のメリットなどを解説
メンタルヘルス・マネジメント検定
メンタルヘルス・マネジメント検定は、大阪商工会議所が所管する民間の資格です。
厚生労働省策定の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を参考に作られた、職場環境でのストレスによる、心の病などを対策するための知識を検定します。また、職場での役割ごとに3タイプの試験に分けられています。
Ⅰ種(マスターコース):経営層や人事の管理職などを対象とした、社内のメンタルヘルス対策を立案、促進する知識。
Ⅱ種(ラインケアコース):部署の管理職としてのメンタルヘルスの知識。
Ⅲ種(セルフケアコース):自分自身でメンタルヘルス対策ができるようになるための知識。
職場の従業員のメンタルケアは、重要度を増しています。知識を習得することでコミュニケーションスキルの向上に役立つでしょう。
受験資格
制限なし
合格率(2021年31回実績)
Ⅰ種(マスターコース):19.8%
Ⅱ種(ラインケアコース):46.4%
Ⅲ種(セルフケアコース):71.2%
詳しくは、以下の記事もお読みください。
関連記事:国内最大規模のドラッグストアが取り組む 従業員視点のメンタルヘルスケア
産業カウンセラー試験
産業カウンセラーは、一般社団法人日本産業カウンセラー協会が所管する民間の資格です。
職場での人間関係の悩みやメンタルヘルスのケア、キャリア開発支援の知識を問う試験です。
「傾聴力」を重視し、従業員に寄り添うコミュニケーションスキルを身につけることができます。
合格率: 62.7%(2020年度実績)
受験資格
受験資格1または2または3のいずれかに該当している場合に受験できます。
●受験資格1
協会が行う産業カウンセリングの学識及び技能を修得するための講座を修了した者。
●受験資格2
1)大学院研究科において心理学又は心理学隣接諸科学、人間科学、人間関係学のいずれかの名称を冠する専攻(課程)の修了者であって、A群からG群(注1)までの科目において、1科目を2単位以内として10科目以上、20単位以上を取得していることを要する。ただし、D群からG群の科目による取得単位は6単位以内とする。
2)社会人として週3日以上の職業経験を通算3年以上有し、大学院研究科において心理学又は心理学隣接諸科学、人間科学、人間関係学のいずれかの名称を冠する専攻(課程)の修了者であって、第3条第4号に定めるA群からG群(※1)までの科目において、1科目を2単位以内として4科目以上、8単位以上を取得していることを要する。ただし、D群からG群の科目による取得単位は2単位以内とする。本号に記載の職業経験とは、雇用形態を問わずすべての職業経験をいう。
●受験資格3
4年制大学学部の卒業者であって、公認心理師法に関する協会が指定する所定の単位を取得した者。ただし、当該大学が公認心理師コースを開始した年度以降に履修した単位に限る。
詳細な受験資格(※2)は、ホームページをご確認ください。
科目群について
A群:産業カウンセリング、カウンセリング、臨床心理学、心理療法各論(精神分析・行動療法など)などの科目群
B群:カウンセリング演習 カウンセリング実習などの科目群
C群:人格心理学、心理アセスメント法などの科目群
D群:キャリア・カウンセリング、キャリア概論などの科目群
E群:産業心理学、産業・組織心理学、グループダイナミックス、人間関係論などの科目群
F群:労働法令の科目群
G群:精神医学、精神保健、精神衛生、心身医学、ストレス学、職場のメンタルヘルスなどの科目群
コーチング検定
コーチングとは、相手との対話の中で、質問や助言をしながら、自発的に答えを見つけ、行動を促す人材育成法です。答えを教えるのではなく、相手が自分で考えて答えを導き出すようにする。自発的な行動を促す所がポイントになります。
ビジネスシーンでは、従業員のモチベーションを引き出すコミュニケーションスキルとして広く活用されています。
コーチング検定は、このコーチングを学ぶ検定になります。
また、民間資格となり、複数の団体が独自の検定を設けています。
労務知識の向上に役立つ資格・検定
学習を通じて、労務に関する知識を身につけることのできる資格・検定を紹介します。
人事総務検定
人事総務検定は、一般社団法人人事総務スキルアップ検定協会が所管する民間の検定です。人事・労務管理・年金などの総合的な知識、実務能力を体系的に学ぶことができます。
1から3級までのランクがあり、1級は課長レベル、2級は主任レベル、3級は担当者レベル相当を対象とし、2級・3級は、特別認定講習を修了することでも取得でき、比較的取得しやすい資格と言えます。
受験資格
1級の受験者は2級に、2級の受験者は3級に合格しており、かつ人事総務スキルアップ検定協会への登録中であること、3級は制限なし。
ビジネス・キャリア検定
ビジネス・キャリア検定とは、中央職業能力開発協会が所管する公的な検定です。厚生労働省が定める「職業能力評価基準」に準拠し、試験は8分野43の試験から、自分の職種を選択し受験します。
「人事・人材開発・労務管理」は、1から3級までの3つのランクに分けられ、1級は実務経験10年以上、2級は実務経験5年以上、3級は実務経験3年以上のスキルをイメージしています。
受験資格
制限なし
合格率(令和3年度前期実績)
1級人事・人材開発・労務管理 10%
2級人事・人材開発 65%
3級人事・人材開発 60%
2級労務管理 41%
3級労務管理 51%
衛生管理者免許試験
衛生管理者免許試験は、公益財団法人 安全衛生技術試験協会が所管し、労働安全衛生法を基にした国家資格です。
従業員の労働環境の管理や労働者の健康管理、労働災害の防止などを学びます。
また、労働安全衛生法により、常時50人以上の従業員がいる事業者は衛生管理者を1人以上置くことが義務付けられています。
事業者側の需要もあり、取得しておくと、転職時に有利に働く場合や、資格手当などを得られる場合があります。
合格率(令和2年度実績)
第一種衛生管理者 43.8%
第二種衛生管理者 52.8%
受験資格
大学、短期大学を卒業していること
- 学校教育法による大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの。ただし、上記には、専修学校、高等専門学校以外の各種専門学校、各種学校は含まれません。
- 大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者又は専門職大学前期課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの。
- 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
- 専修学校の専門課程(2年以上・1700時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に限る)などで、その後大学等において大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
その他にも、受験資格が設定されています。詳細な受験資格(※3)は、ホームページをご確認ください。
社会保険労務士試験
社会保険労務士は、全国社会保険労務士会連合会が所管し、社会保険労務士法を基にした国家資格です。
労務管理や社会保険に関するエキスパートと言え、この資格を取得すれば、人事・労務管理、社会保険、年金、雇用保険などの各書類の作成や提出、就業規則などの公的書類作成、労使間のトラブルの相談など幅広い業務を行うことができます。
受験資格は厳しく制限され、学歴や実務経験、そして、社会保険労務士以外の厚生労働大臣が認めた国家資格を所有していることが条件と成っています。また、試験科目も8科目と多く、出題範囲も広いため、合格率も例年一桁台の取得難度の高い資格といえます。
合格率:6.4%
受験資格
「学歴」、「実務経験」、「国家資格の所有」この3つのうち、いずれか1つを満たしていること。
●学歴による受験資格
学校教育法による大学、短期大学、専門職大学、専門職短期大学若しくは高等専門学校(5年制)を卒業した者又は専門職大学の前期課程を修了した者。
●実務経験による受験資格
労働社会保険法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く)又は従業員として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者。
●国家資格の所有による受験資格
社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者。
その他にも受験資格が設定されています。詳細な受験資格(※4)は、ホームページをご確認ください。
人事総務系で取得しやすい資格・検定
受験資格の制限のある検定や資格もあり、また条件によっても異なりますが、合格率を基にした難易度を紹介します。
コミュニケーションスキル系 資格・検定の難易度
| 資格・検定名 | 種別 | 合格率 |
| メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅲ種 | 民間検定 | 71.2% |
| キャリアコンサルタント | 国家資格 | 64.0% |
| 産業カウンセラー試験 | 民間検定 | 62.7% |
| メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 | 民間検定 | 46.4% |
| メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅰ種 | 民間検定 | 19.8% |
労務知識系 資格・検定の難易度
| 資格・検定名 | 種別 | 合格率 |
| ビジネス・キャリア検定 2級人事・人材開発 | 公的検定 | 65.0% |
| ビジネス・キャリア検定 3級人事・人材開発 | 公的検定 | 60.0% |
| 第ニ種衛生管理者 | 国家資格 | 52.8% |
| ビジネス・キャリア検定 3級労務管理 | 公的検定 | 51.0% |
| 第一種衛生管理者 | 国家資格 | 43.8% |
| ビジネス・キャリア検定 2級労務管理 | 公的検定 | 41.0% |
| ビジネス・キャリア検定 1級 | 公的検定 | 10.0% |
| 社会保険労務士試験 | 国家資格 | 6.4% |
上記以外に、民間検定の人事総務検定2級、3級は、特別認定講習を修了することでも取得でき、比較的取得しやすい資格と言えます。
人事担当は、「ヒト」の人生を扱う重要な業務です。コミュニケーションのスキルや法的な知識は必ず必要になります。合格することも大事ですが、資格や検定へのチャレンジは、体系的な知識を学ぶ良い機会です。積極的にチャレンジすることをおすすめします。
- 労務・制度 更新日:2022/11/17
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-