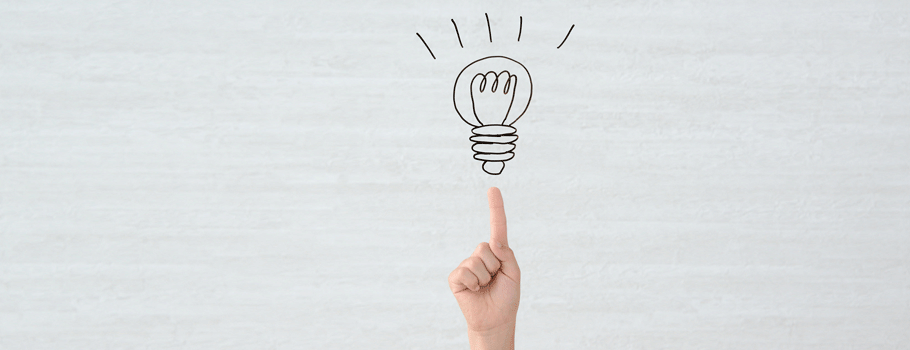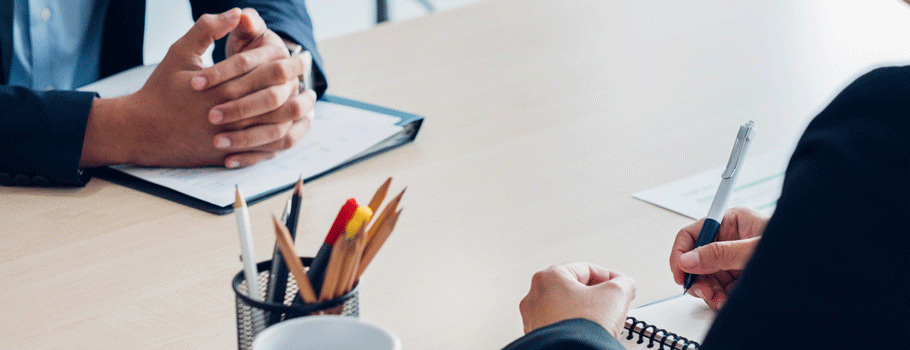人材獲得競争に勝つための7つのテーマ
十分な人数の採用ができないときや、適切な人材を見つけるのに苦労している場合、次の2つの可能性があると著者は指摘します。
- あなたが採用したい人たちが、あなたの組織の存在を知らない
- あなたが採用したい人たちは、あなたの組織についてよく知っているが、意識的に選んでいない
組織のなかにいると、誰もが自分の組織についてよく知っていると勘違いしてしまうことがあります。しかし実際には、組織の名前が新聞やオンライン広告、または採用サイトなどに頻繁に出てこなければ、ほとんどの人はその組織の存在に気づきません。もし求職者が組織の存在に気づかなければ、その人たちが採用試験を受けることはあり得ません。
次に、組織の存在に気づいている求職者が、あえてその組織で働くことを希望していない可能性があります。これは前者よりも大きな問題です。採用を決めたのに断られてしまうのであれば、その理由を候補者に聞くことが必要です。優秀な人材は、なぜ同じような仕事をしている競合他社に行ってしまうのでしょうか? それを考えなければなりません。
「UNABLE」と「UNWILLING」
本書では、問題の原因を「UNABLE(できない)」と「UNWILLING(望まない)」という2つの言葉を使って分析します。それぞれの言葉の定義は次のとおりです。
UNABLE(できない)
目標を達成するための物理的、または精神的な能力が足りていない。この場合、タスクを完了させるためには追加のリソースが必要となります。リソースとは、訓練やツール、技術的な知識などを指します。
UNWILLING(望まない)
タスクを完了させる能力も精神力もあるが、モチベーションに欠けている。タスクの重要性を理解していなかったり、タスクに反発を持っていたりすると、このような状態になります。
例えば求職者が組織について知らないのはUNABLEといえます。一方、求職者が組織を知っているのに、就職を望まないのはUNWILLINGです。採用活動がうまくいかない理由は、リソース不足のせいでしょうか? それともモチベーション不足のせいでしょうか? まずそこを見極めてから次のステップに進みます。
採用活動を農耕スタイルから狩猟スタイルに変える
いま抱えている問題の原因がUNABLEかUNWILLINGかを明確にすることとともに、著者は「狩猟スタイル」の採用活動をする人事部に変えることを提案します。広告を出し応募者が集まるのを待っていてはいけません。もっと積極的に候補者にアプローチできるようにします。次の章からは、その方法が解説されています。
2. セールスマインドを持った人事部をつくる
積極的な採用活動をするために、セールスマインドを持った人事部をつくります。
- 候補者に伝えたいメッセージを決める
- ターゲットを明確にする
- 全ての職種に手本となる人材像をつくる
- 組織内の全ての役職を4つに分類する表をつくる
1. 候補者に伝えたいメッセージを決める
どこの企業でも自社の製品やサービスを多くの人にアピールし、顧客を獲得するためのメッセージ作りに時間をかけます。同じような努力が人事部にも必要です。次のようなことを考慮しながら、才能のある人材に組織を売り込むためのメッセージをつくります。
- 誰に向けてアピールしたいか
- どのような人に組織に入ってほしいか
- 組織がどのような歴史や背景を持っているか
- どのような教育や経験がある人に来てほしいか
- 前職でどのような仕事をしていた人に来てほしいか
2. ターゲットを明確にする
優れたメッセージができても、「どのような人を採用したいのか」を採用担当者が認識できていないとメッセージが無駄になります。ターゲットを明確にし、その人にアピールすることが大切です。
3. 全ての職種に手本となる人材像をつくる
ビジネスで成功したい人は、すでに成功した人からアドバイスを聞いたり、フィードバックを受けたりします。職場でも同じです。手本になる人がいれば、経験の少ない人はアドバイスを受けることができるようになります。
また、理想の人物像がはっきりしていれば、それを目指すことができるでしょう。人事部は、それぞれの職種で成功するために必要な技能や性格の特徴などをリストアップし、その分野で優れた業績を持つ従業員に確認をしてもらいながら理想の人物像をつくります。
4. 組織内の全ての役職を4つに分類する表をつくる
組織のなかには、役割や責任が異なるとてもたくさんの役職があるため、適材を振り分けることに時間がかかりすぎてしまいます。そこで組織内の全ての仕事を4つの作業領域に割り当て、4種類の従業員のプロファイルを作ります。採用活動や人材配置を考えるときに4つのプロファイルに合う性格の候補者を当てはめていけば煩雑さが減るでしょう。
- 主に人と接する仕事。直接人とコミュニケーションする(例:スーパーバイザー、チームリーダー)
- 主に製造や工程に関する仕事。直接人とコミュニケーションする(例:メンテナンス、技術者など)
- 主に人と接する仕事。テクノロジーを通してコミュニケーションする(例:カスタマーサービス)
- 主に製造や工程に関する仕事。テクノロジーを通してコミュニケーションする(例:ITサポート)
3. 従業員にリクルーターになってもらう
従業員の知り合いを紹介してもらうことが、速く、安く、簡単に組織に合った人材を探す方法であることは理にかなっています。問題は、従業員が組織を他の人に勧めたいと思っていない場合です。
もし従業員が友人に自分の所属する組織を「勧めたくない」と思っているなら、組織内になにか問題があると考えるべきです。そして、その問題を修正しなければなりません。
- 雇用主としての評判を確認する
- 給与が上げられないなら、ほかの魅力を打ち出す
- ワークライフバランスの大切さ
- 柔軟性はどの世代にもアピールできる
雇用主としての評判を確認する
雇用主としての評判を知るために、現在働いている人や、これから退職する人を対象にした面接をしても意味がありません。なぜなら、ほとんどの人が本音を話さないからです。それよりもすでに退職して、ほかの企業で働いている人のフィードバックが参考になるでしょう。
また、著者の経験では約20%の人が退職後に元の企業へ戻りたい気持ちがあるといいます。退職した人に企業の問題点を聞くことで、再雇用のチャンスになるかもしれません。
給与が上げられないなら、ほかの魅力を打ち出す
多くの組織が、「業界内での給与が低いせいで採用が上手くいかない」と思っていますが、必ずしもそうではありません。給与そのものよりは、通勤時間や転勤の有無など、毎日の生活に直接かかわる要因によって、人は働く場所を決めます。給与が上げられないのであれば、勤務地や時間の柔軟性、休暇の多さといった別の魅力を打ち出しましょう。
ワークライフバランスの大切さ
新しい仕事を始めるときには先のことはあまり考えていません。しかし家庭を持ったり、年を重ねたりすると「この仕事を続けていけるか?」と考えるようになります。そこで企業が個人の生活を大切にする文化を持っていることや、ワークライフバランスを提供できることが大切になります。
柔軟性はどの世代にもアピールできる
ジョブシェアリング、在宅勤務、無給で休暇を延長するなど、柔軟性は様々な形式で考えられます。組織にとってどのような柔軟性を取り入れることが従業員のためになるか考えます。組織の柔軟性は若い世代だけでなく年配の従業員にも利益があります。
4. 面接でソフトスキルに焦点を当てる
何人面接しても適切な人が採用できなかったり、採用した人がすぐ辞めてしまったりする場合には、2つの可能性があります。適切な人材が応募していないか、適切な人材を落としてしまっているかです。そしてほとんどの場合、後者です。
医療やエンジニアリングなど経験を重視するべき職種もあります。しかし、ほとんどの職種ではその人のテクニカルスキルよりも、時間に正確であることや、頼まれなくても問題解決に向けて動けること、リーダーシップ、顧客に愛されることなどのほうが重要ではないでしょうか。
そこで著者は、技能よりも面接で次のようなソフトスキルを重視するよう提案します。
- コミュニケーション
- 創造性
- イニシアチブ
- 問題解決能力
- チームワーク、リーダーシップ
面接で、上記のようなソフトスキルを持った人材かどうかを見極めるためには、候補者にこれらのソフトスキルに関する失敗談を聞くといいでしょう。誠実な人材は、自分の失敗と失敗から学んだことを話すのが得意です。そのような人でも失敗について話すときには赤面するかもしれません。しかし、そこから学んだことを話せるかどうかがポイントです。
著者の経験では、利己的で誠実でない人は、失敗のことだけを話したり、失敗を人のせいにしたりします。もしくは、自分の失敗を正直に話しません。そのような人は選ばないほうがいいでしょう。
面接で見る3つのポイント
上記のソフトスキルに加え、著者は次の3つのポイントを確認することが面接の主な目的であるといいます。
- 候補者は、本当にそのポジションで働きたいと思っているか
- 候補者と企業がお互いに適しているか
- 候補者が言っていることを信用できるか
「やっと採用した人がすぐに会社を辞めてしまう」という問題がある場合には、この3つのポイントが面接のなかで確認できているか見直してください。
5. 優れた才能を引きつけ、定着させる
人材が不足していると、採用活動に集中してしまいがちですが、採用した人が辞めないようにしなければバケツの底に穴が開いているようなものです。著者は退職につながる3つの理由とその対策を挙げています。
- 適材適所ができていない
- 直属の上司やスーパーバイザーからの悪影響
- 組織の中で将来のビジョンが描けない
適材適所ができていない
自分に向いていない仕事を任されてしまうと、満足な結果が出ず、やる気がなくなり退職につながります。性格診断や適性診断を用いて採用前にその仕事に向いているかどうかを確認することで、この問題を防ぐことができます。
直属の上司やスーパーバイザーからの悪影響
直接かかわる上司と上手くいかないことが退職の原因になります。リーダーの役割となる人全員に、リーダーシップトレーニングを受講させることで、上司と部下が円滑にコミュニケーションできるようにします。
組織の中で将来のビジョンが描けない
組織の中で活躍する将来の自分の姿が思い描けることが大切です。従業員が自分でリサーチをし、自分に合った将来の目標を決め、自分がそのポジションに最適であることを組織に証明する機会が持てるようにします。人事部は、組織内部におけるキャリア形成の道筋を示したキャリアマップを作りましょう。
6. SMEを育成する
SMEとは、Subject Matter Expertの略で、日本では内容領域専門家と呼ばれます。SMEは、特定の領域の情報に優れ、専門知識を豊富に持っている「特定分野の専門家」です。その知識をほかのメンバーに教えたり、仕事が正しい方向に進んでいるかをチェックしたりする役割をします。組織内にSMEを置くことで、以下のように様々なメリットがあります。
- 分析的な問題解決ができる
- カウンセリング力が高くなる(アクティブリスニングができる)
- グループワークが円滑に進む(グループファシリテーションができる)
- 無駄のない生産管理で時間とお金を節約できる(リーン生産方式の実現)
- 意見の相違の根本的な原因を見つけてWin-Winの関係にできる(紛争解決能力がつく)
SMEの育て方
組織のなかでSMEを育てる手順を追ってみましょう。
- SMEが必要と思われる領域をリストアップする
- その分野で優れた成果を出している素行のよい従業員を候補生に選ぶ
- 入社3年目以上の候補者に「プログラムに参加したいか」を尋ねトレーニングを開始 企業が必要とする専門分野のリストを候補者に見せ、どの分野を勉強するか選択させる
- 週に4時間、各自が選択したトピックについて学習時間に充てる (GoogleやYouTubeなど無料のオンラインソースのなかにも役立つものがある)
- 6か月以上勉強したら、学んだトピックについて上司やスーパーバイザーに教えることによってSMEのステイタスを証明する(聞き役のスーパーバイザーは、トピックについて質問しながら候補者の能力をポジティブに試す十分な知識がある人)
- マネージャーが満足できるレベルになったら、毎週または毎月SMEが部門の会議を開催し、トピックの概要を説明したり、組織内の全ての人にトピックの基本を教えたりする
- SMEのプログラムを修了した者にボーナス支給や時給アップなどを約束する報奨制度を用意し、モチベーションを上げる
7. 次世代のリーダーを育てる
組織の将来的な成功は、従業員の将来を計画するのではなく、従業員が自分で思い描いた道に進めるようなツールを提供できるかどうかにかかっています。従業員が将来どのような役割で活躍したいかというキャリアマップの作成を手伝い、その達成をサポートします。
キャリアマップを作る前に、まずは従業員が自分について知ることから始めます。
- オンラインリサーチで自分の性格タイプについて調べる
- 今まで仕事で達成できたことを5つ挙げ、そこから自分のスキルを知る
- 自分の持っているスキルや性格をもとに、将来の仕事で、どのようなことに責任を持ち、どのような問題に取り組みたいかを考える
リサーチ段階
従業員が組織のなかの職種や役職について調べ、自分のスキルに合ったものをリスト化します。本人が挙げたリストについて人事やマネージャーが事実と証拠を基に承認します。
確信段階
本人が次の進路を決め、上司や人事も納得している段階。従業員が目標とする職種に就いている人と直接会って話せる機会をつくり、その進路が本当に希望するものか確認します。その後、マネージャーと本人が面接をして、本当にそのゴールでいいか再確認をしましょう。
ギャップの分析
キャリアマップの最終段階。目標とする職種や役職につくには、技能の不足を解消することが必要です。それを見いだします。
ここで著者が指摘するのは、多くの場合、不足している技能を補うことを「したくない」のではなく、組織のなかでそれが「できない」場合が多いことです。誰でも自分の望みを叶えるためには、一生懸命になります。その熱心さを組織の成長に生かすためには、従業員が望みを叶えるために不足している技能を補うことができるシステム作りが大切です。
人材獲得競争に勝つには、まず人材を失わないこと
- 人材採用・育成 更新日:2022/02/09
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-