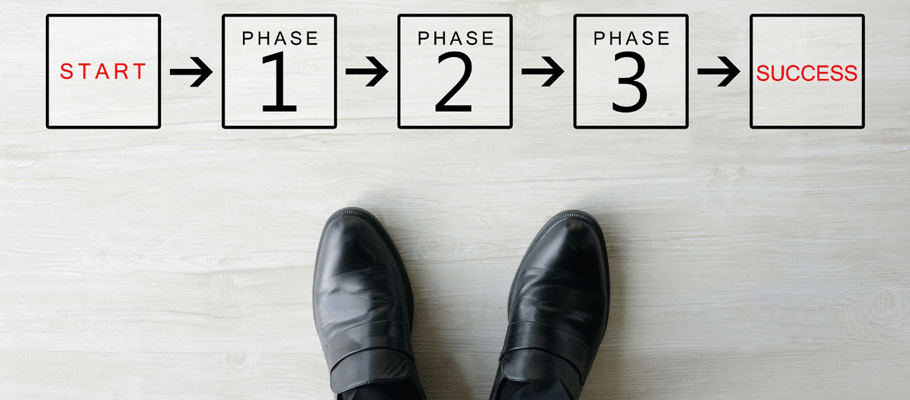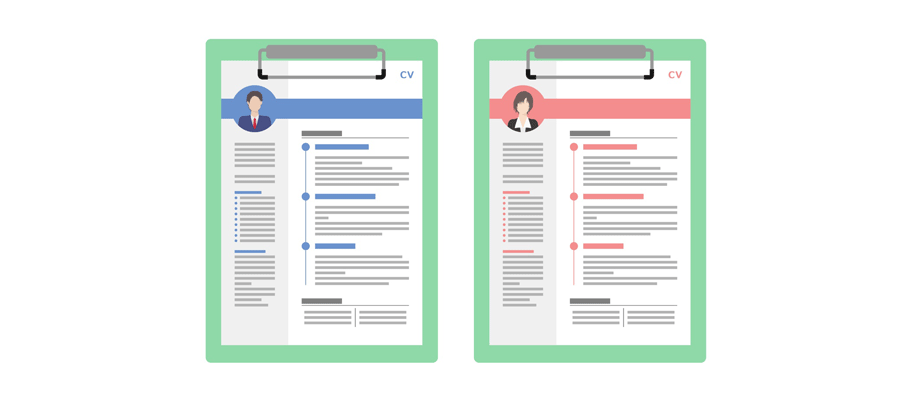ジョブディスクリプションとは?スペシャリストの雇用や育成に役立つ方法を解説
ジョブディスクリプション(job description)とは、職務内容を詳細に記述した文章です。主に欧米での人材採用や人事評価に用いられている一般的な手法で、従来、日本で用いられてきた職務経歴書とは概念が異なるものです。
日本でも、同一労働同一賃金が適用され、職務内容に応じた制度運用が求められるなか、 ジョブディスクリプションに注目が集まっています。
ジョブディスクリプションとは
ジョブディスクリプションを日本語にすると「職務記述書」となります。ジョブディスクリプションには自分が担当する業務内容やそれに伴うスキルなどの他にも、役割や求められる実績や行動、さらには期待される成果が記載されています。
ジョブディスクリプションの目的
ジョブディスクリプションの目的は大きく分けて2つあります。
1つ目は、従業員の業務内容を明確にし、従業員が自身に求められるスキルや業務範囲を理解できるようにすることです。どの業務を誰がやるのか、自分が関わる業務の範囲はどこまでなのかということを従業員自身が十分に理解し、従業員同士の認識のずれを解消することも可能です。
その結果、コミュニケーションの問題や業務の押し付け合いが減り、生産性向上も見込めるほか、ミスマッチによる早期離職を防ぐことにもつながります。
2つ目は、人事評価を適切に行うことです。ジョブディスクリプションには業務の目標や必要とされるスキル・技術といった人事評価に欠かせない内容が記載されています。
この項目が曖昧になっていると「自分はこんなに頑張っているのに評価されない」といった不満が出てくることも多々あります。ジョブディスクリプションを人事評価に導入することで従業員の評価への不満が減り、モチベーションアップにもつながります。
ジョブディスクリプション(職務記述書)と職務経歴
前述の通り、ジョブディスクリプションと職務経歴書は全く異なるものです。
職務経歴書は、「経歴」と記載されているように、求職者が「どのような経歴を歩んできて、どのような経験を積んだ人物であるか? その経験によりいかなる業務で貢献できるのか?」などの人物像を企業に伝えるために、求職者本人が作成し企業に提出します。
一方で、ジョブディスクリプションは、企業が「職務」の内容を詳細に記述したする文章です。人物の経歴ではなく、純粋にその仕事の内容や範囲を記載するもので、求人を出す際に企業側が定義し、作成します。
ジョブディスクリプションの活用場面
ジョブディスクリプションの活用場面は大きく分けて2つあります。
1つ目は採用時の活用です。一般的な求人票は業務内容や賃金、勤務地などの記載にとどまりますが、ジョブディスクリプションにはより詳細な業務内容やその範囲・目的などが明確に記載されているため、募集要項と併せてジョブディスクリプションも提示することで、求職者が具体的なイメージを描くことができます。
前述の通り、ジョブ型雇用が一般的な欧米では、採用時に企業側がジョブディスクリプションを提示することが一般的です。日本では新卒一括採用によるメンバーシップ型雇用が長らく一般的であったため、ジョブ型雇用へ移行する際にはジョブディスクリプションを活用した採用方法が効果的であると言えます。
2つ目は人事評価の基準としての活用です。ジョブディスクリプションには各ポジションで求められるスキルを明確に記載します。そのため、ジョブディスクリプションを人事評価に用いることで、評価基準が明確になり、客観的な評価をすることができます。
「ジョブ型雇用」と「メンバーシップ型雇用」
ジョブディスクリプションは、ジョブ型雇用で用いられます。ここでは、「ジョブ型雇用」と「メンバーシップ型雇用」について解説します。
ジョブ型雇用とは
欧米で採用されている職務を中心とした雇用制度です。詳細な職務内容や範囲を定義し、その職務を希望し、その能力を持つ人材を雇用します。つまり、その職務のスペシャリストを求める雇用形態です。これを「ジョブ型雇用」と呼び、ジョブディスクリプションを中心とした人事制度を運用しています。
メンバーシップ型雇用とは
日本の採用制度は、新卒採用を中心として、「人物」を採用し、その人物に適した職務を会社側が当てはめていく方法を採っています。入社後はジョブローテーションにより、さまざまな「職務」を担当し、あらゆる職務をこなせる、ゼネラリストを育成していきます。これを「メンバーシップ型雇用」と呼びます。雇用の際は、職務の能力ではなく、人物像をはかる職務経歴書を中心に判断を行います。
日本でジョブディスクリプションが採用されなかった理由
前述の通り、日本では独特の新卒採用、終身雇用、年功序列をベースとしたゼネラリスト育成の需要が高く、専門性を評価する「ジョブ型雇用」とそのツールである「ジョブディスクリプション」は、人事の評価軸として適していませんでした。
しかし、日本の高度経済成長を支えた年功序列の人事制度も、時代の変化やグローバル化による競争激化の中、変化が求められています。
今、ジョブディスクリプションが注目される背景
同一労働同一賃金の実施
日本では、2021年4月より、「同一労働同一賃金」が導入されました。これは職務内容が同じであれば、同じ賃金を従業員に支払うことです。つまり、「職務」(仕事内容)に応じて、賃金を支払う「職務給」の考え方で、ジョブ型雇用の概念です。
グローバル人材の獲得
企業のグローバル化により、外国人の従業員が増加していくなか、優秀な人材を確保するために、欧米で主流となっているジョブディスクリプションを中心とした人事採用制度が必要とされています。欧米では従業員を雇用する際には企業側がジョブディスクリプションを提示することが当たり前になっており、グローバル人材を獲得するためには欧米を基準とした採用活動を行う必要があります。
スペシャリストの獲得
日本の企業も年功序列から成果主義へと変化し、新卒から定年までゼネラリストを育てる終身雇用から、中途採用でのスペシャリスト起用に変化しています。若くても、その職務に応じた高額な賃金支払が可能なジョブ型を軸とした制度は、スペシャリストの中途人材確保に有利に働きます。
リモートワークの拡大
新型コロナウイルス感染症の拡大により、多くの企業がリモートワークへの対応を余儀なくされました。リモートワークでは従業員の勤務状態が管理しにくく、対面での指導や評価などがしにくいという課題があります。しかしジョブディスクリプションで従業員の業務範囲や評価基準を定義すると、リモートワークでのマネジメントに適しています。
また、育児や介護と仕事の両立などのダイバーシティへの対応という面でも、勤務時間や勤務形態をあらかじめ定義できるジョブディスクリプションがあることで対応がスムーズになります。
このように時代背景との相性が良いことも、ジョブディスクリプションに注目が集まっている背景といえます。
ジョブディスクリプション導入のメリット
専門人材の雇用と育成
職務に応じた高い報酬設定など、高度な専門性を持つ人材の採用確保や、優秀な外国人人材の確保に有利に働きます。また、社内でも、特定業務を専門的に行うことでスペシャリストを育成できます。
ミスマッチの解消
従来の人事異動は、会社の意図するジョブローテーションのために、全く異なる職務への着任も行われてきました。本人が望まない職務に着任することへの離職やパフォーマンス低下のリスクを減らすことができます。
また、中途採用でも、ジョブディスクリプションに記載されている職務内容、報酬、必要スキルが合うか合わないかで判断できるため、雇用後のミスマッチを解消できます。
業務効率化による生産性向上
ジョブディスクリプションでは、従業員の職務、責任、範囲を明確に定めます。専門外の業務が発生しない分、その専門分野に集中することで、業務効率が改善し、生産性向上につながります。
評価の公平性が保てる
ジョブディスクリプションでは、職務内容と同時に、成果とそれに応じた報酬が明確に定められています。定義されている目標が「できた」、「できなかった」それだけで判断できるため、評価における主観を排除し、客観的な評価ができるようになります。
ジョブディスクリプション導入のデメリット
人事異動がしにくい
専門職として契約した場合、会社都合での異動がしにくい問題があります。 もしも、その部署が解散して、職務事態がなくなってしまった場合の問題もあります。
社内の組織力に影響
日本の企業は、ジョブローテーションでさまざまな部署の人たちと仕事を経験することで社内のネットワークを広げて仕事を円滑に進める土台をつくります。部署異動のないスペシャリストは、強力な社内ネットワークをつくりにくい課題があります。
ゼネラリストの育成がしにくい
ジョブローテーションにより、さまざまな部署を経験することで、社の状況や各部の問題を把握し、全社的な視点で社業を進めるゼネラリストや幹部を育てにくい環境になります。
業務の空白が発生する可能性
ジョブディスクリプションでは、明確に職務内容と範囲が定義されています。従業員はそれだけで評価がおこなわれます。逆に「定義されていない職務は範囲外」になり、曖昧な職務が発生した場合、誰も手をつけずに放置される可能性があります。 この事態を防ぐためにも、職務内容や範囲は細かく記載し、制度設計に織り込む必要があります。
ジョブディスクリプションの導入フロー
人事制度設計の見直し
「職務給」「職能給」などの給与、評価制度を再確認する必要があります。まず、中途採用や管理職などの一部の従業員向けに制度を構築し運用し、課題を洗い出していく方法が堅実です。
幹部と対象職務の定義を定める
会社として対象職務に求めるゴールや内容、責任範囲を、社の幹部、人事、当該部門長を中心に調整し、認識を合わせましょう。
現場の調査
対象職務についての、趣旨と目的を明示し、職務内容を現場からヒアリングし、洗い出します。なるべく多くの従業員にヒアリングが必要です。その際、職務の空白が生まれないように、細かい職務まで、細分化して情報を整理しリストを作成します。
職務の分析
人事、部門長を中心に、従業員から集めた現場の情報を集め精査をし、会社が求めることと現場の情報と差異がある場合は、ここで、調整をしておく必要があります。特に達成すべき目標に関しては合意が必要です。
ジョブディスクリプションの作成
分析した情報を元に、人事担当が中心になり、文章を作成していきます。A4サイズ1枚にまとめるのが目安です。最後に、現場の職務と差異が発生しないように、部門長に確認をしましょう。
導入における注意点
日本では、新卒一括採用を軸としたメンバーシップ型採用が一般的です。新卒採用は基本的にはポテンシャル採用であるため、ジョブディスクリプションを活用した採用にはあまり向いていないと言えます。
また、ジョブ型の雇用時にジョブディスクリプションを活用する際にも、前述の通り曖昧な業務が数多く存在すると業務の空白が生まれる可能性があります。そのため、定期的にジョブディスクリプションの改定を行うことで業務の空白を埋める必要があります。
ジョブディスクリプションに記載する項目と具体的な記載例
ジョブディスクリプションに記載する項目のテンプレート例
以下は、ジョブディスクリプションに記載する。一般的な項目です。この項目を基本として、自社の環境を織り込んで調整し、ジョブディスクリプションを完成させましょう。
●部署・職種・役職
会社が定める部署、職種、職務等級、役職名を記載します。
●詳細な職務内容・範囲
担当職務を細分化し、具体的に記載します。また、職務の責任範囲を明示し、各職務の比重を設定します。
●期待される役割
期待される役割や目標設定を行います。
●評価方法・目標
評価のミスマッチを防ぐために、目標の達成度合いに対する評価方法。基準を事前に明示します。達成度合いが明確な、定量的な目標設定が理想です。
●給与、報酬などの条件
職務に対する報酬や、目標達成時のインセンティブなど、具体的な数値を記載します。
●職務に必要なスキルや経験
職務を遂行するために必要な経験や、スキル、資格を明示します。
ジョブディスクリプションの具体的な記載例
| 部署 | 営業部 |
| 職種 | 営業職 |
| 職務等級 | 3等級 |
| 職務内容・範囲 |
|
| 職務の比重 | 上記、7:2:1の職務比重とする。 |
| 期待される役割 |
|
| 評価方法 |
|
| 給与・報酬 |
給与は等級にあわせて決定する。その他条件は、雇用契約書に準ずる。 上記に加え予算達成120%以上の場合は、30万円を追加報酬とする。 |
| 職務に必要なスキル・知識 |
|
ジョブディスクリプションの導入企業例
2020年より日立製作所や富士通などの大企業がジョブ型人事制度の導入・拡大を発表し、話題になりました。2022年に経団連が行ったアンケート調査によると、大企業の採用手法は新卒一括採用から中途採用、通年採用、職種別採用、またジョブ型採用へと多様化が進んでいることが分かります。また、新卒採用におけるジョブ型採用が、過去5年間では3.8%なのに対し、今後5年で18.8%に増えるという結果も出ているなど、採用の現場ではジョブ型採用の重要度が上がっています。
この傾向はますます加速することが予想されます。ジョブディスクリプションの導入は、グローバル人材・優秀なスペシャリストの獲得や、業務効率化など、企業側に多くのメリットをもたらします。一方で、運用にはゼネラリストの育成や、職務の空白が生まれないように配慮する必要があり、自社の状況にあわせて、独自の「ジョブディスクリプション」を構築する必要があるといえます。
- 人材採用・育成 更新日:2022/01/13
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-