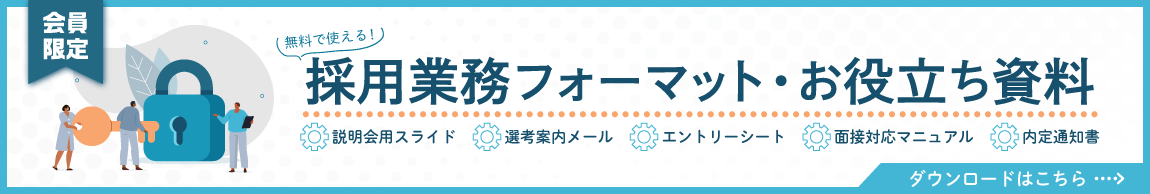採用難易度の高い「首都圏学生」を獲得するために必要なのは「理念」と「スピード感」
白水:
大きく分けて2つです。1つは首都圏に優秀な大学が集中しているため、相対的に学生のレベルが高いこと。もう1つが日本の中心部でもまれ、洗練された感覚を持った学生が欲しいという地方企業の事情です。
― 2つ目の理由についてもう少し伺ってもよろしいでしょうか。
白水: はい。首都圏にある大企業と違い、地方企業は地元からの採用がほとんどということが多いんです。なので、人材の多様性を保ちたいという思いから首都圏学生を欲しがるパターンがありますね。 その面では特に、生まれ育った街を一度出て、新しい環境でのチャレンジをしたいUターンやJターンの学生を希望する企業は多いです。― なるほど。確かにそのチャレンジ精神は評価の対象になりそうですね。
白水: はい、そうですね。特にUターン学生は地元のことも知っているので就職後の定着率も高く、IターンやJターンと比較しても需要が高い傾向にあります。― では、そんなUターンを含めた首都圏学生を獲得する施策として有効なのはどのようなものなのでしょうか?
白水: まず大前提として、採用のオンライン化によって地方企業の採用戦略は非常に多様化し、特に首都圏をはじめとした遠隔地の学生獲得はかなり有利になりました。オンラインでのインターンシップや企業説明会により、学生側にとっても企業側にとっても経費や物理的な負荷が相当削減されましたね。入り口はオンラインを活用することですが、次の手としてお勧めするのはリクルーターの活用です。首都圏の支社に在籍しているOB・OGをリクルーターに起用して、ある程度の権限を持たせて現地で初期の採用活動を任せてしまうのも一つの方法と考えます。
― リクルーター活用のメリットはどのようなものでしょうか?
白水: 私の担当している熊本エリアをはじめとして、一般的に地方では首都圏エリアと比較して学生の動き出しが遅い傾向があります。なので、画一的なスケジュールで動いていると優秀な学生を取り逃してしまうという事情があります。学生の動き出しが早い首都圏での採用活動と地元での採用活動を分けて2ライン用意する必要があるんです。 その時、本社の指示を待たずにある程度の権限を持って動くことのできるリクルーターに先に動き始めてもらうことが大切ですね。
OB・OG訪問の対応はもちろん、地方にある本社からは細かな対応がしにくい訪問、面談後のフォローアップも含めてやってもらいましょう。
― 若手の社員を起用することになると思いますが、思い切った権限移譲が難しいと感じる場合もあるのではないでしょうか。
白水: 確かにそうですね。ただ、実際に効果が出ている事例もあります。ある金融系の企業では、毎年、首都圏学生からの内定承諾率が低いことに悩んでいましたが、リクルーターに思い切った権限を与えて初期の採用活動をしてもらったところ、若手社員のフォローアップが効果を発揮して承諾率のアップに成功しました。
また、採用の中期から終盤にかけては学生の理解度も高くなります。そのため、このタイミングでは経験値が高い社員にクロージングを任せ、更に深いレベルで学生に企業価値や仕事価値を伝えるのもよいでしょう。
白水:
オンライン化したことによって、採用活動自体はリクルーターがいなくてもやりやすくなっているとは思います。ですが、やはり首都圏の学生にとって九州エリアで働くイメージを持ってもらうことは難しいですね。
ただそれも、イメージが湧かないために心理的な距離ができてしまっているに過ぎません。首都圏から出てきて九州エリアで仕事をしている社員からのリアルな声でイメージを明確にしてもらうなど、その心理的距離を埋める方法はあると思いますよ。
なので、イメージを明確にしてもらう活動を積極的に行い、しっかりとグリップしていけば選考段階での学生離れはある程度、防げると思います。
しかし、内定承諾ということになるとまた少し話が変わってきてしまいますね。
つまり、給与をはじめとした待遇面ですね。平均年収ではやはり首都圏の企業の方が上回りますから、その壁をどう乗り越えるか…ということが次の課題になります。
ただそれも、イメージが湧かないために心理的な距離ができてしまっているに過ぎません。首都圏から出てきて九州エリアで仕事をしている社員からのリアルな声でイメージを明確にしてもらうなど、その心理的距離を埋める方法はあると思いますよ。
― なるほど。確かに心理的な距離は感じてしまいますね。ただ、それは「知らない」というだけだと。
白水: そのとおりです。地方企業で働くことに抵抗感を抱いている学生のうち、ほとんどは「そんな遠くで働きたくない」と思っているのではなく、「その場所で働くイメージが湧かないので、イメージしやすい今の場所(首都圏)で働きたい」と思っているに過ぎません。なので、イメージを明確にしてもらう活動を積極的に行い、しっかりとグリップしていけば選考段階での学生離れはある程度、防げると思います。
しかし、内定承諾ということになるとまた少し話が変わってきてしまいますね。
― 内定承諾でまた一つ、関門があるということですか?
白水: 明確に「地方企業で働きたいんだ」と決めている学生はともかく、首都圏の企業も地方企業も同時に選考を進めているような学生の場合、内定を得た後は「現実的な問題」を元にして判断する作業に入ります。つまり、給与をはじめとした待遇面ですね。平均年収ではやはり首都圏の企業の方が上回りますから、その壁をどう乗り越えるか…ということが次の課題になります。
―確かに難しい問題だと思います。働くイメージはできた、内定も出た、しかし首都圏企業ほどの年収はない… となると、よほどの理由がなければ地方企業を選ばない学生が多そうです。
白水: そうなんですよね。しかし、その「よほどの理由」を実は持っている地方企業は少なくないはずです。 実例で言うと、九州エリアにとあるブライダル事業を軸とした企業があります。企業理念を採用においても重視し、インナーブランディングもしっかり行うことで、九州の学生人気も常にトップクラスを維持しています。「辞めたけれどいい会社ランキング」や「働きがいのあるホワイト企業ランキング」などでも常に上位です。
当然企業としての採用戦略が確立されているという点もありますが、企業の持っている世界観の中で働きたい、と学生に思わせることのできる魅力があるため、首都圏学生も順調に獲得できています。
そういった「自社の魅力」を棚卸ししてみると、年収や待遇に負けない魅力を打ち出すことはできるはずです。
― なるほど。学生が最後に直面する「現実問題による判断」に踏み込めるほどの魅力を理念や共感で得ていく、ということですね。
白水: そのとおりです。最近は社会貢献性を重視した就職活動をしている学生が多いので、十分に可能性はあると思います。ただし、その後の定着まで見通して、きちんと事実を伝えることも同じくらい大切です。
― キラキラした情報だけではなく、現実をきちんと伝えると。
白水: そうですね。その際にはやはりリクルーターや若手社員が活躍するでしょう。最近は「ユーザーレビュー」を元にした判断が普通のことになっていますから、企業からの発信だけでは不十分です。リクルーターからの発信が「ユーザーレビュー」だとしたら、人事からの発信は「マスメディア情報」という関係ですよね。リクルーターが個人の話として、学生と直接言葉を交わし、働きがいや理念だけでなく、「こんな面もある」と現実をきちんと話してあげることができれば、学生はその情報も加味して内定承諾の判断ができますので、定着率が上がります。
― 今日はありがとうございました!
このインタビューを担当した私自身は、東京生まれの東京育ちで、実際に就職活動をしていた頃には地方企業で働くことを考えたこともありませんでした。
こうしてオンラインでの接点が持てる時代になり、また情報の提供手法も多様になったことから、地方企業でも自社の魅力をしっかりアピールすることができれば首都圏学生の獲得が可能になったと白水さんのお話から分かりました。
一方で、新卒採用活動において重要な指標である「内定承諾率」だけを追い掛けてしまうと定着率が落ちるという指摘はもっともです。
魅力あふれる地方企業はたくさんありますし、その魅力をアピールする手段もたくさんあります。しかしそれだけではなく、実際に首都圏から地方企業へ就職した社員からの「生の声」をきちんと伝えることで、学生に冷静な判断をする材料を与えることもまた重要であるとのお話は、気付きを得た読者の方も多かったのではないでしょうか。
こうしてオンラインでの接点が持てる時代になり、また情報の提供手法も多様になったことから、地方企業でも自社の魅力をしっかりアピールすることができれば首都圏学生の獲得が可能になったと白水さんのお話から分かりました。
一方で、新卒採用活動において重要な指標である「内定承諾率」だけを追い掛けてしまうと定着率が落ちるという指摘はもっともです。
魅力あふれる地方企業はたくさんありますし、その魅力をアピールする手段もたくさんあります。しかしそれだけではなく、実際に首都圏から地方企業へ就職した社員からの「生の声」をきちんと伝えることで、学生に冷静な判断をする材料を与えることもまた重要であるとのお話は、気付きを得た読者の方も多かったのではないでしょうか。
- 人材採用・育成 更新日:2021/05/21
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-