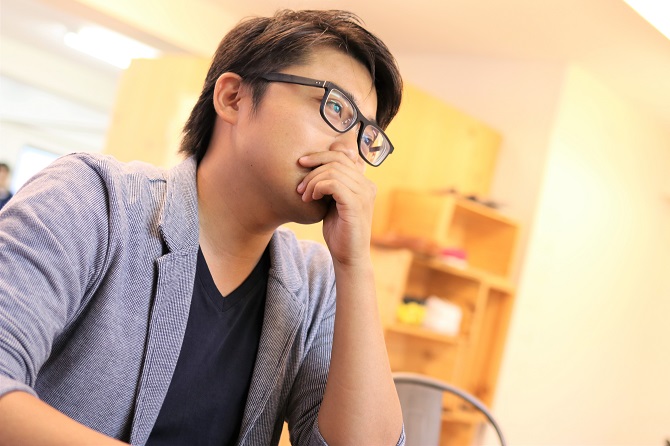マネージャーが転職を決めるとき|ある日偶然バーで隣り合わせた、KOMPEITOの同士たち
優秀なリーダー・マネージャークラスの人材に来てもらうには、「彼らが転職を決めたきっかけ」を知り、それをモデルケースとして自社の採用活動に活かせばいい。そんな趣旨から始まった本連載「マネージャーが転職を決めるとき」。
第4回の主人公は、オフィス向けに旬の野菜や果物を届けるサービス「OFFICE DE YASAI(オフィス・デ・ヤサイ)」を運営する、株式会社KOMPEITO(コンペイトウ)のCTO・黒木信吾さん。
もともとはゲーム関連会社や広告代理業など、野菜とは関係のない業界にいた彼。転職のきっかけになったのはなんと「KOMPEITO創業メンバーと、たまたまバーで隣り合わせたこと」だったというから驚きです。
その裏側にはどんなドラマがあったのでしょうか。今回は、黒木さんの個性的なキャリアにスポットライトを当てます。
黒木:順を追ってお話しすると、社会人になって数年くらいしてから芽生えた「地元に貢献したい」という目標が影響しています。私の地元は宮崎なんですが、地元から離れて東京で暮らしたことで、宮崎の良さが少しずつ客観的にわかるようになってきたんです。
それで、「いつかは、自分の地元やそこで暮らす人たちに貢献できるサービスをつくりたい」と考えるようになっていきました。その夢を、30歳までに叶えたいと思ったんです。
2社目への転職を決めたのも、それが理由です。その企業は全国展開している総合ディスカウントストアのシステムを開発・運営していたので、そこでエンジニアとして働くことで地方に住む人たちにも貢献できるのではと考えました。
そして3社目でも、地方にいる方々の役に立てるようなマッチング系サービスを開発していたんです。
黒木:エンジニアは普段、物流コンサルタントと会って話すなんて機会はほとんどありません。だからこそ、2人が語る「野菜の物流を変える」という概念が私にはとても新鮮に映ったんです。
また、創業メンバーと出会ってしばらくの間は、3社目の会社に勤めながらボランティアとしてKOMPEITOを手伝っていたんですが、その業務を通じて2人がどれだけ真剣に物流を変えようとしているのか、ひしひしと伝わってきたんです。「この人たちは本気だ」と思えました。
加えて、「物流 × 野菜 × IT」という領域で働いているエンジニアは、世の中にほとんどいません。だからこそ、その分野を担うことで、自分自身のエンジニアとしての希少価値も上がるのではないかと考えました。
そしてもう1つの理由が、先ほども出てきた「地元に貢献する」ということ。野菜を生産しているのは、当然のことながら、都会よりも地方在住の方が多いです。つまり、物流を改革して野菜の流通量や消費量を上げることは、巡り巡って地方を元気にすることに繋がります。
これらの要素が揃っていたからこそ、KOMPEITOでCTOとして働くことを決めたんです。
黒木:「自社にはどのようなタイプのエンジニアが必要なのか?」を明確にすることだと思います。
エンジニアにも色々な人がいて、何でもバランス良くこなせるジェネラリストもいれば、特定の分野に特化したスペシャリストもいます。得意とする技術も、エンジニアごとに異なっているでしょう。
だからこそ、たとえば「自社にはまだエンジニアがいないから、幅広い業務をまんべんなくこなせるジェネラリストを採用しよう」とか「サービスを拡大するためにサーバを強化したいから、サーバのスペシャリストを採用しよう」という感じに、方針を決めるといいと思います。
総括すると、エンジニアに対する「期待」と「役割」を明確にすることが、採用では大切なのではないでしょうか。
- 人材採用・育成 更新日:2017/06/13
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-