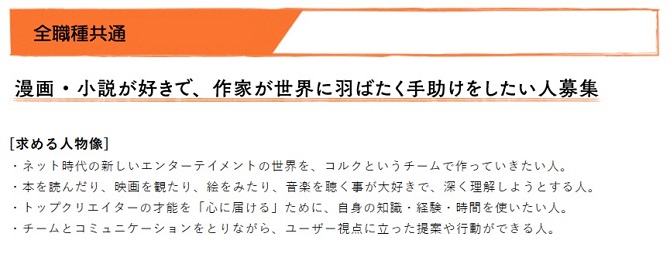マネージャーが転職を決めるとき|コルクCTOを突き動かしたのは、「未来を編集する男」の言葉
リーダー・マネージャークラスの人材を採用する。
これは、多くの人事担当者にとって絶対に叶えたい目標。そして同時に、叶えるのが非常に難しい目標でもあります。なぜなら、そうした人材は企業における事業の根幹を担っており、簡単には他社へ移ってくれないからです。
ではどうすれば、彼らを採用できる可能性が高まるのでしょうか。その1つとして「リーダー・マネージャークラスの人材が、転職を決めた理由や経緯を知る」という方法があります。つまり、過去の事例をモデルケースとすることで、自社の採用活動にそのノウハウを活かせるというわけです。
今回ご登場いただくのは、2016年10月に漫画家や小説家などのエージェント事業を行う「株式会社コルク」の取締役CTOに就任した萬田大作( @daisakku )さん。
彼がコルクへの転職を決めたのは、いったいなぜだったのでしょうか。そして、萬田さんの考える「企業が採用を成功させる方法」とは。その秘密を、あたかも小説のページを1枚ずつめくるように、言葉にしてもらいました。
- 人材採用・育成 更新日:2017/06/13
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-