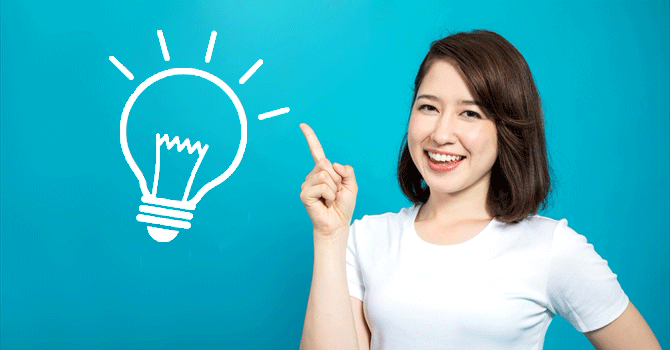採用担当として入社後の社員が離職しない方法を考える
● 1.面接対応時に注意すべきポイント
入社してもらいたいと考える人事担当は、比較的自社の良い情報を応募者に伝えることが多くなる傾向にあり、入社後のギャップが発生しやすくなります。決して嘘をつかないこと。良いことだけを言わないこと。話を良く盛らないことが重要。且つ、入社後のフォロー対応を行うための情報として、転職の目的の深いヒアリング、相手の欲求段階の確認などを行う必要があります。
● 2.内定条件提示時に注意すべきポイント
こちらも上記と同様、内定条件提示時に入社後の条件と違った提示をすると離職の要因に繋がります。「そんな会社さんあるの?」と驚かれるかもしれませんが、年間500名以上の方と面接をしていた頃は、決して少なくない数でその背景から退職をされた方がおられました。各企業にも事情はあったかと思いますが、当初の求人票と情報が違う、内定条件提示で貰った情報と入社後の情報が違うなど、非常に多くのケースが発生しています。条件面の違いで多い項目としては、“業務内容”“雇用形態”“賃金条件”です。働く上で重要な項目で、間違いがあってはならない部分ですが、入社すると違っていたというケースが散見されます。勘違いしていたでは済まない問題ですので、どんな事情があったとしても注意したいポイントです。
● 3.入社後のフォロー対応時に心がけておきたいポイント
入社後のフォローとして重要なことは、コミュニケーションの一言に尽きます。では、いったいどんな内容でコミュニケーションを取っていく必要があるかを考えていきたいと思います。タイミングとしては、入社後1週間以内、1か月後、3か月後、半年後と、少しずつ距離を伸ばしていきます。その他、本人にとって重要な出来事がある日などを記憶しておき、そのタイミングで連絡を取ることも非常に効果的です。
内容としては、
- 現在の状況
- 困っていることはないか
- 楽しいと感じていることはどんな時か
- 現在感じている課題に対してどんな対策を心掛けているか
- プライベートの話題
などがメインとなります。
必要があればアドバイスを伝えますが、特に入社して間もないタイミングであれば、常に聞く姿勢、褒める姿勢で話を展開していきます。相手に“頼ってもいい人”という姿勢を見せておくことが非常に重要となります。離職を考えた時に、まずは相談してもらえるようにしておくことです。
最後に、面接前に聞いていた離職内容と、本当の離職内容を再度確認しておいてもいいかもしれません。面接前はどんなに掘り下げても印象を落とさないよう細心の注意を払う為、リラックスした状況で再度確認を行うことも一つの方法かと思います。本当の離職理由を把握しておくことで、ヒアリング時に浮上した課題優先順位がつけやすくなり、適正な順序で対処が行えるようになります。
今回は入社の入口を担当する採用部隊として、離職防止に取り組む内容を考えていきました。6年という短いマネジメント経験からで恐縮ですが、人が辞める要因の多くは、将来に期待が出来ないと自分で見切りをつけてしまうことから発生しているのではないかと感じています。
給与不満、人間関係不満、勤務地不満、職務内容不満、将来性不安など、全てにおいて「会社が自分の不満・不安を理解し、改善を示してくれなかった」ということになり、その環境下での目標設定を行えなくなってしまう。その結果、転職して新しい環境下で目標を掲げて再チャレンジをしてみたいと考えるようになるのではないかと。
つまるところ、マネジメント不足を含み、組織への見切りが行われた結果、退職してしまうのです。
「私の意識が反映される組織が他にあるはずだ」と考え離職が発生する。マネージャーの役割は、メンバーひとりひとりの強みを組織に反映し、影響力を与えられると感じるような環境づくり・仕組み作りを行うこと。
強みを褒め、認知させ、活かし方を共に考え、仲間の弱みをその力でフォローするよう教育していくこと。なりたい方向性の確認(上記内容で不満に感じていることなど)を行い、登る必要のある階段を提示し導くことだと感じています。
上司部下の関係が構築できれば、給与に不満があったとしても、別の人との人間関係に不満があったとしても、職務内容に不満があったとしても、将来性に不満があったとしても、その組織に居続ける意味を見出すことが出来ます。
いかに見切りをつけさせないか。ここにいる意味を共に見出すかを、共に考える姿勢であれば、その組織は離職が非常に少なくなります。マネージャーのサポートとして、採用担当が面接時に仕入れている情報を、正確に丁寧に共有していくことが、採用担当としての役割ではないかと感じています。
以上、採用としての立場から見た離職を低減する方法でした。皆様の採用活動・組織運営においてお役にたてれば幸いです。
- 人材採用・育成 更新日:2018/10/30
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-