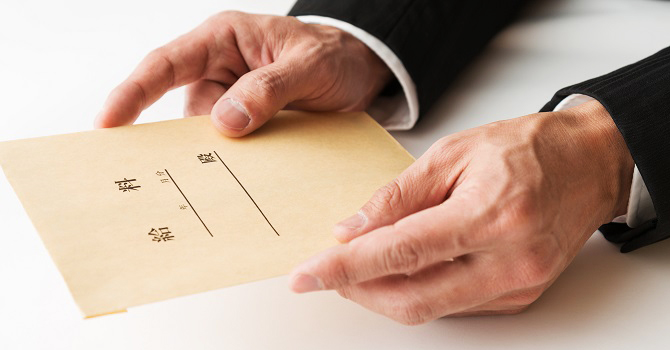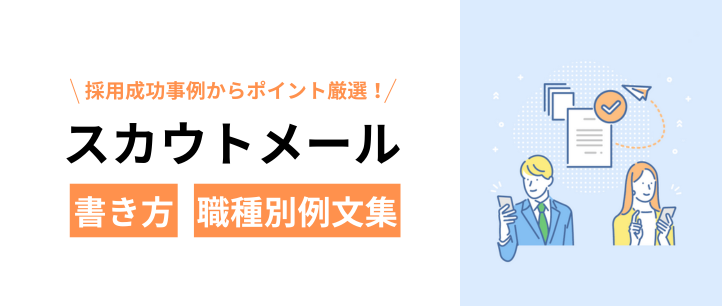目標管理制度(MBO)とは|評価制度を解説します
評価結果を報酬に反映する場合、当然ながらその評価は厳密に行う必要があります。しかし、各メンバーがバラバラに立てた目標を元に、同じ基準で評価をするというのは非常に難易度が高いのです。
例えば、普通に考えれば「高い報酬をもらう人=高い目標レベル」「低い報酬をもらう人=低い目標レベル」となるのが自然です。しかし現実には、中途採用で高い報酬の条件で入社してきた人に、いきなり高い目標を要求するのは厳しいでしょう。また、低い報酬の人であれば、相対的に易しい目標レベルを設定しなければいけないわけですが、期待の新人には背伸びした高い目標を求めたいのがマネージャーの本音です。
このように、メンバーの成長フェーズによっては「報酬」と「目標レベル」との間に乖離が生じるケースがあります。それを考慮した上で評価をしなければいけないからこそ、難しさがあるのです。
また、目標管理制度を運用するにあたって、マネージャーにはある能力が求められます。それは、目標を「言語化する能力」です。
目標管理制度は、何らかの目標や達成基準を決めて、それができたかどうかで期末に評価するという極めて自由度の高い制度です。「やったかどうか=行動」を目標にしてもいいですし、「できたかどうか=結果」を目標にしてもいい。売上も、人材育成も、何でも目標にできます。
何でもいいというのは、一見運用しやすい制度のように見えます。しかし、目標を設定する側からすると、その自由度の高さゆえに何を設定すべきか路頭に迷ってしまうケースもあるのです。そのため、目標管理制度を導入する場合には、各マネージャーが目標設定のための「言語化する能力」を持っているかを十分に確認しましょう。
- 労務・制度 更新日:2017/08/17
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-