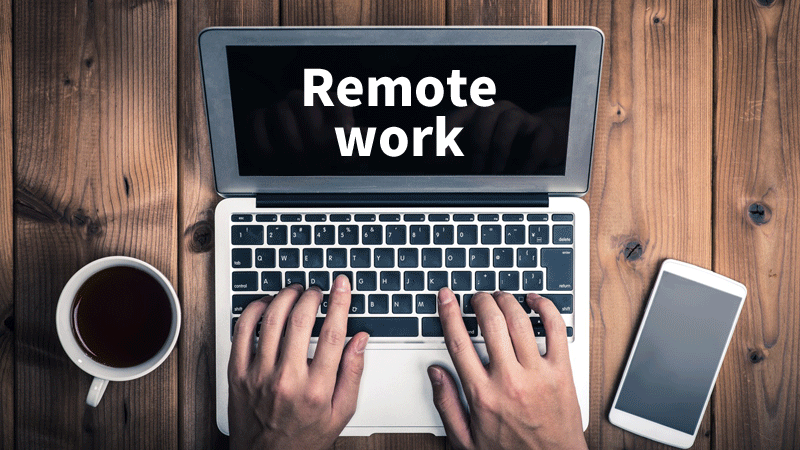中小企業だからこそ、リモートワークを実践できるのか
“働き方改革”が声高に叫ばれるなか、副業解禁と並んで注目されているのが「リモートワーク」です。リモートワークとは、働く場所を会社のオフィスに限定せず、自宅や外出先など遠隔で働くこと。近年日本企業では、パナソニックやリクルート、トヨタ自動車などの大手企業が導入を進めている制度です。
労働者にとって、仕事と育児や介護の両立が容易になることに加え、通勤ラッシュ時のストレスや移動時間の短縮など、大きなメリットと言えるでしょう。けれども、経営者目線で考えてみるといかがでしょうか。社員がどこで何をしているのか分からず、生産性を心配する声もあれば、勤怠や情報の管理を社員に任せることを不安に思う人もいるでしょう。
しかし、株式会社プレスラボ・代表取締役社長の梅田カズヒコ氏はこう語ります。 「有能な人材を確保するに、中小企業こそリモートワークを実践すべきです」
プレスラボは、コンテンツ制作を事業とする、いわゆる「編集プロダクション」。 社員は11名ほど(2017年1月現在)で、その8割は女性が占めており、勤務形態にリモートワークを推奨しているそうです。
ここでは梅田氏の経験談を基に、リモートワーク導入のコツを紹介していきます。
「第二次世界大戦後、日本は世界的にも異例なスピードで社会発展をしましたが、それは均一性のある教育水準のおかげです。国民全員の能力が平均して高かったので成功したわけですね。社会が右肩上がりで成長している時期は、仕事がどんどん生まれている状態なので、自分と同じことをやる人が必要になった。だから、画一化された人が大量に必要でした。これは僕たち日本人が得意とするところです。ところが、今は右肩上がりではないので、仕事を作り出す人が必要になってきています。要するに、イノベーションを起こす人が必要です。これは、画一的な環境では生まれづらいわけです。あらゆる多様性を認める組織がイノベーションには必要です。」
なぜこれからの時代、イノベーティブな社員が必要なのか。それは、与えられた仕事量をこなすだけの業務は、より人件費の安い途上国や、場合によっては人工知能がになうようになるからです。中小企業も、例外ではありません。
「在宅勤務制度を導入するうえで、もっとも大事なのは”やるべきことが明確かどうか”です。社員一人ひとりに対し、どこまでが自分の業務なのか、ということを決めておくこと。たとえば『毎月の売り上げが〇〇円』など明確な指標があり、それを達成していれば、経営者や人事担当者は日報を毎日チェックしなくてもよいのです。生産性を維持するために自宅にカメラをつけて監視している会社もありますが、それだと労働者のモチベーションを維持することは難しく、コストも莫大になります。経営・人事担当者など管理する側と、現場の社員の間で明確な評価軸を設けるのがリモートワークを取り入れるときに必要なことです。」
リモートワークを導入することで、今までとは異なる方法を考えなければならないことも確かです。ただし、それらは経営者・人事側の工夫によって解決できる問題でもあるのです。今や、ほとんどの労務問題はICT(情報処理ツール)を導入することで解決できると言えます。
また、売り上げに直結しない単純作業は、アウトソースすることも可能です。現代社会において「社員がすべき仕事」と「そうでない仕事」の線引きをしておくことで、労働者側の負担を減らすことも視野に入れておきたいところ。評価軸を「勤務態度」に置かず、成果を測る仕組みをつくる必要があるのではないでしょうか。
「そもそも、管理する・管理されるという関係はお互いが不幸だと思います。雇用側も『管理する』という考え方を捨てるべきで、その価値観の転換が今の時代に求められているはず。中小企業は少数精鋭の規模感だからこそ、社員を『パートナー』だと思えば、マネジメントも決して難しいと思いません。」
リモートワークを取り入れる際に心配なのは、情報漏洩リスクです。
「機密情報の管理がリモートワークの最も難しいところと言えるでしょう。弊社の場合は、クライアントからの機密情報を取り扱う機会は少なくし、なるべく機密を受け取らないようにしています。仮に受け取った場合は、その情報を社外に持ち出すことがないようにしています。そうした情報は役員や幹部も巻き込むように管理し、細心の注意を払いつつ厳重に取り扱う必要があります」
大企業に比べると従業員の管理が行き届く中小企業では、定期的に機密情報の取り扱い講座を開くなど、情報漏洩対策を工夫することが可能でしょう。またプレスラボでは、社員とのコミュニケーションについて、チャットツールやグループウェアなどICTの活用はもちろん、全員参加の会議を週に1度開催し、共同意識を維持しているといいます。仕事と関係ない雑談や、なんでも話せることが信頼関係に繋がる基準となるでしょう。個々の能力とは別に、会社と社員の信頼関係を成り立たせておくことで、仕組みとしての労務管理を確立し、勤務形態を整備することができるでしょう。
「すでに『商品の大量生産』の時代は終わりを迎えつつあります。たとえるなら、『3Dプリンタ』。設計士からあがってきた図面に対し、機械に任せて完成物をつくるのは誰でもできるじゃないですか。では、それを使って何を作るか…それを考えるのが、これから働く人に求められること。ダイバーシティという言葉もありますが、こうしたクリエイティブやイノベーションは、働く環境を変えること…つまり、自由度を上げることで生まれることが多いです。特に中小企業は、時代の変化に取り残されるとあっという間に優位性を失うので、なるべく早く取り入れる必要があります。また、自由度の高さというのは、働く側にとって中小企業に勤める優位性になります。これを利用しない手はありません。」
中小企業の経営者は「従来の会社組織」ではなく「一人ひとりにぴったりの働き方を与えられる柔軟さ」を考える組織をつくりあげ、常日頃から社員の意思を汲み取れるほうがいいでしょう。そのため、優秀な人材獲得はもちろん、ICTを駆使することで情報整理を行うのは必然です。一見大変な作業に見えてしまいますが、グループウェアでそれぞれの仕事を共有したり、チャットツールで社内コミュニケーションを見える化したりすることで、社内の風通しをより良くすることも考えられます。
「リモートワークの導入など、働き方の多様性を認めるということは、社員や経営という問題以上に、国民全体の幸福度を増やす考え方でもあると考えます。日本人の労働時間、通勤時間が長いことと、少子化は決して無関係ではありません。僕たちはもう少し自由になる必要があります。」
まずは自社で明確な指針を定め、適材適所の働き方を考えてみることが、社員の多様性を活かすための近道なのかもしれません。
- 労務・制度 更新日:2017/08/01
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-