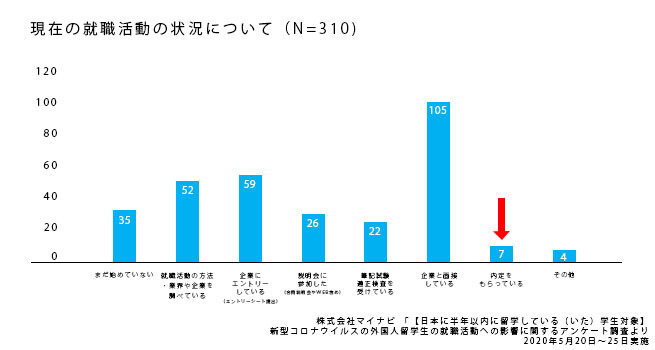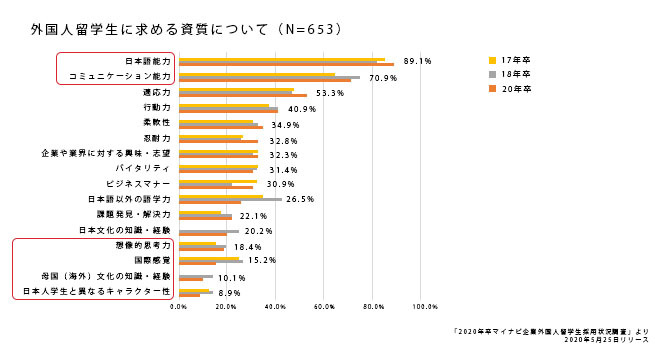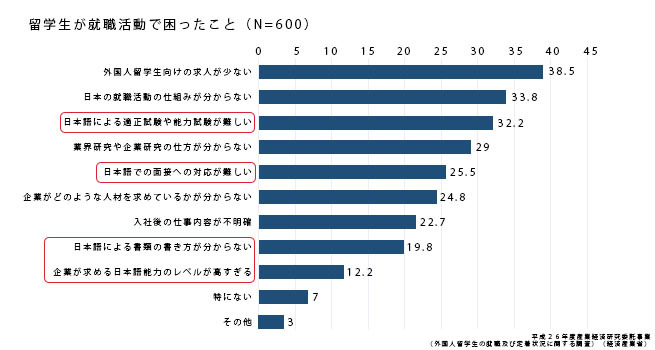【会員限定】外国人が働きやすい企業は異能の人材が活躍できる強い組織! 「組織を強くする」外国人採用の活用方法
この「3つの壁」を解消するため経済産業省では企業における外国人材採用のポイントや事例をまとめたハンドブックを作成し、無料で公開しているそう。
さらに能村室長は、人材戦略上の課題は経営戦略上の課題に直結すると解説します。
「人材が経営のあり方を規定する時代が到来しています。さらに新型コロナウイルスへの対応に伴い時間・場所にとらわれない働き方が広がるなかで、個人・組織が活性化できているのか、という課題も見えてきました。多様な雇用コミュニティが求められるなかで、カギとなる人材の確保が重視されるようになってきていると感じます。そうした人材の確保の手段の一環として外国人材の活用は非常に重要なのです」(能村室長)
さらに能村室長は、人材戦略上の課題は経営戦略上の課題に直結すると解説します。
「人材が経営のあり方を規定する時代が到来しています。さらに新型コロナウイルスへの対応に伴い時間・場所にとらわれない働き方が広がるなかで、個人・組織が活性化できているのか、という課題も見えてきました。多様な雇用コミュニティが求められるなかで、カギとなる人材の確保が重視されるようになってきていると感じます。そうした人材の確保の手段の一環として外国人材の活用は非常に重要なのです」(能村室長)
「採用に至る前のプロセスで外国人材を生かせていれば採用段階での課題が明確になるため、短期間で採用を行うより、まずはじっくりアルバイトやインターンを活用できると良いと思います」(能村室長)
能村室長の話を受け、九門教授は外国人材の採用・定着のためには、採用目的の明確化や採用プロセスの透明化も非常に重要になると指摘します。
「採用の前に、まずどういう仕事をしてもらうかを考えた上で採用目的を明確化する必要があります。定着のためには、外国人材の能力をうまく生かせる配属が非常に重要なんです。その上で、採用サイトやホームページなどで外国人採用の方針や外国人の採用実績などを明示していただけると、採用側と求職者側で齟齬なく採用・受け入れを進められるのではないでしょうか」(九門教授)
ハードではなくソフトを変える。プロセスや仕組みの前に、まずは細やかな気遣いを
企業が外国人材を採用する際に悩みの種となるのが、採用された人がいち早く実力を発揮できるための環境を用意する「オンボーディング」です。このオンボーディングをうまく運用していくためには大きく制度を調整したり、初期投資が必要になるのではないか、と不安に思う採用関係者も少なくありません。
しかし、現場を見てきたお二人によると、ちょっとした気遣いがオンボーディングを円滑にする足掛かりとなるそうです。
「外国人材が入ってきたときにいきなりこの部署に配属して働いてください、というよりも、どういう目的で、どういう仕事をするか、かみ砕いた言葉で分かりやすく発信していくだけでも定着率は大きく変わります」(能村さん)
「能村さんのご指摘はそのとおりで、これはソフトの問題なのでは、と考えています。日本の企業は外国人採用となると、制度やプロセスなどハードを変えようとすることが多いのですが、実際は制度を変えなくともちょっとした声掛けや発信を強め、システムを透明化することで解消する問題も多いのです」(九門教授)
個人やチームなど小さいところから始められる声掛けや情報の伝達。こうした配慮の積み重ねが、新しい人材を受け入れる上では非常に重要になるのかもしれませんね。
外国人材が活躍できる企業は、多様な人材が活躍できる強い組織になる
ここまでさまざまな課題が語られましたが、これらの課題は実は外国人採用だけにとどまりません。九門教授は外国人材という枠組みをいったん離れ、個性の違う個人としてみることが重要だと指摘します。
「漠然と外国人材の採用としてくくるのではなく、一人ひとりがそれぞれ違うバックグラウンドを持った違う人間である、というところを認識することが重要なのかな、と思います。その上で個人の特性に合わせたフィードバックや面談を重ねていくことが、外国人に限らず異能の人材を活用する大きな鍵になるのではないでしょうか。今日の議論は『外国人材がなぜ日本企業で活躍できないのか?』に集約されましたが、『外国人材』を『優秀な若手・女性』『ユニークな人材』と変えても問いが成立する点に大きな課題を感じています」(九門教授)
- 人材採用・育成 更新日:2020/10/22
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-