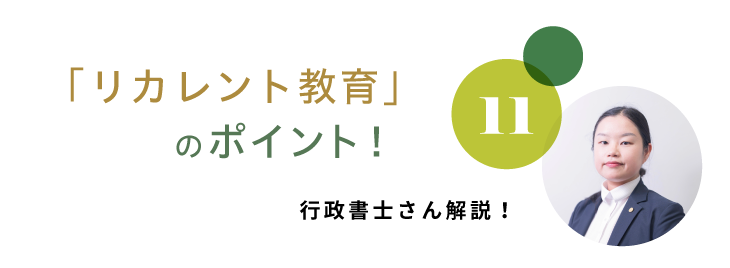学び直しのコストは誰が負担する? リカレント教育を会社に取り入れるためのポイントとは
平成 29(2017)年1月 20 日に発表された「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」によると、「参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講」、また「使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間」は「労働時間」であるとしています。
「使用者の指示により」という部分も注意したいポイントです。たとえば、「自主研修」という名前が付いているのに、勉強時間について具体的な指示をしていた場合については、使用者の指示があったとみなされ、労働時間としてカウントされる可能性があります。
一方で、「〇〇〇検定試験に合格するように勉強してください」という指示を出したとしても、その勉強方法が個人に委ねられているケースについては、使用者の指示があったとまではいえず、労働時間としてカウントされない場合もあります。
過去の判例「NTT西日本ほか (全社員販売等)事件」(大阪地裁2010年4月 23 日判決)では、社員のWEB学習の時間が、労働時間であると認められました。この判決では、以下の点がポイントとなりました。
- 会社が社員の学習時間を把握している
- 学習内容は、会社の業務と密接に関連している
- 市販の書籍では勉強できない内
- 会社固有の仕様で作られていた設備についての内容が含まれる
- 人事評価の参考資料(チャレンジシート)への記入が求められていたこと
これらの点だけでも、会社がかなりの程度、資格取得に積極的に関与していたと思われます。また、この会社に在籍しているからこそ必要になるような内容の勉強をしていたともいえるでしょう。
このようなケースでは、資格取得のための学習時間は労働時間にあたります。
会社が再教育のコストを負担する場合、「再教育後すぐに転職されては困る」という意見もあるでしょう。
この場合、会社がいったん再教育のコストを支払っておき、条件を満たせば返済を免除するという手法(金銭消費貸借契約)があります。教育費を会社が払った後、5年間は勤務を継続するというような条件がついた契約です。
こうすることで、少なくとも会社が希望する期間中は会社に残ってもらえる確率が高まります。もし、残ってもらえなくても、教育費を負担したことによる損は抑えられるという仕組みです。
社員の資格取得のための金銭消費貸借契約を締結する場合、以下の点に留意し、契約書を作成してください。
- 資格取得の目的……何のために資格を取得するのか、何の業務に必要となる資格か。
- 費用貸与の趣旨……なぜ貸与するのか。
- 会社が費用負担する範囲……通信教育の費用なのか、受験料なのか。
- 貸与限度額・貸与年数・返済方法・利息取り扱い等……資格取得後、何年経ったら返済を免除するなどの規定。もし資格取得後に退職する場合、貸与資金を返還しなければならないが、その場合の利息についての取り扱い。
- 労働を不当に拘束するものではないこと……会社からの資格取得は命令ではなく、あくまで個人の取り組みである、ということが趣旨ですので明記しておきましょう。
今回は、リカレント教育とコスト負担について紹介しました。「人生100年時代」を迎え、働く期間が長期化していく一方で、昨今は技術の進歩が非常に速いため、仕事で必要な知識やスキルをアップデートしていく必要があります。
リカレント教育を会社に取り入れるためのポイントは、労使双方にメリットのある制度・運用方法を作ることです。
リカレント教育の必要性はわかっていても、なかなか踏み出せない場合は、再教育のコストと新規採用のコストを比較してみてください。そして、再教育をしてもすぐに辞められたら困る、という場合は契約で一工夫をするのはいかがでしょうか。
企業にとっても、労働者にとっても有益なリカレント教育の仕組みを構築していきましょう。
- 労務・制度 更新日:2021/01/06
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-