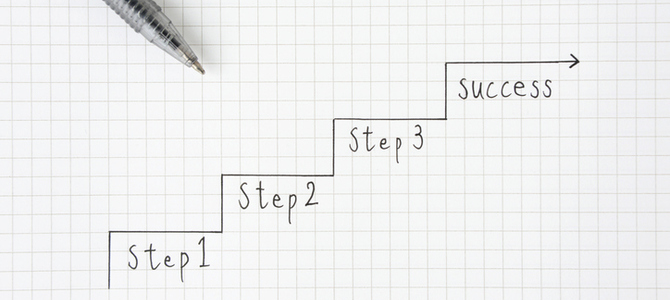優れた人材の退職を防ぐシンプルな戦略
『Love “Em or Lose “Em』-「従業員を愛するか、それとも失うか」というタイトルからも分かるように、この本で紹介されている戦略は従業員を深く理解することが基本になっています。まずは、その戦略を本の目次どおりアルファベット順にあげてみましょう。カッコ内は各章の内容を一言で表しました。
- Ask: What Keeps You? (従業員に仕事を続ける理由を尋ねる)
- Buck: It is Stops Here(部下を愛する管理職になる)
- Careers: Support Growth(従業員が望むキャリアアップのサポートをする)
- Dignity: Show Respect(敬意を持って従業員に接する)
- Enrich: Energize the job(仕事に価値や活力を与える)
- Family: get friendly(ファミリーフレンドリーになる)
- Goals: Expand Options(キャリア成功のためのゴールを決める)
- Hire: Fit is It(企業に合う人材を採用する)
- Information: Share it(情報を共有する)
- Jerk: Don’t be One(嫌な人にならない)
- Kicks: Get Some(職場を楽しくする)
- Link: Create Connection(つながりを作る)
- Mentor: be One(メンターになる)
- Numbers: Run Them(退職や採用のコスト意識を持つ)
- Opportunities: Mine Them(従業員に機会を与える)
- Passion: Encourage It(従業員に情熱を持たせる)
- Question: Reconsider the Rules(ルールを見直す)
- Reward: Provide Recognition(功績を認める)
- Space: Give It(スペースを提供する)
- Truth: Tell It(真実を語る)
- Understand: Listen Deeper(深く聞き理解する)
- Values Define and Align(価値の定義と調整)
- Wellness Sustain It(ウェルネスを維持する)
- X-ers and others Handle with care(世代による違いを知る)
- Yield Power Down(パワーダウンする)
- Zenith go for It(自己評価を繰り返し、進化し続ける)
26の戦略を一つずつ参考にすることもできますし、自分の行動に合わせ、いくつかの戦略を組み合わせてもいいでしょう。ここでは一例として、26の戦略の概要を行動に合わせてご紹介します。
例えば、従業員に現在の仕事を続ける理由を聞いてみましょう。コンピューターかスマートフォンに全従業員の回答を書き写したノートを作ります。毎月、そのノートを見直して、自分が従業員のニーズに沿うように行動できたか反省します。また、ステイインタビューを実施するときに、次のような話し合いのポイントを書いた招待状を渡して従業員に尋ねる内容を考えてもらっておくことも提案されています。
- あなたが、ここで仕事を続ける理由は何ですか?
- どんなことが理由で退職を考えてしまいそうですか?
- 職場であなたをやる気にさせることは何ですか?
- 私たちはあなたの才能を十分に生かせていますか?
- あなたの成功の妨げになるものは何ですか?
- あなたをもっとサポートするために私が変えられることはありますか?
直接本人に尋ねずに推測してはいけません。ボーナスを上げれば従業員が喜ぶだろうと推測してボーナスを上げたところで、ほかに問題があるときには、従業員は退職してしまいます。必ず本人から直接意思を聞かなければいけません。
性格や態度は人によるもので、一人一人に合わせて接することが大切ですが、マーケティングと同じように世代の特色を知っておくと参考になることもあります。
- ミレニアル/ジェネレーションY(1977-1988生まれ)デジタルネイティブでテクノロジーやマルチタスクに強い。仕事には金銭よりも、柔軟性や自由、成長を求める人が多い。
- ジェネレーションX(1965-1976生まれ)中間管理職になっている層。仕事で何が期待されているかをはっきりと知りたい。そして結果を出すためには、自分の好きな時間に自分のやり方で仕事ができるスペース、リソース、自由が必要であると思っている。
- ベビーブーマー(1946-1964生まれ)そろそろリタイアを考える年齢になり、人生の意味を再び考えている。子育てと介護の板挟みになっていることもある。一方で子育てが終わり自由な時間やお金が増え、いつどのように楽しもうか考えている人も。
- マチュア(1933-1945生まれ)一般には退職していると思われている年齢だが意外と多くの人が働いている。知識と経験があるので、人材不足のときにマチュア世代を雇用できるようシニア世代の人材を紹介する機関と提携する企業も多い。
シンプルで分かりやすい26の戦略は、従業員の定着率を上げたいときや、職場の環境改善を目指しているときのチェックリストとしても便利です。第5版は日本語に翻訳されていませんが、過去に『部下を愛しますか? それとも失いますか?』というタイトルで旧版の日本語訳が出版されていました。英語版でも分かりやすい本ですが日本語で読みたいという方は探してみるといいかもしれません。
タイトル Love ‘Em or Lose ‘Em: Getting Good People to Stay : 5th edition
著者 Beverly Kaye, Sharon Jordan-Evans
出版社 Berrett-Koehler Publishers(5版 2014/1/6)
ISBN-10: 160994884X
ISBN-13: 978-1609948849
- 人材採用・育成 更新日:2020/06/17
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-