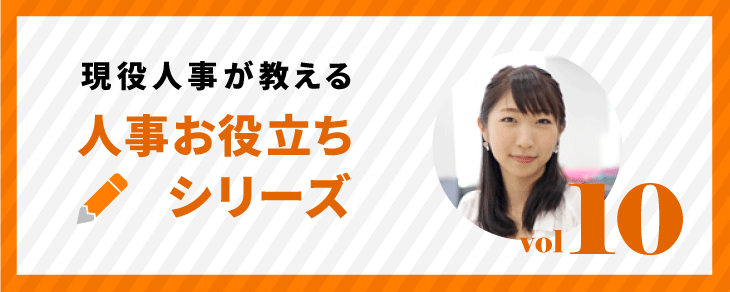ワーキングマザーの葛藤、企業の適切なサポート態勢とは
2013年、安倍総理が国連で女性活躍推進についての演説を行う前から、実は育休産休の制度の導入など、企業での取り組みは進められていました。厚生労働省の発表によると、2010年度の雇用保険育児休業給付取得者は全国で206,036名(内男性3,291名)、そこから7年後、2017年度には育休給付取得者は増加し、342,978名(内男性1,4175名)と、約1.6倍(男性については約4.3倍)の増加となりました。
2008年をピークに日本の人口は減少に転じていますが、育休給付取得者の人数は増加する一方です。育休復帰後すぐに辞めてしまう人も一定数存在するとは思いますが、その後も就業する意欲を保っている女性は多いようです。この結果から、今後もワーキングマザーの働き方支援は、企業にとって考えるべき命題のひとつであると言えるでしょう。
企業の育休制度導入の背景には、「次世代育成支援対策推進法」の存在がありました。これは、少子化の進行を重く受け止め、地方公共団体や事業主による行動計画を策定し、次世代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するというものです。この法律が定められてから多くの企業で育休制度が策定され、社員に急速に浸透していったということが分かります。
ひと昔前の日本では、妊娠したら自然と退職を推奨されることが多かったように思いますが、ここ数年で育休を取ることのほうが自然な状況になってきたのではないでしょうか。
しかし、復帰するワーキングマザーにとっては、子どもの体調不良や育児・家事・仕事の両立を含め、「最初の1年を乗り切れるかどうか」が最初の関門となります。そして、最初の1年を乗り切った後も、次の関門が待っています。時短勤務を選ぶ多くのワーキングマザーは、キャリアアップを望む一方で、責任ある仕事を任せられることへの辛さを抱え、「迷惑をかけている」という気持ちから職場にも相談できず孤独に悩みを抱えているケースも多いと言います。
育休制度を作ったとしても、ワーキングマザーの働き方やキャリアアップ支援に関しては、企業の対応が後手に回っている現状が少なからずあるかもしれません。人事の皆さんにとって、今後ますます増えると予想されるワーキングマザーの就業支援、また、キャリア支援をどのように行っていけばいいのでしょうか。
一般的に、ケア施策を充実させて働きやすい環境を整えてから、フェア施策によってやりがいを刺激し、女性社員が能力を存分に発揮できる職場環境に整えていくのが手順とされていますが、実は「ケア施策」には落とし穴があります。ケア施策は女性の中でも育児に従事する一部の人のみを対象とているため、他の社員が不公平感を抱き、人間関係に溝が出来やすくなってしまうのです。
また、ケア施策による優遇措置によって、徐々に権利を強く主張するワーキングマザーたちが増えてきてしまい、職場での不平不満が後を絶たないケースもあるようです。悲しいことではありますが、助け合いといっても、助けるだけの立場の人と、助けてもらうだけの立場の人とに分かれてしまっては、良い関係が構築できなくなってしまうのは仕方ないでしょう。
この不平不満を解消する方法としては、状況を話し合った上で業務量の割り振りを行うことなどが挙げられます。例えば、「ワーキングマザーには残業をさせられない」、「土日出勤させられない」という状況が常態化してしまうと、他の社員の負担が増えてしまいがちです。
そこで、しっかりと面談を重ねてコミュニケーションをとったうえで、ワーキングマザーにも月1回、月2回などの出来る範囲で、残業対応や土日出勤をしてもらうなどの対策を講じるのも一つの手です。そうすることで、他の社員の負担を減らし、不公平感を減らせたという事例もあります。
このように、ワーキングマザーという立場が「聖域」になりすぎないような工夫を行うことも、ケア施策を成功させる重要なポイントかと思います。
そんな中、子どもがいながら残業を行っているワーキングマザーも存在します。周りは「彼女が出来ているのであれば、他のワーキングマザーも出来るでしょう」と思ってしまいがちですが、その背景には、女性たちの大きな決断があることをご存知でしょうか。
というのも、残業を行っているワーキングマザーのほとんどは、両親か夫のサポートを受けられている、もしくは、収入の多くを使って第三者に委託していて、経済的に無理が生じているケースがあるからです。「昇進を勝ち取るために、一時的に収入の半分をベビーシッターに充てよう」という決断をするご夫婦もいらっしゃるそうです。
そのような個別の家庭事情は会社にとっては知る由もないかもしれませんが、上昇志向の強いワーキングマザーにとって、仕事に打ち込む環境をどこまで作れるか、各自の決断に応じて対応していることを、人事である私達は知っておく必要があるでしょう。
女性活躍推進の中で、女性社員の採用を積極化している企業であれば、5年後10年後にワーキングマザーが増えていくことを想定し、ベビーシッターの補助が支給される制度作りなどを行うことも、有効なサポート手法・社員満足度向上手法の一つかもしれません。
ワーキングマザーと一括りにしても、状況は千差万別です。例えば、保育園によって預けられる時間が異なるため、「延長保育は行っているのか」、「延長は何時まで可能か」、「土日に対応しているのか」などの状況は異なってきます。さらに、「両親が近くにいるか」、「旦那さんの就業状況」などの家庭環境に応じても対応が異なってきます。
「そんなプライベートな情報を把握しても、会社として活用は出来ない」と考える人事の方もいらっしゃるかもしれません。しかし、これらを把握しておくことは、どこまで会社に貢献できるかを計る指標や、不平不満を抱く人への説明材料にもなります。権利と義務をバランスよく保っていくために、プライベートな情報かもしれませんが、共有しておくことでお互いのためになるでしょう。
参考までに、どのような項目でヒアリングを行えばよいか、一例をご紹介します。
- 保育所の保育内容(開園時間、延長保育の有無、休日保育の有無、保護者参加の平日イベントの有無)
- 保育所の場所(最寄駅、送迎手段)
- 夫のサポート態勢(在宅時間、育児家事役割分担)
- 実家のサポート態勢(両家それぞれの場所、就労の有無)
- 地域の保育サービス(ベビーシッター、ファミリーサポートセンター、病児保育の有無、NPOなどの見守り機関)
- 今後のキャリアについての要望や目標
細かい項目ですが、これら一つひとつが今後のワーキングマザーたちの働き方を左右することになります。ぜひ、ご本人と一緒に計画を立てるつもりでヒアリングを行っていただければと思います。
今回はワーキングマザーの抱えている葛藤、会社としてどのようにサポートしていけばいいかなど、考えていきました。
ワーキングマザーが増えているとお伝えしてきましたが、まだまだ仕事との両立は厳しく、離職するワーキングマザーも少なくありません。内閣府が公開した少子化社会対策白書 に掲載されている2017年の統計では、“仕事をしたいが育児との両立が難しくて離職した”という女性正社員が22.5%という結果がでました。22.5%の内訳としては、“勤務時間が合わない”“体力が持たない”“育休が取れない”“産後の体調不良”“職場に両立支援の雰囲気が無い”など、リアルな声があがります。
そうした職場での調整に苦労しているうえに、結婚相手の男性の中には専業主婦になってくれることを望む人もおり、職場での苦労を家庭に持ち込むと夫に“じゃあ辞めたら”という展開になってしまうことから、なかなか家事育児の支援を家庭にも求めづらいという声もあるようです。
仕事に向き合う女性を増やし、女性が活躍するための組織構築を考えると同時に、育児と仕事の両立に向けての支援の機会はまだまだ少ないように思います。人事の皆さんも、育児への理解を示し負担を軽くすることはもちろんですが、それだけではなくキャリアを望む女性の両立方法や支援方法についての学びの場の提供を含め、ぜひ一度考えてみていただきたいと思います。
- 労務・制度 更新日:2020/06/02
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-