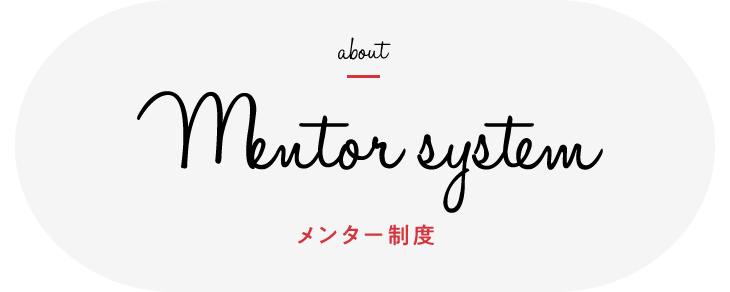早期離職を防ぎ、社員の成長も加速させる?中途社員にメンター制度を適用するメリット
メンター制度とは、新卒社員の精神面をサポートする担当者を設ける制度です。具体的には、メンターが新入社員の悩み相談に乗り、彼らが職場に馴染む手助けをします。メンターは基本的に新卒社員を「評価」「査定」することはありません。メンターが人事権を持たないからこそ、サポートされるメンティは安心してメンターに頼ることができるのです。
慢性的な人材不足が続く昨今、大卒では3割が、高卒では5割が1年以内に退職してしまうと言われます。そんな中、メンター制度は新卒社員の早期離職を防止するための特効薬として、注目されている人事制度なのです。早期離職を防げる制度ならば、新卒社員だけではなく、中途社員にもメンター制度を適用するべきではないでしょうか?
目的:企業文化やルールの浸透
中途社員向けにメンター制度を導入する最大の成果は早期離職を防げること。中途社員は社会人経験があるため、新卒社員と比較するとある程度のビジネスマナーや社会人としての常識を持ち合わせているケースが多いです。
ただ、世の中の会社や業界は千差万別であり、常識と思っていることは、それぞれ違います。前職で身につけた仕事の進め方や会社での立ち振舞い方があだになり、入社後に支障をきたす場合もあるかもしれません。また新しい会社の風土に馴染めない中途社員も少なくないでしょう。
特に中途社員の場合、社会人経験がある分、周囲から「できて当たり前」と思われやすい。また、自分でも「中途だから自分で解決しなきゃ」と思い、一人で問題を抱えてしまうことも多いでしょう。
そんなときメンターが中途社員の悩みにいち早く気づきフォローすることができれば、一人で悩んでいた中途社員はプレッシャーや不安から解放され、結果的に早期離職の防止にも繋がります。
目的:中途社員と既存社員の信頼関係構築
どんなに優秀な人材でも、新しい職場でいきなり高いパフォーマンスを発揮することはできません。一人で仕事を完結できる仕事ならば話は別ですが、基本的に多くの仕事はチームワークが不可欠であり、あらゆる人と関わりながら進めていくことが多いからです。
中途社員は経験があるがゆえに新卒ほど手厚く教育される機会がなく、「あの人は大丈夫でしょ」と思われやすい。入社してから放置され、孤立してしまう人もいます。結果的に、誰に何をお願いしればいいのかわからず、本来の実力を発揮できないケースもあります。
そういった場合でもメンターがいれば、社内の関係者とのハブとしてサポートしてもらえますし、直属の上司に聞きづらい業務上の質問も気軽にできます。
また、メンターとのコミュニケーションを通じて中途社員は自分の課題や目指すべき目標を明確にすることができます。その結果、中途社員のモチベーションが高まり、成長速度の加速にもつながるでしょう。
・職人肌すぎて、言葉が足りない傾向の社員
→職人肌の専門職・技術職に多いタイプですが、「俺の背中を見て仕事を覚えろ」「仕事は見て盗むものだ」といった指導を行う社員には、入社したての社員に対してあえてメンターに指名する妥当性は薄いと思われます。
・高圧的な指導を行う傾向がある社員
→いわゆる「パワハラ体質」の社員です。自分より後輩・若年者に対して普段から厳しすぎる言動を取る社員はメンターに向いていません。
・恋愛体質/セクハラ体質の傾向がある社員
→異性の後輩に対して恋愛感情を抱きやすい社員は要注意です。入社したばかりの社員とプライベートまで踏み込んだ仲になると、関係性が順調なときは大いにプラスに働きます。しかし、それは得てして長続きしないものなのです。
恋愛関係が壊れると、立場が弱い新入社員は職場で居場所がなくなってしまい、結果的に早期退職につながってしまうのです。同様に、セクハラ的な言動を気安く繰り返す社員も、入社直後のセンシティブな時期にあえてメンターに指名しないほうがいいでしょう。
それでは、逆にメンター制度に向いている社員をどうやって選定したらいいのでしょうか? 筆者が前職において効果を挙げた手法は、以下の2点です。
各部署と連携して候補者をピックアップする
普段の業務状況から、後輩の指導に長けていて、かつ指導にモチベーションを捧げられる人材は必ず各組織内に一定数の割合で存在します。こういった「後輩の指導が得意な人材」を人事・各部署の両方でチェックしておいて、いざ新しいメンターの指名が必要になったときに、スムーズに候補者を出せるようにしておくのが、いちばん自然でやりやすい方法です。
メンターの立候補を募る
メンター制度が社内に定着してきたら、各部署からメンターへの自発的な立候補を募るのも非常に有効です。なぜなら、自ら手を挙げた社員は、業務への自覚と責任感を人一倍強く持って、メンターとして仕事に当たってくれるようになるからです。会社側として、きちんとメンター制度の意義や必要性、メリットなどを提示して、立候補を募るとき、意外に多くの手が挙がるでしょう。
また、メンターの職務内容を会社全体としてきちんと定義しておきましょう。上長の職務とメンターの職務の違いを明確化し、フォローアップや業務指導をどの範囲まで行うか、メンターは新入社員に対してどのように指導するのか、トラブル時のルールなど決めておかなければならない事項は多々あります。具体的には、メンター制度の期間、面談の頻度、話し合う内容、面談後の進捗管理方法などの運用ルールを決めるといいでしょう。また、何か不都合が生じたときの「相談窓口」を設けておくことも重要です。
前述した通り、メンターのやるべきことをしっかり決めておくことで、メンター自身も安心して動けますし、いたずらに業務負荷が増大してしまうことを防止できます。
- 人材採用・育成 更新日:2022/12/12
-
いま注目のテーマ
-
-
タグ
-